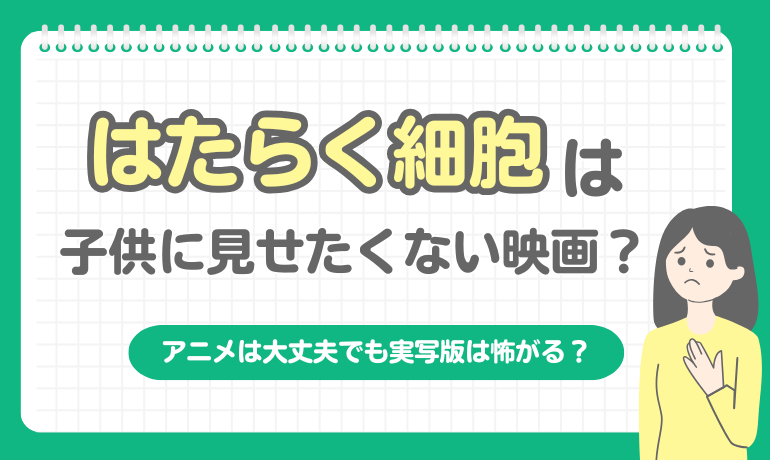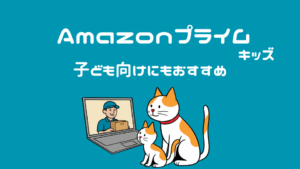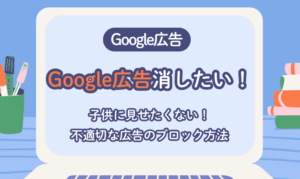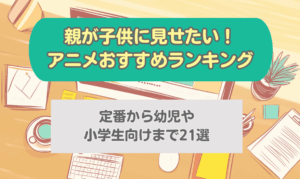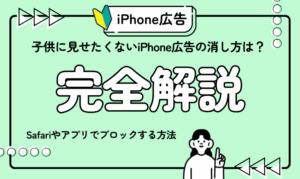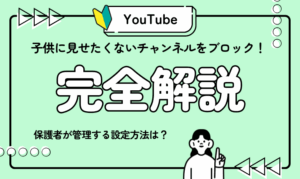子供の教育に良いアニメとして人気の「はたらく細胞」。体の中で働く細胞たちの姿を擬人化し、楽しく人体の仕組みを学べる作品として多くの親子に愛されています。しかし、2023年に公開された実写映画版については「子供に見せたくない」という声が少なくありません。
アニメ版は問題なく見せていたのに、なぜ実写版は子供に見せることをためらう保護者が多いのでしょうか。本記事では、はたらく細胞の映画が子供に見せたくないと言われる理由や、実際に視聴した親子の反応、対象年齢などについて詳しく解説していきます。お子さんと一緒に見るか迷っている保護者の方の参考になれば幸いです。
はたらく細胞の実写版は子供に見せたくない映画?
「はたらく細胞」は、清水茜による漫画作品で、人間の体内で働く細胞たちを擬人化したストーリーです。赤血球や白血球、血小板などの細胞がキャラクターとして登場し、体内で起こる様々な現象を冒険活劇として描いています。2018年にはアニメ化され、子供から大人まで幅広い世代に支持されました。理科や生物の勉強にもなると、教育現場でも活用されている作品です。
2023年12月に公開された実写映画版は、永野芽郁と佐藤健を主演に迎え、アニメとは異なる実写ならではの表現で話題となりました。しかし、この実写版について「子供に見せたくない」という保護者の声が相次いでいます。もちろん、子供の性格や感受性は一人ひとり異なるため、年齢だけで一概に判断することはできません。親御さんがお子さんの特性を考慮しながら判断することが大切ですが、実写版特有の表現が子供に与える影響について、事前に知っておくことは重要でしょう。
特に実写版では、主人公の赤血球が働く体の持ち主が白血病という重い病気を患っているという設定が物語の核となっています。この設定により、アニメ版にはなかったシリアスで重い展開が含まれており、子供への影響を心配する声が上がっているのです。
子供向け映画だが子供向けではない描写も多い
はたらく細胞の実写映画は、一見すると子供向けの教育的な内容を含んだ作品に見えます。実際、体の仕組みを学べる要素は豊富に含まれています。しかし、実写版特有の表現方法により、子供にとっては刺激が強すぎる場面が多く含まれているのが実情です。
アニメ版と実写版の最大の違いは、表現のリアリティにあります。アニメでは可愛らしくデフォルメされていた細菌やウイルスとの戦闘シーンも、実写版では生々しい映像表現となっています。例えば、白血球が細菌を倒すシーンでは、アニメではコミカルに描かれていた部分が、実写では迫力のあるアクションシーンとして表現されます。血しぶきや破壊される細胞の描写も、CGを駆使してリアルに再現されているため、小さな子供にとってはトラウマになりかねません。
また、病気の進行に伴う体内の変化も、実写ならではの重厚な演出で描かれます。がん細胞との戦いや、白血病による体の衰弱などは、アニメよりもはるかに深刻で重い雰囲気で表現されています。大人が見れば感動的なシーンであっても、子供にとっては理解が難しく、ただ怖いだけの映像になってしまう可能性があります。
さらに、実写版では人間ドラマの要素も強く、病気と闘う患者の苦しみや、家族の葛藤なども描かれています。これらの要素は作品に深みを与えていますが、同時に子供には重すぎるテーマとなっています。死や病気という概念をまだ十分に理解できない年齢の子供にとって、これらのシーンは混乱や不安を引き起こす原因となりかねません。
低学年の小学生は怖いと感じる可能性が高い
特に小学校低学年(1年生から3年生)の子供たちにとって、実写版のはたらく細胞は刺激が強すぎる可能性が高いと言えます。この年齢層の子供たちは、まだ現実とフィクションの境界が曖昧で、映画の中の出来事を自分のことのように感じてしまう傾向があります。
小学校1、2年生向けの作品としては、実写版の演出は過激すぎます。暗い画面や大きな音響効果、激しいアクションシーンなどは、この年齢の子供たちにとって恐怖の対象となりやすいのです。また、病気や死といった重いテーマを扱っているため、まだ死生観が形成されていない低学年の子供たちには理解が困難で、ただ恐怖や不安を感じるだけになってしまう可能性があります。
3年生から4年生になると、ある程度物語を理解する力も身についてきますが、それでも実写版の生々しい表現は刺激的すぎるかもしれません。特に感受性の強い子供や、暗いものが苦手な子供にとっては、視聴後に悪夢を見たり、体調を崩したりする可能性も否定できません。
一方で、小学校高学年(5年生、6年生)になると、理科の授業で人体について学ぶ機会も増え、映画の内容を教育的な観点から理解できるようになってきます。この年齢層であれば、保護者と一緒に視聴し、分からない部分を説明してもらいながら見ることで、怖さよりも学びを得られる可能性が高くなります。
ただし、何年生向けかという判断は、あくまで目安に過ぎません。同じ学年でも、子供の成長度合いや性格、これまでの映画視聴経験などによって、受け止め方は大きく異なります。普段から戦隊ものやアクション映画を見慣れている子供であれば、比較的抵抗なく視聴できるかもしれませんし、逆に繊細な子供であれば高学年でも怖がる可能性があります。
年齢制限はPG12。12歳未満は保護者の同伴が好ましい
実写映画「はたらく細胞」の年齢制限はPG12に設定されています。PG12とは「Parental Guidance 12歳未満」の略で、12歳未満の子供が視聴する場合は、保護者の助言や指導が必要という意味です。これは強制的な制限ではなく、あくまで推奨される指針ですが、製作側も子供だけで見るには適さない内容が含まれていることを認識していることを示しています。
PG12が設定される理由としては、暴力的なシーンや、子供には理解が難しいテーマが含まれていることが挙げられます。はたらく細胞の実写版では、細胞同士の戦闘シーンや、病気による体の変化など、子供にとって刺激的な映像が多く含まれています。また、白血病という重い病気を扱っているため、精神的なショックを受ける可能性も考慮されています。
保護者の同伴が推奨される理由は、子供が怖がったり混乱したりした際に、すぐにフォローできるようにするためです。映画の途中で子供が怖がった場合、保護者が状況を説明したり、安心させたりすることができます。また、視聴後に子供が疑問や不安を感じた際に、適切に答えてあげることも重要です。
12歳以上であれば一人で視聴しても問題ないとされていますが、これもあくまで目安です。中学生になっても、怖がりな子供や感受性の強い子供の場合は、保護者と一緒に見ることをお勧めします。逆に、12歳未満でも精神的に成熟している子供であれば、保護者の判断で視聴させることも可能です。
勉強になるし最後は感動できる作品ではある
確かに刺激的なシーンも多い実写版のはたらく細胞ですが、教育的価値や感動的な要素も多く含まれています。人体の仕組みを視覚的に理解できる点では、非常に優れた教材となり得ます。
映画では、赤血球が酸素を運ぶ仕組みや、白血球が細菌と戦う様子、血小板が傷を修復する過程など、体内で起こっている現象が分かりやすく描かれています。これらの知識は、理科の授業で学ぶ内容と直結しており、映像として見ることで理解が深まります。特に、細胞たちが協力して体を守る姿は、チームワークの大切さを学ぶ良い機会にもなります。
また、物語の後半では、病気と闘う細胞たちの姿に感動する場面も多くあります。どんなに困難な状況でも諦めずに働き続ける細胞たちの姿は、子供たちに勇気と希望を与えてくれます。白血病という重い病気を扱いながらも、最終的には希望を持てる結末となっており、生命の大切さや、体を大切にすることの重要性を学ぶことができます。
さらに、実写版ならではの迫力ある映像は、アニメでは表現しきれなかった体内の壮大さを感じさせてくれます。ミクロの世界でありながら、まるで一つの宇宙のような体内の様子は、子供たちの想像力を刺激し、科学への興味を育てるきっかけになるかもしれません。
ただし、これらの教育的価値や感動を十分に受け取るためには、ある程度の精神的成熟が必要です。怖さや不安が先行してしまうと、せっかくの学びの機会も失われてしまいます。そのため、お子さんの成長度合いを見極めて、適切なタイミングで視聴することが大切です。
子供に見せたくない?はたらく細胞の映画を見た人の口コミ
実際にはたらく細胞の実写映画を視聴した保護者や子供たちの反応はどうだったのでしょうか。様々な口コミから、リアルな声を集めてみました。
子供の反応が心配になるほど怖がってしまった
多くの保護者から寄せられた口コミの中で、最も多かったのが「子供が怖がってしまった」という内容でした。
「小学2年生の息子と一緒に見に行きましたが、序盤の戦闘シーンで泣き出してしまいました。アニメは大好きで何度も見ていたので大丈夫だと思っていたのですが、実写の迫力は別物でした。途中退場も考えましたが、なんとか最後まで見ることができました。ただ、その夜は怖い夢を見たようで、しばらく一人で寝るのを嫌がっていました」
「5歳の娘を連れて行きましたが、完全に失敗でした。血液の描写がリアルすぎて、『お腹の中に悪い虫がいる』と言って泣き続けていました。アニメの血小板ちゃんが可愛いから見たいと言っていたのですが、実写版の雰囲気は全く違いました。子供向けだと思って気軽に連れて行ったことを後悔しています」
このように、アニメ版を楽しんでいた子供でも、実写版の表現には耐えられないケースが多く見られました。特に低年齢の子供ほど、その傾向が強いようです。
気まずいシーンや残酷な描写にひどいと感じる親も
保護者の中には、子供と一緒に見るには気まずいシーンが多いと感じた方も少なくありませんでした。
「戦闘シーンの暴力的な描写が思った以上に激しく、子供に見せるにはひどい内容だと感じました。細菌を倒すシーンでは血しぶきのような表現もあり、これを教育的だと言えるのか疑問です。PG12という年齢制限があることを事前に知っていれば、もっと慎重に判断したのですが」
「白血病の患者さんの苦しむ姿が生々しく描かれていて、8歳の娘には刺激が強すぎました。『なんでこの人は苦しいの?死んじゃうの?』という質問に答えるのも難しく、気まずい雰囲気になってしまいました。アニメのような明るい雰囲気を期待していただけに、がっかりしました」
また、映画の内容に医学的な誤りがあることを指摘する声もありました。
「医療従事者として見ると、細胞の働きについて誇張や誤解を招く表現が多々ありました。エンターテイメントとして楽しむ分には良いですが、これを教育的な内容として子供に見せるのは問題があると思います。正しい知識を身につけさせたいなら、きちんとした図鑑や教材を使うべきです」
高学年の子供なら勉強になったという意見も
一方で、小学校高学年以上の子供と視聴した保護者からは、肯定的な意見も寄せられています。
「小学5年生の息子と見ました。理科で人体について勉強していたこともあり、『授業で習ったことが映像で見られて分かりやすかった』と言っていました。確かに怖いシーンもありましたが、それも含めて体の中で起こっていることを理解できたようです」
「中学1年の娘は、最初は怖がっていましたが、次第に物語に引き込まれていきました。特に白血球が体を守るために戦うシーンは感動的で、『自分の体の中でもこんなことが起きているんだ』と驚いていました。病気の怖さも理解できたようで、健康に気をつけようという意識も芽生えたようです」
このように、ある程度の年齢に達した子供であれば、教育的な価値を見出すことができるという意見もありました。
家族で見るには重すぎるテーマという声
映画のテーマ自体が重すぎるという意見も多く見られました。
「家族で楽しめる映画だと思って見に行きましたが、白血病という重いテーマに家族全員が沈んでしまいました。確かに感動的な部分もありましたが、休日に家族で見る映画としては重すぎます。子供も『悲しい映画だった』という感想しか持てなかったようです」
「エンディングで涙を流している観客も多かったですが、9歳の息子は『なんで皆泣いているの?』と不思議そうでした。感動するには、ある程度人生経験や死生観が必要だと感じました。子供にはまだ早い作品だと思います」
その他の口コミ
キャストや映画全体の質についての意見も様々でした。
永野芽郁さんと佐藤健さんの演技については「素晴らしかった」「キャラクターにぴったり」という好意的な意見が多数ありました。特に白血球役の佐藤健さんのアクションシーンは見応えがあったという声が多く聞かれました。
映画全体の質については意見が分かれており、以下のような声がありました:
- CGのクオリティが高く、体内の世界観がよく表現されていた
- アニメ版と比べると暗い雰囲気で、別物として見るべき
- 大人向けの作品として作られており、子供向けではない
- 医学的な監修がもっとしっかりしていれば良かった
- 上映時間が長く、子供には集中力が持たない
- 音響効果が大きすぎて、小さい子供には刺激が強い
- ストーリーは感動的だが、子供には理解しづらい部分が多い
はたらく細胞のアニメを子供に見せたくない人もいる
実は、実写版だけでなく、アニメ版のはたらく細胞についても「子供に見せたくない」という意見があります。その理由を見ていきましょう。
アニメ版でも戦闘シーンや血の表現があることを心配する保護者の声があります。
「アニメ版でも白血球が細菌を倒すシーンで血しぶきが飛ぶ表現があり、3歳の娘には見せられませんでした。教育的な内容だと聞いていたのですが、バトルアニメの要素が強すぎます」
「5歳の息子がアニメを見て以来、『体の中で戦争が起きている』と言って怖がるようになってしまいました。細菌やウイルスとの戦いが激しく描かれすぎていて、幼児には刺激が強いと感じます」
「がん細胞の話は、小学校低学年の子供には重すぎました。『がんって何?死んじゃうの?』という質問に答えるのが難しく、見せなければよかったと後悔しています」
また、医学的な内容の難しさを指摘する声もあります。
「専門用語が多く、小学生には理解できない部分が多いです。説明なしでは内容を理解できず、ただのバトルアニメとして見てしまう可能性があります」
その他にも以下のような意見がありました:
- 血小板を幼女として描いているのが気持ち悪い
- 擬人化することで、かえって正しい理解を妨げる
- 体内で起こることを戦いとして描くのは教育上良くない
- キャラクターに愛着を持ちすぎて、実際の細胞の働きと混同する
- 病気になることへの恐怖心を植え付ける可能性がある
一般的には、アニメ版のはたらく細胞は小学校中学年(3、4年生)以上であれば、保護者と一緒に視聴することで教育的な効果が期待できるとされています。しかし、それより低年齢の子供、特に未就学児には刺激が強すぎる可能性があります。
アニメ版を見せる際も、子供の年齢や性格を考慮し、必要に応じて保護者が説明を加えながら視聴することが大切です。また、怖がったり不安を感じたりした場合は、無理に続けず、もう少し成長してから改めて見せることも検討すべきでしょう。
まとめ
はたらく細胞の実写映画は、確かに教育的価値や感動的な要素を含んだ作品ですが、子供に見せる際には慎重な判断が必要です。特に小学校低学年以下の子供にとっては、実写版の生々しい表現や重いテーマは刺激が強すぎる可能性が高いと言えるでしょう。
PG12という年齢制限が設けられていることからも分かるように、12歳未満の子供が視聴する場合は保護者の同伴が推奨されています。これは、子供が怖がったり混乱したりした際に、適切なフォローができるようにするためです。
一方で、小学校高学年以上の子供であれば、保護者と一緒に視聴することで、人体の仕組みを学ぶ良い機会となる可能性があります。ただし、これもお子さんの性格や感受性によって異なるため、画一的な判断はできません。
アニメ版についても、低年齢の子供には刺激的な部分があるため、視聴の際は保護者の判断が重要です。お子さんの成長度合いや性格を考慮し、適切なタイミングで、必要に応じて説明を加えながら視聴することをお勧めします。
最終的に、はたらく細胞を子供に見せるかどうかは、保護者の方がお子さんをよく観察し、慎重に判断することが大切です。無理に見せる必要はありませんし、もし視聴して怖がってしまった場合は、しっかりとフォローしてあげることが重要です。
子供の教育や娯楽として映画を選ぶ際は、年齢制限や口コミを参考にしながら、お子さんに合った作品を選んであげてください。はたらく細胞も、適切な年齢になれば素晴らしい学びの機会となる作品です。焦らず、お子さんの成長に合わせて楽しんでいただければと思います。