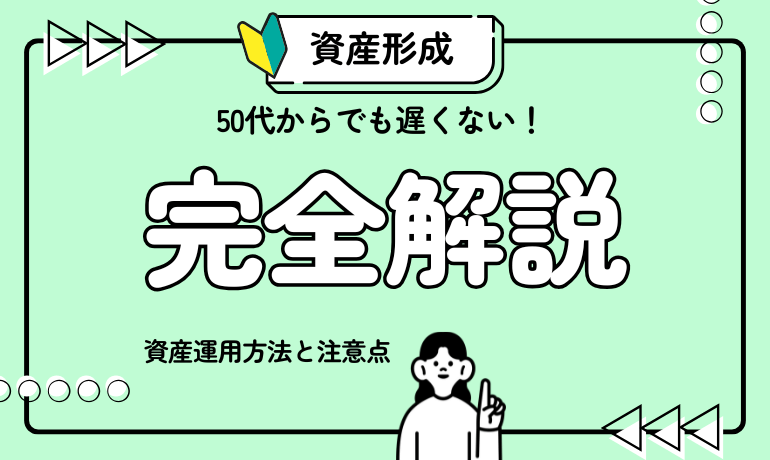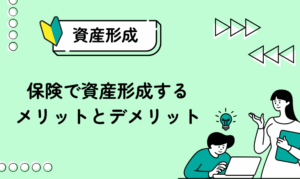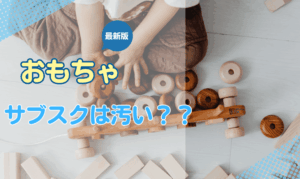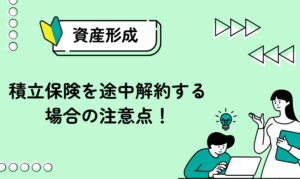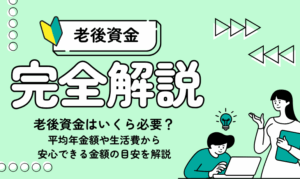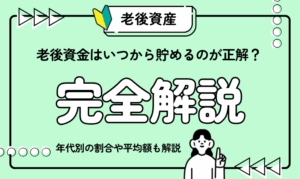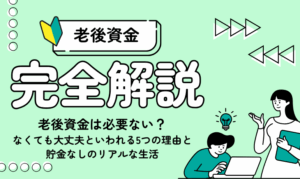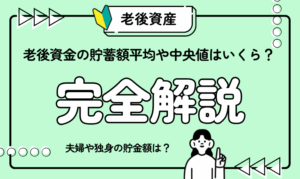遅くない!50代からでも資産形成はできる
50代は子育てや住宅ローンなど大きな支出が一段落し、毎月の家計に余裕が生まれやすい時期です。それまで子供や住宅に充てていたお金を資産運用に回せる余力ができるケースも多いでしょう。若い頃より運用期間は短くなりますが、その分まとまった資金を投資に充てられるため、効率よく資産を増やせます。
定年退職まで10年以上残されている点も、50代から資産運用を始める十分な理由です。現在は定年が延び、平均寿命も伸びているため、50代からでも老後まで20年前後の運用期間を確保できます。「今さら……」と迷っている時間はもったいないでしょう。思い立った今こそ始めどきと言えます。
さらに、50代は退職後の生活が具体的に見えてくる時期でもあります。年金の受取見込み額が分かり始め、自分たちに必要な老後資金の概算も立てやすくなります。老後の住まいや趣味・旅行などのプランを考えることで目標金額が明確になれば、資産形成の計画も立てやすくなるでしょう。
50代の初心者の資産形成におすすめの資産運用方法
50代から資産運用を始めたいと思っても、「具体的に何をすれば良いのか分からない」という初心者の方も多いでしょう。ここでは、50代の資産形成におすすめの資産運用方法をいくつか紹介します。いずれも比較的リスクが低めで、初心者でも取り組みやすい方法です。それぞれの特徴やメリット・デメリットも解説します。
投資信託(ファンド)
投資信託は、投資家から集めた資金をまとめ、運用のプロが国内外の株式や債券などに分散投資する金融商品です。少額から購入でき、プロに任せられるため、投資経験がない50代の初心者にも適しています。
投資信託のメリットは、効率的な分散投資と運用をプロに任せられる点です。少額資金でも世界中の株式や債券に幅広く分散でき、自分で市場を分析しなくても専門家が運用してくれます。デメリットは元本保証がないことと、手数料がかかることです。運用成績次第では元本割れする可能性があり、保有中には信託報酬などのコストも発生します。購入前にどの程度の手数料がかかるか確認しておきましょう。
債券投資
債券への投資も、50代の資産形成に適した方法のひとつです。債券投資とは、債券を購入して償還日に利子を受け取り、満期に元本が戻ってくる資産運用方法です。債券は国や地方自治体、企業などが発行するもので、国が発行するものは国債と呼ばれます。メリットは定期的に利子収入が得られ、満期まで保有すれば元本が戻る点です。
ただしデメリットとして、大きなリターンは期待しにくいことが挙げられます。決められた利息分しか資産は増えないため、低金利の時期にはリターンも小さくなります。また、発行体が破綻するリスクもゼロではありません。万一そのような事態になれば元本や利息を受け取れなくなる可能性があります。
NISA(少額投資非課税制度)
NISA(ニーサ)とは、株式や投資信託の運用益が非課税になるお得な制度です。2024年から始まった新NISAでは、非課税で投資できる生涯の限度額として1,800万円の「非課税保有限度額」が設定されました。年間の投資上限額は合計で360万円ですが、2つの枠から構成されます。長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託が対象の「つみたて投資枠」(年間120万円)と、上場株式なども購入できる「成長投資枠」(年間240万円)です。特に注意すべきは、生涯1,800万円の枠のうち、「成長投資枠」で利用できるのは最大1,200万円までという点です。また、非課税で資産を保有できる期間が無期限になったため、50代からでも腰を据えた長期投資が可能です。
NISAを利用するメリットはなんといっても運用益が非課税になることです。複利効果で増えた利益にも税金がかからず、手取り額を最大化できます。少額からの積立投資にも適しており、50代の初心者でも始めやすい制度です。ただし、NISAだからといって元本が保証されるわけではない点には注意しましょう。投資した商品の価値が下がれば損失を被る可能性はあります。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCo(イデコ)は、自分で積み立てて運用し、60歳以降に受け取る私的年金制度です。掛金拠出時から運用中、受取時まで各段階で税制優遇が受けられるのが大きなメリットで、運用益は非課税、掛金は全額所得控除になるため高い節税効果があります。
原則60歳まで引き出せないため、着実に老後資金を準備できる制度です。50代からでも加入可能ですが、老齢給付金の受給開始年齢は、iDeCoの通算加入者等期間によって変動する点に注意が必要です。60歳から受給するためには10年以上の加入期間が必要ですが、期間がそれに満たない場合、受給開始年齢が以下のように繰り下げられます。例えば、55歳で新規加入した場合、60歳までの加入期間は5年となり、受給開始は63歳からとなります。このルールを理解することが、50代からのiDeCo活用プランの鍵となります。
デメリットとしては、60歳まで資金を動かせない流動性の低さがあります。加入者の属性によって掛金の上限額が決まっている点や、金融機関ごとに口座管理手数料がかかる点も確認が必要です。しかし、老後の年金づくりとしては非常に有力な制度なので、公的年金を補完したい人は積極的に活用すると良いでしょう。
また、2022年の制度改正により、iDeCoに加入できる年齢が原則65歳未満まで延長され、受給開始時期も75歳まで選択できるようになるなど、より柔軟な活用が可能になっています。結果、例えば60代で働きながら掛金を拠出し、掛金の全額所得控除という税制優遇を受け続けるといった選択肢も生まれました。人生100年時代における老後資産形成の有力な選択肢として、制度が進化していることを示しています。
個人年金保険
個人年金保険は、現役のうちに保険料を積み立て、60歳や65歳から年金形式で受け取る民間の年金商品です。確実に老後資金を用意できる安心感がメリットですが、運用利回りは低めで長期間資金が拘束される点がデメリットです。最近は運用結果で受取額が変動する変額タイプもありますが、元本保証はなくリスクが伴います。大きなリターンは望みにくいものの、貯蓄感覚で堅実に準備したい人には選択肢となるでしょう。
50代からの資産形成にはリスクが高い方法
資産運用の方法にはさまざまなものがありますが、中には50代から始めるにはリスクが高いと考えられるものもあります。ここでは、特に慎重な扱いが必要な代表例として株式投資と不動産投資を取り上げます。これらは大きなリターンが期待できる反面リスクも高いため、初心者がいきなり大金を投じるのはやめておいたほうがよいでしょう。ただし、余裕資金があり経験を積む意思があるならポートフォリオの一部に組み込むこともできます。
株式投資
株式投資は、株式市場で企業の株を売買し、その値上がり益や配当金などで利益を狙う投資方法です。うまくいけば短期間で大きな利益を得られる可能性がありますが、同時に価格変動のリスクが大きい点に注意が必要です。株価は日々上下動するため、個別株に集中投資すると値下がり時の損失も大きく、50代初心者にはハードルが高めです。
株式の魅力は、企業の成長によって高いリターンを期待できる点です。購入した株が数倍に値上がりする可能性もあり、保有期間中の配当金など収入も得られます。しかし株価が暴落すれば資産が大きく目減りするリスクもあります。特に50代は運用期間が短いため、一度大きな損失を出すと取り戻すことが難しくなるでしょう。
したがって、株式投資を始める場合は余裕資金の一部で少しずつ行うのが賢明です。資産の大半を株式につぎ込まず、安全資産をベースにリスク許容範囲で株式にもチャレンジするという姿勢が大切です。また、銘柄選びの際は企業の情報を十分に調べ、分散投資によってリスクを抑える工夫も行いましょう。
不動産投資
不動産投資は、マンションやアパート、一戸建てなどの不動産物件を購入して賃貸に出し、家賃収入(インカムゲイン)や売却益(キャピタルゲイン)を得る投資方法です。長期にわたり安定した家賃収入が期待でき、実物資産を持てる安心感が魅力ですが、その分まとまった初期資金が必要で、空室や物件価格の下落など特有のリスクも大きい投資です。
メリットとして、適切な物件を選べば毎月の賃料という安定収入が期待できます。一方で、物件購入には多額の資金が必要で、ローンを組めば返済負担が重くのしかかります。また空室が出れば収入が途絶え、修繕費など維持管理コストもかかるため、初心者にはハードルが高い投資と言えます。
不動産投資を検討する場合は、専門家に相談して綿密な資金計画を立て、無理のない範囲で始めることが大切です。十分な知識と準備がないまま大きな資金を投じるのは避けましょう。
50代から資産形成を目指すときの注意点
50代から資産形成・資産運用を行うにあたって、注意しておきたいポイントがあります。若い頃に比べ時間的猶予が少ない分、失敗を避けつつ効率よくお金を増やす視点が重要です。以下に、50代で資産運用を始める初心者が押さえておくべき注意点・コツをまとめます。
資産運用に回せる資金を計算する
自分の資産状況や毎月の家計を把握し、運用に回せるお金の範囲を明確にしましょう。例えば生活費やローンなど必要な支出を差し引いて、毎月いくら投資に回せるか算出してみましょう。退職までに必要な貯蓄額や退職金の使い道も考慮して、無理のない資金計画を立てることが大切です。
余裕資金でコツコツ運用することで、万が一損失が出ても生活に致命傷を負わずに済みます。日々の生活を犠牲にしない範囲で計画することが、資産運用を長続きさせるコツです。
投資の基礎を勉強する
50代から投資を始める場合でも、基礎知識の学習は避けて通れません。投資の世界には、リスクとリターンの関係や分散投資の重要性、複利効果などの基本原則があります。初心者向けの入門書やセミナー、金融機関の情報サイトなどで最低限の知識を身につけましょう。
また、具体的に購入する商品ごとの仕組みやリスクを理解してから投資することも鉄則です。理解せずに勧められるまま買ってしまうと、予想外の値下がりに慌ててしまうことになりかねません。「〇%値上がりしたら利益確定する」「△%下落したら損切りする」など、自分なりの出口戦略も決めておけば冷静に運用しやすくなります。50代は時間に限りがあるので行き当たりばったりではなく計画的な運用を心がけましょう。基礎を勉強しておけば、相場が変動しても落ち着いて判断できるようになります。
分散投資をする
資産運用で成功するための鉄則の一つが分散投資です。特に50代からの運用では、一つの投資先に資産を集中させないことが重要になります。万一ある投資で損失が出ても、資産の一部で済むようにしておくべきだからです。できる限り資産をさまざまな対象に分散させてリスクを低減しましょう。
分散投資には複数の観点があります。まず投資対象の分散です。株式だけでなく債券や投資信託、不動産投資信託(REIT)など、異なる値動きをする資産クラスにお金を配分することで、一つの市場が低迷しても他の資産でカバーできる可能性が高まります。また国内だけでなく海外の資産も組み入れれば、為替や各国景気の違いによるリスクヘッジにもなります。
次に時間の分散も有効です。一度にまとまった金額を投じるのではなく、購入時期をずらすことで価格変動リスクを平均化できます。毎月一定額をコツコツ積み立てていく積立投資は、時間分散の代表的な方法です。高値づかみするリスクを減らし、安い時には多く買うことで長期的な平均取得単価を平準化できます。
このように、複数のかごに卵を分けて持つイメージで運用することが大切です。50代の資産形成では、リスクを抑えながら着実に増やす視点を忘れないようにしましょう。
積立投資をする
資産形成を堅実に行うには、積立投資も強力な手法です。積立投資とは、毎月など定期的に一定額を投資し続ける方法で、ドルコスト平均法とも呼ばれます。50代から投資を始める場合でも、毎月コツコツ積み立てる習慣を取り入れることで、無理なく資産を増やすことができます。
積立投資の最大の利点は、時間分散の効果によってリスクを抑えられることです。市場は上がったり下がったりを繰り返しますが、積立であれば高い時には買付額あたりの購入数量が少なく、安い時には多く買うことになり、結果的に購入価格を平均化できます。一度に大金を投入してタイミングを誤る心配が少なく、初心者でも安心して始めやすい方法と言えるでしょう。
また、家計への負担が少ないのも積立投資の魅力です。例えば毎月1万円を積み立てる設定にすれば、大きな出費をした実感がないまま年間12万円を投資に回せます。これを5年10年と続ければ、まとまった資産形成につながります。自分の収支に合わせて無理なく継続しましょう。もちろん、積立投資でも投資対象の選定は重要です。長期で積み立てる以上、将来的に成長が期待できる商品を選ぶようにしましょう。
積立投資は「継続は力なり」を地で行く手法です。途中で相場が下落する局面があっても、やめずに続けることが成功のカギとなります。毎月の積み重ねが将来大きな果実となって返ってくる可能性を信じて、楽しみながら取り組んでみてください。
長期的な視点で運用する
50代から資産運用を始める場合でも、長期的な視点に立って運用することが大切です。残された時間が限られているからといって、短期間で結果を求めようとすると失敗するリスクが高まります。焦らずにじっくり時間をかけて資産を育てる意識を持ちましょう。
デイトレードのような短期売買で一時的に儲けることは、高度な知識と経験が必要でリスクも高いため初心者には向きません。50代の資産形成では、「退職までの残り時間で無理なく増やす」というスタンスが基本です。仮に定年まで10~15年あるなら、その期間で計画的に増やすことを目指し、日々の値動きに一喜一憂しすぎないようにしましょう。
また、長期運用すれば複利効果による資産増加も期待できます。短期売買では得られない恩恵を受けられる点で、長期視点の運用には大きなメリットがあります。「急がば回れ」の精神で着実に資産を築くことを目指してください。
50代からの資産形成におすすめのポートフォリオ
最後に、50代で資産運用を行う際のポートフォリオの考え方について紹介します。ポートフォリオとは資産配分のことで、どんな商品にどの程度の割合で投資するかという資産の組み合わせを指します。50代は「守りながら増やす」姿勢が重要です。ポートフォリオ(資産配分)を考える際は、安全資産(預貯金や債券など)の割合を高め、リスク資産(株式や株式型投信など)は抑えめにするのが基本です。例えば全体を80%程度の堅実な運用商品(コア部分)と残り20%の積極運用商品(サテライト部分)に分けるコア・サテライト戦略などは、リスクを抑えつつリターンを追求できる一例でしょう。
なお、年齢が上がればさらに安全資産の比率を高めるなど、市場環境やライフステージに応じて定期的にポートフォリオを見直すことも大切です。例えば50代前半ではやや株式比率を高めにし、60代に近づいたら徐々に債券や現金比率を上げていく、といった段階的なシフトでリスク管理しやすくなります。
要するに、50代の資産運用では分散と安全性を重視した堅実なポートフォリオを心がけることが大切です。人によって「最強のポートフォリオ」は異なりますが、基本は攻めすぎず守りを固める方針で、自分に合ったバランスを見つけましょう。老後に向けた資産形成は50代からでも遅くありません。今できる一歩を踏み出し、将来の安心につなげていきましょう。