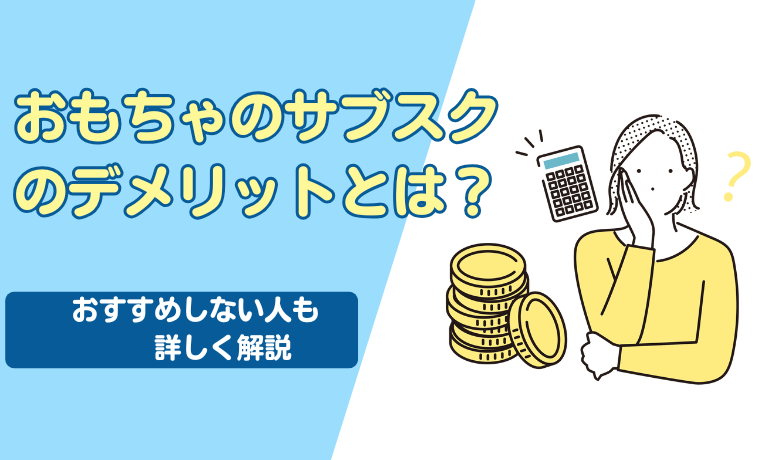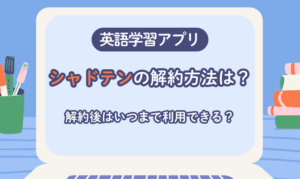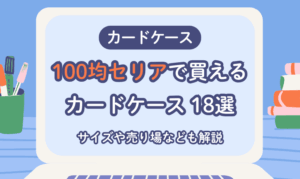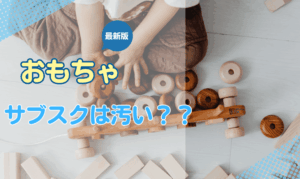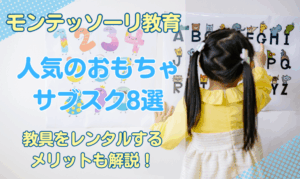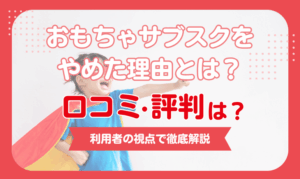おもちゃのサブスクとは、月額定額の料金を支払って子どものおもちゃを定期レンタルできるサービスです。毎月または隔月サイクルで年齢に合った知育玩具が届き、買わなくてもさまざまなおもちゃを試せる便利さから、近年子育て世代に注目されています。ただ、一方で「おもちゃ サブスク デメリット」「おもちゃサブスク やめた」といったネガティブな声も耳にします。実際に利用する前に、デメリットを把握しておくことは大切です。
そこでこの記事では、おもちゃのサブスクに興味があるものの契約するか悩んでいる方に向けて、サービスのデメリット10選を詳しく解説します。また、デメリット以外でおもちゃサブスクをやめる主な理由、サービスのメリット、さらにおもちゃのサブスクをおすすめしない人・おすすめな人についても紹介しますので、契約を検討する際の判断材料にしてください。
おもちゃのサブスクのデメリット10選
おもちゃのサブスクには多くのメリットがある反面、人によっては以下のようなデメリットを感じる場合があります。ここでは代表的なデメリット10個に加え、それぞれどんな人に向いていないか、逆にどんな人なら気にならないかを見ていきましょう。
1. 毎月の固定費が負担になる
おもちゃのサブスクは、基本的に毎月一定の料金が発生します。主なサービスの月額料金は平均して約3,000〜4,000円程度で、プランによってはそれ以上の場合もあります。例えば、定番サービスのトイサブ!は月額約1,980〜3,980円、ChaChaCha(チャチャチャ)は月額約3,910円~4,950円程度です。この毎月の費用が家計にとって負担に感じる人にとっては、大きなデメリットと言えるでしょう。
特におもちゃ代をできるだけ節約したいご家庭では、「毎月数千円の固定費」は痛手になります。そのような場合、おもちゃのサブスクはおすすめできません。一方で、毎月一定額でおもちゃが使い放題になるメリットを重視する人や、月に数万円分のおもちゃを購入してしまう傾向にある人にとっては、この固定費が許容範囲になる場合もあります。実際、自分で知育玩具をいくつも購入すれば簡単に月数千円以上はかかるため、サブスクのほうが割安だと感じる利用者もいます。家計に余裕がある方や、おもちゃ購入費用の代わりとしてサブスク料金を捻出できる方であれば、このデメリットはさほど気にならないでしょう。
2. 新品でないため汚いと感じることがある
おもちゃのサブスクで届くおもちゃは、基本的に中古品です。他の家庭で使われたレンタル品が回ってくるため、「新品じゃないおもちゃを子どもに与えるのはちょっと…」と衛生面や安全面を不安に思う方もいるでしょう。特に小さな子どもは何でも口に入れたり舐めたりしますから、他人が使ったおもちゃだと汚いのではと心配になるのも自然なことです。
しかし、大手おもちゃサブスク各社では返却されたおもちゃを毎回しっかりクリーニング・消毒しています。専用の洗浄方法で清潔にしてから次の利用者へ発送しているため、基本的には衛生面の心配をしすぎる必要はないでしょう。それでも「やっぱり新品じゃないと嫌だ」という潔癖気味の方や、どんなに消毒済みでも中古品に抵抗がある方には、この点がデメリットになります。このような方には、おもちゃのサブスクはおすすめしません。逆に、リユース品に理解があり「おもちゃは清掃済みなら中古でも構わない」「環境にも優しいし合理的」と考えられる方にとっては、大きな問題にはならないでしょう。
3. 最低契約期間が決まっている
サービスによっては、最低利用期間(最低契約期間)が定められていることがあります。「○ヶ月未満で解約すると違約金」または、「○ヶ月間は解約不可」というルールが定められているケースが珍しくないのです。。例えば、トイサブ!では最低利用期間が60日(2ヶ月)とされており、ChaChaChaではプランによって最低90日(3ヶ月)以上の利用が条件になっています。つまり、試しに1ヶ月だけ使ってすぐ解約…のようにできないことがあるのです。
解約したくても契約から一定期間はやめられないのは、短期間で合わないと感じた場合にデメリットになります。「子どもの反応を見てダメそうならすぐやめたい」と考えている、せっかちな方には向いていません。また、引っ越しや環境の変化などで急にサービスをやめたくなっても、最低期間内だと融通が利かない可能性があります。一方で、「長く使うつもりだから最低○ヶ月くらい問題ない」「最初から数ヶ月は試す覚悟がある」という方であれば、この制約は気にならないでしょう。契約前に各サービスの最低契約期間を確認し、自分の利用予定と合うか検討することが大切です。短期利用しか考えていない人にはおすすめできませんが、腰を据えて利用できる人にはあまりデメリットにはならないでしょう。
4. 返送の手間がかかる
レンタル品である以上、定期的におもちゃを返却しなければなりません。多くのサービスでは1〜2ヶ月に1回のペースで玩具の交換があり、その際に使い終わったおもちゃを返送する必要があります。おもちゃを箱にまとめ、伝票を貼って発送する作業は、忙しい育児の合間では面倒に感じる人もいるでしょう。
特に小さいお子さんがいるご家庭では、荷造りや郵便局への持ち込みなどの返送作業自体が負担になり得ます。おもちゃのパーツをなくさないよう事前に揃えたり、梱包したりという手間も発生します。この返送作業の手間を煩わしく思う人には、おもちゃサブスクは向いていないでしょう。
一方で、各サービスも利用者の負担を減らす工夫をしています。例えば、次回のおもちゃが届く際に交換で引き取りをしてもらえるサービスや、専用の返送キット・着払い伝票が用意されている場合も多いです。そうした仕組みに慣れてしまえば、返送作業はそれほど大変ではないとの声もあります。こまめに部品を片付けておくなど、工夫次第で手間は軽減できます。多少の返送手続きは許容できる、むしろ定期的におもちゃを入れ替える作業も楽しめるという方であれば、このデメリットはあまり気にならないでしょう。
5. 子どもが気に入っても返却する必要がある
サブスクで借りたおもちゃはいずれ返却しなければならないため、子どもがおもちゃをとても気に入った場合でも手元に置き続けることができません。子どもが「あのおもちゃ大好き!返したくない!」となってしまうと、返却時に寂しい気持ちになったり、泣いて嫌がったりすることもあります。親としても、子どもが夢中で遊んでいるお気に入りのおもちゃを返すのは心苦しいものです。
愛着が湧いたおもちゃを手放さなければならない点は、情緒面でデメリットに感じる人もいるでしょう。特にお気に入りのものは買い取って手元に残したいと思う親御さんには、ストレスになります。一方、ほとんどのサービスでは気に入ったおもちゃをそのまま購入できるオプションが用意されています(中古品として、割引価格で買い取れることもあります)。どうしても子どもがお別れできない場合は購入する手もあるため、結果的に「絶対に返さなければならない」というわけではありません。ただし、当然追加の費用は発生します。
「レンタルのおもちゃはあくまで一時的なもの」と割り切れる場合、この問題はそれほど大きくありません。いろんなおもちゃを短期間で循環させたいと考えるご家庭では、返却も計画のうちなのでデメリットと感じにくいでしょう。しかし、お子さんが一つの玩具に強い愛着を持ちやすいタイプだったり、思い出の品を手放すことに抵抗があったりする場合は、おもちゃのサブスクにストレスを感じる可能性があります。
6. 興味を持ってくれないおもちゃが届くことがある
おもちゃのサブスクでは、基本的に各社のプランナーやおもちゃ選定のプロが子どもの月齢・発達に合った玩具を選んで送ってくれます。しかし、届いたすべてのおもちゃを子どもが気に入るとは限りません。時には親が期待していた反応と違い、子どもがまったく興味を示さないおもちゃが混ざっていることもあります。
子どもの好みは千差万別なので、これはある意味仕方のないことです。サブスクで提供される玩具は一般的に評価の高い知育玩具ですが、どんなに良いおもちゃでも子どもの性格やタイミングによっては遊んでくれない可能性があります。しかし、この「遊ばないおもちゃが届くかもしれない」というリスクをデメリットと感じる人もいるでしょう。せっかく料金を払って借りたのに、子どもが見向きもしないおもちゃがあればコストパフォーマンスが悪く感じられます。
こうしたミスマッチを避けるために、サービスによっては事前に好みをヒアリングしたり、嫌いなおもちゃのジャンルを伝えたりできる仕組みもあります。また、届いたおもちゃに子どもが興味を示さなかった場合、早めに交換を依頼できるサービスもあるので、それを利用するのもひとつの手です(プランによっては追加料金が必要な場合あり)。それでも完全に子どもの嗜好を当てるのは難しいため、この点に不満を感じやすい人はサブスクの利用を迷う傾向にあります。
一方、「買ってから遊ばないよりは、借りて合わない方がダメージが少ない」と前向きに捉える考え方もできます。サブスクなら子どもが興味を持たなかったおもちゃは返却して次に期待すれば良いだけなので、購入して無駄になるリスクを減らすことが可能です。子どもの好みは実際与えてみないと分からないものと割り切れる方には、このデメリットはそれほど大きくないでしょう。
7. 自宅にあるおもちゃと被ることがある
レンタルで届くおもちゃが、すでに自宅に持っているものと重複してしまうケースも考えられます。例えば、似たような積み木やパズル、すでに持っている知育玩具と同じもの(または類似品)が送られてくると、「これ家にあるのに…」と感じてしまうでしょう。同じようなおもちゃが2つあっても意味がないため、この点は無駄に思えてデメリットです。
特に、ご家庭におもちゃがたくさんある場合や兄姉からのお下がりが豊富な場合は、重複の可能性が高まります。ただ、この問題は事前に対策可能です。多くのサービスでは申込み時に「持っているおもちゃリスト」や好きなおもちゃの傾向をヒアリングする項目があり、持っているものは避けて選んでくれる仕組みがあります。例えばChaChaChaでは、既に持っている玩具の名前やジャンルを伝えておけば、重複しないよう配慮してくれると案内されています。とはいえ完全に被りをゼロにする保証はなく、情報を伝え忘れたり、新たに購入したおもちゃとタイミング悪く被ったりする可能性は否定できません。
「家に似たおもちゃが増えても構わない、小さい違いでも子どもは楽しめる」と考える方や、そもそもまだ手持ちのおもちゃが少ない初心者ママ・パパであれば、この問題はそれほど気にならないでしょう。逆に、すでに充実したおもちゃコレクションがあるご家庭では「今さら借りなくても家に十分ある」という状況になりがちです。そうした方にはおもちゃのサブスクはあまりメリットがなく、この点がデメリットとなる可能性が高いです。
8. 弁償しなければいけないことがある
レンタルサービスのため、借りたおもちゃを紛失したり破損した場合には弁償が必要になることがあります。子どもは遊び方が豪快だったり、パーツをどこかに隠してしまったりと、壊したり無くしたりするリスクはどうしてもゼロにできません。「もしおもちゃをダメにしてしまったらどうしよう…」と常に心配してしまうという声もあります。
実際には、通常の使用による傷や汚れ、小さな部品の紛失程度であれば弁償不要としているサービスがほとんどです(各社で補償ルールを定めています)。例えばトイサブ!では禁止事項に該当する行為による破損の場合500円程度、日常的な汚れや傷は基本無料となっており、ChaChaChaでも細かな傷は弁償不要だが主要部品を丸ごと紛失した場合は上限1,000円の費用負担というルールです。とはいえ、明らかに壊れて動かなくなった・重要な部品をなくしてしまった、といった場合には買取(弁償)扱いになる可能性があります。高額なおもちゃだと弁償額も高くなるため、利用中はヒヤヒヤするという人もいるでしょう。
このように、「壊したらどうしよう」というストレスを感じながら利用するのはデメリットです。特に活発で物を壊しがちな子がいる家庭や、細かいパーツの管理が苦手な方にはあまり向いていません。一方で、「もし壊れても仕方ない」と割り切れる人や、子どもがおもちゃを大切に扱える年齢なら、それほど心配は要らないでしょう。さらに、おもちゃサブスクでは紛失・破損時の対応も各社で工夫されており、保険オプションが用意されているサービスもあります(例:キッズ・ラボラトリーでは月額数百円で補償パックに加入可)。万一の際に大きな負担を負わなくて済む仕組みを選べば、安心して利用できます。いずれにせよ、契約前に弁償規定を確認し、自分が許容できる範囲かチェックすることが大切です。
9. レンタル数に制限がある
おもちゃのサブスクでは、一度に借りられるおもちゃの数に制限があります。各サービスやプランによって異なりますが、概ね一度に3〜6個程度のおもちゃをレンタルするのが一般的です(多いプランでも最大で10個前後)。つまり、家に届くおもちゃの数は上限が決まっており、自宅にある全てのおもちゃを総動員して遊ぶのと比べると、どうしてもラインナップが限られてしまいます。
「限られた数のおもちゃだけでは子どもが飽きてしまうのでは?」という懸念を持つ親御さんもいるでしょう。特に好奇心旺盛で次々と新しい遊びを求める子だと、6個程度では物足りなく感じることが想定されます。また兄弟姉妹がいる場合、ひとり分のプランだとおもちゃをシェアすることになるため、数が少ないと取り合いになる可能性もあります(※兄弟プラン対応のサービスもあります)。
この借りられるおもちゃの数が少ない点は、おもちゃを豊富に与えたい派の家庭にはデメリットです。自宅にたくさんおもちゃを常備している人にとっては、数個だけしか借りられないサブスクは物足りなく感じるでしょう。一方で、おもちゃが多すぎると片付けや収納が大変になるため、敢えて適量に絞りたいと考える家庭にはサブスクの個数制限がちょうど良い場合もあります。限られたおもちゃを集中的に遊ばせ、飽きた頃に交換する循環には、むしろ子どもの集中力を養ったり物を大事にする気持ちを育んだりするというメリットもあります。おもちゃの数が少ないことで散らかりにくく、管理しやすいという利点もあるでしょう。
要するに、たくさんの玩具に囲まれて自由に遊ばせたいタイプのご家庭には向かず、必要最低限の質の良いおもちゃで十分と考えるご家庭には合っていると言えます。申し込み時に選べるプランでレンタル個数を増やせる場合があるので、子どもの様子に合わせてプランを選択すると良いでしょう。
10. 対象年齢が限られている
おもちゃサブスクには、利用できる対象年齢が設定されています。多くのサービスは生後3ヶ月頃から、小学校入学前後(6歳〜8歳程度)までが対象です。例えばトイサブ!やChaChaChaでは0歳3ヶ月~6歳が基本の対象年齢範囲になっており、キッズ・ラボラトリーはサービスによって8歳くらいまで対応しています。裏を返せば、それ以上の年齢の子どもにはサービスを提供していないか、提供していてもラインナップが非常に限られています。
そのため、子どもが成長して対象年齢を超えた時点でサブスクは卒業せざるを得ません。大体は幼稚園〜年長さんくらいでサブスクを終えるケースが多く、長くても小学校低学年まででしょう。これはデメリットというより当然のことではありますが、「せっかく慣れたサービスも子どもが大きくなれば使えなくなる」という点で少し寂しいところです。また、新生児~生後2ヶ月くらいの本当に小さい赤ちゃんにはまだおもちゃ遊びが難しいため、この期間もサブスクは実質的に不要です。
まとめると、おもちゃのサブスクは主に乳幼児〜未就学児向けのサービスなので、子どもがある程度大きくなったら自然と卒業になることを念頭に置く必要があります。もしお子さんがすでに5〜6歳以上であれば利用できる期間は短いですし、小学生以上のお子さんには基本的にメリットがありません。そのため、そういった年齢のお子さんをお持ちの家庭にはおすすめしません。一方、0〜5歳くらいまでの間で子どもの成長に合わせて最大限に活用しようという前提であれば、対象年齢の制限は問題にならないでしょう。サービスによっては発達に不安がある子向けの特別プラン(例:ChaChaChaの特別支援教育プラン)や、上の子と下の子で一緒に利用できる兄弟パックなども用意されています。自分の子どもの年齢にフィットするサービスを選ぶことが大切です。

自分で選べるおもちゃ/育児用品の定額レンタル!今ならトライアルプランでかなりお得!
デメリット以外でおもちゃのサブスクをやめる理由
上記のようなデメリット以外にも、利用者がおもちゃのサブスクをやめた理由として挙げるものがいくつかあります。必ずしもサービスに不満があるわけではなく、環境の変化や子どもの成長によるポジティブな理由で解約するケースも多いです。ここでは、デメリット以外でサブスクを終了する主な理由を3つ紹介します。
保育園や幼稚園に入ったから
お子さんが保育園や幼稚園に入園したことをきっかけに、サブスクを解約する家庭は多いです。園に通い始めると日中はほとんど家にいませんし、保育園ではたくさんの遊具やおもちゃで遊べる環境があります。その結果、自宅で遊ぶ時間や必要性がグッと減ってしまいます。いくら良いおもちゃが定期的に届いても、子どもが家にいなければ活用できません。実際、「保育園に入り自宅で過ごす時間が減ったので解約した」「半年ほど利用して満足したが、今後は保育園のおもちゃで十分」という声もあります。
このように生活リズムが変わって家で遊ぶ時間が少なくなれば、おもちゃサブスクを利用する価値を感じにくくなるでしょう。保育園や幼稚園に通う前の、長く家で過ごす時期には重宝したけれど、入園後は必要なくなるというのは自然な理由です。
外で遊ぶことが増えたから
子どもが成長するにつれて公園や屋外で遊ぶ時間が増えたことも、サブスクをやめる理由としてよくあります。特に天気の良い日は外遊びを優先したり、習い事やお出かけが増えて家でおもちゃで遊ぶ時間が少なくなったりすると、定期的に新しいおもちゃが届いても消化しきれません。せっかく借りても、ほとんど使わず返却するようではもったいないですよね。
「子どもが活発になって家より外で遊びたがる」「公園や児童館で十分遊んでエネルギーを発散している」という場合、おもちゃサブスクの必要性は下がります。外遊び中心の生活スタイルになった家庭では、一旦サービスをお休み・解約する判断をすることもあるでしょう。これはデメリットというより、ライフスタイルの変化による卒業理由と言えます。
好きなおもちゃが見つかったから
おもちゃのサブスクを利用する中で、子どもの特に好きなおもちゃや遊びのジャンルがはっきりしてきたためにやめる、というケースもあります。サブスクを通じて様々なおもちゃを試すことで、「うちの子は◯◯系のおもちゃが大好きなんだ」と分かることがあります。例えばブロック遊びが性に合って集中して遊ぶようになった、とか、プラレールや特定のキャラクターものに夢中になった等です。
こうして子どものお気に入りや定番のおもちゃが決まってきたなら、毎回新しい玩具を借りなくても、その好きなおもちゃを中心に遊ばせれば十分という考えになります。「これ以上サブスクで色々試さなくても、もう子どもが本当に好きなものがわかった」という段階になったら、サブスクを卒業するひとつのタイミングです。実際に「子どもの好きなおもちゃが明確になったので解約した」という声もあります。お気に入りを購入して存分に遊ばせた方が良いと判断するわけですね。
このように、おもちゃサブスクは永遠に続けるものではなく、子どもの成長や環境の変化に応じて「卒業」するサービスです。上記のような理由で、円満に役目を終えるケースも多いことを覚えておきましょう。

自分で選べるおもちゃ/育児用品の定額レンタル!今ならトライアルプランでかなりお得!
おもちゃのサブスクのメリットは?
ここまでデメリットや解約理由を中心に見てきましたが、もちろんおもちゃのサブスクにはたくさんのメリットも存在します。最後に、主なメリットを簡潔にまとめておきます。
- 常に年齢に合った知育玩具で遊べる: 月齢・成長に合わせたおもちゃが定期的に届くため、子どもの発達に適した遊びを提供できます。専門家が選ぶ良質なおもちゃで遊ぶことで、モンテッソーリ教育的な知育効果も期待できます。
- おもちゃの購入・処分の手間が省ける: 気に入ったおもちゃ以外は定期的に返却するため、家におもちゃが増えすぎて収納に困る心配が減ります。飽きたおもちゃを処分する手間も不要で、常に新鮮な遊び環境を保てます。
- 経済的に色々なおもちゃを試せる: 高価な知育玩具や大型のおもちゃでも定額で試せるため、購入するより費用を抑えて幅広い種類のおもちゃを体験できます。買って遊ばなかったという無駄もなくなり、コストパフォーマンスが高いです。
- 専門家のサポートでおもちゃ選びが楽: プランナーや保育士など、プロが子どもの興味・発達に合うおもちゃを提案してくれるサービスもあります。「どんなおもちゃを与えたら良いか分からない」という悩みが減り、育児の負担軽減につながります。
- 環境に優しくサステナブル: 複数家庭でおもちゃをシェアすることで、使い捨てのおもちゃを減らせます。大量のおもちゃを買って捨てるより環境負荷が低く、サステナビリティの観点でも注目されています。
このように、おもちゃのサブスクはデメリットを上回る多くのメリットがあるサービスです。ポイントは、各家庭のニーズにそのメリットが合致するかどうかです。メリット・デメリット双方を理解した上で、自分たちにとって有益か判断すると良いでしょう。

自分で選べるおもちゃ/育児用品の定額レンタル!今ならトライアルプランでかなりお得!
おもちゃのサブスクをおすすめしない人とは
以上の内容を踏まえ、おもちゃのサブスクをおすすめしない人と、反対におすすめできる人の特徴を整理します。サービスの向き不向きを見極める参考にしてください。
おもちゃのサブスクをおすすめしない人: (以下のような方には利用をあまり推奨しません)
- お下がりや既に持っているおもちゃが十分あり、新しいおもちゃを増やしたくない人
- 他の子どもが使った中古のおもちゃに対する抵抗が強く、衛生面の心配が拭えない人
- 毎月の費用を極力抑えたい節約志向の人や、定期支出の増加を負担に感じる人
- おもちゃの返却や交換などの手続きが面倒に思えてしまい、手間をかけたくない人
- 子どもが気に入ったおもちゃは手元に置いておきたいと考える人(貸し借りより購入派の人)
- 決まった期間継続利用する自信がなく、短期間でやめる可能性が高い人
おもちゃのサブスクをおすすめできる人: (以下のような方には利用するメリットが大きいでしょう)
- 常に子どもの発達段階に合った知育玩具で遊ばせてあげたいと考える人
- 家におもちゃが増えすぎるのを防ぎたい、賢くおもちゃを循環させたいミニマル志向の人
- 毎回のおもちゃ選びに悩んでいる初めての子育て世帯や、プロのアドバイスを活用したい人
- 色々なおもちゃを試して子どもの興味関心を広げたい人(モンテッソーリ教育などにも関心がある)
- 高価なおもちゃをいきなり買うのは不安なので、まずレンタルで試してみたいと考える人
- 月数千円のプラン料金でおもちゃを定期レンタルすることに納得感があり、家計的にも許容できる人
自分やお子さんのタイプが「おすすめできない人」に当てはまる場合、無理に利用しても不満が残る可能性があります。逆に「おすすめの人」に当てはまる場合は、おもちゃのサブスクのメリットを存分に享受できるでしょう。ぜひ、各家庭の状況に合わせて検討してみてください。
おすすめのおもちゃサブスクはこちらをチェック!
おもちゃのサブスクは現在さまざまな会社から提供されており、それぞれ料金や特徴が異なります。デメリット・メリットを理解した上で「じゃあ具体的にどのサービスが良いの?」と気になった方は、おすすめのおもちゃサブスクを比較した別記事をぜひチェックしてみてください。主要なおもちゃサブスク各社(トイサブ!、ChaChaCha、キッズ・ラボラトリー、And TOYBOXなど)の特徴や料金プランを一覧で比較し、ご家庭にピッタリのサービスを見つけるお手伝いをいたします。
▶︎ 関連記事:「おもちゃ サブスク 比較」 – 各サービスの詳細とおすすめポイントを紹介していますので、興味のある方は参考にしてください。
おもちゃのサブスクは、上手に活用すれば育児の強い味方になります。デメリットとメリットを見極めつつ、ご家庭に合ったサービス選びをしてみましょう。子どもの笑顔と健やかな成長をサポートする、素敵なおもちゃとの出会いがありますように。

自分で選べるおもちゃ/育児用品の定額レンタル!今ならトライアルプランでかなりお得!