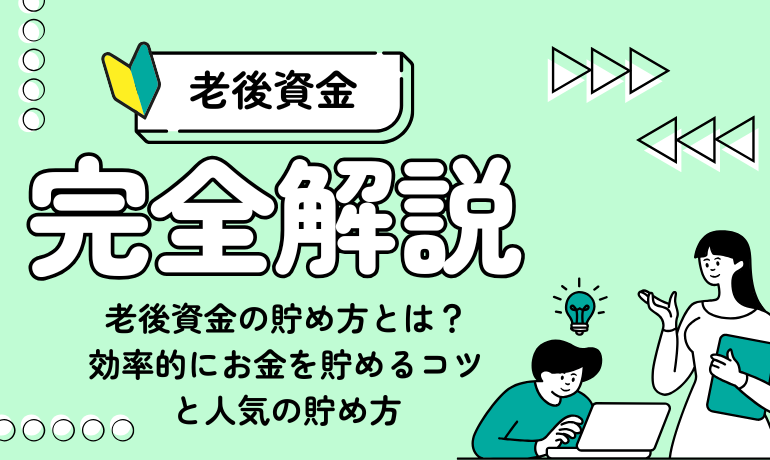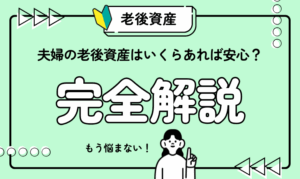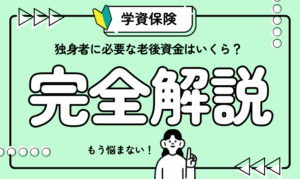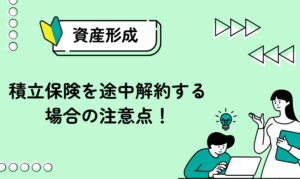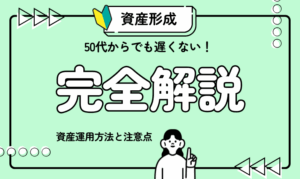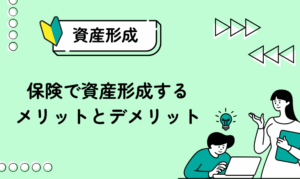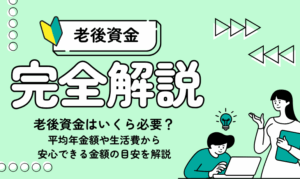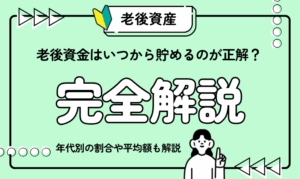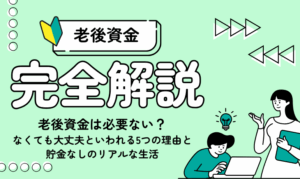「人生100年時代」といわれる現代、ゆとりある老後生活を送るためには、公的年金に加えて自分自身で資産形成を行うことの重要性が増しています。「老後資金を貯めないといけないのはわかるけど、何から始めたらいいかわからない」「どうすれば効率的に貯められるの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、老後資金をこれから準備しようと考えている方に向けて、貯め方の基本的なコツから、人気の制度を活用した具体的な方法、そして年代別のおすすめアプローチまでを網羅的に解説します。この記事を読めば、ご自身の状況に合った老後資金の貯め方が見つかり、着実に準備を始める第一歩を踏み出せるはずです。
老後資金の貯め方とは?成功する6つのコツ
老後資金の準備は、特別なことではありません。日々の少しの工夫と計画的な行動が、将来の大きな安心につながります。ここでは、資産形成を成功させるために押さえておきたい6つの基本的なコツを解説します。
生活費を見直して支出を減らす
老後資金を確実に貯めるための第一歩は、「支出を減らすこと」です。収入を増やすのは簡単ではありませんが、支出の管理は今日からでも始められます。まずは家計簿アプリやノートなどを活用して、自分や家族が毎月何にいくら使っているのかを正確に把握することから始めましょう。
支出には、毎月ほぼ一定額が出ていく「固定費」と、月によって変動する「変動費」があります。見直しの効果が大きいのは、一度手続きすれば節約効果が続く「固定費」です。
<見直したい固定費の例>
住居費:
現在の収入やライフプランに対して家賃が高すぎないか検討する。持ち家の場合は、住宅ローンの借り換えで金利負担を軽減できないか確認する。
通信費:
スマートフォンを大手キャリアから格安SIMに乗り換えるだけで、月々数千円の節約につながるケースが多くあります。不要なオプションの解約も有効です。
保険料:
加入している生命保険や医療保険の内容が、現在のライフステージに合っているか定期的に見直しましょう。保障内容の重複や、必要以上の保障は保険料の無駄につながります。
サブスクリプションサービス:
利用頻度の低い動画配信サービスや雑誌の定期購読など、不要なものがないかチェックし、解約を検討します。
固定費の見直しと並行して、食費や交際費、趣味の費用といった「変動費」の無駄も探してみましょう。ただし、変動費の過度な節約はストレスにつながる可能性もあるため、無理のない範囲で「メリハリ」をつけることが大切です。
先取り貯金をする
「給料が余ったら貯金しよう」と考えていると、ついつい使いすぎてしまい、なかなかお金は貯まりません。そこでおすすめなのが「先取り貯金」です。これは、毎月の収入があったら、まず先に貯金する分を取り分けてしまう方法です。
例えば、「毎月3万円を老後資金にする」と決めたら、給料日に普通預金口座から3万円を別の口座に移します。残ったお金で1カ月間やりくりする習慣をつけることで、意思の力に頼らず、半ば強制的に貯蓄の仕組みを作ることができます。
金融機関の「自動積立定期預金」などのサービスを利用すれば、毎月決まった日に決まった金額を自動で定期預金口座に振り替えてくれるため、手間もかからず、忘れずに実行できるのでおすすめです。
老後資金専用の口座を開く
先取り貯金で確保したお金は、普段使いの生活費用口座とは別の「老後資金専用口座」で管理しましょう。目的を「老後資金」に限定することで、他の用途(旅行や買い物など)に安易に使ってしまうのを防ぐことができます。
口座を分けることで、老後資金が今いくら貯まっているのかが一目でわかり、モチベーションの維持にもつながります。「この口座のお金は、将来の自分のためのもの」という意識を持つことが、長期的な資産形成を続ける上で非常に重要です。
長期的かつ計画的に準備する
老後資金の準備は、マラソンのような長期戦です。できるだけ早くから始めることで、時間を味方につけることができます。その最大のメリットが「複利効果」を得られることです。
複利とは、投資で得た利益(利息や分配金など)を元本に加えて再投資し、その合計額に対してさらに利益が生まれる仕組みのことです。雪だるま式に資産が増えていくイメージで、運用期間が長ければ長いほどその効果は大きくなります。
例えば、毎月3万円を年利3%で30年間積み立て投資した場合、元本1,080万円(3万円×12カ月×30年)に対し、運用収益は約667万円となり、合計で約1,747万円になります。同じ条件で、開始が10年遅れて20年間だった場合、元本720万円に対し、運用収益は約265万円、合計は約985万円です。この差が、早くから始めることの大きなアドバンテージです。
「いつから貯めるべきか」と悩んでいるなら、答えは「今すぐ」です。少額からでもいいので、一日でも早くスタートを切ることが、将来の自分を助けることにつながります。
貯金だけでなく資産運用で増やす
現在の日本は、超低金利時代が長く続いています。銀行の定期預金にお金を預けておくだけでは、ほとんど利息はつきません。さらに、物価が上昇するインフレが起きた場合、お金の価値そのものが目減りしてしまうリスクもあります。例えば、年2%のインフレが起きると、今の100万円の価値は1年後には実質的に98万円になってしまうのです。
このインフレリスクに備え、預貯金で生活防衛資金(病気や失業など、万が一の事態に備えるお金。一般的に生活費の半年~1年分が目安)を確保しつつ、余剰資金は積極的に「資産運用」に回して「増やす」ことを考えるのが、現代の資産形成のセオリーです。
もちろん、投資には元本割れのリスクが伴います。しかし、後述するNISAやiDeCoといった制度を活用し、「長期・積立・分散」という投資の基本原則を守ることで、リスクを抑えながら安定的なリターンを目指すことが可能です。
収入を増やすことも検討しよう
支出を減らし、資産運用を行うことと同時に、「収入を増やす」という選択肢も視野に入れると、資産形成のスピードは格段に上がります。
会社員であれば、資格取得やスキルアップを通じて昇進・昇給を目指す、より待遇の良い会社へ転職するといった方法が考えられます。また、近年では副業を認める企業も増えてきました。平日の夜や休日など、空いた時間を活用して副業に取り組むことで、月に数万円でも収入を増やすことができれば、その分を丸ごと貯蓄や投資に回すことができます。
配偶者が専業主婦(主夫)の家庭であれば、パートで働き始めることも大きな力になります。扶養の範囲内で働くとしても、年間100万円程度の収入があれば、家計に大きなゆとりが生まれるでしょう。
効率的に増やそう!老後資金の人気の貯め方3選
老後資金を効率的に準備するためには、国が用意した税制優遇制度を最大限に活用しない手はありません。ここでは、特に人気が高く、多くの人が利用している3つの方法「NISA」「iDeCo」「個人年金保険」について、それぞれの特徴やメリット、注意点を詳しく解説します。
NISA(少額投資非課税制度)
NISAは、個人投資家のための税制優遇制度です。通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をして利益(配当金、分配金、譲渡益)が出ると、約20%の税金がかかります。しかし、NISA口座内で得た利益には、この税金が一切かかりません。
2024年からは新しいNISA制度がスタートし、より使いやすく、パワフルな制度に生まれ変わりました。
<新NISAのポイント>
- 制度の恒久化・非課税保有期間の無期限化:
いつでも始められ、ずっと非課税で運用できます。 - 年間投資枠の拡大:
- つみたて投資枠:
年間120万円。長期・積立・分散投資に適した、国が厳選した低コストの投資信託などが対象。 - 成長投資枠:
年間240万円。投資信託のほか、個別株やETF(上場投資信託)など、比較的幅広い商品が対象。
- つみたて投資枠:
- 生涯非課税保有限度額の設定:
生涯にわたって非課税で保有できる上限額として1,800万円(簿価残高ベースで管理)が設定されました。 - 売却枠の再利用が可能:
NISA口座内の商品を売却した場合、その商品の簿価(取得価額)分の非課税枠が翌年以降に復活し、再利用できます。
メリット:
運用益が非課税:
最大のメリットです。利益がそのまま手元に残るため、効率的な資産形成が可能です。
いつでも引き出し可能:
iDeCoとは異なり、必要な時にはいつでも売却して現金化できます。ライフイベントの変化にも柔軟に対応可能です。
少額から始められる:
金融機関によっては月々1,000円や100円といった少額から積立設定が可能です。
注意点・リスク:
元本保証ではない:
投資であるため、購入した金融商品の価格が下落し、元本割れするリスクがあります。
損益通算・繰越控除ができない:
NISA口座での損失は、他の課税口座(特定口座や一般口座)で得た利益と相殺(損益通算)することはできません。また、損失を翌年以降に繰り越すこと(繰越控除)も不可能です。
老後資金形成の初心者の方は、まずはリスクが比較的抑えられ、コツコツ積み立てられる「つみたて投資枠」から始めるのがおすすめです。全世界株式や全米株式に連動するインデックスファンドなどが、長期的な資産形成の第一歩として人気を集めています。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCo(イデコ)は、自分で掛金を拠出し、自分で運用方法を選んで資産を形成する「私的年金」制度です。公的年金に上乗せする形で、より豊かな老後生活を目指すための制度といえます。
メリット:
iDeCoの最大の魅力は、その強力な税制優遇措置にあります。
掛金が全額所得控除:
毎月の掛金がその年の所得から全額控除されます。これにより、所得税と住民税が軽減されます。例えば、毎月2万円(年間24万円)を拠出している課税所得300万円(所得税率10%・住民税率10%)の会社員の場合、年間で約4.8万円(24万円 × 20%)の節税効果が期待できます。
運用益が非課税:
NISAと同様に、運用期間中に得た利益(利息、分配金など)には税金がかかりません。利益が再投資されることで、複利効果を最大限に活かすことができます。
受け取り時にも控除がある:
60歳以降に年金または一時金として受け取る際にも、「公的年金等控除」や「退職所得控除」といった税制上の優遇措置が適用されます。
注意点・リスク:
原則60歳まで引き出せない:
年金制度という性格上、途中で資金が必要になっても、原則として60歳になるまで引き出すことはできません。老後まで使う予定のない資金で始めることが大前提です。
各種手数料がかかる:
加入時や毎月の運用期間中、金融機関所定の手数料(口座管理手数料など)がかかります。
元本保証ではない:
NISAと同様、選んだ運用商品によっては元本割れのリスクがあります。(ただし、定期預金などの元本確保型商品も選択可能です)
iDeCoは、節税メリットを享受しながら、半ば強制的に老後資金を貯められる非常に優れた制度です。特に、所得控除の恩恵を受けられる現役世代にとっては、活用しない手はないといえるでしょう。
個人年金保険
個人年金保険は、生命保険会社などが提供する貯蓄型の保険商品です。毎月一定の保険料を払い込み、契約時に定めた年齢(60歳や65歳など)から、一定期間または一生涯にわたって年金形式でお金を受け取ることができます。
メリット:
計画的に貯蓄できる:
保険料が口座から自動で引き落とされるため、着実に老後資金を準備できます。
元本保証に近い安定性:
運用を保険会社に任せるため、日々の価格変動を気にする必要がありません。契約時に将来受け取れる年金額が確定している商品が多く、計画が立てやすいのが特徴です。(※変額個人年金保険など、運用実績によって受取額が変動するタイプもあります)
生命保険料控除の対象:
一定の要件を満たす個人年金保険料税制適格特約を付加した場合、支払った保険料に応じて「個人年金保険料控除」が適用され、所得税・住民税が軽減されます。
注意点・リスク:
予定利率が低い:
現在の低金利環境では、保険の予定利率も低く設定されており、NISAやiDeCoでの運用に比べて大きなリターンは期待しにくい傾向にあります。
インフレに弱い:
受取額が固定されている商品は、将来インフレが進行した場合、お金の価値が実質的に目減りしてしまうリスクがあります。
中途解約すると元本割れの可能性:
契約から短い期間で解約すると、解約返戻金が払込保険料総額を下回り、元本割れするケースがほとんどです。
投資のリスクは取りたくないけれど、銀行預金よりは少しでも有利に、かつ計画的に老後資金を準備したい、という安定志向の方に向いている選択肢といえるでしょう。
年代別:老後資金のおすすめの貯め方
老後資金の貯め方は、年齢やライフステージによって最適なアプローチが異なります。ここでは、20代から60代まで、それぞれの年代ごとのおすすめの貯め方や考え方のコツを紹介します。
20代におすすめの方法
20代は、老後まで40年以上の時間があり、「時間」という最大の武器を持っています。この時期に資産形成を始める最大のメリットは、長期運用による「複利効果」を最大限に享受できることです。
- コツとポイント:
- 少額からでも始める:
まずは月々5,000円や1万円でも構いません。「先取り貯金」を習慣づけ、資産運用を始める経験をすることが重要です。 - iDeCoとNISA(つみたて投資枠)の活用:
税制優遇の恩恵を受けながら、長期的な視点でコツコツ積立投資を行いましょう。特に、iDeCoは所得控除による節税効果が大きく、若いうちから始めることで長期間にわたり恩恵を受けられます。 - リスク許容度は高めに:
運用期間が長いため、一時的な価格の下落があっても回復を待つ余裕があります。全世界株式インデックスファンドなど、ある程度リスクを取って高いリターンが期待できる商品を中心にポートフォリオを組むのも有効な戦略です。
- 少額からでも始める:
30代におすすめの方法
30代は、キャリアアップによる収入増が期待できる一方、結婚、出産、住宅購入といった大きなライフイベントが集中する時期でもあります。教育資金や住宅ローン返済など、老後資金以外にもお金が必要になるため、計画的な資金管理が求められます。
- コツとポイント:
- ライフプランと資金計画の具体化:
家族構成やマイホームの予定などを踏まえ、教育資金や住宅資金と並行して、老後資金をいくら、どのように準備していくかの具体的な計画を立てましょう。 - iDeCoとNISAの併用と増額:
20代から継続している場合は、収入の増加に合わせて掛金や積立額の増額を検討します。iDeCoで着実に節税しながら老後資金を確保し、NISAで流動性を保ちながら資産拡大を目指す、といった併用が効果的です。 - リスクバランスの見直し:
ライフイベントでお金が必要になった際に慌てないよう、資産の一部を預貯金や債券などの比較的安全な資産で確保しておくなど、リスクのバランスを意識し始めましょう。
- ライフプランと資金計画の具体化:
40代におすすめの方法
40代は、収入がピークに達する人が多い一方で、子どもの教育費や住宅ローンの負担が最も重くなる時期でもあります。まさに資産形成の中核を担う世代であり、老後への意識も高まってきます。
- コツとポイント:
- 資産の棚卸しと目標の見直し:
これまで形成してきた資産(預貯金、保険、有価証券など)をすべて洗い出し、現状を正確に把握します。その上で、老後の目標額に対して順調に進んでいるかを確認し、必要であれば計画を修正します。 - NISAの非課税枠を積極的に活用:
収入に余裕が出てきたら、NISAの非課税枠(年間最大360万円)を積極的に活用し、資産形成のペースを加速させましょう。退職金が期待できない場合などは、特にこの時期の頑張りが重要になります。 - iDeCoの拠出も継続: 節税メリットは依然として大きいため、掛金の上限まで拠出を続けたいところです。
- 資産の棚卸しと目標の見直し:
50代におすすめの方法
50代になると、子どもの独立などで教育費の負担が軽くなる一方、自身の健康問題や親の介護なども現実味を帯びてきます。老後が目前に迫り、資産形成の「仕上げ」と「守り」を意識する時期です。
- コツとポイント:
- 退職金の見込み額を確認:
会社の退職金制度を確認し、おおよその受給額を把握します。退職金と現在の自己資産、公的年金を合わせて、老後の生活設計をより具体的にシミュレーションしましょう。 - リスクを抑えた運用へシフト:
老後資金を使い始めるまで時間がないため、大きな損失を避けることが重要になります。株式などリスクの高い資産の比率を少しずつ下げ、債券や預貯金など安定的な資産の割合を増やしていく「リバランス」を検討します。 - 「出口戦略」を考え始める:
60歳以降、資産をどのように取り崩していくかを考え始める時期です。NISA口座の資産は非課税で引き出せるため、生活費の補填に充てるなど、具体的な活用法を検討しておきましょう。
- 退職金の見込み額を確認:
60代におすすめの方法
60代は、多くの人が定年退職を迎え、セカンドライフが始まる時期です。退職金というまとまったお金をどう扱うかが、その後の生活を大きく左右します。
- コツとポイント:
- 退職金の賢い管理・運用:
受け取った退職金を、金融機関の言われるがままにリスクの高い商品に一括投資するのは避けましょう。まずは生活防衛資金を確保した上で、残りを安全性の高い預貯金や個人向け国債、そして一部をNISAなどを活用して低リスクで運用するのが基本です。 - 計画的な取り崩し:
公的年金の受給額を確認し、不足分を自己資産からいくら取り崩していくかを計画します。資産寿命を延ばすため、「定率で取り崩す」などルールを決めておくと良いでしょう。 - NISAの生涯非課税枠を活用:
60代からでもNISAは活用できます。退職金の一部をNISA口座に移し、低リスクの分配金が出る投資信託などで運用すれば、非課税の分配金を生活費の足しにすることも可能です。生涯使える非課税枠なので、長期的な資産の置き場所として有効です。
- 退職金の賢い管理・運用:
老後資金はいくら必要?平均の貯金額も知りたい!
老後資金の準備を始めるにあたり、多くの人が気になるのが「いったい、いくら必要なのか?」そして「他の人は、どれくらい貯めているのか?」という点でしょう。ここでは、必要な老後資金の目安と、年代別の平均的な貯金額について解説します。
必要な老後資金の目安
かつて金融庁の報告書をきっかけに「老後2,000万円問題」という言葉が話題になりました。これは、高齢夫婦無職世帯では、年金などの収入だけでは毎月の生活費を賄えず、約2,000万円の貯蓄の取り崩しが必要になるという試算でした。
これはあくまでひとつのモデルケースであり、必要な老後資金は、その人のライフスタイル(どこに住むか、どんな生活を送りたいか)、家族構成、健康状態、そして受け取れる公的年金の額によって大きく異なります。
総務省の「家計調査報告(家計収支編)2023年」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の1カ月の収支は以下のようになっています。
- 実収入: 244,917円(うち社会保障給付(公的年金など)が220,019円)
- 消費支出: 250,677円
- 不足分: 5,760円
このデータだけ見ると不足額は小さいように見えますが、税金や社会保険料などの「非消費支出(約3.1万円)」を含めると、毎月約3.7万円の赤字となります。仮に65歳から90歳までの25年間、この赤字が続くと仮定すると、
の不足が生じる計算です。さらに、これはあくまで平均的な生活費の話です。実際には、以下のような臨時的な支出も考慮しておく必要があります。
- 介護費用: 生命保険文化センターの調査では、介護にかかった費用(住宅改修、介護用品購入など)の合計は平均で765万円、月々の費用は平均8.3万円とされています。
- 住宅のリフォーム費用: 持ち家の場合、老朽化に伴うリフォーム費用がかかります。
- 医療費: 病気やケガによる自己負担額の増加。
- 趣味や旅行などの娯楽費: ゆとりのある生活を送るための費用。
これらの費用を考えると、やはり1,500万円~2,000万円、あるいはそれ以上をひとつの目安として、自分自身の理想の老後生活をイメージしながら目標額を設定することが重要です。
平均的な老後資金の貯金額
では、他の人は実際にどれくらいの金融資産を保有しているのでしょうか。金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年)」によると、二人以上世帯の年代別の金融資産保有額は以下の通りです。
| 年代 | 平均値 | 中央値 |
| 20代 | 224万円 | 44万円 |
| 30代 | 563万円 | 150万円 |
| 40代 | 825万円 | 200万円 |
| 50代 | 1,253万円 | 300万円 |
| 60代 | 1,819万円 | 550万円 |
ここで注目すべきは「平均値」と「中央値」の違いです。
この表を見ると、どの年代でも平均値が中央値を大きく上回っており、一部の人が多くの資産を保有している一方で、貯蓄がそれほど多くない世帯もかなりいることがわかります。特に、働き盛りの30代~50代でも中央値は150万円~300万円となっており、多くの家庭が資産形成の途上にあることがうかがえます。
他の人の金額はあくまで参考です。大切なのは、平均や中央値に一喜一憂するのではなく、自分自身の目標に向かって、今日から着実に一歩を踏み出すことです。
まとめ:自分に合った貯め方を見つけ、今日から始めよう
老後資金の準備は、将来の自分自身への最高の贈り物です。豊かなセカンドライフを送るためには、公的年金だけに頼るのではなく、若いうちから計画的に資産形成を進めていくことが不可欠です。
まずは、今回ご紹介した「6つの成功のコツ」を実践することから始めてみましょう。
- 生活費を見直し、支出を減らす
- 先取り貯金で確実に貯める
- 老後資金専用の口座で管理する
- 長期的視点で計画的に準備する
- 貯金だけでなく資産運用で増やす
- 収入を増やす努力もする
そして、税制優遇のメリットが大きい「NISA」や「iDeCo」といった制度を積極的に活用し、効率的に資産を増やしていくことが重要です。
老後資金の準備に「遅すぎる」ということはありませんが、「早すぎる」ということもありません。ご自身の年代やライフプランに合った方法で、まずは少額からでも第一歩を踏み出してみましょう。今日の小さな一歩が、20年後、30年後のあなたの笑顔と安心につながるはずです。