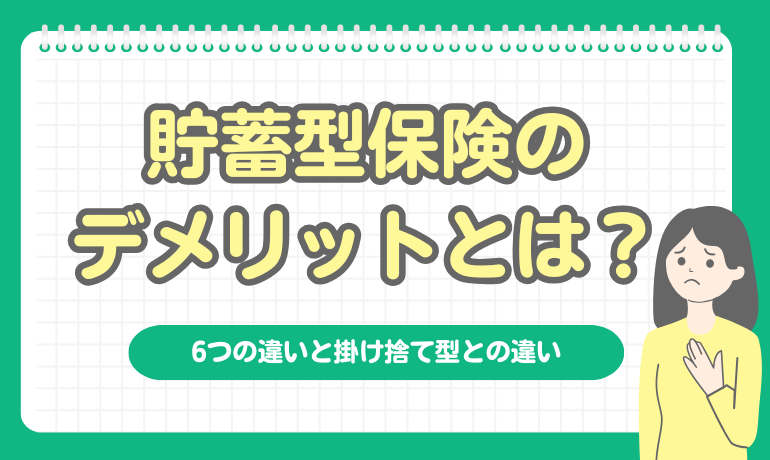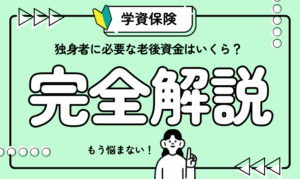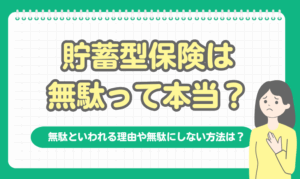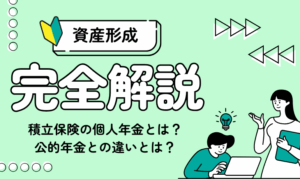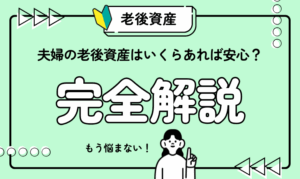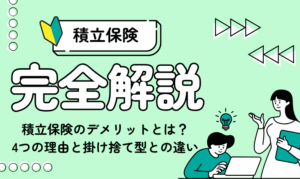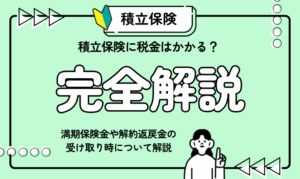「万一への備えと、将来のための貯蓄を同時にできる」
そんな魅力的なキャッチコピーで紹介されることが多い「貯蓄型保険」。しかし、インターネットやSNSで検索すると、「貯蓄型保険はやめとけ」「保険で貯蓄をしてはいけない」といったネガティブな意見も多く見られます。
なぜ、貯蓄型保険は「やめとけ」といわれてしまうのでしょうか。
この記事では、貯蓄型保険への加入を検討している方や、すでに加入しているけれど本当にこのままで良いのか不安に感じている方に向けて、以下の点を詳しく解説します。
- 貯蓄型保険の6つの具体的なデメリット
- 掛け捨て型保険との根本的な違い
- 貯蓄型保険の主な種類と、それぞれが持つ特有のデメリット
- デメリットを理解した上で、それでも貯蓄型保険が向いている人の特徴
- もし加入後に後悔した場合の、最適な対処法
この記事を最後まで読めば、貯蓄型保険のメリット・デメリットを正しく理解し、ご自身のライフプランやお金に対する価値観に本当に合っているのかを判断できるようになります。保険選びで後悔しないために、ぜひじっくりと読み進めてください。
貯蓄型保険の6つのデメリット
貯蓄型保険が「やめとけ」といわれる背景には、金融商品としての特性や、他の選択肢(掛け捨て型保険、投資など)と比較した際の明確なデメリットが存在します。
ここでは、貯蓄型保険を検討する上で必ず理解しておきたい6つのデメリットを解説します。なぜ「ダメな理由」として挙げられるのか、その背景までしっかり理解し、後悔のない選択につなげましょう。
1. 掛け捨て型より保険料が高い
貯蓄型保険の最も分かりやすいデメリットは、掛け捨て型保険と比較して月々の保険料が格段に高いことです。
【なぜ保険料が高いのか?】
つまり、貯蓄型保険は「保障」と「貯蓄」という2つの機能を1つの商品で実現しようとするため、その分保険料が高くなるのです。
【家計への影響】
例えば、30歳男性が死亡保障300万円を確保する場合を考えてみましょう。
※保険会社や商品、契約条件により保険料は異なります。
同じ保障額でも、月々の支払いは数千円単位で変わってきます。この差額は、年間で数万円、払込期間全体では数十万円から百万円以上の大きな差になる可能性もあります。
特に、子どもの教育費や住宅ローンなどで家計に余裕がない時期に高い保険料を払い続けるのは、大きな負担となりかねません。保険料の支払いが困難になり、結果的に後述する「元本割れ」のリスクを抱えながら解約せざるを得ない状況に陥ることも、「やめとけ」といわれる大きな理由の一つです。
保険を検討する際は、まず「自分に必要な保障は何か」を明確にし、その保障を確保するためのコストとして保険料が妥当かどうかを判断することが重要です。
2. 途中解約すると元本割れすることが多い
貯蓄型保険の最大の落とし穴ともいえるのが、払込期間の途中で解約すると、支払った保険料の総額よりも少ない金額しか戻ってこない「元本割れ」のリスクが高いことです。
銀行預金であれば、いつでも預けた金額(元本)を引き出すことができますが、貯蓄型保険は全く性質が異なります。
【なぜ元本割れが起こるのか?】
支払った保険料の一部は、保険会社の運営経費や人件費、契約の締結・維持に必要な費用(事業費)として使われます。そのため、解約時には「解約控除」としてこれらの費用が差し引かれ、特に契約から年数が浅いほど、戻ってくるお金(解約返戻金)は払込保険料総額を大きく下回ります。
多くの貯蓄型保険では、払込保険料総額が解約返戻金を上回る(=元本割れしない)までには、10年、20年といった長い年月、あるいは保険料の払込が完了するまで待たなければなりません。
ライフステージの変化は誰にでも起こり得ます。
- 急な失業や収入減
- 子どもの進学や結婚による予期せぬ出費
- 住宅購入の頭金が必要になった
このような不測の事態で現金が必要になった際、貯蓄のつもりで続けてきた保険を解約したら、払った分よりも損をしてしまう。この柔軟性の低さが、貯蓄型保険が「いざという時に頼りにならない」といわれる所以です。
3. インフレで資産価値が目減りする
インフレ(インフレーション)とは、物価が継続的に上昇し、相対的にお金の価値が下がることです。例えば、今まで100円で買えていたジュースが120円に値上がりした場合、同じ100円でできることが減るため、お金の価値は実質的に下がったことになります。
貯蓄型保険は、このインフレに非常に弱いというデメリットを持っています。
多くの貯蓄型保険は、契約時に定められた「予定利率」で将来受け取れる満期金や年金額が固定されています。現在の日本では低金利が続いているため、この予定利率も低い水準で設定されています。
仮に、年率0.5%の予定利率で30年後に500万円を受け取れる保険に加入したとします。しかし、もしこの30年間で年平均2%のインフレが続いた場合、30年後の500万円の価値は、現在の価値に換算すると約276万円まで目減りしてしまいます。
つまり、額面では500万円を受け取れても、そのお金で買えるモノやサービスの量は、契約時に想定していたものの半分程度になってしまう可能性があるのです。
将来の学資金や老後資金といった長期的な資産形成を目的とする場合、このインフレリスクを考慮しないと、「お金は貯まったけれど、これでは足りない」という事態に陥る危険性があります。
4. 高い返戻率が期待できない
貯蓄型保険を検討する際、「返戻率(へんれいりつ)」という言葉をよく目にします。返戻率とは、支払った保険料総額に対して、将来受け取れる満期金や解約返戻金がどれくらいの割合になるかを示す数値です。
返戻率が100%を超えれば、支払った保険料よりも多くのお金が戻ってくることになります。
確かに、超低金利時代の銀行預金と比較すれば、貯蓄型保険の返戻率(100%〜110%程度が一般的)は魅力的に見えるかもしれません。しかし、これはあくまで「貯蓄」の側面だけを見た場合の話です。
資産を「増やす」という目的で考えた場合、貯蓄型保険のリターンは、NISAやiDeCoといった投資制度を活用した資産運用と比較すると、見劣りするケースがほとんどです。
投資には元本割れのリスクがありますが、長期・積立・分散を前提とすれば、年率3〜5%程度のリターンを期待することも非現実的ではありません。
貯蓄型保険は、あくまで「保険」です。支払う保険料には保障のコストや保険会社の経費が含まれているため、純粋な金融商品である投資信託などと比べると、どうしても運用効率は低くなります。
「保障も貯蓄も」という一見便利な仕組みは、「保障は中途半端、リターンも期待できない」という結果になりがちです。お金を増やすことを主な目的とするのであれば、保障は割安な掛け捨て型保険で確保し、浮いたお金を投資に回す「保障と貯蓄の分離」が、より合理的で効率的な選択肢となります。
5. 気軽にお金の引き出しができない
銀行の普通預金であれば、ATMやインターネットバンキングを通じて、いつでも好きな時にお金を引き出すことができます。しかし、貯蓄型保険は「貯蓄」という名前がついていますが、預貯金のように自由にお金を引き出すことはできません。
貯蓄型保険から現金を手にする方法は、基本的に以下の2つです。
- 解約する:
前述の通り、早期解約は元本割れのリスクが非常に高いため、気軽に選択できる手段ではありません。 - 契約者貸付制度を利用する:
解約返戻金の一定範囲内(通常7〜9割程度)で、保険会社からお金を借りる制度です。
「契約者貸付」は、解約せずに資金を調達できる便利な制度に見えますが、注意が必要です。これはあくまで「借金」であり、所定の利息が発生します。返済が滞ったり、借り入れ額が解約返戻金を上回ったりすると、最悪の場合、保険契約が失効してしまうこともあります。
急な出費が必要になった際に、「貯蓄のつもりだったのに、簡単には使えない」というのが実態です。この流動性の低さは、日常生活における資金計画の柔軟性を著しく損なう要因となり得ます。
6. 保障内容が手薄い保険がある
貯蓄型保険は、貯蓄性に重きを置くあまり、同程度の保険料を支払う掛け捨て型保険と比較して、肝心の「保障」が手薄になる傾向があります。
特に、働き盛りで子育て中の世代など、万一の際に遺された家族のために大きな死亡保障が必要な時期には、貯蓄型保険だけでは保障額が不十分になるケースが少なくありません。
例えば、月々2万円の保険料を支払う場合を考えてみましょう。
このように、同じ保険料でも確保できる保障の大きさには歴然とした差が生まれます。
また、貯蓄性をアピールする商品の中には、死亡保障が非常に小さく、実質的には節税対策や相続対策に特化したような保険も存在します。
「保障と貯蓄を両立したい」と考えて貯蓄型保険を選んだつもりが、実際には「十分な保障は得られず、貯蓄効率も悪い」という中途半端な結果に終わってしまう可能性があるのです。保険に加入する本来の目的である「万一への備え」が疎かになっては本末転倒です。
貯蓄型保険の種類とデメリット
一口に貯蓄型保険といっても、その目的や仕組みによっていくつかの種類に分けられます。ここでは、代表的な5つの貯蓄型保険の特徴と、それぞれが持つ特有のデメリットについて解説します。
特徴:
デメリット:
こんな人には向いていない:
養老保険
特徴:
デメリット:
こんな人には向いていない:
個人年金保険
特徴:
デメリット:
こんな人には向いていない:
学資保険
特徴:
デメリット:
こんな人には向いていない:
医療保険
特徴:
デメリット:
こんな人には向いていない:
貯蓄型保険のメリット
ここまでデメリットを中心に解説してきましたが、もちろん貯蓄型保険にもメリットは存在します。デメリットと比較し、ご自身にとってどちらの価値が大きいかを判断することが大切です。
保障を得ながら、半強制的に貯蓄ができる
生命保険料控除で税負担が軽減される
契約者貸付制度でお金を借りられる
これらのメリットは、保障と貯蓄を別々に管理するのが面倒な方や、とにかく強制力のある仕組みで将来の資金を準備したい方にとっては、魅力的に映るかもしれません。
貯蓄型保険への加入をおすすめしない人とは
これまでのデメリットとメリットを踏まえると、貯蓄型保険への加入を積極的におすすめできない人の特徴が見えてきます。
【貯蓄型保険をおすすめしない人】
一方で、以下のような考え方を持つ人にとっては、貯蓄型保険が選択肢の一つになる可能性もあります。
【貯蓄型保険が選択肢になりうる人】
重要なのは、「なんとなく良さそうだから」という理由で選ぶのではなく、デメリットをすべて理解した上で、なお自分にはメリットの方が大きいと判断できるかどうかです。
貯蓄型保険に入ってしまった!後悔したときのやめどきは?
「デメリットを知って、今入っている貯蓄型保険をやめたくなってきた……」
すでに加入している方の中には、そう感じている方もいらっしゃるかもしれません。
貯蓄型保険をやめる(解約する)際に最も避けたいのは、払込保険料総額を大きく下回る「元本割れ」です。では、できるだけ損をしないためには、どのタイミングで解約すれば良いのでしょうか。
結論から言うと、解約のベストタイミングは「解約返戻率が100%を超える、もしくは100%に限りなく近くなったとき」です。
【確認方法】
- 保険証券を手元に用意する
- 証券に添付されている「解約返戻金推移表」を確認する
この表には、契約からの経過年数ごとに、解約した場合にいくら戻ってくるかが記載されています。ご自身の払込保険料総額と照らし合わせ、返戻率が100%を超えるのが何年後かを確認しましょう。
もし、返戻率が100%を超えるまでまだ何年もかかる場合は、すぐに解約するのではなく、以下の方法も検討してみてください。
払済保険(はらいずみほけん)への変更
延長(定期)保険への変更
すぐに解約して損をするのではなく、「払済」や「延長」に変更して保険料の負担をなくし、元本割れしなくなるタイミングを待ってから解約するというのも賢い選択です。
どの方法が最適かは、契約内容や現在の家計状況によって異なります。まずは保険会社のコールセンターや、加入した代理店に相談し、ご自身の契約でどのような選択肢があるのかを確認してみましょう。
まとめ:貯蓄型保険のデメリットを理解し、自分に合った選択を
今回は、貯蓄型保険のデメリットについて、多角的な視点から詳しく解説しました。
- 保険料が高い
- 途中解約で元本割れしやすい
- インフレに弱い
- リターンが期待できない
- お金を自由に引き出せない
- 保障が手薄になりがち
「保障と貯蓄がひとつに」という言葉は、一見すると非常に効率的に聞こえます。しかしその実態は、「保障」は割高な掛け捨て保険に、「貯蓄」は効率の悪い金融商品に、それぞれお金を払っている状態に近いといえるかもしれません。
より合理的で効率的な方法は、「保障」と「貯蓄(資産形成)」を切り離して考えることです。
保障:
必要な保障額を算出し、割安な掛け捨て型保険(定期保険、収入保障保険など)で備える。
貯蓄・資産形成:
掛け捨て型保険で浮いたお金を、NISAやiDeCoといった税制優遇制度を活用しながら、投資信託などで長期的に運用する。
この考え方であれば、月々の負担を抑えながら十分な保障を確保し、かつ貯蓄型保険よりも高いリターンを期待することができます。
もちろん、貯蓄型保険がすべての人にとって悪い選択というわけではありません。貯金が苦手な方や、管理を一本化したい方にとっては、有効な手段となり得ます。
最も重要なのは、貯蓄型保険のメリット・デメリットの両方を正しく理解し、ご自身のライフプラン、価値観、そしてお金に対する考え方に照らし合わせて、主体的に選択することです。
もし保険選びに迷ったら、特定の保険会社に属さないファイナンシャルプランナーや、複数の保険会社の商品を扱う保険ショップなどで、専門家の意見を聞いてみるのも良いでしょう。客観的な視点から、あなたに最適なプランを提案してくれるはずです。
この記事が、あなたの後悔しない保険選びの一助となれば幸いです。