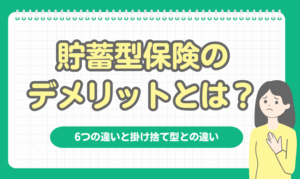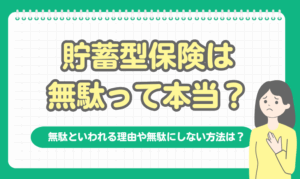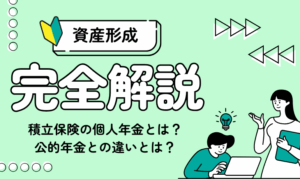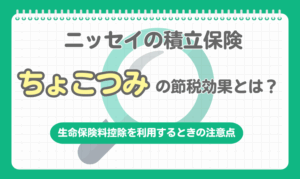貯蓄型保険は、保障と貯蓄の両方の機能を持つ保険商品として、多くの方に選ばれています。将来の資産形成を考えながら、万が一の備えもできる点が大きな魅力です。しかし、数多くの保険会社から様々な商品が販売されており、どれを選べばよいか迷う方も少なくありません。
本記事では、貯蓄型保険のおすすめランキングを終身型、一時払い、10年満期、5年満期といったタイプ別にご紹介します。それぞれの特徴やメリット、選び方のポイントも詳しく解説しますので、あなたに最適な貯蓄型保険選びの参考にしてください。
【終身型】貯蓄型保険のおすすめランキングTOP5
終身型の生命保険は、一生涯にわたって死亡保障が続く保険です。保険料の払込期間が終了した後も保障は継続し、解約時には解約返戻金を受け取ることができます。長期的な資産形成と保障を両立させたい方に人気の高い保険タイプです。
終身保険の大きな特徴は、保険料が掛け捨てにならないことです。支払った保険料は積み立てられ、将来的に解約返戻金として戻ってくる仕組みになっています。また、契約者貸付制度を利用すれば、解約することなく一時的な資金調達も可能です。
TOP1:かんぽ生命保険 新ながいきくん
かんぽ生命保険の「新ながいきくん」は、ゆうちょ銀行や郵便局で手軽に申し込める終身保険として、幅広い年齢層から支持されています。特に50代以降の方や、身近な場所で相談しながら加入したいという方におすすめです。
この保険の最大の特徴は、全国の郵便局窓口で気軽に相談できる点です。保険の専門知識がない方でも、郵便局の担当者が丁寧に説明してくれるため、安心して契約を検討できます。また、健康状態に不安がある方でも加入しやすい「はじめのかんぽ」というプランも用意されています。
保険料の払込期間は60歳、65歳、70歳から選択でき、ライフプランに合わせた設計が可能です。死亡保険金は最低100万円から設定でき、必要な保障額に応じて柔軟に調整できます。
| 項目 | 内容 |
| 契約可能年齢 | 15歳~85歳 |
| 払込期間 | 60歳、65歳、70歳払済など |
| 保険期間 | 終身 |
| 最低保険金額 | 100万円 |
TOP2:オリックス生命 終身保険RISE(ライズ)
オリックス生命の終身保険RISEは、業界でもトップクラスの返戻率を誇る終身保険です。貯蓄性を重視する方に特におすすめで、長期的な資産形成を目指す30代、40代の方から高い評価を得ています。
RISEの特徴は、保険料払込期間を短く設定することで、より高い返戻率を実現できる点です。10年払済、15年払済といった短期払いを選択すれば、早期に返戻率が100%を超えるため、効率的な資産形成が可能になります。
また、保険料の払込免除特約を付加することで、がん・急性心筋梗塞・脳卒中といった三大疾病に罹患した場合、以降の保険料支払いが免除される安心の保障も用意されています。
| 項目 | 内容 |
| 契約可能年齢 | 15歳~75歳 |
| 払込期間 | 10年、15年、20年、60歳、65歳払済など |
| 保険期間 | 終身 |
| 最低保険金額 | 200万円 |
TOP3:楽天生命スーパー終身保険
楽天生命スーパー終身保険は、インターネットで簡単に申し込みができる手軽さと、楽天ポイントが貯まるお得さが魅力の終身保険です。楽天経済圏を活用している方や、オンラインで保険を完結させたい方に最適です。
この保険の特徴は、保険料の支払いで楽天ポイントが貯まることです。貯まったポイントは楽天市場でのショッピングなど、様々な用途に使用できるため、実質的な保険料負担を軽減できます。
申込手続きは全てオンラインで完結し、医師の診査も不要な告知のみで加入できるプランも用意されています。保険料も他社と比較して競争力のある水準に設定されており、コストパフォーマンスを重視する方にもおすすめです。
| 項目 | 内容 |
| 契約可能年齢 | 20歳~79歳 |
| 払込期間 | 10年、20年、60歳、65歳払済など |
| 保険期間 | 終身 |
| 最低保険金額 | 100万円 |
TOP4:アフラック生命保険 かしこく備える終身保険
アフラック生命保険の「かしこく備える終身保険」は、低解約返戻金型の終身保険として、保険料を抑えながら大きな保障を確保したい方に選ばれています。特に子育て世代で、教育資金の準備と死亡保障を両立させたい方におすすめです。
この保険は、保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定することで、月々の保険料を抑える仕組みになっています。払込期間満了後は解約返戻金が大幅に増加し、通常の終身保険と同等以上の返戻率となります。
また、三大疾病保険料払込免除特約や、災害死亡時の保険金増額特約など、様々なオプションを付加することで、より充実した保障内容にカスタマイズすることも可能です。
| 項目 | 内容 |
| 契約可能年齢 | 0歳~85歳 |
| 払込期間 | 10年、15年、60歳、65歳、70歳払済など |
| 保険期間 | 終身 |
| 最低保険金額 | 100万円 |
TOP5:アクサ生命 アクサの「一生保障」の終身保険
アクサ生命の「一生保障」の終身保険は、外資系保険会社ならではの充実した保障内容と、柔軟な設計が可能な終身保険です。特に女性の方や、将来の介護に備えたい方から支持を得ています。
この保険の特徴は、介護保障特約を付加できる点です。所定の要介護状態になった場合、一時金や年金形式で給付金を受け取ることができ、老後の介護費用に備えることができます。
保険料の払込方法も月払い、半年払い、年払いから選択でき、家計の状況に合わせて無理なく継続できます。また、健康体割引制度により、非喫煙者や健康状態が良好な方は保険料が割引になるメリットもあります。
| 項目 | 内容 |
| 契約可能年齢 | 5歳~75歳 |
| 払込期間 | 10年、15年、20年、60歳、65歳払済など |
| 保険期間 | 終身 |
| 最低保険金額 | 200万円 |
【一時払い】貯蓄型保険のおすすめランキングTOP3
一時払い保険は、契約時に保険料を一括で支払う保険商品です。まとまった資金がある方が、相続対策や資産運用の一環として活用することが多く、月々の保険料支払いの負担がないため、退職金や満期保険金などを有効活用したい方に適しています。
一時払い保険の最大のメリットは、総支払保険料が少なくて済むことです。分割払いと比較して、保険料の総額を大幅に抑えることができ、その分返戻率も高くなります。また、契約後すぐに一定の解約返戻金が確保されるため、急な資金需要にも対応しやすいという特徴があります。
TOP1:住友生命 ふるはーとJロードIII
住友生命の「ふるはーとJロードIII」は、一時払い終身保険として高い人気を誇る商品です。相続対策を考える50代以降の方や、退職金の運用先を探している方に特におすすめです。
この保険の特徴は、契約時から高い解約返戻金が設定されている点です。契約直後でも払込保険料の90%以上の解約返戻金が保証されており、流動性を確保しながら資産運用ができます。
また、死亡保険金は相続税の非課税枠(500万円×法定相続人数)を活用できるため、相続対策としても有効です。さらに、指定代理請求特約を付加することで、契約者が意思表示できない状態になった場合でも、あらかじめ指定した代理人が手続きを行えます。
| 項目 | 内容 |
| 契約可能年齢 | 15歳~90歳 |
| 払込期間 | 一時払い |
| 保険期間 | 終身 |
| 最低保険料 | 100万円 |
TOP2:メットライフ生命 ビー ウィズ ユー プラスⅡ
メットライフ生命の「ビー ウィズ ユー プラスⅡ」は、米ドル建ての一時払い終身保険です。円建て商品よりも高い利回りを期待でき、資産の一部を外貨で運用したい方におすすめです。
この保険の魅力は、米ドルベースでの運用により、日本の低金利環境下でも比較的高い利回りが期待できる点です。契約時に定期支払コースを選択すれば、毎年一定額の生存給付金を受け取ることも可能で、年金の補完として活用できます。
為替リスクはありますが、長期的な資産形成を考える方にとっては、通貨分散によるリスクヘッジ効果も期待できます。また、契約後も市場金利の動向に応じて積立利率が見直されるため、金利上昇局面でのメリットも享受できます。
| 項目 | 内容 |
| 契約可能年齢 | 0歳~90歳 |
| 払込期間 | 一時払い |
| 保険期間 | 終身 |
| 最低保険料 | 2万米ドル |
TOP3:マニュライフ生命 未来を楽しむ終身保険
マニュライフ生命の「未来を楽しむ終身保険」は、外貨建て一時払い終身保険として、豪ドルや米ドルでの運用が選択できる商品です。将来の生活資金準備と相続対策を両立させたい方に適しています。
この保険の特徴は、契約通貨を米ドルまたは豪ドルから選択でき、それぞれの通貨の特性を活かした運用ができる点です。また、契約後15年経過以降は、毎年定期引出しが可能になり、老後の生活資金として計画的に活用できます。
目標値到達時に円建て終身保険移行特約を付加すれば、あらかじめ設定した目標額に到達した時点で、自動的に円建て終身保険に移行し、為替リスクを回避することも可能です。
| 項目 | 内容 |
| 契約可能年齢 | 0歳~90歳 |
| 払込期間 | 一時払い |
| 保険期間 | 終身 |
| 最低保険料 | 1万米ドル/1万豪ドル |
【10年満期】貯蓄型保険のおすすめランキングTOP3
10年満期の貯蓄型保険は、比較的短期間で満期を迎えるため、教育資金の準備や住宅購入資金の積立など、明確な目的がある方に適しています。満期時には満期保険金を受け取れるため、計画的な資産形成が可能です。
TOP1:日本生命 ちょこつみ
日本生命の「ちょこつみ」は、手軽に始められる積立型の保険として注目を集めています。月々3,000円から始められる手軽さと、10年という比較的短い期間で満期を迎える点が特徴です。
この保険は、将来の目標に向けて計画的に資金を積み立てたい方に最適です。保険料は月払いで、口座振替により自動的に積み立てられるため、貯蓄が苦手な方でも確実に資産形成ができます。
満期時には積み立てた保険料に利息相当分を加えた満期保険金を受け取れます。また、契約期間中に万が一のことがあった場合は、死亡保険金が支払われるため、保障機能も備えています。
| 項目 | 内容 |
| 契約可能年齢 | 3歳~65歳 |
| 払込期間 | 10年 |
| 保険期間 | 10年 |
| 最低保険料 | 月額3,000円 |
TOP2:明治安田生命 じぶんの積立
明治安田生命の「じぶんの積立」は、10年満期の積立保険として、確実に資産を増やしたい方から支持されています。元本割れのリスクがなく、安心して積み立てられる点が最大の魅力です。
この保険の特徴は、いつ解約しても払込保険料以上の解約返戻金が受け取れることです。急な資金需要が発生した場合でも、損をすることなく解約できるため、流動性を重視する方にも適しています。
保険料は月額5,000円から設定でき、無理のない範囲で積立が可能です。満期時には103%程度の返戻率となり、銀行預金よりも有利な条件で資産運用ができます。
| 項目 | 内容 |
| 契約可能年齢 | 18歳~65歳 |
| 払込期間 | 5年 |
| 保険期間 | 10年 |
| 最低保険料 | 月額5,000円 |
TOP3:住友生命 Chakin
住友生命の「Chakin」は、スマートフォンアプリと連動した新しいタイプの積立保険です。健康増進活動でポイントが貯まり、実質的な保険料負担を軽減できる仕組みが特徴的です。
この保険は、毎日の歩数や健康診断の結果に応じてポイントが付与され、そのポイントを保険料の支払いに充当できます。健康的な生活を送りながら、お得に資産形成ができる画期的な商品です。
10年満期で計画的な積立ができ、アプリで積立状況をリアルタイムで確認できるため、若い世代を中心に人気を集めています。また、契約者同士でグループを作り、励まし合いながら積立を継続できる機能も好評です。
| 項目 | 内容 |
| 契約可能年齢 | 18歳~50歳 |
| 払込期間 | 10年 |
| 保険期間 | 10年 |
| 最低保険料 | 月額3,000円 |
【5年満期】貯蓄型保険のおすすめランキングTOP3
5年満期の貯蓄型保険は、短期間での資産形成を目指す方に適しています。また、5年ごと利差配当付タイプの保険も含めて、比較的短いサイクルで見直しができる商品をご紹介します。
TOP1:JA共済 養老生命共済
JA共済の養老生命共済は、5年から30年まで自由に満期を設定できる柔軟性の高い商品です。5年満期を選択すれば、短期間での資産形成が可能で、農業従事者以外の方でも加入できます。
この共済の特徴は、満期共済金と死亡共済金が同額に設定されている点です。満期まで継続すれば確実に共済金を受け取れ、万が一の場合も同額の保障があるため、バランスの取れた商品設計となっています。
また、JA共済は相互扶助の精神に基づいて運営されているため、営利を目的とした一般の保険会社と比較して、掛金が割安に設定されている傾向があります。地域に根ざした組織のため、きめ細やかなサポートも期待できます。
| 項目 | 内容 |
| 契約可能年齢 | 0歳~75歳 |
| 払込期間 | 5年~30年 |
| 保険期間 | 5年~30年 |
| 最低共済金額 | 50万円 |
TOP2:ソニー生命保険 養老保険
ソニー生命保険の養老保険は、5年ごと利差配当付養老保険として、安定した運用実績を誇る商品です。ライフプランナーによる対面でのコンサルティングを通じて、最適なプランを設計できます。
この保険の魅力は、運用実績に応じて5年ごとに配当金が支払われる可能性がある点です。基本的な満期保険金に加えて、配当金による上乗せが期待でき、インフレリスクにも対応できます。
保険期間は5年から設定可能で、教育資金の準備や定年退職までの資産形成など、様々な目的に活用できます。また、保険料払込免除特約を付加すれば、所定の状態になった場合、以降の保険料が免除される安心の保障も用意されています。
| 項目 | 内容 |
| 契約可能年齢 | 0歳~78歳 |
| 払込期間 | 5年~30年 |
| 保険期間 | 5年~30年 |
| 最低保険金額 | 100万円 |
TOP3:SOMPOひまわり生命保険 養老保険
SOMPOひまわり生命保険の養老保険は、5年ごと利差配当付タイプとして、短期から長期まで幅広い期間設定が可能な商品です。特に健康に自信がある方は、健康体料率により保険料が割引になるメリットがあります。
この保険の特徴は、契約時の健康状態や喫煙習慣によって保険料が変動する点です。非喫煙者で健康状態が良好な方は、標準体の方と比較して最大20%程度保険料が安くなる可能性があります。
5年満期から設定可能で、満期時には満期保険金を一括で受け取るか、年金形式で受け取るかを選択できます。老後の生活資金準備として活用する場合は、年金形式での受取りを選択することで、計画的な資金活用が可能になります。
| 項目 | 内容 |
| 契約可能年齢 | 3歳~75歳 |
| 払込期間 | 5年~25年 |
| 保険期間 | 5年~25年 |
| 最低保険金額 | 100万円 |
貯蓄型保険の選び方や注意点
貯蓄型保険は、保障機能と貯蓄機能を併せ持つ保険商品です。支払った保険料が掛け捨てにならず、満期時や解約時に一定の金額が戻ってくる仕組みになっています。一方、掛け捨て型保険は、保険料が安い代わりに、満期時や解約時の返戻金がない、または極めて少ない保険です。
貯蓄型保険は、将来の資産形成を目的とする方や、保険料が無駄にならないことを重視する方に適しています。ただし、掛け捨て型と比較して保険料が高額になる傾向があるため、家計とのバランスを考慮して選択することが重要です。
貯蓄型保険を選ぶ際は、加入目的を明確にし、それに適した商品を選ぶことが大切です。また、返戻率や解約返戻金の水準、継続可能な保険料であることなど、複数の観点から総合的に判断する必要があります。
加入目的や保障内容で選ぶ
貯蓄型保険には様々な種類があり、それぞれ特徴が異なります。主な種類として、終身保険、養老保険、学資保険、個人年金保険などがあり、目的に応じて選択することが重要です。
終身保険
養老保険
学資保険
定期保険
返戻率や解約返戻金を確認する
返戻率
返戻率100%を超える商品を選べば、支払った保険料以上の金額を受け取ることができます。ただし、返戻率は保険料の払込期間や保険期間、解約時期などによって大きく変動するため、契約前に詳細なシミュレーションを行うことが重要です。
解約返戻金
利回りという観点から見ると、貯蓄型保険の実質的な利回りは、銀行預金と比較して必ずしも高いとは限りません。保険には保障機能があるため、純粋な運用商品と単純比較することはできませんが、資産運用を主目的とする場合は、他の金融商品との比較検討も必要です。
元本割れのリスクを避けるためには、保険料払込期間を満了するまで継続することが基本です。やむを得ず途中解約する可能性がある場合は、解約返戻金の推移を事前に確認し、損失を最小限に抑えられるタイミングを把握しておくことが大切です。
払い続けられる保険料であることも大切
貯蓄型保険の多くは積立型で、毎月または毎年、定期的に保険料を支払う必要があります。途中で保険料の支払いが困難になり解約すると、元本割れにより大きな損失を被る可能性があるため、無理のない保険料設定が極めて重要です。
保険料を設定する際は、現在の収入だけでなく、将来の収入変動も考慮する必要があります。転職や退職、子どもの教育費増加など、ライフイベントによる支出増加を見込んで、余裕を持った保険料設定を心がけましょう。
一般的に、保険料は手取り収入の5~10%程度が適正とされていますが、これはあくまで目安です。住宅ローンの有無、子どもの人数、他の金融商品への投資状況など、個々の家計状況に応じて調整することが必要です。
お金に余裕がある時期に一時払いや年払いを選択すれば、保険料の総額を抑えることができます。ただし、一度に大きな金額を支払うことで、手元の流動性資金が不足しないよう注意が必要です。緊急時の備えとして、生活費の3~6か月分程度は預貯金として確保しておくことをおすすめします。
保険料の支払いが困難になった場合の対処法として、減額や払済保険への変更、契約者貸付の利用などがあります。これらの制度を事前に理解しておくことで、万が一の際も適切な対応が可能になります。
まとめ
貯蓄型保険は、保障と貯蓄を両立させる優れた金融商品です。終身型、一時払い、10年満期、5年満期など、様々なタイプがあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。本記事でご紹介したランキングを参考に、ご自身のライフプランに最適な商品を選んでください。
保険選びで最も重要なのは、自分自身の目的を明確にすることです。老後の資産形成を重視するのか、相続対策として活用したいのか、それとも教育資金の準備が目的なのか、目的によって選ぶべき商品は異なります。
また、保険は長期にわたる契約となるため、信頼できる保険会社を選ぶことも大切です。財務健全性や顧客対応の評判、アフターフォローの充実度なども考慮して、総合的に判断することをおすすめします。
貯蓄型保険への加入を検討する際は、複数の保険会社の商品を比較検討し、必要に応じて保険の専門家に相談することも有効です。ファイナンシャルプランナーや保険代理店の担当者は、豊富な知識と経験を持っているため、あなたに最適なプランを提案してくれるでしょう。
最後に、貯蓄型保険は万能な金融商品ではありません。「保険で貯蓄をしてはいけない」という意見があるのも事実で、その理由として以下の4つが挙げられます。
これらのデメリットを理解した上で、保障機能の必要性や、強制的な積立効果、相続対策としての活用など、貯蓄型保険ならではのメリットを重視する方には、依然として有効な選択肢となります。
貯蓄型保険と掛け捨て型保険、どちらが優れているという単純な比較ではなく、それぞれの特徴を理解し、自分のニーズに合った選択をすることが重要です。場合によっては、両方を組み合わせることで、より効果的な保障と資産形成を実現することも可能です。
50代の方であれば、老後資金の準備と相続対策を兼ねた終身保険や一時払い保険が適しているかもしれません。女性の方なら、医療保障を充実させた貯蓄型保険や、介護保障特約付きの商品を検討する価値があります。
年齢や性別、家族構成、資産状況など、個々の状況に応じて最適な保険は異なります。画一的な答えはありませんが、本記事でご紹介した情報を参考に、じっくりと検討していただければ幸いです。
保険の見直しは定期的に行うことも大切です。ライフステージの変化に応じて、必要な保障内容や保険金額は変わってきます。結婚、出産、住宅購入、子どもの独立、定年退職など、人生の節目では保険の見直しを検討しましょう。
貯蓄型保険は、適切に活用すれば、将来の安心と豊かな生活を実現するための強力なツールとなります。ただし、過度に保険に依存することなく、預貯金や投資信託、株式投資など、他の金融商品とのバランスを考えた総合的な資産形成を心がけることが、真の意味での経済的安定につながります。
保険は「転ばぬ先の杖」であると同時に、計画的な資産形成の手段でもあります。本記事が、あなたの保険選びの一助となり、より良い未来への第一歩となることを願っています。賢明な選択により、安心できる将来を築いていきましょう。