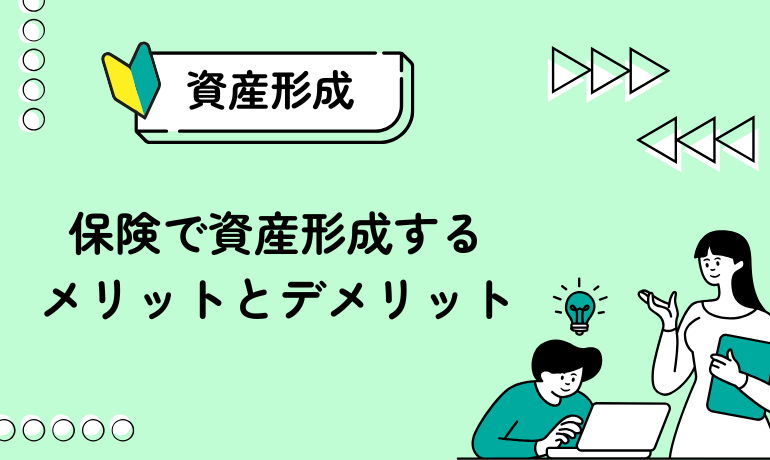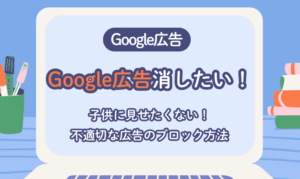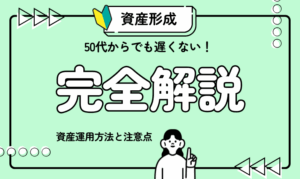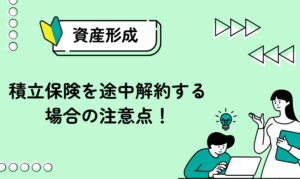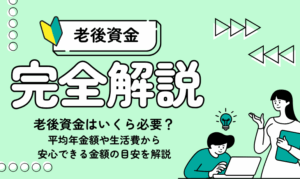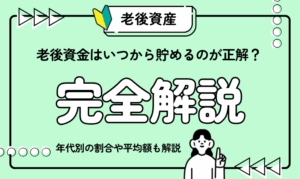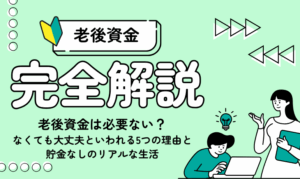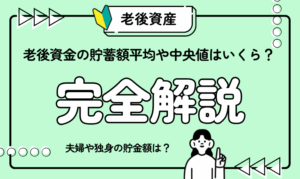昨今、銀行預金だけでお金を増やすことが難しい中で、「資産形成」の手段として保険を活用する方法が注目されています。保険で資産形成をしたいと考えても、「どんな保険商品を選べばよいのか」「投資と何が違うのか」など疑問を持つ方も多いでしょう。そこで本記事では、保険で資産形成する仕組みやメリット・デメリット、さらに投資による資産運用との違いを解説します。また、資産形成に向くおすすめの積立型保険商品や、保険以外の資産形成制度(NISAやiDeCo)についても紹介します。
資産形成できる保険とは
資産形成できるのは積立型の保険
保険には、大きく分けて掛け捨て型(保障のみで満期返戻金がないタイプ)と積立型(将来満期金や解約返戻金を受け取れるタイプ)があります。資産形成ができるのは積立型の保険です。積立型保険では、保険期間満了時に満期保険金として、途中解約時には解約返戻金として、契約時に定めた一定の金額を受け取れます。つまり、死亡や入院などへの保障に加えて、将来のための貯蓄機能も備えている点が特徴です。
具体的な積立型保険としては、終身保険や養老保険などが代表的です。例えば終身保険では、長期間契約を継続することで解約返戻金が増加し、タイミングによっては払込保険料総額を上回る返戻金を受け取れる場合もあります。また、学資保険(こども保険)や個人年金保険も積立型の一種です。これらは決められた時期に祝い金や年金を受け取りつつ、契約者に万一のことがあれば残りの保険料の支払いが免除され、予定通り満期金を受け取れる仕組みになっており、ライフイベントに合わせて資金準備ができる保険です。
保険での資産形成と投資による資産運用の違い
保険と投資はどちらも資産運用の手段ですが、その目的や特徴は大きく異なります。投資(株式や投資信託、不動産など)は、利益を追求して資産を増やすことが目的です。市場の状況によっては大きく資産が増える可能性がありますが、同時に元本割れなど損失のリスクも伴います。また、成果を上げるには専門的な知識や相場を見る時間も必要です。さらに、投資商品には万一の保障(生命保障など)がありません。そのため、投資で資産を増やしつつ万一に備える場合は、別途保険などで保障を確保する必要があります。
一方、保険で資産形成を行う場合、運用自体は保険会社が代わりに行ってくれるため、投資のように自分で細かく運用商品を選ぶ手間はかかりません。ただし、運用成果は投資ほど大きく期待できるものではなく、利回りは控えめです。その代わり、保険ならではの保障(死亡保険金や高度障害保険金など)が付いており、万一の際にも備えながら将来の資産形成ができる点が特徴です。つまり、「リスクを抑えてコツコツ資産を準備したい人」には保険が向いており、「高いリターンを狙いたい人」には知識とリスク許容度次第で投資が適しています。
資産形成できる保険の種類
資産形成に活用できる主な保険商品には以下のようなものがあります。それぞれ保障内容や貯蓄性の特徴が異なるため、自分の目的に合ったものを選ぶことが大切です。
終身保険(生命保険)
終身保険は、一生涯の死亡保障が得られる生命保険です。被保険者が死亡(または高度障害状態)になったときに、死亡保険金が支払われます。終身保険の特徴は、解約返戻金が用意されている点です。払い込む保険料は掛け捨てではなく一部が積み立てられ、契約から長期間が経過すると解約返戻率(返戻金の額/払込保険料累計)が高まり、場合によっては払込総額以上の返戻金を受け取れることもあります。ただし、加入後早い時期で解約すると返戻率が低く、払込額を大きく下回るため注意が必要です。
終身保険には、保険料払込期間中の解約返戻金を低く抑えることで保険料を割安にした低解約返戻金型終身保険といった商品もあります。このタイプでは払込期間中に解約すると返戻率が低い代わりに、払込満了後は返戻金が増加しやすく、同じ保障額でも通常の終身保険より保険料を抑えられるメリットがあります。まとまった資金がある場合、一時払い(全期分の保険料を一括払い)で加入することも可能で、その場合は月払いよりも割引が利いて効率よく資産を積み立てられます。
終身保険は老後の備えや相続対策として活用されることが多い保険です。長期間じっくりと資産形成しつつ、万一の際にはまとまった保障を家族に残したい人に向いています。
学資保険
学資保険(こども保険)は、子どもの教育資金を計画的に準備するための貯蓄型保険です。契約者(親など)が一定期間保険料を積み立て、子どもが高校入学時や大学入学時など節目の年齢に達したときに祝い金や満期保険金を受け取れます。商品によって、18歳もしくは22歳満期で満期金が支払われるタイプなどがあります。
学資保険最大の特徴は、契約者に万一のことがあった場合の保障です。契約者(親など)が死亡または高度障害状態になった場合、以後の保険料払い込みが免除される特約を付けられる商品が一般的です。保険料の払込免除となった後も、契約内容に従い子どもが所定の年齢に達すれば予定通り祝い金や満期金が受け取れるため、親に万一のことがあっても子どもの教育資金を確保できる点で安心です。
学資保険の返戻率(受取総額÷払込保険料総額)は、保険会社や契約条件によって大きく異なります。貯蓄性を重視した商品では、保険料の払込期間を短くする、保険料を一括払い(全期前納)にする、祝い金の受け取りがないプランを選ぶといった工夫により、返戻率が著しく高まる傾向にあります。
例えば、明治安田生命の「つみたて学資」では特定の条件下で最大127.4% 、日本生命の「ニッセイ学資保険」では2025年1月の保険料率改定により最大約112.0% といった高い返戻率を実現するプランも存在します。一方で、医療保障などの特約を付加した場合や、払込期間が長いプランでは、返戻率が100%を下回る(元本割れする)場合もあるため、契約前に必ずご自身の条件で見積もりを取り、シミュレーションで確認することが極めて重要です。
養老保険
養老保険は、あらかじめ定めた一定期間の保障と貯蓄を兼ね備えた保険です。例えば「15年満期」「60歳満期」など保険期間を決めて契約します。保険期間中に被保険者が死亡した場合は死亡保険金が支払われ、生存したまま満期を迎えれば満期保険金を受け取れます。多くの場合、満期保険金額は死亡保険金額と同額に設定されており、満期まで生存しても死亡しても同額のお金が手に入る仕組みになっています。
養老保険のメリットは、保障を確保しながら計画的に資産形成できることです。保険期間を自由に設定できるため、「○年後に○○の資金が必要」といった目的に合わせて契約期間を選べます。例えばお子様の独立資金や、自身のリタイア後資金を〇歳時点で準備したい、といったニーズに応じて期間を設定できる柔軟性があります。ただし、その分終身保険に比べると保険料は割高になる傾向があり、満期返戻率も商品によりますが概ね100%前後(払込保険料総額と同程度)に設計されている場合が多いです。
養老保険は確実に一定額の資金を貯めたい人に向いています。満期時に元本確保(場合によっては利息相当分を含めて増加)されたお金を受け取れるため、安全重視で資産形成したい場合に検討するとよいでしょう。
個人年金保険
個人年金保険は、公的年金を補完し、老後の生活資金を準備することを目的とした貯蓄型保険です。契約時に定めた年金受取開始年齢(例えば60歳や65歳)から、年金形式でお金を受け取れる点が特徴です。保険料は契約期間中コツコツと払い込み、受取開始年齢になると毎年(または毎月)決まった年金額が受け取れます。
個人年金保険には、確定年金(一定期間必ず年金を受け取れる)、有期年金(一定期間受取れるが期間中に死亡した場合打ち切り)、終身年金(一生涯受取れる)などの種類があります。いずれのタイプでも、年金受取開始前に被保険者が死亡した場合は死亡給付金(それまで払込んだ保険料相当額など)が支払われるため、無駄にはなりません。
個人年金保険の利回りは商品によりますが、近年の円建て商品では低金利の影響もあり、大きな増加は期待しづらい状況です。ただし、個人年金保険料税制適格特約を付けることで生命保険料控除(個人年金保険料控除)の対象になり、所得税・住民税の負担軽減効果を得られるメリットがあります(後述)。老後資金を計画的に準備したい方や、貯蓄と同時に長生きリスクに備えたい方に適した保険です。
変額保険
変額保険は、預けた保険料を保険会社が特別勘定(投資信託のような運用口座)で運用し、その成果に応じて保険金額や解約返戻金が変動するタイプの保険です。契約者は複数用意された特別勘定から運用先を選ぶことができ、株式型・債券型・バランス型など自分のリスク許容度に応じてポートフォリオを組むことも可能です。運用期間中は保険会社がプロとして資産運用を行い、その成果が契約者の積立金額や将来受け取る保険金額に反映されます。
変額保険には有期型(満期がある)と終身型(終身保障)があります。有期型変額保険では満期時に満期保険金が支払われ、終身型では生涯保障が続きます。いずれの場合も、契約期間中に被保険者が死亡した場合は死亡保険金が支払われ、この死亡保険金には最低保証が付いていることが一般的です(契約時に定めた基本保険金額は保障)。つまり、運用が悪く元本割れになっている時期に死亡しても、最低限の保険金は受け取れる仕組みになっています。
変額保険の魅力は、運用実績次第で解約返戻金や死亡保険金が増える可能性があることです。市場環境が良好で運用がうまくいけば、払い込んだ保険料累計よりも大きなお金を手にできるかもしれません。ただし反対に、株価の下落や為替変動などで運用が悪化すれば、解約返戻金が払込保険料を下回るリスクもあります。また、保険会社による運用管理費や特別勘定の信託報酬など各種費用も差し引かれるため、長期的な視点で見ないと期待したほど増えないケースもあります。「保険+投資」の性格が強いため、リスクを取りつつも保障も欲しい人に向いている商品と言えるでしょう。
外貨建て保険
外貨建て保険は、保険料の払い込みや保険金の運用・受け取りを外貨(米ドルや豪ドルなど)で行う保険です。保険会社は集めた外貨建ての保険料を海外の債券や株式などで運用します。一般に日本円よりも外貨の金利水準が高い場合、外貨建て保険は円建てより有利な利回りが期待できます。例えば米ドル金利が日本より高ければ、同じ保障額を準備するのに円建て商品より少ない保険料で済む場合もあります。結果として、長期的に円預金で貯めるより高い資産増加が見込める点が魅力です。
しかし、外貨建て保険には為替リスクが伴います。契約時から満期・受取時までの為替レートの変動により、円換算した受取額が元本を下回る可能性も否定できません。たとえば契約時よりも円高が進行すると、せっかく運用で増やしても円に戻すと目減りしてしまうことがあります。また、為替手数料など外貨を取り扱う上でのコストもかかります。したがって、外貨建て保険を利用する際は為替動向に注意し、リスクを十分理解した上で検討する必要があります。
外貨建て保険は、国内の低金利を補完して少しでも有利に資産形成したい人や、将来的に外貨で資金が必要な人(例えば留学資金を米ドルで用意したい等)に向いています。ただしリスクもある商品ですので、契約前にシミュレーションやパンフレットを確認し、メリットとデメリットをしっかり把握しましょう。
保険で資産形成をするメリット
万が一の保障がある
保険を活用して資産形成を行う最大のメリットは、もしもの時の保障を確保しながらお金を貯められる点です。本来保険商品は、死亡や病気・ケガといった不測の事態に備えることが目的です。貯蓄型保険であれば、たとえ資産形成中に契約者や被保険者に万一のことが起きた場合でも、保険金が遺族に支払われます。家族にお金を残しつつ、それまで積み立ててきた解約返戻金も無駄になりません。
純粋な投資商品には死亡保障などは付いていません。十分な金融資産があれば保険に加入しなくてもよい場合もありますが、「資産形成もしたいし、万が一の備えも欲しい」という方にとって、保険は一石二鳥の手段となります。保障と貯蓄を両立できるのは保険ならではの強みです。
貯蓄よりも利率がよくて低リスク
資産形成目的で保険を活用するメリットとして、銀行預金で貯蓄するよりは有利な利回りが得られる商品が多い点も挙げられます。預金の金利が極めて低い現在、ただ貯金するだけではお金はほとんど増えません。それに対し、積立型保険では予定利率(保険の運用利回り)が定められており、契約時の利率で将来の受取額が計算される商品もあります。また、外貨建て保険や変額保険のように、市場金利や運用成果によっては預金以上の利回りを得られる可能性もあります。
さらに、一般的に保険会社は契約者から預かった資金を安定的な運用で管理します。個人で株式投資をするよりリスクを抑えられる場合が多く、元本割れしにくい商品設計になっているものもあります(※ただし商品によってリスク度合いは異なりますので注意が必要です)。例えば第一生命の「ステップジャンプ」のように一定期間経過後は元本(払込保険料累計額)を保証しつつ運用益が期待できる商品も登場しており、投資に比べローリスク・ミドルリターン程度の堅実な資産形成手段として保険を活用できるケースもあります。
このように、投資ほどハイリスクではない一方で預金より有利な商品が多いのは、貯蓄型保険の魅力です。「コツコツ増やしたいが預金だけでは物足りない」という人にとって、保険は選択肢の一つとなるでしょう。
生命保険料控除が利用できる
保険で資産形成を行うメリットには、税制上の優遇を受けられることも含まれます。生命保険や個人年金保険に加入すると、その年に支払った保険料に応じて生命保険料控除を受けることができます。生命保険料控除とは、一定の計算式で算出された額を年間所得から差し引ける制度で、所得税や住民税の負担を軽減できるものです。
生命保険料控除は、支払った保険料の種類に応じて「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つの枠に分けて計算されます。2012年1月1日以降に契約した新制度の場合、各枠で適用される控除上限額は下表の通りです。
| 控除の種類 | 所得税の控除上限額 (年間) | 住民税の控除上限額 (年間) |
| 一般生命保険料控除 | 40,000円 | 28,000円 |
| 介護医療保険料控除 | 40,000円 | 28,000円 |
| 個人年金保険料控除 | 40,000円 | 28,000円 |
| 合計適用限度額 | 120,000円 | 70,000円 |
3つの枠をすべて利用した場合、所得税では最大120,000円(40,000円×3)、住民税では最大70,000円が総所得金額等から控除されます。例えば、一般生命保険のみに年間100万円の保険料を支払っていても、控除額は所得税40,000円、住民税28,000円が上限となります。複数の保険に加入することで、各枠を最大限活用できる可能性があります。
ただし、控除の適用には契約内容や契約時期による条件があります。2012年1月1日以降の契約は新制度、以前は旧制度と扱いが異なり、また個人年金保険料控除を受けるには受取人や年金受取期間について所定の要件を満たす必要があります。いずれにせよ、保険料控除を活用すれば実質的な手取りが増える形になりますので、積立保険に加入する際は忘れず年末調整や確定申告で申告しましょう。
保険で資産形成をするデメリット
長期的に継続する必要がある
貯蓄型の保険で資産形成を図る場合、長期契約の継続が前提となります。短期間で解約してしまうと多くの場合、受け取れる解約返戻金は払込保険料累計より少なくなってしまいます。保険商品は契約当初の数年間は解約返戻率が低く抑えられているものが多く、早期解約は元本割れを招きやすいのです。そのため、まとまった運用成果(満期金や高い返戻率)を得るには一定の長期加入が必要である点を理解しておかねばなりません。
また、保険契約では原則として契約時に決めた保険料を途中で減額したり停止したりできません。投資なら経済状況に応じて積立額を増減したり、一時休止することも可能ですが、保険料は決まった額を継続して払い込む義務が生じます。さらに、同じ保障内容であれば掛け捨て保険に比べて貯蓄型保険の保険料は高めです(保障に加えて貯蓄部分の積立があるため)。したがって、将来にわたって無理なく支払い続けられる額で契約しないと、途中で家計が苦しくなり解約せざるを得なくなるリスクがあります。
ネット上には「保険で貯蓄をしてはいけない」という意見も見られます。その理由の多くは今述べたように、長期拘束と途中解約時のペナルティにあります。資産形成目的で保険を選ぶ際は、将来にわたり継続できる保険料設定か慎重に検討し、途中で解約しなくても済むよう計画しましょう。
投資のような利益が期待できない
保険での資産形成はローリスクである反面、ハイリターンは狙いにくいというデメリットもあります。保険会社の運用方針は安全重視であることが多く、契約時に将来受け取る額が確定している商品も少なくありません(予定利率固定型など)。そのため、一般的な預金よりは利回りが高い傾向にあるものの、株式投資や投資信託のように大きなリターンを得るのは難しいでしょう。
例えば、外貨建て保険や変額保険といった商品は保険の中では利回りが期待できる部類ですが、それでも直接株式投資を行うのに比べればリスクが抑えられている分、リターンの上限も限られます。結果として「投資で得られるかもしれない利益」と比べれば物足りなく感じるかもしれません。もし大きな資産増加を目指すのであれば、保険よりもNISAや株式運用など投資の比重を高める方が良い場合もあります。
要するに、保険はあくまで堅実派向けの資産形成手段です。「多少リスクを取ってでも高利回りを狙いたい」という場合には不向きと言えます。その場合は後述するNISA(ニーサ)やiDeCoなど、投資性の高い制度の活用を検討するとよいでしょう。一方で「大きな利益はなくてもいいから元本割れせず着実に増やしたい」という方には、保険はマッチする選択肢です。
資産形成におすすめの積立保険ランキング
ここからは、資産形成に適した積立型保険商品を厳選し、おすすめ順にランキング形式で紹介します。それぞれの商品特徴やメリット・デメリット、どんな人に向いているかについて解説します。保険会社ごとの代表的な商品を挙げていますので、検討の参考にしてください。
TOP1:ソニー生命「変額個人年金保険 SOVANI(そばに)」
ソニー生命の「SOVANI」は、2022年10月の発売開始から約2年で預かり資産残高1兆円、累計新契約件数80万件を突破(2024年12月時点)した人気の変額個人年金保険です。老後資金の準備を主目的に設計されており、月額3,000円という少額からスタートできる手軽さが特徴です。加入時に国内外の株式・債券などで運用する特別勘定を最大8種類まで選択でき、自分の運用スタイルに合わせて資産配分を決められます。運用成績次第で将来受け取る年金額が増減しますが、契約者が死亡した場合の死亡給付金や災害保障も備えており、万一の際にも一定額は受け取れる安心感があります。
商品の特徴(例):
| 契約可能年齢 | 保険料払込方法・期間 | 年金受取開始年齢 | 投資先(特別勘定) |
| 0歳〜85歳 | 月払い(最低月額3,000円~)一時払いも可能 | 60歳~75歳から選択 | 国内外の株式型・債券型など、ソニー生命が厳選した16種類の特別勘定から最大8種類を選択可能 |
※正式な契約可能年齢範囲は商品パンフレット等で要確認
メリット:
デメリット:
どんな人におすすめか:
TOP2:第一生命「ステップジャンプ」(指数連動型個人年金保険)
第一生命の「ステップジャンプ」は、元本保証と運用成果の両立を図った指数連動型の個人年金保険です。契約日から3年経過以後は、解約時に払い込んだ保険料の累計額(基本年金原資)が最低保証されます。その上で、毎年1回設定された参照指数(株価指数など)が前年より上昇した場合、上乗せ部分の年金原資が増えていきます。仮に翌年指数が下がっても、一度増えた上乗せ部分は減少せず据え置かれるという「リセット型」の仕組みになっています。この2階建て構造により、「元本が減らない安心感」と「増える期待」を両立しているのが大きな特徴です。
商品の特徴(例):
| 契約可能年齢 | 保険料払込期間 | 元本保証の条件 | 年金受取形態 |
| 0歳~80歳 | 最短5年〜最長40年程度(設計による) | 契約から3年経過後基本年金原資を保証 | 5年/10年確定年金など選択(年金受取開始60歳以降) |
メリット:
デメリット:
どんな人におすすめか:
TOP3:アクサ生命「ユニット・リンク」(有期型変額保険)
アクサ生命の「ユニット・リンク」は、“資産形成のための変額保険”というコンセプトで提供されている有期型の変額保険です。保険期間と保険料払込期間を10年・15年・20年……80歳満了などから設定でき、死亡・高度障害保障を備えながら資産運用ができます。契約者は保険料の一部を用いて特別勘定で資産運用を行い、将来の満期保険金や解約返戻金が運用実績によって増減します。死亡または高度障害時には死亡保険金が支払われ、基本保険金額が最低保証されているため、運用が不調でも一定額の保障が確保されます。
商品の特徴(例):
| 契約可能年齢 | 保険期間/払込期間 | 運用スタイル | 死亡保障 |
| 0歳~65歳 | 10年・15年・20年・25年・30年満了または50歳〜80歳満了から選択 | 国内外の株式・債券・バランス型など、アクサ生命が用意する13種類の特別勘定の中から、最大10種類を組み合わせて選択・運用できます。 | 基本保険金額を保証(最低保障あり) |
メリット:
デメリット:
どんな人におすすめか:
TOP4:プルデンシャル生命「養老保険」(リタイアメント・インカム)
プルデンシャル生命の「養老保険」は、貯蓄性と保障を兼ね備えた定期型の積立保険です。「リタイアメント・インカム」は、満期保険金を年金形式でも受け取れる「年金支払型特殊養老保険」です 。主に「米国ドル建リタイアメント・インカム」として提供されており、米国の金利環境を活かした資産形成が期待できる商品です。基本は米ドル建てですが、「円換算支払特約」などを付加することで、保険料の支払いや保険金・年金の受け取りを円で行うことも可能です 。ただし、その際には為替手数料が発生し、為替レートの変動により円換算での受取額が払込保険料の円換算額を下回る「為替リスク」が伴います。円建ての同名商品も存在しますが、主力は米ドル建て商品です。
商品の特徴(例):
| 契約可能年齢 | 保険期間 / 払込期間 | 通貨建て | 満期金の受取方法 |
| 0歳~60歳前後(契約プランによる) | 10年・15年・20年など選択(もしくは60歳満期など) | 円建て / 外貨建て(米ドル建など) | 一括受取 or 年金受取選択可 |
メリット:
デメリット:
どんな人におすすめか:
保険以外で資産形成におすすめの制度
最後に、資産形成の手段として保険以外に利用できる代表的な制度についても触れておきます。保険は保障と貯蓄を兼ねられる反面、流動性やリターン面で制約があります。そこで、より積極的に資産を増やしたい人や、保障は別途確保して運用は運用で行いたい人向けに、NISAとiDeCoという2つの制度を紹介します。いずれも税制優遇を活かして効率よくお金を増やすためのもので、保険商品と併用して資産形成することも可能です。
NISA(少額投資非課税制度)
NISA(ニーサ)は、投資による利益が一定枠まで非課税になる制度です。株式や投資信託などに投資して得た売却益や配当に本来20%程度課税されるところ、NISA口座内での運用益は非課税になるため、税金を気にせず運用できるメリットがあります。日本国内に在住する、その年の1月1日時点で18歳以上の方であれば誰でも証券会社等でNISA口座を開設できます。
NISAにはこれまで一般NISAとつみたてNISAの2種類がありましたが、2024年から制度が拡充・恒久化され、新NISAとして一本化されました。新NISAでは年間最大360万円の投資枠(成長投資枠と積立枠の合計)で株式や投資信託を購入でき、生涯の投資上限額は1,800万円となっています。年間の投資上限額360万円の内訳は、長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託が対象の「つみたて投資枠」が120万円、上場株式なども購入できる「成長投資枠」が240万円です。生涯にわたる非課税保有限度額は合計で1,800万円ですが、そのうち成長投資枠で利用できるのは最大1,200万円までという上限も設けられています。非課税保有期間も無期限化され、ずっと非課税で運用可能です。少額からのコツコツ積立投資にも、大きな額の一括投資にも対応できる柔軟な制度になりました。
NISAの活用ポイント:
どんな人におすすめか:
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCo(イデコ)は、個人で加入する任意の私的年金制度で、公的年金に上乗せして老後資金を準備するための仕組みです。毎月一定額を積み立てて、自分で選んだ金融商品(定期預金・投資信託・保険商品など)で運用し、60歳以降にその積立金を年金または一時金で受け取ります。公的年金の将来額に不安がある中、自助努力で老後資金を作る手段として注目されています。
iDeCo最大の特徴は、掛金が全額所得控除になる点です。毎月拠出する掛金はその年の所得から差し引けるため、所得税・住民税が減額されます。例えば月2万円(年間24万円)拠出している人なら、年収にもよりますが毎年数万円程度の節税効果が得られます。また、運用益も非課税、受け取る時も公的年金等控除・退職所得控除の対象となり税負担が抑えられるというトリプル税制優遇が魅力です。
ただし、iDeCoは原則60歳まで資金を引き出せない(途中解約不可)という制約があります。老後資金専用と割り切り、長期で積み立てる覚悟が必要です。また加入できる掛金上限は職業によって異なり、会社員(企業年金なし)は月額2.3万円まで、公務員は1.2万円までなどと定められています。
iDeCoの活用ポイント:
どんな人におすすめか:
まとめ
今回は保険による資産形成についてメリット・デメリットから具体的な商品、他の制度まで幅広く解説しました。保険は「万が一への保障」と「計画的な貯蓄」を両立できる手段ですが、その分長期的な契約継続や大きなリターンは望めないといった制約もあります。大切なのは、自分や家族のライフプランを踏まえて、「どのくらいの保障が必要か」「いつまでにいくら貯めたいか」「リスクをどの程度取れるか」を総合的に判断することです。保険商品も金融情勢や制度改正によって新しいものが登場したり内容が変わったりしますので、最新情報を確認しつつ検討してください。
資産形成の方法は一つではありません。保険と投資、そして公的制度を上手に組み合わせて、安心で豊かな将来に向けた資産づくりを始めましょう。