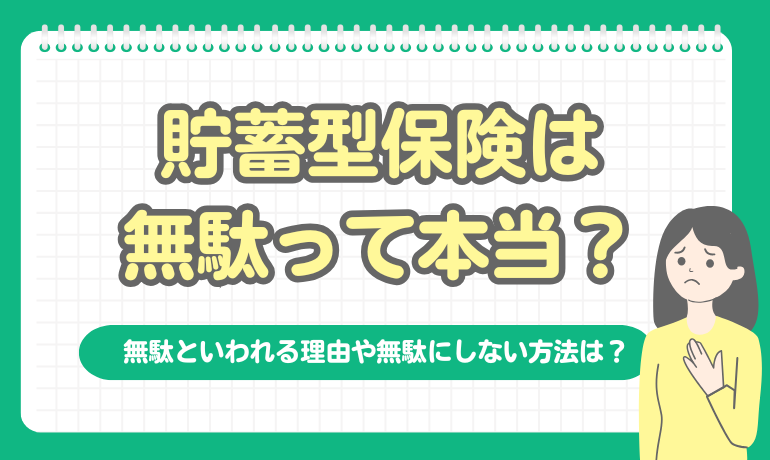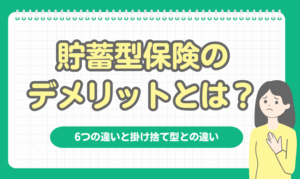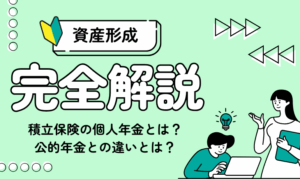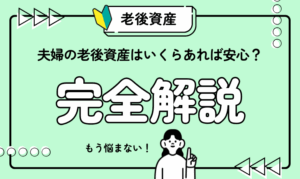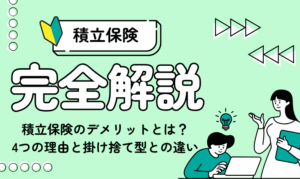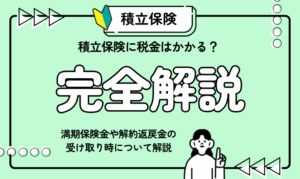「万が一の備えをしながら、将来のためにお金も貯められる」という魅力的なキャッチフレーズで知られる貯蓄型保険。しかし、インターネットやSNSでは「貯蓄型保険は無駄」「入ると損をする」といったネガティブな意見も多く見られます。
これから加入を検討している方にとっては、「本当に無駄なのだろうか?」と不安になりますし、すでに加入している方も「もしかして自分は損をしているのかも……」と心配になるかもしれません。
この記事では、「貯蓄型保険は無駄」というキーワードに焦点を当て、なぜ無駄といわれるのか、その具体的な理由を深掘りします。さらに、貯蓄型保険のメリットや、どのような人にとって無駄になり、どのような人には向いているのかを徹底解説。
すでに入ってしまった方が損をしないための対策や、これから選ぶ方が無駄にしないための賢い選び方まで、網羅的にご紹介します。この記事を読めば、あなたが貯蓄型保険に入るべきかどうかの判断基準が明確になり、ご自身の資産形成にとって最適な選択ができるようになるでしょう。
貯蓄型保険は加入しても無駄な保険?
結論から言うと、貯蓄型保険はすべての人にとって一概に「無駄」というわけではありません。無駄だと感じておすすめしない人がいる一方で、そのメリットを理解し、有効活用している人がいるのも事実です。
大切なのは、貯蓄型保険の特性を正しく理解し、自分の目的やライフプラン、価値観に合っているかどうかを見極めることです。
そこで、まずはこの記事の要点として、どのような人が貯蓄型保険を「無駄」と感じやすく、どのような人が「無駄ではない」と感じるのか、その特徴を見ていきましょう。
貯蓄型保険が無駄になる人の特徴
より高いリターンを求めて積極的に資産を増やしたい人:
「保障」と「貯蓄」を分けて効率的に管理したい人:
近い将来、大きな出費の予定がある人:
インフレによる資産価値の目減りを懸念する人:
保障内容を充実させたいが、保険料は抑えたい人:
貯蓄型保険が無駄ではない人の特徴
貯金が苦手で、半強制的にでもお金を貯める仕組みが欲しい人:
投資の元本割れリスクを取るのが怖い、または避けたい人:
万が一の保障と将来の資産形成を、一つの契約でシンプルに管理したい人:
生命保険料控除を活用して、少しでも節税したい人:
このように、貯蓄型保険は個人の考え方や状況によって、その価値が大きく変わります。では、なぜこれほどまでに「無駄」「やめとけ」といわれてしまうのでしょうか。次の章で、その具体的な理由を詳しく見ていきましょう。
貯蓄型保険は無駄!やめとけといわれる4つの理由
貯蓄型保険が「無駄だ」「損をする」といわれる背景には、主に4つの明確な理由(デメリット)があります。これらの点を理解することが、適切な判断を下すための第一歩です。
1. 返戻率が低く、期待するほどお金が増えない
「貯蓄型」という名前から、銀行預金よりも大きくお金が増えることを期待するかもしれません。しかし、現在の超低金利時代においては、貯蓄型保険の返戻率も決して高いとはいえません。
返戻率とは、支払った保険料の総額に対して、将来受け取れる満期保険金や解約返戻金がどれくらいの割合かを示す数値です。
この返戻率が100%を下回っている期間に解約すると、元本割れを起こして損をします。100%を超えて初めて、支払った保険料よりも多くのお金が戻ってくることになります。
例えば、30歳男性が保険料払込期間30年(60歳満了)、死亡保障300万円の終身保険に加入したケースを考えてみましょう。
- 月払保険料:8,000円
- 年間保険料:96,000円
- 30年間の払込保険料総額:2,880,000円
- 60歳時点の解約返戻金:約2,950,000円
この場合の返戻率は、約102.4%(295万円 ÷ 288万円 × 100)です。30年かけて、ようやく7万円増える計算になります。年利に換算すると、ごくわずかなリターンしか得られません。
もちろん、銀行の普通預金(金利0.001%など)よりは魅力的ですが、資産を「増やす」という目的で考えると、物足りなさを感じる人が多いのが実情です。
2. 長期的にみると資産が目減りする
貯蓄型保険のもう一つの大きな弱点は、インフレに弱いことです。インフレとは、物価が継続的に上昇し、相対的にお金の価値が下がることです。
例えば、現在100円で買えるジュースが、20年後にはインフレで120円になっているかもしれません。これは、20年後の100円の価値が、現在の100円よりも低くなっていることを意味します。
貯蓄型保険の多くは、契約時に将来受け取る金額が固定されている「固定金利型」です。仮に30年後に300万円を受け取る契約を結んだとします。インフレが年2%で進んだ場合、30年後の300万円の実質的な価値は、現在の価値に換算すると約165万円にまで目減りしてしまいます。
たとえ返戻率が105%や110%で、額面上は数十万円増えていたとしても、インフレ率がそれを上回っていれば、実質的には資産が減っている(=損をしている)ことになるのです。
このインフレリスクを考慮すると、長期間資金が固定される貯蓄型保険は、将来の購買力を維持するという観点からは不利な商品といえるかもしれません。
3. 保障を重視すると保険料が高くなる
「保障も貯蓄も」というのが貯蓄型保険の魅力ですが、実はこの二つを両立させようとすると、月々の保険料が非常に高額になります。
保険料の内訳は、万が一の際に支払われる保険金の原資となる「保障部分」のコストと、将来の返戻金のために積み立てる「貯蓄部分」のコスト、そして保険会社の運営経費などで構成されています。
手厚い死亡保障や医療特約などをつければつけるほど、保障部分のコストが膨らみ、保険料全体が跳ね上がります。
ここで比較対象となるのが、貯蓄機能のない「掛け捨て型保険」です。掛け捨て型保険は、保障機能に特化しているため、同じ保障内容であれば貯蓄型保険よりも圧倒的に保険料が安く済みます。
例えば、30歳男性が死亡保障1,000万円を確保する場合、
- 貯蓄型保険(終身保険):月々2万円~3万円程度
- 掛け捨て型保険(定期保険):月々2,000円~3,000円程度
これほどの価格差が生まれます。
「保険は保険、貯蓄は貯蓄」と割り切って考える人から見れば、「同じ保障を得るために、毎月2万円以上の差額を支払うのは無駄だ。その差額を自分でNISAなどで運用した方が、はるかに効率的にお金を増やせる」という結論に至るのです。これが、「貯蓄型保険はやめとけ」といわれる大きな理由の一つです。
4. 途中解約をすると損をする
貯蓄型保険の最大のデメリットであり、最も注意すべき点が、途中解約による元本割れのリスクです。
契約から年数が浅い段階で解約した場合、解約返戻金は払込保険料総額を大幅に下回ることがほとんどです。なぜなら、支払った保険料から、保険会社の運営経費や保障コストなどが優先的に差し引かれるため、貯蓄に回る分が少ないからです。
特に、保険料の払込期間中の解約返戻金を低く抑える代わりに、払込満了後の返戻率を高く設定している「低解約返戻金型終身保険」などは、払込期間中に解約すると損失がさらに大きくなるため注意が必要です。
人生には、転職による収入減、子どもの進学、住宅購入など、予期せぬライフイベントの変化がつきものです。その際に保険料の支払いが苦しくなり、やむを得ず解約を選択した場合、大きく損をしてしまう可能性があります。
「いつでも引き出せる貯金」という感覚でいると、いざという時に大きな損失を被る危険性があるのです。この流動性の低さとペナルティの大きさも、「無駄」「損をする」といわれる所以です。
無駄じゃない!貯蓄型保険のメリット
ここまで貯蓄型保険のデメリットを中心に解説してきましたが、もちろんメリットも存在します。これらのメリットが自分のニーズに合致すれば、貯蓄型保険は「無駄ではない」有効な選択肢となります。
1. 保障を受けながらも貯蓄ができる
最大のメリットは、万が一の死亡や病気・ケガに備える「保障」と、将来に向けた「貯蓄」を一つの商品で同時に準備できる点です。
特に、自分でお金を管理するのが苦手、貯金しようと思ってもつい使ってしまうという人にとっては、毎月自動的に保険料が引き落とされる仕組みは、半強制的に資産形成を進める上で非常に効果的です。まさに「貯金代わり」の役割を果たしてくれます。
保険料の払込期間が満了すれば、基本的には支払った保険料以上の満期金や解約返戻金を受け取れるため、「保障は必要だけど、掛け捨てで何も戻ってこないのはもったいない」と感じる人にとっては、魅力的な商品といえるでしょう。
2. 投資のようなリスクがない
株式投資や投資信託は、高いリターンが期待できる一方で、経済情勢などによって価格が変動し、元本割れするリスクが常に伴います。
一方、貯蓄型保険(円建ての定額タイプ)は、契約時に将来受け取れる金額が確定しているため、マーケットの変動を気にする必要がありません。
「投資は怖いけれど、銀行預金以上の利回りは確保したい」という、安定志向の方のニーズに応えることができる金融商品です。計画的に、着実に、決められた金額を貯めていきたい人にとっては、この安心感が大きなメリットとなります。
3. 生命保険料控除で節税ができる
貯蓄型保険の保険料を支払うと、「生命保険料控除」という制度を利用して、所得税と住民税の負担を軽減できます。
生命保険料控除には、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つの枠があり、それぞれに控除の上限額が定められています(2012年1月1日以降の契約の場合)。
| 控除の種類 | 年間払込保険料 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
| 一般生命保険料 | 80,001円以上 | 最大4万円 | 最大2.8万円 |
| 介護医療保険料 | 80,001円以上 | 最大4万円 | 最大2.8万円 |
| 個人年金保険料 | 80,001円以上 | 最大4万円 | 最大2.8万円 |
| 合計 | 最大12万円 | 最大7万円 |
仮に、年収500万円(所得税率20%、住民税率10%)の人が、一般生命保険料控除の枠で年間8万円以上の保険料を支払った場合、どのくらい節税できるか見てみましょう。
- 所得税の軽減額:40,000円(控除額) × 20%(税率) = 8,000円
- 住民税の軽減額:28,000円(控除額) × 10%(税率) = 2,800円
- 合計の年間節税額:10,800円
年間約1万円の節税は、決して小さな金額ではありません。保険の返戻率に加えて、この節税効果も加味すると、実質的なリターンはもう少し高くなります。これは掛け捨て型保険でも同様に適用されますが、貯蓄型保険のメリットの一つとして挙げられます。
やめたいけど損したくない!貯蓄型保険を無駄にしない方法
「デメリットを読んで、今入っている貯蓄型保険をやめたくなった。でも、解約すると損をするのは避けたい…」
そう考えている方も少なくないでしょう。すでに加入してしまった保険を無駄にしないためには、いくつかの方法があります。安易に解約する前に、以下の選択肢を検討してみてください。
基本は「払込満了まで待つ」
最もシンプルで確実な方法は、保険料の払込期間が満了するまで支払いを続けることです。そして、返戻率が100%を超えたタイミングで解約、または満期を迎えれば、元本割れを防ぐことができます。支払いが苦しくないのであれば、これが最も損の少ない選択肢です。
「払済保険」に変更する
今後の保険料の支払いが難しい場合は、「払済(はらいずみ)保険」への変更を検討しましょう。これは、保険料の支払いを中止し、その時点での解約返戻金を元手(一時払保険料)として、保障期間が一生涯の、より保障額の小さい保険に切り替える方法です。
例えば、死亡保障1,000万円の終身保険を、解約返戻金が200万円の時点で払済保険に変更すると、死亡保障は300万円に減るものの、一生涯の保障として残すことができます。保障は確保しつつ、今後の保険料負担をゼロにできるのがメリットです。
「延長(定期)保険」に変更する
「延長(定期)保険」も、今後の保険料の支払いをストップする方法です。これは、解約返戻金を元手として、元の保険と同じ保障額の「定期保険」に切り替えるものです。
保障額は変わりませんが、保障期間は元の終身から、10年、15年といった一定期間に変更(短縮)されます。一定期間だけでも手厚い保障を確保したい場合に有効な方法です。
「契約者貸付」を利用する
一時的にお金が必要になっただけで、保険料の支払いは続けられるという場合は、「契約者貸付制度」を利用しましょう。これは、解約返戻金の一定の範囲内(通常7〜9割程度)で、保険会社からお金を借りられる制度です。
解約ではないため、保障はそのまま継続され、元本割れのリスクもありません。ただし、所定の利息がかかるため、返済計画はしっかり立てる必要があります。
無駄にならない貯蓄型保険の選び方
これから貯蓄型保険への加入を検討するなら、これまでに解説した「無駄になる理由」を回避するための選び方を実践することが重要です。以下の4つのポイントを押さえて、後悔のない保険選びをしましょう。
1. ライフプランに合わせた期間を選ぶ
なぜ、いつまでに、いくら貯めたいのか――。この「目的」を明確にすることが、最も重要です。
これらのライフプランを具体的に描き、お金が必要になる時期に合わせて満期や保険料の払込期間を設定しましょう。例えば、18歳の子どもの大学進学資金が目的なら、払込期間を10年や15年に設定する学資保険などが候補になります。
期間が長くなるほど月々の保険料は安くなりますが、その分、途中で支払えなくなるリスクも高まります。無理なく支払い続けられる保険料であるかを、慎重に判断してください。
2. 目的に合わせた保障内容を選ぶ
貯蓄性を重視するのか、保障を重視するのかによって、選ぶべき商品は変わります。貯蓄が第一目的なら、保障は必要最低限に絞りましょう。
死亡保障、医療保障、介護保障、先進医療特約など、様々な保障(特約)がありますが、不要な保障をつければつけるほど保険料は高くなり、貯蓄性が下がってしまいます。
すでに他の保険で十分な保障を確保している場合は、保障の重複にも注意が必要です。自分にとって本当に必要な保障は何かを見極め、できるだけシンプルな設計にすることが、無駄にしないためのコツです。
3. 返戻率の高い保険を選ぶ
貯蓄目的で加入する以上、返戻率は最も重要な比較ポイントです。少しでも有利な条件で資産形成できるよう、複数の保険会社の商品を比較検討しましょう。
低解約返戻金型終身保険:
払込期間中の解約返戻金が低い分、払込満了後の返戻率が高めに設定されています。最後まで払い切る自信がある人向けです。
外貨建て保険:
米ドルや豪ドルなどで保険料を支払い、保険金も外貨で受け取る商品。為替リスクはありますが、日本の円建て保険より高い利回りが期待できます。
変額保険:
支払った保険料を株式や債券で運用し、その運用実績によって保険金額や解約返戻金が変動する商品。ハイリスク・ハイリターンを狙えます。
最近では、満期まで待たずとも、数年で返戻率が100%を超えるような貯蓄性の高い商品も出てきています。自分のリスク許容度と目的に合わせて、最適な商品を選びましょう。
4. 可能なら一括払いにする
もし手元にまとまった資金があるのなら、「一時払(一括払い)」を検討するのも有効な手段です。保険料を契約時に一括で支払う方法で、月払いや年払いに比べて総支払保険料が割り引かれます。
支払う保険料の総額が少なくなるため、結果的に返戻率が高くなるというメリットがあります。資金に余裕がある場合は、非常に効率的な選択肢といえるでしょう。
まとめ:貯蓄型保険は特性を理解すれば無駄じゃない
「貯蓄型保険は無駄で損をする」という意見は、主に「返戻率の低さ」「インフレリスク」「保険料の高さ」「途中解約での元本割れ」といったデメリットに基づいています。特に、より高いリターンを求める人や、「保障」と「貯蓄」を分けて効率的に運用したい人にとっては、「無駄」と感じられる可能性が高いでしょう。
一方で、貯金が苦手な人が半強制的に資産形成できる「貯金代わり」の仕組みや、投資のような元本変動リスクがない「安心感」、生命保険料控除による「節税効果」といったメリットも確かに存在します。
結論として、貯蓄型保険が無駄になるかどうかは、あなたの目的や価値観次第です。
大切なのは、メリット・デメリットの両方を正しく理解し、ご自身のライフプランや資産状況、リスク許容度に照らし合わせて、最適な選択をすることです。この記事が、あなたが「貯蓄型保険」と賢く向き合うための一助となれば幸いです。
おすすめの貯蓄型保険はこちらをチェック!
自分に合った貯蓄型保険がどのようなものか、さらに詳しく知りたい方や、具体的な商品を比較検討したい方は、保険の専門家やランキングサイトなどを参考にしてみることをお勧めします。複数の選択肢の中から、あなたの未来を豊かにする最適な一本を見つけてください。