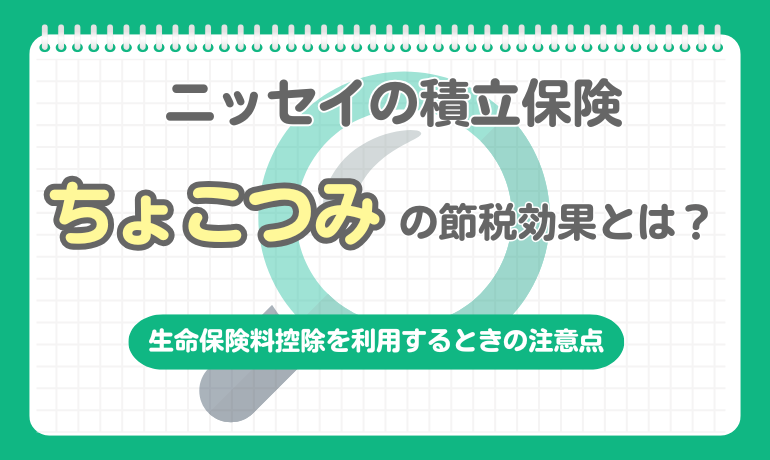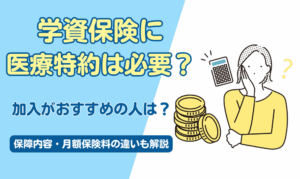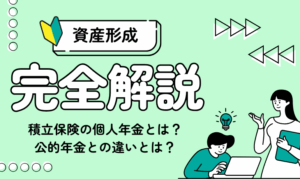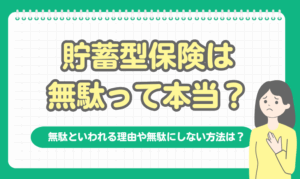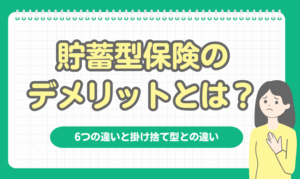節税対策を検討している方の中で、日本生命の「ちょこつみ」に注目する方が増えています。毎月わずかな保険料で始められるこの積立保険は、生命保険料控除を活用した節税効果が期待できる商品として知られています。
しかし、実際にどの程度の節税効果があるのか、また加入する際にはどのような点に注意すべきなのか、詳しく理解している方は少ないのではないでしょうか。本記事では、ちょこつみの節税効果について具体的な数値を交えながら解説し、効果的に活用するためのポイントをお伝えします。
節税できる!日本生命のちょこつみは生命保険料控除の対象
日本生命のちょこつみは、正式名称を「ニッセイ積立保険」といい、傷害保障付積立保険として分類されています。しかし、保障内容は最小限に抑えられており、実質的には節税保険としての性格が強い商品設計となっています。
生命保険料控除とは、1年間に支払った生命保険料に応じて、所得税や住民税から一定額が控除される制度です。この制度を利用することで、年末調整や確定申告を通じて税負担を軽減することができます。控除の対象となる保険は、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3つの区分に分かれており、ちょこつみは一般生命保険料に該当します。
ちょこつみの返戻率は約103%程度と、他の貯蓄型保険と比較して特別高いわけではありません。しかし、節税効果を利回りに換算すると、年収や保険料によって異なりますが、実質的に7.5%から28%という驚異的な数値になることもあります。これは、支払った保険料に対して得られる節税メリットが非常に大きいことを意味しています。
特に注目すべきは、月々3,000円という少額から始められる点です。年間36,000円の保険料で、所得税と住民税を合わせて数千円から1万円以上の節税効果が期待できるため、投資効率の観点から見ても優れた選択肢といえるでしょう。
ちょこつみの実際の節税効果
所得税と住民税の控除額
ちょこつみに加入した場合の節税効果を具体的に見ていきましょう。生命保険料控除の仕組みは、年間の保険料支払額に応じて段階的に控除額が決まります。
- 20,000円以下:支払保険料の全額
- 20,001円~40,000円:支払保険料×1/2+10,000円
- 40,001円~80,000円:支払保険料×1/4+20,000円
- 80,001円以上:一律40,000円
- 12,000円以下:支払保険料の全額
- 12,001円~32,000円:支払保険料×1/2+6,000円
- 32,001円~56,000円:支払保険料×1/4+14,000円
- 56,001円以上:一律28,000円
月額3,000円(年間36,000円)の場合、所得税の控除額は28,000円、住民税の控除額は23,000円となります。月額5,000円(年間60,000円)では、所得税35,000円、住民税28,000円の控除を受けることができます。
保険料と年収別の節税効果
実際の節税効果は、個人の年収によって適用される税率が異なるため、同じ保険料でも節税額に差が生じます。以下、具体的な事例を見ていきましょう。
保険料3000円の場合の節税効果
月額3,000円(年間36,000円)の保険料を支払った場合の節税効果を年収別に示します。
| 年収 | 所得税率 | 所得税節税額 | 住民税節税額 | 合計節税額 | 実質利回り |
| 300万円 | 5% | 1,400円 | 2,300円 | 3,700円 | 10.3% |
| 500万円 | 10% | 2,800円 | 2,300円 | 5,100円 | 14.2% |
| 700万円 | 20% | 5,600円 | 2,300円 | 7,900円 | 21.9% |
| 1000万円 | 23% | 6,440円 | 2,300円 | 8,740円 | 24.3% |
保険料5000円の場合の節税効果
月額5,000円(年間60,000円)の場合の節税効果は以下のとおりです。
| 年収 | 所得税率 | 所得税節税額 | 住民税節税額 | 合計節税額 | 実質利回り |
| 300万円 | 5% | 1,750円 | 2,800円 | 4,550円 | 7.6% |
| 500万円 | 10% | 3,500円 | 2,800円 | 6,300円 | 10.5% |
| 700万円 | 20% | 7,000円 | 2,800円 | 9,800円 | 16.3% |
| 1000万円 | 23% | 8,050円 | 2,800円 | 10,850円 | 18.1% |
保険料10000円~の場合の節税効果
月額10,000円(年間120,000円)の場合、控除額は上限に達するため、それ以上保険料を増やしても節税効果は変わりません。
| 年収 | 所得税率 | 所得税節税額 | 住民税節税額 | 合計節税額 | 実質利回り |
| 300万円 | 5% | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | 4.0% |
| 500万円 | 10% | 4,000円 | 2,800円 | 6,800円 | 5.7% |
| 700万円 | 20% | 8,000円 | 2,800円 | 10,800円 | 9.0% |
| 1000万円 | 23% | 9,200円 | 2,800円 | 12,000円 | 10.0% |
このように、保険料が少額であるほど実質利回りは高くなる傾向があります。特に月額3,000円の場合、高所得者であれば20%を超える実質利回りを実現できることがわかります。
節税目的でちょこつみに加入するときの注意点
節税できるのは最初の3年間だけ
ちょこつみの最大の特徴であり、同時に注意すべき点は、保険料の支払期間が3年間に限定されていることです。満期は10年ですが、4年目以降は保険料の支払いがないため、生命保険料控除を利用できるのは加入から3年間のみとなります。
つまり、10年間の保険期間のうち、実際に節税メリットを享受できるのは最初の30%の期間だけということになります。4年目から10年目までの7年間は、積み立てた資金が据え置かれるだけで、新たな節税効果は生まれません。この点を理解せずに加入すると、期待していた節税効果が得られず、がっかりすることになりかねません。
控除枠には他の保険も含まれる
生命保険料控除には上限額が設定されており、一般生命保険料控除の場合、所得税で最大40,000円、住民税で最大28,000円までしか控除を受けることができません。
重要なのは、この控除枠はちょこつみだけでなく、他の生命保険も含めた合計額で計算されることです。例えば、すでに終身保険や定期保険、学資保険などに加入している場合、それらの保険料とちょこつみの保険料を合算して控除額が決まります。
生命保険料控除の対象となる主な保険商品には、終身保険、定期保険、養老保険、学資保険、収入保障保険などがあります。医療保険やがん保険は介護医療保険料控除の対象となり、個人年金保険は個人年金保険料控除の対象となるため、それぞれ別枠で控除を受けることができます。
既に他の生命保険で年間8万円以上の保険料を支払っている場合、ちょこつみに加入しても追加の節税効果は期待できません。加入前に、現在の保険料支払状況を確認し、控除枠に余裕があるかどうかを確認することが重要です。
ちょこつみの節税以外のメリットやデメリット
ちょこつみのメリット
ちょこつみには節税効果以外にも、以下のようなメリットがあります。
少額から始められる柔軟性
元本保証がある安心感
解約の自由度が高い
再加入が可能
手続きが簡単
ちょこつみのデメリット
一方で、以下のようなデメリットも存在します。
保障機能が限定的
インフレリスクへの対応不足
運用益が少ない
節税期間が短い
年齢制限がある
ちょこつみとじぶんの積立、節税効果が高いのはどちら?
節税保険として、明治安田生命の「じぶんの積立」もよく比較対象として挙げられます。両商品の節税効果を比較してみましょう。
じぶんの積立の最大の特徴は、保険料の支払期間が5年間である点です。ちょこつみが3年間であるのに対し、2年長く生命保険料控除を利用できるため、トータルの節税額はじぶんの積立の方が大きくなります。
例えば、月額5,000円の保険料で年収500万円の方の場合、ちょこつみでは3年間で18,900円の節税効果があるのに対し、じぶんの積立では5年間で31,500円の節税効果が期待できます。単純計算で1.67倍の差があることになります。
ただし、ちょこつみには大きなアドバンテージがあります。それは、解約後すぐに再加入できることです。じぶんの積立は解約後に一定の空白期間を設ける必要があり、連続して節税効果を得ることができません。
ちょこつみの場合、3年間加入して満期を迎える前に解約し、すぐに新規で契約することで、再び3年間の節税効果を得ることができます。この方法を活用すれば、理論上は永続的に節税メリットを享受することが可能です。
どちらを選ぶべきかは、個人の状況や考え方によって異なります。手間をかけずに長期間の節税効果を得たい方はじぶんの積立、定期的な見直しを苦にせず、継続的に節税効果を最大化したい方はちょこつみが適しているといえるでしょう。
まとめ
ニッセイの積立保険ちょこつみは、生命保険料控除を活用した効果的な節税手段として注目されています。月々3,000円から始められる手軽さと、実質利回り10%を超える節税効果は、特に所得税率の高い方にとって大きなメリットとなります。
ただし、節税効果が得られるのは最初の3年間のみであること、他の生命保険との控除枠の兼ね合いを考慮する必要があることなど、注意すべき点も少なくありません。
節税保険として活用する場合は、自身の保険加入状況や税率を確認し、どの程度の節税効果が期待できるかを事前にシミュレーションすることが重要です。また、3年後の解約・再加入を視野に入れた長期的な活用計画を立てることで、より効果的な節税対策となるでしょう。
ちょこつみは、節税という観点から見れば優れた商品ですが、あくまでも保険商品であることを忘れてはいけません。保障内容や資産運用の観点も含めて総合的に判断し、自身のライフプランに合った活用方法を選択することが大切です。
節税対策は個人の状況によって最適な方法が異なります。ちょこつみの活用を検討される際は、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家にも相談しながら、自身にとって最適な節税戦略を構築していくことをおすすめします。