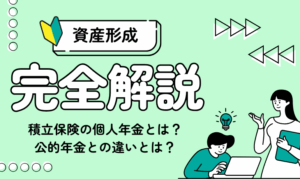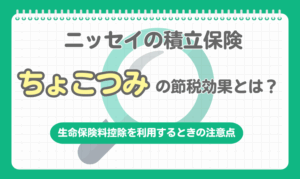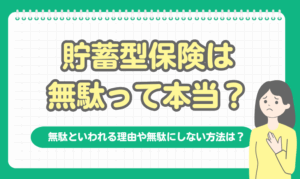節税効果が注目される日本生命の「ちょこつみ」。保険料控除を活用できる積立保険として人気を集めていますが、メリットばかりではありません。
本記事では、ちょこつみに興味はあるものの「本当にデメリットはないのか」と疑問を持つ方に向けて、ちょこつみの注意すべきデメリットを詳しく解説します。加入を検討する前に、しっかりとデメリットも理解しておきましょう。
節税ができる日本生命のちょこつみにデメリットはある?
ちょこつみは、日本生命が提供する積立保険です。正式名称は「ニッセイ みらいのカタチ 積立保険」で、月々5,000円から始められる手軽な積立保険として知られています。
この保険の最大の特徴は、生命保険料控除の対象となることです。年末調整や確定申告で保険料控除を受けることで、所得税や住民税の節税効果が期待できます。つまり、単なる貯蓄ではなく、税制優遇を受けながらお金を積み立てられる商品として設計されています。
積立期間は3年間で、その後は7年間の据置期間を経て満期を迎えます。途中解約しても元本割れしないという特徴もあり、リスクを抑えた資産形成の手段として注目されています。
しかし、一見メリットばかりに見えるちょこつみにも、実はいくつかのデメリットが存在します。特に、資産を大きく増やしたい方や長期的な積立を考えている方にとっては、期待に応えられない部分もあるのです。
ちょこつみの5つのデメリット
ちょこつみには主に5つのデメリットがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
満期の返戻率が低い
ちょこつみの最も大きなデメリットは、満期時の返戻率が決して高くないことです。
積立期間3年、据置期間7年の合計10年で満期を迎えた場合、返戻率は約105.2%となります。つまり、100万円積み立てた場合、10年後に受け取れる満期金は約105万2,000円ということになります。
具体的な数字で見てみましょう。月々1万円を3年間積み立てた場合、総払込保険料は36万円です。この場合の返戻金は以下のようになります。
- 1年経過時点:約35万8,000円(返戻率99.4%)
- 2年経過時点:約35万9,000円(返戻率99.7%)
- 3年経過時点:36万円(返戻率100.0%)
- 5年経過時点:約36万7,000円(返戻率101.9%)
- 7年経過時点:約37万4,000円(返戻率103.9%)
- 10年満期時点:約37万9,000円(返戻率105.2%)
最初の3年間は全く増えず、その後も年率にすると0.5%程度の増加率です。現在の低金利時代においても、10年で5.2%の増加は決して魅力的な数字とは言えません。投資信託やNISAなどと比較すると、資産を増やす目的には不向きと言わざるを得ません。
保険だけど保障内容が薄い
ちょこつみには傷害保障が付いていますが、その保障内容は極めて限定的です。
具体的な保障内容は以下の通りです。
- 災害死亡保険金:払込保険料の1.1倍
- 災害高度障害保険金:払込保険料の1.1倍
例えば、総払込保険料が36万円の場合、災害死亡時に受け取れる保険金は約39万6,000円です。通常の死亡保険と比較すると、保障としてはあくまでおまけ程度と考えるべきでしょう。
また、この保証は「災害」による死亡や高度障害に限定されています。病気による死亡の場合は、積立金相当額しか受け取れません。保険としての保障機能を期待する方には、物足りない内容となっています。
積立できる期間が短い
ちょこつみの積立期間は3年間と決められており、これ以上長期での積立はできません。
多くの方が老後資金の準備や子どもの教育資金など、10年、20年といった長期スパンでの資産形成を考えています。しかし、ちょこつみは3年で積立が終了してしまうため、長期的な積立計画には適していません。
3年間の積立終了後は、7年間の据置期間に入りますが、この期間中は新たに保険料を払い込むことはできません。つまり、継続的に積立を続けたい方にとっては、使い勝手が悪い商品設計となっています。
年間を通じて計画的に積立を続けたい方や、毎月一定額を長期間積み立てたい方には、他の積立商品を検討する必要があるでしょう。
生命保険料控除の枠が残っていないと節税できない
ちょこつみの大きなメリットとして挙げられる節税効果ですが、これは生命保険料控除の枠が残っている場合に限られます。
生命保険料控除とは、支払った生命保険料に応じて、その年の所得から一定額を控除できる制度です。控除額の上限は以下の通りです。
【所得税の場合】
- 新制度(平成24年1月1日以降の契約):最高4万円
- 旧制度(平成23年12月31日以前の契約):最高5万円
【住民税の場合】
- 新制度:最高2万8,000円
- 旧制度:最高3万5,000円
すでに他の生命保険に加入していて、年間保険料が8万円を超えている場合、新たにちょこつみに加入しても追加の控除は受けられません。つまり、節税効果はゼロということになります。
多くの方が医療保険や死亡保険などに加入している現状を考えると、生命保険料控除の枠が残っている方は限定的かもしれません。加入前に、現在の保険料控除の利用状況を確認することが重要です。
49歳までしか加入できない
ちょこつみの加入年齢は、契約時の年齢が3歳から49歳までと定められています。
50歳以上の方は加入できないため、老後資金の準備を本格的に始めたい50代以降の方にとっては選択肢から外れてしまいます。また、年齢制限があることで、家族全員で同じ商品に加入することが難しいケースも出てくるでしょう。
特に、退職が見えてきた50代の方が節税効果を期待して加入を検討しても、年齢制限により断念せざるを得ません。この点は、幅広い年齢層に対応している他の積立保険と比較すると、大きなデメリットと言えます。
ちょこつみは途中解約しても元金割れしないって本当?
積立保険の多くは、途中解約すると元本割れするリスクがあります。しかし、ちょこつみは「いつ解約しても元本割れしない」という特徴を持っています。
これは事実で、ちょこつみの大きな強みの一つです。契約から1年目であっても、支払った保険料の99.4%以上は返ってきます。3年の積立期間が終了すれば、100%の返戻率が保証されます。
一般的な積立保険では、早期解約すると70%や80%程度しか返ってこないケースも珍しくありません。その点、ちょこつみは急な資金需要が発生した場合でも、大きな損失を被ることなく解約できる安心感があります。
ただし、ここで注意すべきは「元本割れしない」ことと「お金が増える」ことは別だということです。3年以内に解約した場合、返戻率は100%を下回ります。また、満期まで持っても105.2%程度の増加率であることを考えると、インフレリスクを考慮すれば実質的な価値は目減りする可能性もあります。
元本割れしないという安全性は確かに魅力的ですが、それは同時に大きなリターンも期待できないことを意味しています。リスクとリターンは表裏一体であることを理解した上で、加入を検討する必要があります。
ちょこつみのメリットもチェックしよう
デメリットばかりではなく、ちょこつみには以下のようなメリットもあります。
主なメリット
- 生命保険料控除による節税効果が期待できる
- いつ解約しても元本割れしない安全性
- 月々5,000円から始められる手軽さ
- 保険料の払込期間が3年と短い
- 災害死亡・高度障害の保障がついている
- クレジットカード払いが可能
- 健康状態の告知が不要で加入しやすい
- 日本生命という大手保険会社の安心感
特に、健康状態に不安がある方でも加入できる点は大きなメリットです。持病がある方や健康診断で指摘を受けた方でも、問題なく加入できます。
また、保険料の支払いにクレジットカードが使えるため、カードのポイントも貯められます。節税効果と合わせて、実質的な利回りを高めることができるでしょう。
ちょこつみの口コミ評判
実際にちょこつみを利用している方や検討した方の口コミを見てみましょう。
「節税目的で加入しました。年末調整で戻ってくるお金を考えると、実質的な利回りは悪くないと思います。ただ、3年で積立が終わってしまうのは物足りない感じがします」(30代男性)
「元本割れしないという安心感が決め手でした。投資は怖いけど、銀行預金よりは増やしたいという私にはぴったりでした」(40代女性)
「生命保険料控除の枠が空いていたので加入しましたが、すでに他の保険に入っている人にはメリットが薄いと思います。返戻率も期待していたほど高くありませんでした」(30代女性)
「日本生命の営業の方に勧められて加入しましたが、NISAの方が断然お得だと後から気づきました。解約しようか迷っています」(20代男性)
「50歳になってから加入しようと思ったら、年齢制限で入れませんでした。もう少し加入可能年齢を引き上げてほしいです」(50代男性)
その他の意見としては、以下のような声も聞かれます。
肯定的な意見
- 日本生命という大手の安心感がある
- 手続きが簡単で分かりやすい
- 少額から始められるので負担が少ない
否定的な意見
- 投資商品と比べると魅力に欠ける
- 3年という積立期間が中途半端
- 保障内容が薄すぎる
- もっと長期で積立したい
ちょこつみがおすすめの人とおすすめしない人
これまでの内容を踏まえて、ちょこつみがおすすめの人とそうでない人をまとめました。
おすすめの人
- 生命保険料控除の枠が余っている人
- リスクを取らずに少しでも増やしたい人
- 3年程度の短期で積立を考えている人
- 健康状態に不安があるが保険に加入したい人
- 元本割れのリスクを絶対に避けたい人
- 節税効果を重視する人
- 投資経験がなく、安全性を最優先する人
おすすめしない人
- すでに生命保険料控除の枠を使い切っている人
- 資産を大きく増やしたい人
- 10年以上の長期積立を考えている人
- 50歳以上の人
- 充実した保障内容を求める人
- NISAやiDeCoなどの投資に抵抗がない人
- インフレリスクを考慮した資産運用をしたい人
ちょこつみとじぶんの積立の違い
節税目的の積立保険として、ちょこつみとよく比較されるのが明治安田生命の「じぶんの積立」です。両者は似た商品ですが、いくつかの違いがあります。
| 項目 | ちょこつみ(日本生命) | じぶんの積立(明治安田生命) |
| 保険会社 | 日本生命 | 明治安田生命 |
| 月額保険料 | 5,000円~ | 5,000円、10,000円、15,000円、20,000円 |
| 積立期間 | 3年 | 5年 |
| 満期 | 10年 | 10年 |
| 満期時返戻率 | 約105.2% | 103.0% |
| 加入年齢 | 3歳~49歳 | 18歳~65歳 |
| 途中解約 | いつでも元本割れなし | いつでも100%返戻 |
| 保障内容 | 災害死亡・高度障害保障あり | 災害死亡給付金あり |
| 健康告知 | 不要 | 不要 |
| 保険料払込方法 | 口座振替、クレジットカード | 口座振替のみ |
大きな違いは、積立期間と加入可能年齢です。じぶんの積立は5年間積立を続けられ、65歳まで加入できるため、より幅広い層に対応しています。一方、ちょこつみは満期時の返戻率が若干高く、クレジットカード払いに対応している点が優れています。
どちらを選ぶかは、個人のニーズによって異なります。長期間積立を続けたい方や50歳以上の方は「じぶんの積立」、返戻率を重視する方や3年で積立を終えたい方は「ちょこつみ」が適しているでしょう。
まとめ
日本生命のちょこつみは、生命保険料控除を活用した節税効果と、元本割れしない安全性が魅力の積立保険です。しかし、満期時の返戻率が105.2%と低く、積立期間が3年と短いなど、いくつかのデメリットも存在します。
特に注意すべきは、すでに生命保険料控除の枠を使い切っている場合、節税メリットが得られないことです。また、49歳までしか加入できない年齢制限も、多くの方にとってネックになる可能性があります。
ちょこつみは「リスクを取らずに少しでも増やしたい」「節税効果を活用したい」という方には適していますが、「資産を大きく増やしたい」「長期的に積立を続けたい」という方には不向きです。
加入を検討する際は、自身の保険加入状況、資産運用の目的、リスク許容度などを総合的に判断することが重要です。節税効果だけに目を奪われず、他の選択肢とも比較検討した上で、最適な商品を選ぶようにしましょう。
投資目的であればNISAやiDeCo、保障重視であれば他の生命保険、安全性重視であれば定期預金など、それぞれの目的に応じた金融商品があります。ちょこつみはあくまでその選択肢の一つとして、メリット・デメリットをしっかり理解した上で活用することが大切です。