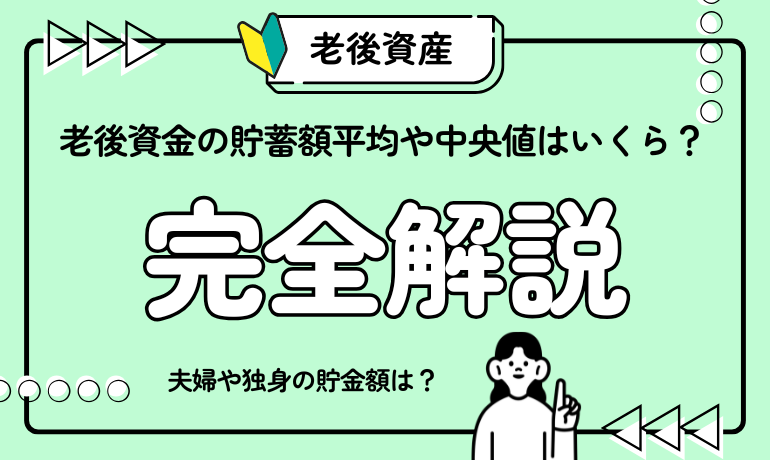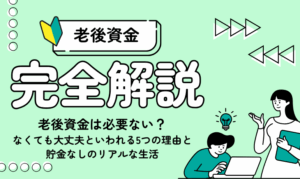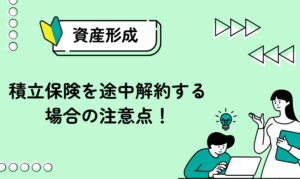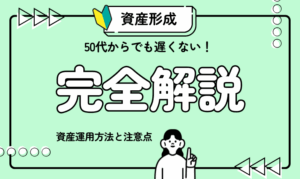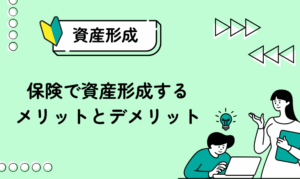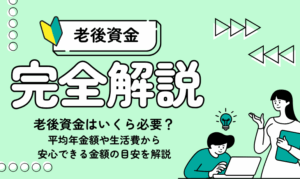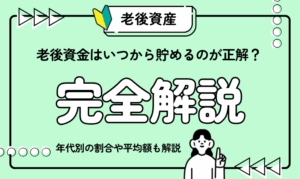老後資金をコツコツと貯めているものの、「自分の貯蓄額は他の人と比べて多いのか少ないのか」と気になっている方は多いのではないでしょうか。老後の生活に向けて準備を進める中で、周りの人がどれくらい貯めているのか、平均的な貯蓄額はどの程度なのかを知ることは、自分の老後資金計画を見直す良いきっかけになります。
本記事では、夫婦世帯や独身世帯が実際に準備している老後資金の平均額と中央値を年代別に詳しく解説します。また、老後資金が十分でないと感じている方に向けて、今からでも始められる資産形成の方法についてもご紹介します。
いくら貯めてる?準備している老後資金の平均額
老後資金について「みんなどうしてるの?」という疑問を持つ方は多いでしょう。ここでは、実際の平均貯蓄額について詳しく解説していきます。
夫婦2人の平均額と中央値
夫婦2人世帯の老後資金として準備している金額は、年代によって大きく異なります。平均値と中央値の両方を確認することで、より実態に近い数字を把握できます。
平均値は全体の合計を人数で割った数値ですが、一部の高額貯蓄者の影響を受けやすいという特徴があります。一方、中央値は全体を順番に並べたときの真ん中の数値を示すため、より多くの人の実態を反映していると言えます。全体の真ん中の数字が知りたいなら中央値を見ると良いでしょう。
50代夫婦世帯の貯蓄額
- 平均値:1,825万円
- 中央値:1,100万円
- 貯蓄額の分布
- 100万円未満:8.2%
- 100~500万円:14.8%
- 500~1,000万円:15.3%
- 1,000~2,000万円:23.1%
- 2,000~3,000万円:14.5%
- 3,000万円以上:24.1%
60代夫婦世帯の貯蓄額
- 平均値:2,154万円
- 中央値:1,200万円
- 貯蓄額の分布
- 100万円未満:7.5%
- 100~500万円:12.3%
- 500~1,000万円:13.8%
- 1,000~2,000万円:21.5%
- 2,000~3,000万円:16.2%
- 3,000万円以上:28.7%
- 5,000万円以上の割合:約12%
70代夫婦世帯の貯蓄額
- 平均値:2,209万円
- 中央値:1,300万円
- 貯蓄額の分布
- 100万円未満:6.8%
- 100~500万円:11.2%
- 500~1,000万円:12.5%
- 1,000~2,000万円:22.3%
- 2,000~3,000万円:17.8%
- 3,000万円以上:29.4%
これらのデータから、年代が上がるにつれて貯蓄額も増加していることがわかります。しかし、注目すべきは5,000万円以上の貯蓄がある世帯の割合は全体の約12%程度にとどまっているという点です。
独身の平均額と中央値
一人暮らしやおひとりさまの老後資金準備状況も確認してみましょう。独身世帯の貯蓄額は夫婦世帯と比較すると少ない傾向にあります。
50代独身世帯の貯蓄額
- 平均値:1,048万円
- 中央値:53万円
- 貯蓄なしの割合:41.0%
60代独身世帯の貯蓄額
- 平均値:1,388万円
- 中央値:300万円
- 貯蓄なしの割合:29.5%
70代独身世帯の貯蓄額
- 平均値:1,433万円
- 中央値:485万円
- 貯蓄なしの割合:28.3%
独身世帯の特徴として、平均値と中央値の差が夫婦世帯以上に大きいことが挙げられます。これは貯蓄額の二極化が進んでいることを示しており、十分な貯蓄がある人とほとんど貯蓄がない人の差が大きいことを意味しています。
老後資産は必要ない?60代で貯蓄ゼロの人も多い
60代で貯金ゼロの世帯は、実は思っている以上に存在します。夫婦世帯では約20.8%、独身世帯では約29.5%が貯蓄ゼロという状況です。これは決して珍しいことではありません。
老後資産は必要ないという考え方もあり、その理由として以下のような点が挙げられます。
まず、公的年金だけで生活をやりくりできる場合があります。生活水準を調整し、年金収入の範囲内で暮らすことを選択する人も少なくありません。また、健康であれば70代でも働き続けることが可能で、収入を得続けることで貯蓄に頼らない生活を送ることもできます。
さらに、持ち家がある場合は住居費の負担が軽く、生活費を抑えやすいという利点もあります。子どもからの援助を受けられる環境にある人もいるでしょう。
ただし、貯蓄ゼロにはリスクも伴います。急な病気や介護が必要になった際の費用、家のリフォームや修繕費、想定外の出費に対応できない可能性があります。また、年金だけでは生活が苦しくなった場合の選択肢が限られてしまうこともリスクの一つです。
老後資金のための平均的な毎月の貯蓄額
老後資金を準備するために、各年代で毎月どれくらい貯蓄しているのでしょうか。年代別の平均的な毎月の貯蓄額を見てみましょう。
年代別の毎月の貯蓄額(夫婦世帯)
- 20代:月額3.8万円
- 30代:月額5.2万円
- 40代:月額6.5万円
- 50代:月額7.8万円
- 60代:月額3.2万円
年代別の毎月の貯蓄額(独身世帯)
- 20代:月額2.5万円
- 30代:月額3.8万円
- 40代:月額4.3万円
- 50代:月額5.1万円
- 60代:月額2.1万円
働き盛りの40代・50代で貯蓄額が最も多くなり、60代になると収入の減少に伴い貯蓄額も減少する傾向があります。これは退職や再雇用による収入減少が影響していると考えられます。
重要なのは、無理のない範囲で継続的に貯蓄することです。少額でも長期間続けることで、まとまった老後資金を準備できます。
お金は足りる?必要な老後資金の目安とは
安心して老後を過ごすためには、どれくらいの資金が必要なのでしょうか。ここでは一般的に必要とされる老後資金の額について詳しく見ていきます。
必要な老後資金の額
老後の生活費は、夫婦2人世帯で月額約27万円、独身世帯で月額約15万円が平均的な支出とされています。これに対して、公的年金の平均受給額は夫婦2人で月額約22万円、独身者で月額約14万円程度です。
この差額を65歳から90歳までの25年間で計算すると、夫婦世帯では約1,500万円、独身世帯では約300万円の不足が生じます。さらに、ゆとりある老後生活を送りたい場合は、夫婦世帯で約38万円、独身世帯で約20万円の月額生活費が必要とされ、不足額はさらに大きくなります。
老後資金の必要額の目安
- 夫婦世帯(最低限の生活):約1,500万円
- 夫婦世帯(ゆとりある生活):約4,000万円
- 独身世帯(最低限の生活):約300万円
- 独身世帯(ゆとりある生活):約1,500万円
これらの金額には、介護費用、リフォーム費用、葬儀費用などの特別な出費は含まれていません。これらを考慮すると、さらに500~1,000万円程度の準備が望ましいとされています。
実際の貯蓄額とは開きがある
先ほど紹介した中央値と、必要とされる老後資金の額を比較すると、大きな開きがあることがわかります。例えば、60代夫婦世帯の貯蓄額の中央値は1,200万円ですが、ゆとりある生活に必要とされる4,000万円には2,800万円も不足しています。
しかし、この差額があるからといって過度に心配する必要はありません。実際には多くの人が収入の範囲内で生活をやりくりしています。生活レベルは理想より下がるかもしれませんが、工夫次第で十分に生活することは可能です。
十分な貯金がなかったり、平均に届かない人はあなただけではありません。むしろ、中央値を見れば分かるように、多くの人が同じような状況にあります。大切なのは、現実を受け入れた上で、今からできることを着実に実行していくことです。
今からでも遅くない!十分な老後資金を準備する方法
老後資金の準備が十分でないと感じても、今から始めれば間に合います。ここでは、効果的な老後資金の準備方法をご紹介します。
家計を見直し支出を減らす
まず取り組むべきは家計の把握と見直しです。毎月の収支を正確に把握することで、無駄な支出を発見できます。特に固定費の見直しは効果的です。
固定費削減のポイントとして、携帯電話料金の見直し(格安SIMへの変更)、保険の見直し(重複した保障の整理)、サブスクリプションサービスの整理、電力・ガス会社の変更などが挙げられます。これらの見直しにより、月額1~3万円程度の節約が可能な場合もあります。
また、変動費についても、外食の頻度を減らす、趣味や娯楽費を見直す、衝動買いを控えるなどの工夫により、さらなる節約が期待できます。節約した分を老後資金として積み立てることで、着実に資産を増やしていけます。
定年後も働き続ける
定年後も働き続けることは、老後資金不足を補う最も確実な方法の一つです。65歳以降も収入を得続けることで、貯蓄を取り崩すペースを遅らせることができます。
現在では、再雇用制度や定年延長により、65歳や70歳まで働ける環境が整ってきています。また、フルタイムでなくても、パートタイムやアルバイト、シルバー人材センターの活用など、様々な働き方の選択肢があります。
月額10万円の収入でも、5年間働けば600万円の追加収入となります。この収入があれば、生活費の不足分を補いながら、貯蓄も維持できます。健康が許す限り、何らかの形で働き続けることは、経済的にも精神的にもプラスになります。
早めに老後のための資産形成を始める
資産形成は早く始めるほど有利です。時間を味方につけることで、少額の積立でも大きな資産を形成できます。主な資産形成の方法として、以下のような選択肢があります。
個人年金保険は、老後に年金として受け取れる保険商品です。毎月決まった額を積み立て、将来確実に受け取れるため、計画的な老後資金準備に適しています。
終身保険も老後資金準備に活用できます。死亡保障を確保しながら、解約返戻金を老後資金として活用することが可能です。加入時期が早いほど保険料も安くなります。
積立投資は、毎月一定額を投資信託などに投資する方法です。長期間の運用により、複利効果で資産を増やすことができます。リスクはありますが、20年以上の長期投資であれば、元本割れのリスクも低減されます。
これらの方法を組み合わせることで、リスクを分散しながら着実に老後資金を準備できます。重要なのは、少額でも良いので今すぐ始めることです。
資産運用にはNISAやiDeCoを活用する
投資などで資産運用をするなら、節税効果のあるNISAやiDeCoの活用がおすすめです。これらの制度を利用することで、効率的に老後資金を準備できます。
NISA(少額投資非課税制度)は、投資で得た利益が非課税になる制度です。2024年から始まった新NISAでは、年間360万円まで投資でき、生涯投資枠は1,800万円となっています。運用益が非課税になるため、通常の投資より約20%もお得に資産形成ができます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を拠出し、運用する私的年金制度です。掛金が全額所得控除となるため、所得税・住民税が軽減されます。さらに、運用益も非課税で、受け取り時も退職所得控除や公的年金等控除が適用されます。
例えば、年収500万円の会社員が月2万円をiDeCoに拠出した場合、年間約4.8万円の節税効果があります。この節税分も老後資金として貯蓄すれば、さらに効率的な資産形成が可能です。
両制度とも長期的な資産形成に適しており、老後資金準備の強い味方となります。ただし、iDeCoは原則60歳まで引き出せないなどの制限もあるため、自分のライフプランに合わせて活用することが大切です。
老後に年金だけでは足りないときの対処法
実際に老後を迎えて年金だけでは生活が厳しいと感じた場合、どのような対処法があるのでしょうか。ここでは具体的な対処法をご紹介します。
公的支援を利用する
生活が困窮した場合には、様々な公的支援制度を利用できます。これらの制度を知っておくことで、いざという時の安心につながります。
主な公的支援制度
- 生活困窮者自立支援制度:住居確保給付金や就労支援など、生活の立て直しを総合的に支援
- 生活福祉資金貸付制度:低所得世帯などへの無利子または低利での資金貸付
- 高額療養費制度:医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に払い戻しを受けられる
- 介護保険制度:要介護認定を受けることで、介護サービスを1~3割の自己負担で利用可能
- 高額介護サービス費制度:介護サービスの自己負担額が上限を超えた場合に払い戻しを受けられる
- 国民健康保険料・介護保険料の減免制度:所得が低い場合に保険料が軽減される
- 後期高齢者医療制度:75歳以上の医療費自己負担が原則1割(一定以上の所得がある場合は2~3割)
これらの制度は申請しないと利用できないものがほとんどです。困った時は、まず市区町村の福祉窓口に相談することをおすすめします。
持ち家を利用する
持ち家がある場合は、それを活用して老後資金を確保する方法もあります。代表的な方法として、リバースモーゲージとリースバックがあります。
リバースモーゲージは、自宅を担保に金融機関から融資を受ける制度です。生存中は利息のみを支払い、死亡後に自宅を売却して元金を返済します。自宅に住み続けながら、まとまった資金や毎月の生活費を確保できるメリットがあります。ただし、長生きすると融資限度額に達してしまうリスクや、不動産価値の下落リスクもあります。
リースバックは、自宅を不動産会社に売却し、その後賃貸として住み続ける方法です。売却代金をまとめて受け取れるため、老後資金として活用できます。所有権は失いますが、引っ越しの必要がなく、固定資産税などの維持費負担もなくなります。ただし、家賃の支払いが続くため、長期的な収支計画が必要です。
これらの方法は、それぞれメリット・デメリットがあるため、家族とよく相談し、専門家のアドバイスを受けながら検討することが重要です。
まとめ
老後資金の平均額や中央値を見ると、多くの人が必要とされる額に届いていないことがわかります。60代夫婦世帯の貯蓄額の中央値は1,200万円、独身世帯では300万円と、理想的な老後資金にはほど遠い現実があります。
しかし、だからといって過度に不安になる必要はありません。実際には、多くの人が収入の範囲内で生活をやりくりし、工夫しながら老後を過ごしています。平均に届かない人はあなただけではなく、むしろ多数派であることを理解しておくことが大切です。
重要なのは、現実を受け入れた上で、今からできることを着実に実行していくことです。家計の見直し、定年後の就労継続、NISAやiDeCoを活用した資産運用など、様々な方法で老後資金を準備することができます。
また、公的支援制度の活用や持ち家の有効活用など、いざという時の対処法も知っておくことで、老後への不安を軽減できます。完璧な老後資金を準備できなくても、知識と工夫次第で安心して老後を迎えることは十分可能です。
老後資金の準備は、早く始めるほど有利です。今日からでも、小さな一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。少額の積立でも、長期間続けることで確実に老後の安心につながります。