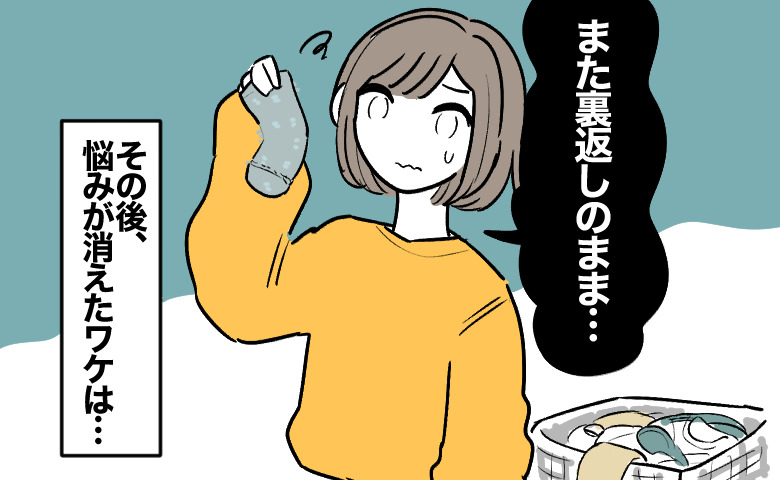10数年に渡って多くの家計相談に携わっていますが、貯蓄ができない人の多くに共通することがあります。貯蓄をすることだけが正しいわけではありませんが、ご自身やお子さんの将来の目的のために、ほとんどの方にとって貯蓄は必要なことです。
今回は貯蓄のできないご家庭に共通する事柄についての主な3点についてお伝えしてまいります。
1.収入に対して支出が多い
衝動買いや不要な会費の支払いなどしていませんか?
収入は年齢や職業、雇用形態等によって異なりますが、支出はご家庭の状況や消費する対象によって大きく異なります。収入に対して支出が多ければ、当然貯蓄はできません。高収入であればお金も貯まりそうな感じもあると思いますが、収入が多い人は支出も多い場合があり、高収入の人でも貯蓄が十分でないケースが散見されます。
年収1000万円でも1年の支出が1000万円のご家庭よりは、年収500万円でも1年の支出が400万円のご家庭の方が貯蓄はできているのです。
結婚や出産、住宅の購入などで、一時的に支出が増えるのはやむを得ないのですが、将来に必要な貯蓄が1年以上できない状態や足りていない状態であれば、無駄な支出を抑えることが最も必要です。何をもって無駄な支出かはそれぞれかと思いますが、最低でも1か月間は支出の記録を付け、支出の全体像から把握されると良いでしょう。
思い当たる人はコンビニエンスストアや自動販売機の利用は適切か、不要な会費やサブスクリプションの支払いはないか、不必要なものを衝動買いしていないかなど支出の行動を確認しましょう。
2.貯蓄をする目的・期間・金額が決まっていない
支出の金額把握していますか?
収入より支出が少ない人は何となく貯蓄はできてしまいますが、支出が多い人や把握していない人は、貯蓄をする目的や期間、金額が決まっていないために適切な貯蓄ができていないことがよくあります。
時間を掛け計画的に仕事に取り組んでいる人はイメージしやすいと思いますが、例えば「1年後にお店をオープンする」とした場合、オープンに向けて建物や設備、スタッフの配置、予算などを準備・計画をするのと同様に、ライフプランにおける資金準備=貯蓄も準備・計画を必要とすると分かりやすいです。
お子さんが生まれて、18年後に進学費用が必要とする場合には、金額と期間を考慮すると、毎月貯蓄に必要な金額が具体的になります。
一例として「0歳のお子さんの18年後から21年後の4年間に毎年150万円の学費を必要とする」場合、単純計算として150万円×4年間=600万円を21年間で均等に割ると、月に約2.4万円の貯蓄が必要となります。
貯蓄をする目的・期間・金額を決めることによって必要な貯蓄額が分かれば、それを実行すれば良いのですが、目的・期間・金額が決まっていないと、貯蓄すべき具体的な金額や期間も把握できないため、貯蓄が後回しになるケースが少なくありません。
3.定期的に貯蓄をする仕組みを利用していない
積立定期預金やiDeCoなどの積立商品、しっかり理解していますか?
貯蓄をしっかり意識していない場合には「収入」-「支出」=「貯蓄」と考えがちですが、余った金額を貯蓄するだけでは、計画的に貯蓄をすることは難しいです。貯蓄を計画的に取り組むには、「収入」-「貯畜」=「支出」と考え実行した方が確実性は高まります。そのためにも、給与天引きや口座振替等で貯蓄をする仕組みを利用すると計画的に貯蓄がしやすいでしょう。
給与天引きであれば財形貯蓄や社内預金、口座振替であれば積立定期預金や学資保険、iDeCoやつみたてNISAなどがその一例です。積立商品はリスクがあるものや現金化できる時期に指定があるものもありますので、貯蓄の目的・期間に合ったものを活用するようにしましょう。
ここでお伝えしたのは、多くの方の家計相談で見受けられる貯蓄ができないケースの主なものですが、ご家庭ごとに状況も意識も必要額も異なります。貯蓄ができていないと思った人や、これから貯蓄をしようと思った人はこの記事を参考に貯蓄ができる家計になるよう取り組まれると良いでしょう。