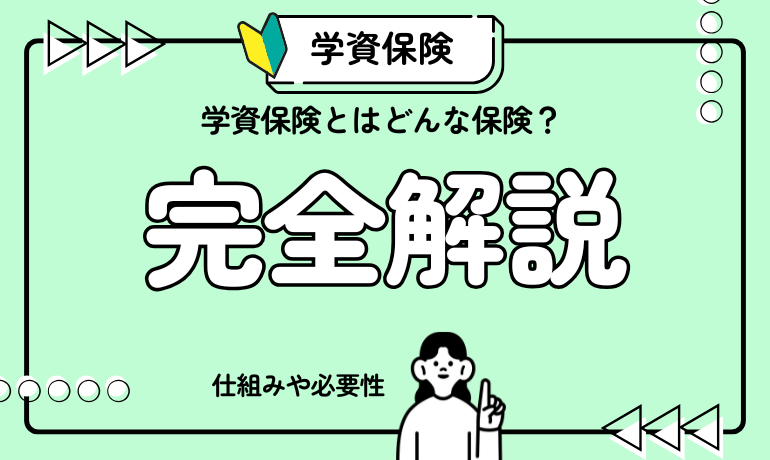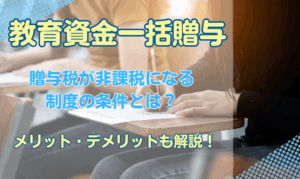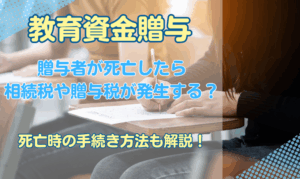子どもの将来の教育費を考えると、「学資保険に入った方がいいのかな?」と悩む方も多いのではないでしょうか。学資保険という言葉はよく聞くものの、実際にどのような保険なのか、本当に必要なのかわからない方も少なくありません。
この記事では、学資保険の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、必要な教育費の目安まで、わかりやすく解説します。学資保険への加入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
学資保険とは?仕組みやメリットをわかりやすく解説!
学資保険とは、子どもの教育資金を準備するための貯蓄性が高い保険です。契約者(多くの場合は親)が毎月保険料を支払い、子どもの進学時期に合わせて祝金や満期保険金を受け取ることができます。
一般的な貯蓄との大きな違いは、保障機能がついていることです。万が一契約者に何かあった場合でも、子どもの教育資金を確保できる仕組みになっています。
祝金や満期保険金の形で受け取ることができる
学資保険では、子どもの成長段階に合わせてお金を受け取れます。主な受け取りタイミングと名称は以下の通りです。
- 小学校入学時:入学祝金
- 中学校入学時:進学祝金
- 高校入学時:進学祝金
- 大学入学時:満期保険金
これらの費用は、制服代や教材費、入学金など、進学時に必要な費用に充てることができます。特に、大学進学時は入学金や授業料などまとまった費用が必要になるため、満期保険金として大きな金額を設定するプランが一般的です。
貯蓄の場合は自分で計画的にお金を積み立て、必要な時期に引き出す必要がありますが、学資保険なら自動的に決められた時期にお金を受け取れるため、教育費の準備がより確実になります。
万が一に対する保障がある
学資保険は貯蓄性が高い保険ですが、万が一の時の保障機能もついています。主な保障内容は以下の通りです。
保険料払込免除特約
契約者が死亡や高度障害状態になった場合、以後の保険料の支払いが免除されます。予定していた祝金や満期保険金は契約通り受け取れるため、子どもの教育資金を確実に準備できます。
育英年金特約
一部の学資保険では、契約者に万が一のことがあった場合、子どもが成人するまで毎年一定額の育英年金を受け取れる特約を付けられます。
医療保障特約
子どもの病気やケガに対する医療保障を付けられる商品もあります。ただし、特約を付けると貯蓄性が下がる場合があります。
通常の貯蓄では、契約者に万が一のことがあると、それ以降の積み立てができなくなってしまいます。学資保険なら保険の保障機能により、契約者に何かあっても子どもの教育資金を確保できます。
貯蓄よりも計画的に貯めやすい
学資保険は、貯蓄が苦手な人でも計画的にお金を貯めやすい仕組みになっています。
自動引き落としで確実に積み立て
毎月決まった日に口座から自動的に保険料が引き落とされるため「今月は貯金できなかった」という事態にはなりません。家計の中で教育費の準備が自動化されるため、確実に資金を積み立てられます。
簡単に引き出せないため継続しやすい
銀行預金の場合、急な出費があるとつい教育費用の貯金に手を付けてしまうことがあります。学資保険は簡単に引き出せないため、教育費以外の用途に使うリスクを避けられます。
目標金額が明確
学資保険は契約時に満期保険金額を決めるため「大学入学時までに300万円準備する」といった明確な目標ができます。毎月の保険料も自動的に計算されるため、計画的な資金準備が可能です。
貯蓄が苦手な人や、ついお金を使ってしまう人にとって、学資保険の「強制的に貯蓄できる」仕組みは大きなメリットといえるでしょう。
保険料の支払総額より多く受け取れる可能性がある
学資保険のプランや契約期間によっては、支払った保険料の総額よりも多くの保険金を受け取れる場合があります。これを「返戻率」で表します。
返戻率とは:
返戻率 = 受取総額 ÷ 支払保険料総額 × 100
例えば、18年間で360万円の保険料を支払い、満期時に370万円を受け取った場合は「370万円 ÷ 360万円 × 100 = 102.8%」となり、支払った金額より約3%多く受け取れます。
返戻率を高めるポイント
- 払込期間を短くする(10年払いなど)
- 特約を付けすぎない
- 一括払いや年払いを選択する
- 早い時期に契約する
通常の銀行預金の金利が非常に低い現在、学資保険の返戻率は魅力的な選択肢の一つです。ただし、すべての学資保険で返戻率が100%を超えるわけではないため、商品選びが重要になります。
生命保険料控除も受けられる
学資保険の保険料は、所得税と住民税の「生命保険料控除」の対象になります。
生命保険料控除とは
生命保険料控除は、1年間に支払った生命保険料の一定額を所得から差し引くことで、税金の負担を軽減する制度です。
控除額の目安
- 所得税:年間保険料8万円超で最大4万円の控除
- 住民税:年間保険料5.6万円超で最大2.8万円の控除
実際の節税効果
例えば、所得税率10%、住民税率10%の場合は以下のようになります。
- 所得税の軽減:4万円 × 10% = 4,000円
- 住民税の軽減:2.8万円 × 10% = 2,800円
- 合計:年間6,800円の節税効果
節税効果は毎年受けられるため、18年間継続すると約12万円の税金軽減になります。通常の貯蓄では得られない、学資保険ならではのメリットです。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
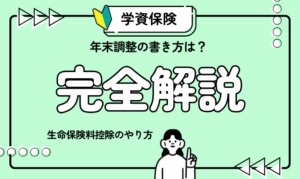
学資保険は入らない方がいい?デメリットもわかりやすく解説
学資保険にはメリットがある一方で、デメリットや注意点もあります。加入前にしっかりと理解しておくことが大切です。
途中解約すると元本割れのリスクが高まる
学資保険の最大のデメリットの一つが、途中解約時の元本割れリスクです。
途中解約による元本割れ
学資保険を契約期間の途中で解約すると、解約返戻金が支払った保険料総額を下回る可能性が高くなります。特に契約から数年以内の解約では、解約返戻金がほとんどない場合もあります。
元本割れの他の原因
途中解約以外でも、以下のような場合に元本割れのリスクがあります。
- 特約を多く付けた場合
- 保険会社の運用成績が悪化した場合
- インフレが進行した場合(実質的な価値の目減り)
対策
- 契約前に家計の状況を十分検討する
- 保険料の支払いが困難になった場合の減額制度を確認する
- 返戻率の高い商品を選ぶ
途中解約は大きな損失につながるため、契約時には長期間継続できるかどうかを慎重に判断しましょう。
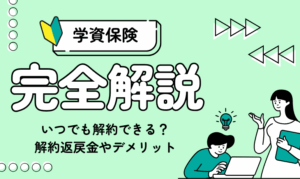
インフレに弱い
学資保険は固定金利の商品が多く、インフレ(物価上昇)に弱いという特徴があります。
インフレとは、物価が継続的に上昇することです。お金の価値が相対的に下がり、同じ金額でも購入できるものが少なくなります。
学資保険がインフレに弱い理由
学資保険は契約時に将来受け取る金額が決まっているため、インフレが進行すると実質的な価値が目減りします。
例えば、現在300万円で4年間の大学費用をまかなえるとしても、18年後にインフレが進んで同じ教育を受けるのに400万円必要になった場合、300万円では不足してしまいます。
インフレ対策
- 変額保険タイプの学資保険を検討する
- 学資保険だけでなく、株式投資なども組み合わせる
- 定期的に教育費の必要額を見直す
長期間の契約になる学資保険では、インフレリスクを考慮した資金計画が必要です。
保険料が負担になることがある
契約時は無理のない保険料でも、子どもの成長とともに家計状況が変わり保険料の支払いが負担になることがあります。
保険料負担が重くなる要因
- 住宅ローンの支払い開始
- 子どもの習い事や塾費用の増加
- 第二子、第三子の出産
- 収入の減少や転職
- 親の介護費用の発生
対策
- 家計に余裕を持った保険料設定にする
- 年払いや半年払いで保険料を軽減する
- 払済保険への変更制度を確認する
- 減額制度の有無を確認する
保険料の支払いが困難になった場合の対処法を事前に確認しておくことが大切です。
受け取り方によっては税金がかかる
学資保険の保険金を受け取る際、契約者と受取人の関係や受け取り方法によっては税金がかかる場合があります。
所得税がかかるケース
契約者と受取人が同じ場合、受け取った保険金は一時所得として所得税の対象になります。ただし、一時所得には50万円の特別控除があるため、利益が50万円以下なら税金はかかりません。
贈与税がかかるケース
契約者と受取人が異なる場合(例:父親が契約者、子どもが受取人)、受け取った保険金は贈与税の対象になる可能性があります。
年金形式で受け取る場合
保険金を年金形式で受け取る場合、雑所得として所得税がかかります。
税負担を抑える受け取り方
- 契約者と受取人を同一にする
- 一括受取を選択する
- 必要に応じて税理士に相談する
税金の負担を抑えるためには、契約時に受け取り方法を慎重に検討することが重要です。
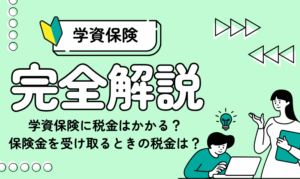
資産運用としては効率的でない
学資保険は安全性の高い商品ですが、資産運用の観点では効率的とはいえません。
学資保険の返戻率は、良好な商品でも102~105%程度です。年率に換算すると1%未満の運用益となり、株式投資や投資信託と比較するとリターンは非常に低いです。
例えば、毎月2万円を18年間積み立てた場合は以下のようになります。
- 学資保険(返戻率103%):約445万円
- 投資信託(年利3%):約520万円
- 投資信託(年利5%):約610万円
投資にはリスクがあり、元本割れの可能性もあることを理解しておく必要があります。
学資保険が適している人
- リスクを取りたくない人
- 投資の知識や経験がない人
- 確実に教育費を準備したい人
資産を大きく増やしたい人には学資保険は向いていませんが、安全確実に教育費を準備したい人には適した選択肢といえます。
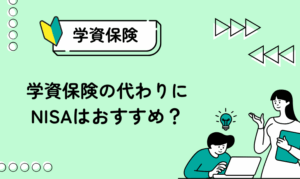
加入できる期間が短い
学資保険は、子どもが小さい時期にしか加入できない商品が多く、加入タイミングを逃すと選択肢が限られます。
多くの学資保険では、子どもの加入年齢に制限があります。
- 0歳~6歳:多くの商品から選択可能
- 7歳~12歳:選択肢が限定される
- 13歳以上:加入できる商品が非常に少ない
遅い加入のデメリット
・保険料が高くなる
・払込期間が短くなり月々の負担が増える
・返戻率が下がる可能性がある
・商品の選択肢が少なくなる
早期加入のメリット
・保険料を抑えられる
・払込期間に余裕がある
・返戻率の高い商品を選べる
・商品選択の幅が広い
学資保険を検討している場合は、できるだけ早い時期に加入することをおすすめします。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険への加入がおすすめの人の特徴
これまでのメリット・デメリットを踏まえ、学資保険への加入がおすすめの人の特徴をまとめました。
学資保険がおすすめの人
- 貯蓄が苦手な人:自動引き落としで確実に積み立てたい
- 安全確実に教育費を準備したい人:元本保証や保険機能を重視する
- 計画的な資金準備をしたい人:決まった時期に決まった金額を受け取りたい
- 万が一の保障も欲しい人:契約者に何かあっても教育費を確保したい
- 投資経験がない・リスクを取りたくない人:安全性を最優先に考える
- 生命保険料控除を活用したい人:税制優遇も受けたい
- 子どもが小さい人:早期加入で有利な条件を活用できる
学資保険が向いていない人
- 積極的に資産運用したい人:より高いリターンを求める
- 家計に余裕がない人:長期間の保険料支払いが困難
- 既に十分な貯蓄がある人:追加の教育費準備が不要
- 投資知識が豊富な人:他の運用方法でより効率的に増やせる
- 途中で資金が必要になる可能性が高い人:流動性を重視する
自分の家計状況、価値観、投資経験などを総合的に考慮して、学資保険が適しているかどうかを判断することが大切です。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険の保険料は月にいくら?必要な教育費とは
学資保険を検討する際に気になるのが、「月にいくら払えばいいのか」「そもそも教育費はいくら必要なのか」という点です。具体的な金額を見ていきましょう。
必要な教育費の目安
子どもの教育費は、進路によって大きく異なります。文部科学省の調査データを基に、教育費の目安をまとめました。
幼稚園から高校まで(3歳~18歳)
| 進路パターン | 総額 |
| すべて公立 | 約574万円 |
| 小学校のみ私立 | 約999万円 |
| 中学校のみ私立 | 約729万円 |
| 高校のみ私立 | 約649万円 |
| すべて私立 | 約1,838万円 |
大学費用(4年間)
| 大学種別 | 総額 |
| 国立大学 | 約242万円 |
| 公立大学 | 約254万円 |
| 私立大学文系 | 約396万円 |
| 私立大学理系 | 約542万円 |
| 私立大学医歯薬系 | 約2,357万円 |
教育費準備の目安
多くの家庭では、大学進学費用を中心に準備を進めています。一般的な目標額は以下の通りです。
- 最低限の準備:200万円~300万円(国公立大学の費用をカバー)
- 標準的な準備:300万円~500万円(私立大学文系までカバー)
- 余裕のある準備:500万円~800万円(私立大学理系や一人暮らし費用も含む)
これらの金額はあくまで目安であり、家庭の経済状況や教育方針によって調整が必要です。
月の保険料の目安
学資保険の月々の保険料は、目標金額と払込期間によって決まります。具体的な例を見てみましょう。
目標金額300万円の場合
| 払込期間 | 月額保険料 | 払込総額 | 返戻率(例) |
| 18年払い | 約14,000円 | 約302万円 | 99.3% |
| 15年払い | 約16,500円 | 約297万円 | 101.0% |
| 10年払い | 約24,500円 | 約294万円 | 102.0% |
目標金額200万円の場合
| 払込期間 | 月額保険料 | 払込総額 | 返戻率(例) |
| 18年払い | 約9,300円 | 約201万円 | 99.5% |
| 15年払い | 約11,000円 | 約198万円 | 101.0% |
| 10年払い | 約16,300円 | 約196万円 | 102.0% |
目標金額500万円の場合
| 払込期間 | 月額保険料 | 払込総額 | 返戻率(例) |
| 18年払い | 約23,300円 | 約504万円 | 99.2% |
| 15年払い | 約27,500円 | 約495万円 | 101.0% |
| 10年払い | 約40,800円 | 約490万円 | 102.0% |
保険料設定のポイント
- 家計に占める割合:一般的に手取り収入の5~10%程度が目安
- 払込期間の選択:短期払いの方が返戻率は高いが月々の負担は重い
- 他の教育費との兼ね合い:習い事や塾費用も考慮して設定
- 収入の変動リスク:転職や収入減少の可能性も考慮
上記の保険料で準備できる金額が、実際に必要な教育費のどの程度をカバーできるかを見てみましょう。
- 国立大学費用(242万円):200万円の準備で約83%カバー
- 私立大学文系(396万円):300万円の準備で約76%カバー
- 私立大学理系(542万円):500万円の準備で約92%カバー
学資保険だけですべての教育費をまかなうのは困難な場合が多いため、他の準備方法との組み合わせも検討することが大切です。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
おすすめの学資保険はこちらをチェック!
学資保険の基本的な仕組みやメリット・デメリットについて理解できたら、次は具体的な商品選びです。保険会社によって返戻率や保障内容、加入条件などが異なるため、以下のポイントをもとに、複数の商品を比較検討することが重要です。
- 返戻率の高さ
- 保障内容の充実度
- 保険会社の信頼性
- 加入条件(年齢制限など)
- 保険料の支払い方法
- 特約やオプションの内容
同じような保障内容でも、保険会社によって返戻率に数%の差が出ることがあります。長期間の契約になる学資保険では、この差が大きな金額の違いにつながるため、しっかりと比較することが大切です。
また、インターネットで情報収集するだけでなく、保険の専門家に相談したり、複数の保険会社から資料を取り寄せたりして、詳細な条件を確認することをおすすめします。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
まとめ
学資保険は、子どもの教育費を計画的に準備するための有効な手段の一つです。確実性と保障機能というメリットがある一方で、途中解約のリスクやインフレに弱いデメリットもあります。
重要なのは、自分の家計状況や価値観、リスク許容度に合った選択をすることです。学資保険だけでなく、定期預金や投資信託、株式投資など、さまざまな選択肢を検討し、場合によっては複数の方法を組み合わせることも有効です。
子どもの将来のために、早めの準備と慎重な検討を心がけましょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!