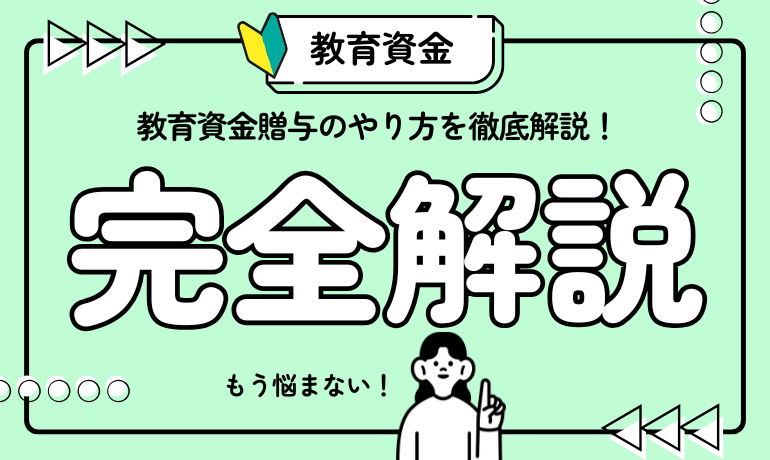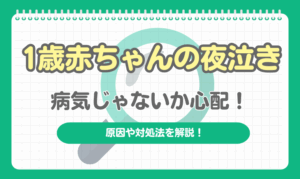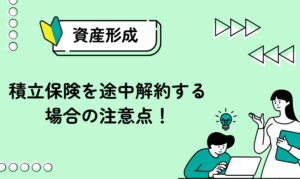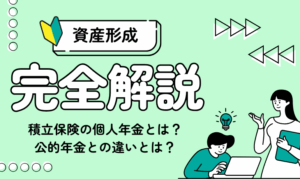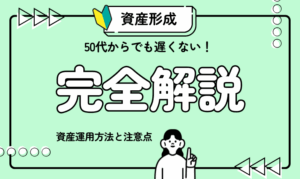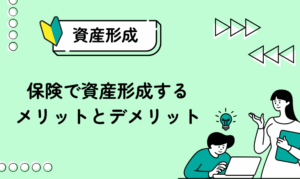教育資金の準備は、多くの家庭にとって大きな課題です。子どもや孫の将来のために、まとまった資金を用意したいと考える祖父母の方も多いのではないでしょうか。そんな時に活用できるのが、教育資金贈与の非課税制度です。
この制度を利用すれば、最大1,500万円まで非課税で教育資金を贈与できます。しかし、実際にどのような手続きが必要なのか、どんな条件があるのか、詳しく知らない方も少なくありません。
本記事では、教育資金贈与のやり方について、利用条件から具体的な手続き方法、注意点まで徹底的に解説します。非課税制度を賢く活用して、大切な家族の教育を支援する方法を一緒に確認していきましょう。
教育資金贈与のやり方【利用条件】
教育資金贈与とは、正式には「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」という制度です。この非課税制度を利用することで、祖父母などから子や孫への教育資金の贈与について、一定の要件を満たせば贈与税が課税されません。
通常、年間110万円を超える贈与には贈与税が課税されますが、この教育資金贈与の課税制度を活用すれば、最大1,500万円まで非課税で贈与できるという大きなメリットがあります。ただし、この制度を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。それでは、具体的な利用条件について詳しく解説していきます。
利用できる期限
教育資金贈与の非課税制度には、利用できる期限が定められています。現在のところ、この制度は令和8年(2026年)3月31日までの時限措置となっています。つまり、いつまでも利用できる制度ではないということです。
期限が近づくにつれて、制度の延長や内容の見直しが行われる可能性もありますが、現時点では令和8年3月31日までに信託等を設定し、教育資金を拠出する必要があります。この期限を過ぎてしまうと、非課税制度を利用できなくなってしまうため、検討している方は早めの準備が大切です。
また、制度の利用開始後も、受贈者が30歳に達した時点で口座は終了となります。このため、贈与を受ける人の年齢も考慮して、計画的に制度を活用することが重要になります。
贈与者の条件(贈与する人)
教育資金贈与の非課税制度を利用して贈与できる人には、明確な条件があります。贈与者となれるのは、受贈者の直系尊属に限定されています。直系尊属とは、父母、祖父母、曽祖父母など、直接の血縁関係にある上の世代の人々を指します。
つまり、祖父母から孫への贈与、父母から子への贈与などが対象となります。一方で、叔父や叔母、兄弟姉妹からの贈与は、この制度の対象外となるため注意が必要です。
贈与者の年齢に特別な制限はありませんが、贈与の時点で生存していることが条件となります。また、複数の直系尊属から同一の受贈者に対して贈与することも可能ですが、非課税限度額は受贈者一人につき1,500万円までという点は変わりません。
受贈者の条件(贈与を受ける人)
教育資金贈与を受けられる人にも、いくつかの条件があります。まず、受贈者は贈与者の直系卑属(子・孫・ひ孫など)でなければなりません。さらに、贈与を受ける時点で30歳未満であることが必要です。
また、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であることも条件となっています。この所得制限は、平成31年4月1日以降の贈与から適用されており、高所得者への優遇を防ぐ目的で設けられました。
受贈者一人につき、複数の贈与者から贈与を受けることは可能ですが、非課税限度額の合計は1,500万円までとなります。また、すでに他の金融機関で教育資金贈与の口座を開設している場合、新たに別の金融機関で口座を開設することはできません。
対象となるもの
教育資金贈与の非課税制度で対象となる費用には、明確な範囲が定められています。適用される費用を正しく理解しておくことで、制度を有効に活用できます。
学校等に直接支払われる費用については、以下のようなものが対象となります。入学金、授業料、学費、入園料、保育料、施設設備費、教育充実費、修学旅行費、学校給食費などです。これらの費用については、1,500万円まで非課税となります。
学校等以外に支払われる費用も、一定の条件を満たせば対象となりますが、この場合の非課税限度額は500万円までとなります。具体的には、学習塾や習い事の月謝、スポーツクラブの指導料、通学定期券代、留学渡航費などが含まれます。
ただし、すべての教育関連費用が対象となるわけではありません。例えば、下宿代や生活費、娯楽費などは対象外となります。また、23歳以上の受贈者については、学校等以外への支払いは教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費用に限定されるなど、年齢によって範囲が異なる点にも注意が必要です。
教育資金贈与のやり方【申込手続き方法】
教育資金贈与の非課税制度を利用するためには、適切な手続きを踏む必要があります。通常の贈与とは異なり、金融機関での専用口座開設や必要書類の提出など、いくつかのステップを経る必要があります。ここでは、実際の申込手続きの流れを順を追って詳しく説明します。
1:贈与契約書を作成する
教育資金贈与を行う際の第一歩は、贈与契約書の作成です。この契約書は、贈与者と受贈者の間で贈与の意思を明確にし、後々のトラブルを防ぐために重要な書類となります。
贈与契約書には、贈与者と受贈者の氏名、住所、贈与する金額、贈与の目的が教育資金であること、贈与の実行日などを明記します。また、教育資金贈与の非課税制度を利用する旨も記載しておくことが望ましいでしょう。
契約書は必ずしも公正証書にする必要はありませんが、将来の相続時などにおいて贈与の事実を証明する重要な書類となるため、できるだけ詳細に記載し、両者が署名・押印したものを保管しておくことが大切です。金融機関によっては、独自の契約書フォーマットを用意している場合もあるので、事前に確認しておくとスムーズに手続きを進められます。
2:口座開設する金融機関を選ぶ
教育資金贈与の非課税制度を利用するためには、必ず専用口座の開設が必要です。これは通常の贈与との大きな違いであり、制度の適用を受けるための必須条件となっています。専用口座を開設する理由は、教育資金の使途を明確に管理し、適切に非課税措置を適用するためです。
口座開設に必要な書類は、一般的に以下のようなものが挙げられます。贈与契約書、贈与者と受贈者の本人確認書類、受贈者の戸籍謄本または住民票(贈与者との続柄が確認できるもの)、印鑑、受贈者のマイナンバー確認書類などです。金融機関によって必要書類が異なる場合があるため、事前に確認しておくことをお勧めします。
教育資金贈与信託を取り扱っている金融機関は多数あります。主要な金融機関一覧として、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行、りそな銀行などの信託銀行があります。また、ゆうちょ銀行をはじめ、地方銀行や信用金庫でも取り扱いがある場合があります。
金融機関を選ぶ際は、手数料体系、引き出し手続きの利便性、店舗へのアクセス、サポート体制などを比較検討することが重要です。特に、領収書の提出方法や払い戻しの手続きは金融機関によって異なるため、利用しやすい金融機関を選ぶことが長期的な利用を考えると大切になります。
3:教育資金を一括で振り込む
金融機関での専用口座開設が完了したら、次は教育資金を一括で振り込む手続きを行います。贈与者は、開設された専用口座に教育資金を振り込みます。この際、振込金額は最大1,500万円まで可能ですが、必ずしも上限額まで振り込む必要はありません。
振込が完了すると、金融機関から「教育資金非課税申告書」が交付されます。この申告書は、受贈者が記入し、金融機関を通じて税務署に提出する必要があります。申告書には、贈与者と受贈者の情報、贈与金額、口座開設日などが記載されます。
申告書の提出により、正式に教育資金贈与の非課税措置が適用されることになります。この手続きが完了すれば、受贈者は必要に応じて教育資金を引き出すことができるようになります。ただし、引き出しには一定のルールがあるため、次章で詳しく説明します。
教育資金贈与のやり方【引き出す方法】
教育資金贈与の専用口座から資金を引き出す際には、通常の預金口座とは異なる特別な手続きが必要です。これは、非課税措置を適切に適用するために、使途を明確に証明する必要があるためです。ここでは、実際の引き出し方法と注意点について詳しく解説します。
引き出しには領収書の提出が必要
教育資金贈与の専用口座から資金を引き出す際の最も重要なポイントは、領収書などの証明書類の提出が必要だということです。これは、引き出した資金が確実に教育目的で使用されたことを証明するためのもので、非課税措置を受けるための必須条件となっています。
引き出し方法は、主に2つのパターンがあります。1つ目は「後払い方式」で、まず教育費を立て替えて支払い、その後領収書を金融機関に提出して払い戻しを受ける方法です。2つ目は「前払い方式」で、事前に必要な金額を引き出し、後日領収書を提出する方法です。
領収書には、支払日、金額、支払者(受贈者本人)の氏名、支払先の名称、摘要(何の費用か)が明記されている必要があります。また、領収書は原則として支払から1年以内に金融機関に提出する必要があります。期限を過ぎると、その分は非課税措置の対象外となってしまうため、注意が必要です。
金融機関によっては、オンラインで領収書の画像をアップロードできるサービスを提供している場合もあり、手続きの利便性が向上しています。
領収書がない場合の引き出し方法
すべての教育費において領収書が発行されるわけではありません。例えば、交通系ICカードで支払う通学定期代など、領収書の入手が困難な場合もあります。そのような場合の対応方法についても理解しておく必要があります。
領収書がない場合でも、振込明細書や支払い証明書など、支払いの事実を証明できる書類があれば、それらで代用できる場合があります。金融機関によって認められる書類の種類は異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
ただし、領収書なしで引き出せる金額には上限があります。いくらまで領収書なしで引き出せるかは金融機関によって異なりますが、一般的には年間の引き出し額に制限が設けられています。多くの場合、小額の教育関連費用については、領収書なしでの引き出しが認められることもありますが、これはあくまで例外的な取り扱いとなります。
領収書が取得できない支払いについては、できる限り他の証明書類を保管し、金融機関に相談することをお勧めします。また、可能な限り領収書が発行される支払い方法を選択することで、後々の手続きをスムーズに進めることができます。
教育資金贈与を利用するときの注意点
教育資金贈与の非課税制度は大きなメリットがある一方で、いくつかの注意点やデメリットも存在します。制度を利用する前に、これらの点を十分に理解しておくことが、後悔のない選択をするために重要です。ここでは、特に注意すべき4つのポイントについて詳しく説明します。
30歳までに使い切れないと贈与税の対象になる
教育資金贈与の最も重要な注意点の一つは、受贈者が30歳に達した時点で口座に残高がある場合、その残額に対して贈与税が課税されることです。これは制度の大きなデメリットといえるでしょう。
例えば、1,500万円の贈与を受けたものの、30歳までに1,000万円しか使用できなかった場合、残りの500万円は贈与税の課税対象となります。この場合、通常の贈与税率が適用されるため、相当額の税金を支払う必要が生じる可能性があります。
ただし、30歳に達した時点で学校等に在学している場合や、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合は、最長で40歳まで延長されることがあります。しかし、この延長措置にも条件があるため、計画的な資金の使用が求められます。
このリスクを避けるためには、受贈者の教育計画を慎重に検討し、必要な金額を適切に見積もることが大切です。過度に多額の贈与を行うと、使い切れずに課税されるリスクが高まるため、現実的な金額設定が重要となります。
贈与者死亡で相続税の対象になることがある
教育資金贈与を行った後に贈与者が死亡した場合、一定の条件下では残額が相続税の課税対象となることがあります。これは平成31年度の税制改正により導入された規定で、制度利用者にとって重要な注意点となっています。
具体的には、贈与者死亡時において、受贈者が23歳未満の場合、学校等に在学している場合、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合を除き、贈与者死亡時の残額は相続税の課税価格に加算されます。
また、贈与者死亡前3年以内に行われた教育資金贈与についても、一定の条件下で相続税の課税対象となる可能性があります。これは、相続税の節税目的での駆け込み的な贈与を防ぐための措置です。
このようなリスクを考慮すると、贈与者の年齢や健康状態、受贈者の年齢や教育計画などを総合的に判断して、制度の利用時期や金額を決定することが重要になります。場合によっては、通常の暦年贈与を活用する方が適している可能性もあるため、税理士などの専門家に相談することも検討すべきでしょう。
引き出しには手間がかかる
教育資金贈与の専用口座からの引き出しは、通常の預金口座と比べて面倒な手続きが必要となります。これは制度利用上の大きなデメリットの一つといえるでしょう。
まず、支払いの都度、領収書を金融機関に提出する必要があります。学校の授業料のような大きな支出だけでなく、参考書の購入や通学定期券の購入といった細かな支出についても、その都度領収書を保管し、提出しなければなりません。
領収書の提出期限も定められており、原則として支払から1年以内に提出する必要があります。期限を過ぎてしまうと、その支出は教育資金として認められず、非課税措置の対象外となってしまいます。このため、領収書の管理には細心の注意が必要です。
また、金融機関の窓口での手続きが必要な場合も多く、平日の営業時間内に足を運ばなければならないこともあります。最近ではオンラインでの手続きに対応している金融機関も増えていますが、それでも通常の口座と比べると手間がかかることは否めません。
このような手続きの煩雑さを考慮すると、頻繁に少額の教育費を支払う場合には不向きかもしれません。大学の入学金や授業料など、まとまった金額の支払いに活用することで、手続きの負担を軽減することができるでしょう。
口座の解約はできない
教育資金贈与の専用口座は、一度開設すると原則として途中解約ができません。これは制度の終了まで継続することが前提となっているためです。
口座が終了するのは、以下のいずれかの場合に限られます。受贈者が30歳(条件により40歳)に達したとき、受贈者が死亡したとき、口座の残高がゼロになり、かつ受贈者と金融機関の間で終了の合意があったときです。
これ以外の理由での解約は認められていないため、例えば「やはり通常の贈与に切り替えたい」「別の金融機関に変更したい」といった理由での解約はできません。このため、金融機関選びは慎重に行う必要があります。
また、一度贈与した資金を贈与者に返還することも原則としてできません。家族間であっても、贈与は法的に完了した行為となるため、後から取り消すことは困難です。
このような制約があることから、制度の利用を決める前に、十分な検討期間を設けることが重要です。家族でよく話し合い、教育計画や資金需要を慎重に見極めた上で、制度の利用を決定することをお勧めします。
まとめ
教育資金贈与の非課税制度は、最大1,500万円まで贈与税がかからずに教育資金を贈与できる魅力的な制度です。祖父母から孫へ、親から子へと、大切な家族の教育を支援する有効な手段となります。
制度を利用するためには、贈与者と受贈者の関係、年齢、所得などの条件を満たし、金融機関での専用口座開設や教育資金非課税申告書の提出といった適切な手続きを行う必要があります。また、教育費の支払いごとに領収書を提出するなど、継続的な管理も求められます。
一方で、30歳までに使い切れなかった残額への課税、贈与者死亡時の相続税課税、手続きの煩雑さ、口座解約ができないといった注意点もあります。これらのメリット・デメリットを十分に理解した上で、家族の状況や教育計画に応じて、制度の利用を検討することが大切です。
令和8年3月31日までの時限措置であることも踏まえ、利用を検討している方は早めに準備を進めることをお勧めします。必要に応じて税理士などの専門家にも相談しながら、最適な教育資金の贈与方法を選択してください。