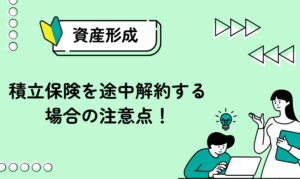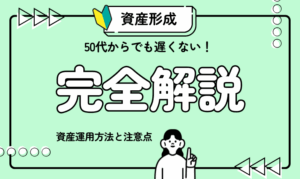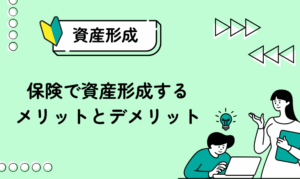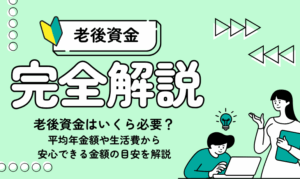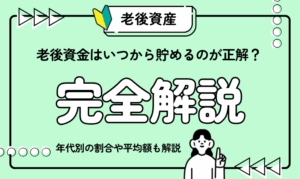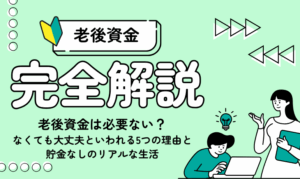「将来のために着実に資産形成をしたい」「万一の保障も備えながら、効率的にお金を貯めたい」
このようにお考えの方にとって、「貯蓄型保険」は魅力的な選択肢の一つです。しかし、数ある商品の中から自分に合ったものを選ぶ際、必ず目にするのが「返戻率(へんれいりつ)」という言葉。
「返戻率が高い方がお得なのはわかるけど、そもそもどういう意味?」
「利率や利回りとは何が違うの?」
「今の時代、返戻率の目安はどれくらい?」
「少しでも返戻率の高いおすすめの保険は?」
など、さまざまな疑問が浮かんでくるのではないでしょうか。
この記事では、貯蓄型保険への加入を検討している方や、保険の知識に自信がない方に向けて、以下の内容を徹底的に解説します。
- 貯蓄型保険の「返戻率」の基本的な意味と計算方法
- 混同しがちな「利率」「利回り」との明確な違い
- 保険料がなぜ増えて戻ってくるのか、その仕組み
- 知っておくべき返戻率の重要なポイント(保険期間や途中解約のリスク)
- 現在の貯蓄型保険における返戻率の目安
- 【2025年最新版】返戻率が高いおすすめ貯蓄型保険ランキングTOP3
- 今日からできる、貯蓄型保険の返戻率をさらに高めるコツ
- 貯蓄型保険のメリット・デメリットと賢い選び方
この記事を最後まで読めば、あなたは「返戻率」を正しく理解し、数多くの商品の中からご自身の目的やライフプランに最適な貯蓄型保険を見つけ出すことができるようになります。保障と資産形成を両立させるための第一歩を、ここから踏み出しましょう。
貯蓄型保険の返戻率とはどういう意味?
まず最初に、貯蓄型保険を比較検討する上で最も重要な指標となる「返戻率」の基本的な意味から理解していきましょう。
保険料総額に対して受け取れるお金の率のこと
返戻率とは、「払い込んだ保険料の総額に対して、満期保険金や解約返戻金として将来受け取れるお金の総額がどれくらいの割合になるか」を示す数値です。
読み方は「へんれいりつ」です。
この数値を見れば、支払った保険料が最終的にどれくらい増える(あるいは減る)のかが一目でわかります。
- 返戻率100%:払い込んだ保険料と受け取るお金が同額(元本と同じ)
- 返戻率100%超:払い込んだ保険料よりも多くのお金を受け取れる(利益が出る)
- 返戻率100%未満:払い込んだ保険料よりも受け取るお金が少なくなる(元本割れ)
貯蓄目的で保険に加入する場合、この返戻率が100%を超えているかどうかが、一つの大きな判断基準となります。当然、返戻率の数値が高ければ高いほど、貯蓄性が高い商品であると言えます。
返戻率と利率との違い
返戻率とよく似た言葉に「利率(りりつ)」があります。どちらもお金の増え方を示す指標ですが、その意味は全く異なります。
利率とは
利率とは、「預けた元本に対して、1年間でどれくらいの利息がつくか」を示す割合です。主に銀行の預金などで使われる言葉です。
例えば、100万円を「年利率1%」の定期預金に預けた場合、1年後には1万円の利息がつきます(税金は考慮しない場合)。
返戻率と利率の決定的な違い
| 項目 | 返戻率 | 利率 |
| 対象 | 払込保険料の総額 | 預けた元本(1年あたり) |
| 期間 | 保険契約期間全体 | 1年間 |
| 計算基礎 | 払込保険料総額と受取総額 | 元本と利息 |
| 主な用途 | 貯蓄型保険 | 銀行預金など |
【具体例で比較】
月々1万円の保険料を10年間払い込み、10年後に125万円の満期保険金を受け取る貯蓄型保険があったとします。
- 払込保険料総額:1万円 × 12カ月 × 10年 = 120万円
- 受取総額:125万円
- 返戻率:125万円 ÷ 120万円 × 100 = 約104.1%
一方、もし120万円をまとめて銀行に預け、10年後に125万円になった場合の「年利率」を考えてみましょう。これは少し複雑な計算(複利計算)が必要になりますが、おおよそ年利率0.4%程度に相当します。
このように、返戻率は契約期間全体での増え方を示しているのに対し、利率は1年あたりの増え方を示しているという違いがあります。単純に数値の大小だけで比較できない点に注意が必要です。
返戻率と利回りとの違い
もう一つ、混同しやすい言葉に「利回り(りまわり)」があります。
利回りとは
利回りとは、「投資した元本に対して、1年間あたりで得られる利益(利息だけでなく、売却益なども含む)の割合」を示す指標です。投資信託や株式などの金融商品でよく使われます。
計算式は以下の通りです。
利回り(%) = (1年間の収益 ÷ 投資元本) × 100
返戻率と利回りの決定的な違い
| 項目 | 返戻率 | 利回り |
| 対象期間 | 契約期間全体 | 1年間(年率換算) |
| 考慮する収益 | 満期金や解約返戻金 | 利息、分配金、売却益など |
| 時間的価値 | 考慮しない | 考慮する |
| 主な用途 | 貯蓄型保険 | 投資信託、株式、債券など |
利回りは、返戻率を「1年あたりの平均的な収益率」に換算したもの、とイメージすると分かりやすいでしょう。
先ほどの例(10年で120万円が125万円になる)で考えると、返戻率は約104.1%でしたが、これを年利回りに換算すると約0.8%となります。(※計算方法により多少異なります)
貯蓄型保険を他の金融商品(投資信託など)と比較する際には、返戻率の数字だけを見るのではなく、この「利回り」に換算して考えることが重要です。そうすることで、どの方法がより効率的に資産を増やせるのかを客観的に比較することができます。
返戻率の計算方法
返戻率の計算方法は非常にシンプルです。以下の式で誰でも簡単に計算できます。
返戻率(%)=受け取るお金の総額÷払い込む保険料の総額×100
【具体例:返戻率120%の場合】
例えば、ある貯蓄型保険に加入し、最終的に返戻率が120%になったケースを考えてみましょう。
- 月払保険料:2万円
- 払込期間:20年
- 満期:20年後
この場合、
- 払い込む保険料の総額を計算する
2万円 × 12カ月 × 20年 = 480万円 - 受け取るお金の総額を計算する
払込保険料総額 × 返戻率 = 受取総額
480万円 × 120% (1.2) = 576万円
このケースでは、払い込んだ480万円が、満期時には576万円になって戻ってくることになります。差額の96万円が、この保険を通じて得られた利益(儲け)です。
このように、返戻率が分かれば、将来いくら受け取れるのかを簡単にシミュレーションすることができます。保険を検討する際には、必ずこの計算を行い、具体的な金額をイメージすることが大切です。
返戻率が100%を上回る仕組み
「なぜ、万一の保障がありながら、支払った保険料以上のお金が戻ってくるの?」と不思議に思う方もいるかもしれません。
返戻率が100%を上回る理由は、保険会社が契約者から集めた保険料(の一部)を運用して利益を出しているからです。
貯蓄型保険の保険料は、大きく分けて2つの部分から構成されています。
- 保障部分の保険料:死亡保障や医療保障など、万一の事態に備えるためのコスト。いわゆる「掛け捨て」部分に相当します。
- 貯蓄部分の保険料:将来の満期保険金や解約返戻金のために積み立てられる部分。
保険会社は、この「貯蓄部分の保険料」を、国債や株式、不動産など、比較的リスクの低い安定的な投資先に分散投資して運用します。そして、その運用によって得られた利益の一部を、契約者に満期保険金などの形で還元しているのです。
つまり、運用による利益が、保障にかかるコストや保険会社の経費を上回った場合に、返戻率は100%を超えることになります。
ただし、近年の歴史的な低金利の影響で、保険会社の運用環境は厳しくなっています。そのため、かつてのような高い返戻率を誇る商品は少なくなり、元本割れのリスクがないとは言えない商品も増えているのが現状です。
貯蓄型保険の返戻率のポイント
返戻率の意味を理解したところで、次に貯蓄型保険を選ぶ際に知っておくべき返戻率に関する重要なポイントを2つ解説します。このポイントを知らないと、思わぬ損をしてしまう可能性もあるため、しっかりと押さえておきましょう。
返戻率は保険期間が長い程高くなる
一般的に、貯蓄型保険の返戻率は、保険料の払込期間や保険期間が長ければ長いほど高くなる傾向があります。
これは、保険会社が長期間にわたって資金を運用できるためです。運用期間が長ければ長いほど、複利効果(利息が利息を生む効果)が大きくなり、より多くの利益を期待できます。その結果、契約者に還元できる金額も増え、返戻率が高くなるのです。
例えば、同じ商品でも、
- 10年満期よりも20年満期
- 60歳払込満了よりも終身払い(ただし解約時期による)
の方が、返戻率は高くなるのが一般的です。
将来の資産形成を目的として貯蓄型保険に加入する場合、できるだけ若いうちに加入し、長期間コツコツと積み立てていくことが、返戻率を高める上で非常に有効です。ただし、長期間の契約は、ライフプランの変更に対応しにくいという側面もあるため、無理のない範囲で計画を立てることが重要です。
途中解約すると返戻率は100%以下になる可能性が高い
貯蓄型保険における最大の注意点が、途中解約のリスクです。
満期まで継続すれば返戻率が100%を超える商品であっても、保険料の払込期間中に解約してしまうと、解約返戻金が払込保険料総額を大幅に下回り、元本割れする可能性が非常に高いのです。
なぜ途中解約で元本割れするのでしょうか?
その理由は、私たちが支払う保険料の中から、契約の初期段階で保険会社の経費(人件費、広告費、新契約の締結費用など)が大きく差し引かれるためです。
契約の初期は、貯蓄に回るお金よりも保障や事業経費に使われるお金の割合が大きいため、解約してもほとんどお金が戻ってこない、あるいは全く戻ってこないケースもあります。
特に、契約から数年以内の早期解約は、元本割れの幅が非常に大きくなるため、絶対に避けなければなりません。
貯蓄型保険は、あくまでも満期まで継続することを前提とした商品です。加入を検討する際には、
- 将来、急な出費で保険料の支払いが困難にならないか?
- ライフイベントの変化(結婚、出産、転職など)があっても、支払いを続けられる金額か?
といった点を慎重にシミュレーションし、無理のない保険料設定をすることが、資産形成を成功させるための鍵となります。もし「途中でやめたい」と思う可能性があるなら、流動性の高い他の金融商品(つみたてNISAなど)を検討する方が賢明かもしれません。
貯蓄型保険の返戻率の目安
では、現在の低金利時代において、貯蓄型保険の返戻率はどのくらいを目安に考えれば良いのでしょうか。銀行預金や他の金融商品と比較しながら解説します。
現在の日本の金融市場は、依然として超低金利が続いています。この影響を受け、貯蓄型保険の返戻率も全体的に低下傾向にあります。
一昔前のように、返戻率120%や130%といった高いリターンを期待できる商品はほとんど見られなくなりました。現在販売されている円建ての貯蓄型保険(終身保険、養老保険、学資保険など)の返戻率の目安は、おおよそ103%〜110%程度が一般的です。
特に、保険期間が10年程度の比較的短い商品(10年満期など)では、返戻率が101%〜105%程度と、元本をわずかに上回る水準になることも珍しくありません。
【他の金融商品との比較】
- 銀行の定期預金:大手銀行の定期預金金利は年0.002%程度(2025年8月時点の想定)です。100万円を10年間預けても、利息はわずか200円(税引前)です。これと比較すれば、返戻率103%(10年で3%の利益)の貯蓄型保険の方が、貯蓄性は格段に高いと言えます。
- 投資信託(つみたてNISAなど):一方で、株式などで運用する投資信託は、より高いリターンを期待できます。例えば、全世界株式インデックスファンドなどに長期で積み立て投資した場合、年平均3%〜7%程度のリターンが期待できると言われています。これは、10年後の返戻率に換算すると115%〜140%程度に相当し、貯蓄型保険を大きく上回る可能性があります。
ただし、投資には元本割れのリスクが伴います。市場の状況によっては、大きな損失を被る可能性もゼロではありません。
【結論として】
貯蓄型保険の返戻率は、
- 銀行預金よりは高いが、
- 本格的な投資商品(投資信託など)よりは低い
という位置づけになります。
そのため、「元本割れのリスクは極力避けたいけれど、銀行預金よりは少しでも効率的にお金を増やしたい」という、安定志向の方や資産形成の初心者に向いている商品と言えるでしょう。
「貯蓄型保険は無駄だ」「保険で貯蓄をしてはいけない」といった意見も聞かれますが、これは主に投資と比較した場合の収益性の低さを指摘するものです。しかし、万一の保障を備えながら、強制的に貯蓄できる仕組みは、貯金が苦手な方にとっては大きなメリットとなり得ます。ご自身の性格やリスク許容度、そして何よりも加入目的を明確にした上で、最適な選択をすることが重要です。
返戻率が高いおすすめ貯蓄型保険ランキングTOP3
ここからは、数ある貯蓄型保険の中から、特に返戻率が高く、多くの方におすすめできる商品をランキング形式で3つご紹介します。ご自身の目的やライフプランと照らし合わせながら、比較検討してみてください。
※本ランキングや返戻率の数値は、特定の契約条件に基づいた一例であり、契約者の年齢、性別、保険期間、払込期間、保険金額などによって変動します。正確な返戻率は必ず保険会社の設計書でご確認ください。
TOP1:住友生命「たのしみワンダフル」
返戻率の目安:109.7%
(契約例:契約年齢30歳男性、保険期間5年、月払保険料29,067円、5年ごと利差配当付積立保険)
【商品の特徴】
住友生命の「たのしみワンダフル」は、5年という短い保険期間で満期を迎えられる積立保険です。短期間で着実に資産形成をしたい方や、近い将来に使う予定のある資金(結婚資金、車の購入費用、旅行費用など)を準備したい方に最適な商品です。
最大の特徴は、5年という短期間ながら109.7%という業界でもトップクラスの高い返戻率を実現している点です。保険料の払込は契約時の1回のみ(一時払い)ではなく、5年間月々払い続ける形式のため、まとまった資金がなくても始めやすいのが魅力です。
死亡保障もシンプルで、払い込んだ保険料相当額が死亡保険金として支払われるため、掛け捨て部分が少なく、その分貯蓄性に特化しています。
【どんな人におすすめ?】
- 5年〜10年程度の短いスパンで、目標額を貯めたい方
- 銀行預金よりも有利な貯蓄方法を探している方
- リスクを抑えながら、着実に資産を増やしたい方
- まとまった資金はないが、コツコツ積立を始めたい方
【契約概要(一例)】
| 項目 | 内容 |
| 契約可能年齢 | 0歳~70歳 |
| 保険期間 | 5年 |
| 払込方法 | 月払・年払 |
| 払込期間 | 5年 |
| 配当 | 5年ごと利差配当付 |
TOP2:明治安田生命「じぶんの積立」
返戻率の目安:106.3%
(契約例:保険期間10年、保険料払込期間5年、いつ解約しても100%以上の返戻率)
【商品の特徴】
明治安田生命の「じぶんの積立」は、シンプルさと自由度の高さで人気を集めている積立保険です。商品名の通り、「じぶん」のペースで、目的を選ばずに積み立てられるのが大きな特徴です。
この商品の最大の魅力は、保険料払込期間(5年間)が終了すれば、いつ解約しても返戻率が100%を上回る点です。通常の貯蓄型保険は満期前に解約すると元本割れしますが、「じぶんの積立」は5年後以降、好きなタイミングで資金を引き出すことができます。
また、満期保険金は10年間据え置くことも可能で、その間も所定の利率で運用されるため、さらに返戻率を高めることができます。保険料は月々5,000円から1,000円単位で設定でき、最大2万円まで。手軽に始められる点も人気の理由です。
【どんな人におすすめ?】
- 貯蓄型保険の「途中解約による元本割れ」が不安な方
- 使う時期は決まっていないが、とりあえず貯蓄を始めたい方
- 少額からコツコツ積立を始めたい保険初心者の方
- 生命保険料控除(一般生命保険料控除)を活用して節税したい方
【契約概要(一例)】
| 項目 | 内容 |
| 契約可能年齢 | 0歳~75歳 |
| 保険期間 | 10年 |
| 払込方法 | 月払(口座振替) |
| 払込期間 | 5年 |
| 月払保険料 | 5,000円~20,000円(1,000円単位) |
TOP3:明治安田生命「年金かけはし」
返戻率の目安:105.9%
(契約例:契約年齢30歳男性、保険料払込期間10年、年金受取開始60歳)
【商品の特徴】
明治安田生命の「年金かけはし」は、将来のセカンドライフに備えるための個人年金保険です。着実に老後資金を準備したいというニーズに応える商品設計となっています。
この商品は、保険料払込期間中の死亡保障を、払い込んだ保険料相当額に抑えることで、その分を年金の原資に回し、高い返戻率を実現しています。いわゆる「保障」よりも「貯蓄」を重視したタイプの個人年金保険です。
契約時に将来受け取れる年金額が確定する「確定年金」タイプなので、将来のライフプランを立てやすいのが特徴です。また、保険料の払込期間を10年と短めに設定できるため、子育てが一段落した40代・50代の方でも、定年までに払込を終えるプランが立てやすいでしょう。
【どんな人におすすめ?】
- 公的年金だけでは不安で、老後資金を計画的に準備したい方
- 保障は他の保険で確保しているので、貯蓄性に特化した商品を探している方
- 個人年金保険料控除を活用して、所得税・住民税を節税したい方
- 将来の受取額が確定している安心感を重視する方
【契約概要(一例)】
| 項目 | 内容 |
| 契約可能年齢 | 20歳~70歳 |
| 年金受取開始年齢 | 50歳~75歳 |
| 払込方法 | 月払・年払・一時払 |
| 払込期間 | 10年・15年・20年、または年金受取開始年齢まで |
| 年金種類 | 確定年金(5年・10年・15年) |
貯蓄型保険の返戻率を高めるコツ
同じ保険商品でも、契約の仕方やプランの選び方によって返戻率は変わってきます。ここでは、少しでも有利な条件で契約するために、貯蓄型保険の返戻率を高めるための3つの具体的なコツをご紹介します。
1. シンプルな保障内容を選ぶ
貯蓄型保険には、主契約である死亡保障や満期保険金に加えて、「特約」として入院保障やがん保障、先進医療保障などを付加できる商品が多くあります。
手厚い保障は安心につながりますが、特約を多く付加すればするほど、その分の保険料は「掛け捨て」となり、貯蓄に回るお金が減ってしまいます。その結果、主契約部分の返戻率は低下してしまいます。
返戻率を最優先に考えるのであれば、特約はできるだけ付けずに、主契約のみのシンプルなプランで加入するのが鉄則です。医療保障やがん保障などが必要な場合は、貯蓄型保険に付加するのではなく、別途、割安な掛け捨て型の医療保険やがん保険で備える方が、トータルで見て保険料を抑えられ、効率的です。
保険選びの際は、「保障」と「貯蓄」の目的を明確に分け、それぞれの目的に合った最適な商品を組み合わせる「ハイブリッドな考え方」が重要になります。
2. 祝金は受け取らない
学資保険などでは、子どもの進学時期に合わせて「進学準備金」や「お祝い金」が支払われる商品があります。
この祝い金を都度受け取るのではなく、受け取らずに保険会社に預けておく(据え置く)ことで、満期時の受取総額が増え、結果的に返戻率が高まる場合があります。
据え置かれた祝い金は、保険会社によって所定の利率で運用されます。この利率は現在の金融情勢では決して高くはありませんが、それでも普通預金に預けておくよりは有利なケースがほとんどです。
すぐに使う予定のないお金であれば、満期まで据え置く選択肢を検討してみましょう。契約時に、祝い金を受け取るか据え置くかを選択できる場合が多いので、シミュレーションを依頼して、どちらが有利になるかを確認することをおすすめします。
3. 保険料は月払いではなくまとめて払う
保険料の支払方法には、毎月支払う「月払」の他に、半年に1回支払う「半年払」や、1年に1回支払う「年払」があります。さらに、契約時に全期間の保険料をまとめて支払う「一時払」や「全期前納払」といった方法もあります。
一般的に、保険料をまとめて支払うほど、割引が適用されて総払込保険料が安くなります。受け取る満期保険金額が同じであれば、払込総額が安くなる分、返戻率は高くなります。
例えば、月払保険料が1万円の場合、年払にすると11万8,000円(月払の合計12万円より2,000円安い)といった具合です。
まとまった資金に余裕がある場合は、月払よりも年払や一時払を選択することで、より高い返戻率を目指すことができます。特に、相続した資金の運用先として貯蓄型保険を検討している50代、60代の方などは、一時払を活用することで効率的な資産形成が可能です。
ただし、一度に大きな金額を支払うことになるため、家計のキャッシュフローを圧迫しないよう、手元の資金計画を慎重に立てた上で選択することが大切です。
理解を深める!貯蓄型保険の種類と返戻率の特徴
貯蓄型保険と一言でいっても、その目的や保障内容によっていくつかの種類に分かれます。ここでは代表的な4つの種類を取り上げ、それぞれの特徴と返戻率の傾向について解説します。
1. 終身保険
特徴:
一生涯の死亡保障が続く保険です。被保険者(保険の対象となる人)が亡くなった際に、遺族に死亡保険金が支払われます。保険料の払込期間を60歳や65歳などで終えれば、その後は保険料の負担なく一生涯の保障を確保できます。払込期間満了後に解約すれば、払込保険料総額を上回る解約返戻金を受け取れることが多く、老後資金や長期的な資産形成の手段としても活用されます。
返戻率の傾向:
払込期間が満了してから時間が経てば経つほど、解約返戻金が増え続け、返戻率が高まっていきます。長期で寝かせておける資金の運用に向いています。特に、低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間中の解約返戻金を低く抑える代わりに、払込満了後の返戻率を高く設定しているのが特徴です。
2. 養老保険
特徴:
死亡保障と貯蓄の両方の性質をバランス良く備えた保険です。保険期間は10年、20年、あるいは60歳満了など、一定の期間で設定されます。保険期間中に死亡した場合は死亡保険金が、無事に満期を迎えた場合は死亡保険金と同額の満期保険金が支払われます。保障と貯蓄の目的が明確なため、計画的に資金を準備したい場合に適しています。ゆうちょ銀行などで取り扱われることも多い商品です。
返戻率の傾向:
かつては高い返戻率で人気でしたが、近年の低金利下では返戻率が100%をわずかに上回る程度か、商品によっては元本割れするものもあります。保障と貯蓄を両立している分、貯蓄性に特化した他の商品と比べると返戻率はやや低めになる傾向があります。
3. 学資保険
特徴:
子どもの教育資金を準備することを目的とした保険です。契約者である親に万一のことがあった場合、その後の保険料の払込が免除され、祝い金や満期保険金は予定通り受け取れる「払込免除特約」が付いているのが一般的です。子どもの進学時期に合わせて、中学校入学時、高校入学時、大学入学時などにお祝い金が支払われるプランが多く見られます。
返戻率の傾向:
返戻率は商品によって幅広く、103%~108%程度のものが主流です。医療特約などを付加すると元本割れするケースも多いため、返戻率を重視するなら保障はシンプルなものを選ぶのがおすすめです。祝い金を受け取らずに据え置くことで、返戻率を高めることができます。
4. 個人年金保険
特徴:
公的年金に上乗せする形で、私的な老後資金を準備するための保険です。保険料を一定期間(例えば60歳や65歳まで)払い込み、その後、一定期間(5年、10年など)または一生涯にわたって年金形式でお金を受け取ります。年末調整や確定申告で「個人年金保険料控除」が使えるため、節税メリットが大きいのが魅力です。
返戻率の傾向:
円建ての確定年金の場合、返戻率は105%~110%程度が目安となります。運用実績によって年金額が変動する「変額個人年金」や、米ドルなどの外貨で運用する「外貨建て個人年金」は、より高いリターンを期待できる一方、為替リスクや元本割れのリスクも伴います。
加入前に知るべき貯蓄型保険のメリット・デメリット
貯蓄型保険は魅力的な商品ですが、万能ではありません。メリットとデメリットの両方を正しく理解した上で、ご自身の資産形成プランに合致するかどうかを判断することが重要です。
貯蓄型保険の4つのメリット
- 万一の保障と貯蓄を両立できる
最大のメリットは、不慮の事故や病気で亡くなった場合の死亡保障を備えながら、同時にお金を貯められる点です。特に、扶養家族がいる方にとっては、自分に万一のことがあった際の生活費を確保しつつ、将来の教育資金や老後資金を準備できる安心感は大きいでしょう。 - 強制的に貯蓄する仕組みが作れる
銀行預金のように自由に出し入れができないため、「あるとつい使ってしまう」という方でも、半強制的に貯蓄を継続できる仕組みが作れます。毎月、口座から自動的に保険料が引き落とされるため、意志の力に頼らずとも着実に資産を積み上げていくことができます。 - 生命保険料控除による税金の軽減効果がある
支払った保険料は、所得税や住民税を計算する際に「生命保険料控除」の対象となり、課税所得から一定額を差し引くことができます。これにより、年間の税負担を軽減することが可能です。特に、個人年金保険には専用の控除枠があり、節税メリットは大きくなります。 - 銀行預金よりは高い利回りが期待できる
前述の通り、現在の超低金利下において、銀行の普通預金や定期預金にお金を預けていてもほとんど増えません。その点、貯蓄型保険は、元本割れのリスクを抑えながらも、銀行預金よりは高い返戻率が期待できます。
貯蓄型保険の4つのデメリット(保険で貯蓄をしてはいけないと言われる理由)
一方で、貯蓄型保険には注意すべきデメリットも存在します。これらが、「保険で貯蓄をしてはいけない」と言われる主な理由にもなっています。
- 掛け捨て型保険に比べて保険料が割高
貯蓄部分がある分、同じ保障内容の掛け捨て型保険と比較すると、月々の保険料はかなり高くなります。家計に占める保険料の割合が大きくなりすぎると、他のこと(自己投資や趣味など)にお金を使えなくなったり、急な出費に対応できなくなったりする可能性があります。 - 途中解約すると元本割れの可能性が高い
これが最大のデメリットです。契約から短い期間で解約した場合、解約返戻金が払込保険料を大幅に下回ります。人生には予期せぬ出来事がつきものです。収入の減少や急な出費などで支払いが困難になり、やむを得ず解約せざるを得なくなった場合、大きな損失を被るリスクがあります。 - インフレに弱い
契約時に将来受け取る金額が確定している円建ての貯蓄型保険は、インフレ(物価の上昇)に弱いという弱点があります。例えば、30年後に300万円を受け取る契約をしたとします。もし、その間に物価が2倍になっていれば、300万円の実質的な価値は現在の150万円分にまで目減りしてしまいます。お金の額面は増えても、購買力が低下してしまうリスクがあるのです。 - 資金の流動性が低い
一度保険料として支払うと、満期や解約をしない限り、そのお金を自由に引き出して使うことはできません。(※契約者貸付制度を利用できる場合もありますが、利息がかかります。)急にまとまったお金が必要になった際に、すぐに対応できないという資金の流動性の低さは、デメリットと言えるでしょう。
これらのデメリットを理解した上で、「保障は掛け捨ての保険」「貯蓄はNISAなどの投資」と、目的を分けて考える方が合理的だという意見が、「保険で貯蓄をしてはいけない」という主張の根拠となっています。
失敗しない!貯蓄型保険の選び方と注意点
最後に、これまでの内容を踏まえて、ご自身に最適な貯蓄型保険を選ぶための具体的なステップと注意点を解説します。
- 加入する目的を明確にする
まず最も重要なのは、「何のために」「いつまでに」「いくら」必要なのかを明確にすることです。- 老後資金のため? → 個人年金保険
- 子どもの教育資金のため? → 学資保険
- 10年後の住宅購入の頭金のため? → 養老保険
- 相続対策や長期的な資産形成のため? → 終身保険
目的が明確になれば、選ぶべき保険の種類が自ずと絞られてきます。
- 複数の保険会社の商品を比較・検討する
貯蓄型保険は、保険会社や商品によって返戻率や保障内容が大きく異なります。1つの保険会社や1人の担当者の提案だけを鵜呑みにせず、必ず複数の会社から資料を取り寄せたり、保険ショップなどで相談したりして、客観的に比較検討しましょう。その際、必ず「返戻率」が何パーセントになるのかを確認することが重要です。 - ライフプランに合った保険期間・払込期間を設定する
返戻率を高くしたいからといって、無理に長すぎる払込期間を設定するのは危険です。子どもの独立や定年退職など、将来の収入の変動を考慮し、余裕を持って払い続けられる期間を設定しましょう。特に50代から加入を検討する場合は、定年までに払込を終える短期払いのプランなどがおすすめです。 - 外貨建て保険や変額保険のリスクを理解する
円建て保険よりも高い返戻率を提示されることが多いのが、「外貨建て保険」や「変額保険」です。これらは高いリターンが期待できる反面、為替変動リスクや運用実績による元本割れリスクを伴います。仕組みが複雑なため、リスクを十分に理解できない場合は、まずは円建てのシンプルな商品から検討するのが賢明です。 - 信頼できる専門家に相談する
保険選びは、ご自身の家庭の状況や将来の夢を映し出す、非常にパーソナルな作業です。自分一人で判断するのが難しい場合は、特定の保険会社に属さない独立系のファイナンシャルプランナー(FP)や、複数の保険会社の商品を扱う保険代理店(保険ショップ)の専門家に相談するのも有効な方法です。客観的な視点から、あなたに合った保険選びをサポートしてくれるでしょう。
まとめ
今回は、貯蓄型保険の「返戻率」について、その意味や計算方法、利率・利回りとの違いから、返戻率を高めるコツ、そしておすすめの商品ランキングまで、幅広く解説しました。
最後に、この記事の重要なポイントを振り返ります。
- 返戻率とは、払込保険料総額に対して受け取れるお金の割合のこと。100%を超えれば利益が出る。
- 返戻率は契約期間が長いほど高くなり、途中解約すると元本割れする可能性が高い。
- 現在の返戻率の目安は103%〜110%程度。銀行預金よりは有利だが、投資よりはリターンが低い。
- 返戻率を高めるコツは「保障をシンプルに」「祝い金は据え置き」「保険料はまとめて払う」こと。
- 貯蓄型保険には、保障と貯蓄を両立できるメリットと、保険料の割高感やインフレに弱いといったデメリットがある。
- 保険を選ぶ際は、目的を明確にし、複数の商品を比較することが何よりも大切。
貯蓄型保険は、あなたの将来の夢や家族の安心を支える力強いツールになり得ます。しかし、それは「返戻率」という指標を正しく理解し、ご自身のライフプランに合った商品を賢く選んでこそです。