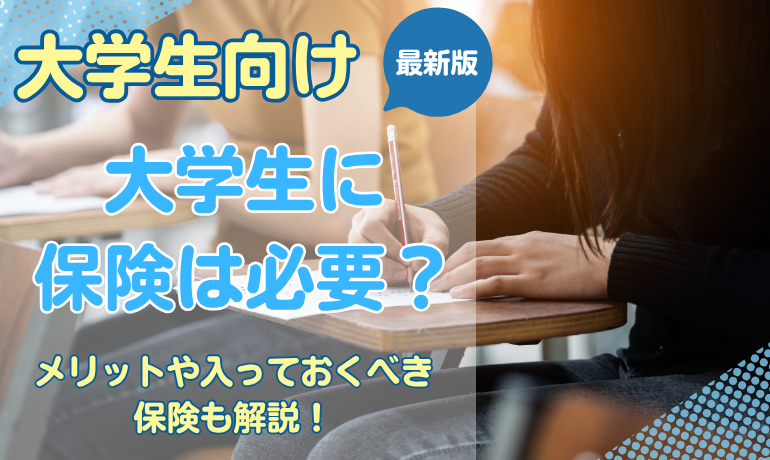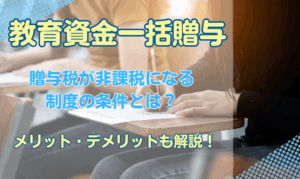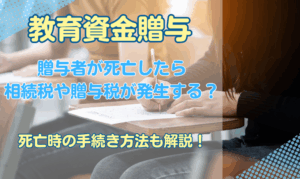大学生になるお子さんを持つ親御さんにとって、「大学生に保険は必要か?」という疑問は重要なテーマです。経済的に親を頼れない学生本人も、自分に保険が必要か悩むことがあるでしょう。本記事では、大学生に保険が必要かどうか、その加入状況やメリット、そして大学生に必要な保険の種類について詳しく解説します。親御さんが安心できるよう、丁寧に説明していきます。
大学生に保険は必要か?入っている割合は?
まず初めに、大学生に保険が必要かどうか見ていきましょう。結論から言うと、大学生にとって保険への加入は義務ではありませんが、備えとして検討する価値は大いにあります。実際にどれくらいの大学生が保険に加入しているのか、統計データを紹介します。
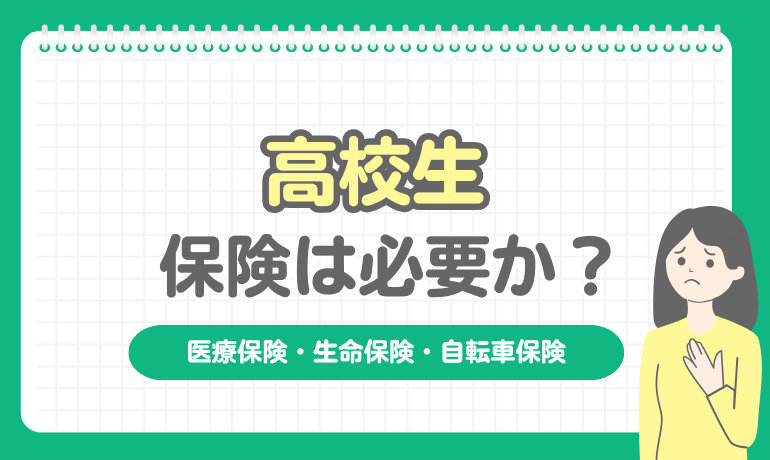
大学生の3~4割がなんらかの保険に加入している
公的な正確なデータは多くありませんが、いくつかの調査から大学生の約3~4割は何らかの保険や共済に加入していることが分かっています。たとえば、厚生労働省の調査によると20~24歳の若年層の約4割が生命保険や個人年金保険に加入しているとの結果があります。また、大学生活協同組合(生協)の学生向け共済への加入者数は2022年度で約69.7万人(約2~3割)にのぼります。これらの数字から見ても、大学生の一定数は何らかの保険でリスクに備えていると言えるでしょう。
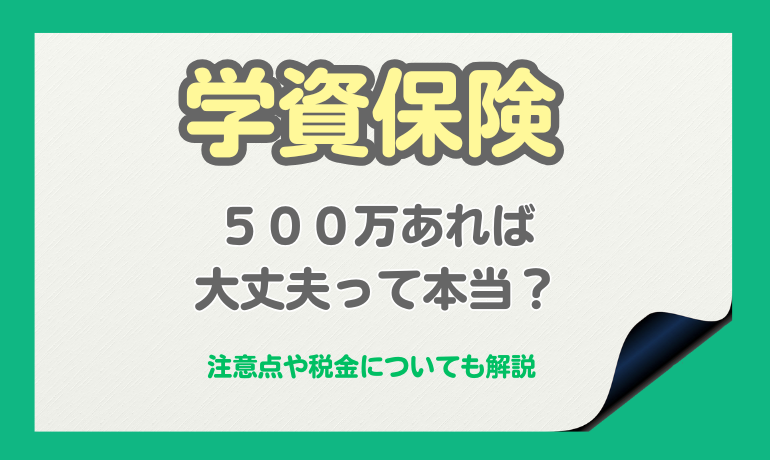
大学生用の保険には入らないことも多い
一方で、大学生の多くは民間の保険や学生共済に加入していないのも実情です。半数以上の学生は特に保険に入らずに大学生活を送っています。なぜ加入しない学生が多いのでしょうか。その理由としては次のような点が考えられます。
経済的な理由
大学生は収入が限られており、保険料の負担を避けたいと考えるケースがあります。奨学金を利用している学生や、家計に余裕がない家庭では、「保険まで手が回らない」という声もあります。
必要性を感じていない
若いから大きな病気や事故は起こらないだろうと楽観視し、保険の必要性を感じていない人もいます。また、「国民健康保険で医療費はある程度カバーできるので十分」と考え、あえて民間の医療保険などに加入しない場合もあります。
情報不足・手続きの手間
大学入学時に生協や保険会社から案内はあるものの、保険内容を難しく感じたり、手続きが面倒で後回しにしているうちに加入しそびれてしまったりするケースもあります。「なんとなく入らずに過ごしているうちに卒業してしまった」という先輩も珍しくありません。
保険加入が必須のこともある
ただし、大学生活の状況によっては保険加入が事実上必須となる場合もあります。大学やプログラムによっては、学生に特定の保険への加入を求めるケースがあるのです。たとえば、以下のようなケースが挙げられます。
大学指定の学生教育研究災害傷害保険(学研災)
実験や実習を伴う学部では、学生全員に「学研災」への加入が義務付けられていることがあります。学研災は授業中や大学行事中のケガを補償する保険で、多くの大学で加入が推奨されています。
クラブ・部活動での保険加入
スポーツ系のクラブ活動では、部活動中の事故に備えてスポーツ保険に加入する例もあります。大学の体育会系クラブでは、団体でスポーツ安全保険に加入し、万一の怪我に備えていることが一般的です。また、合宿や大会参加の際に短期の保険加入を義務づける場合もあります。
留学や海外研修時の保険
大学から海外留学に行く場合、留学先や大学側が留学生保険(海外旅行保険)への加入を必須としていることがほとんどです。留学中の病気・ケガやトラブルに備えるため、渡航前に所定の保険に入ることが求められます。たとえば、東北大学では公式に「対象となる海外渡航を行う学生全員が旅行保険に加入すること」を原則としています。
自動車・バイクの運転
大学生になって車やバイクの免許を取得する人もいますが、車やバイクを利用する場合は自賠責保険(強制保険)への加入が法律で義務付けられています。さらに任意の自動車保険にも加入しないと、万一の事故で高額賠償を背負うリスクがあります。このため、実質的に車やバイクを運転する学生は保険加入が必須と言えます。
このように、大学生でも状況によっては保険なしでは活動できないことがあります。したがって、「大学生に保険は必要か?」という問いに対しては、「必ずしも全員が必要とまでは言えないが、多くのケースで備えがあったほうが安心」という答えになるでしょう。
親御さんの口コミ:
実際、インターネット上には大学生の子を持つ親御さんから次のような相談も寄せられています。

来春から大学生になる息子がいます。大学生になったら保険に入るべきか悩んでいます。皆さんは大学生のお子さんに保険をかけていますか?



家計に余裕がなく、大学生の娘に保険をかけるか迷っています。保険料も安くないので、周りのご家庭がどうしているか気になります…
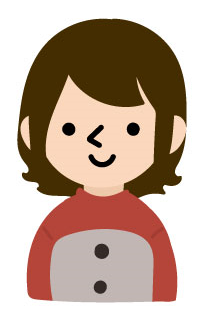
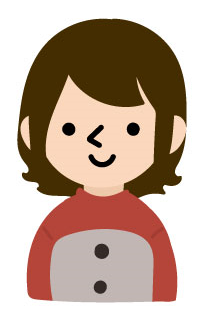
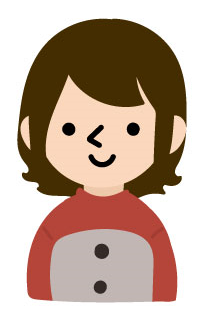
家計に余裕がなく、大学生の娘に保険をかけるか迷っています。保険料も安くないので、周りのご家庭がどうしているか気になります…
上記のように、「大学生に保険は必要?他の家庭はどうしてるの?」と悩む親御さんは少なくありません。本記事の後半では、大学生が保険に入ることのメリットや、実際にどんな保険に加入すべきかについて詳しく見ていきましょう。
大学生が保険に加入する4つのメリット
大学生が保険に入っておくと、具体的にどんなメリットがあるのでしょうか。ここでは大学生が直面しやすいリスクに備える4つのメリットを解説します。
本人のケガや病気への備え
大学生でも、大きなケガや病気になるリスクはゼロではありません。サークル活動中のケガ、アルバイト中の事故、インフルエンザや肺炎などによる入院など、若い世代でも思わぬ病気やケガで治療が必要になることがあります。特に一人暮らしの場合、入院や手術の際には家族のサポートや予想外の出費が必要になるため、学生本人にとって大きな負担です。例えば、大学生協の共済(学生総合共済)のデータでは、1年間で学生の病気による入院給付の支払い件数が1万件を超えています。急性虫垂炎で手術・入院したり、スポーツ中の骨折で入院するといったケースも実際に多数発生しています。公的医療保険では医療費の一部しかカバーされませんが、民間の医療保険や共済に加入していれば入院日数に応じた給付金が支給され、自己負担分や雑費を補えます。保険に入っていれば、万一大学生本人が病気やケガで入院・手術となった際に金銭面の心配を減らし、治療に専念できるという大きなメリットがあります。


他人へのケガや賠償責任への備え
大学生になると行動範囲が広がり、他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまうリスクも高まります。自転車で通学中に歩行者と衝突して相手にケガを負わせてしまった、誤って友人の高価なノートパソコンを壊してしまった、アパートで水漏れ事故を起こして下の階の部屋に損害を与えてしまったなど、賠償責任を負う事故は起こり得ます。そのような場合、数百万〜数千万円単位の高額な損害賠償を請求されることもあります。実際、大学生協の「学生賠償責任保険」で500万円以上の高額賠償となった事例を見ると、アパートでの水漏れ事故や自転車事故が多く発生しています。中には数千万円規模の賠償金支払いとなったケースもあり、本人や家族だけではとても賄えません。こうした他人への損害に備え、個人賠償責任保険に加入しておけば、法律上の賠償責任が発生した際に保険会社から保険金が支払われます。特に近年は自転車事故による高額賠償事例も増えており、一部の自治体では自転車保険の加入が義務化されているほどです。保険によっては1事故あたり1億円以上の賠償責任もカバーできるので、万一のときに備えて他人への賠償責任保険に入っておくメリットは大きいでしょう。
火災や水漏れなど住居トラブルへの備え
地方大学などで一人暮らしを始める学生も多いですが、賃貸住宅での火災や水漏れといったトラブルにも備えが必要です。一人暮らし用のアパートやマンションでは、火の不始末による火事や、水道の閉め忘れによる漏水事故などが起こることがあります。万が一自分の部屋が火元となって建物全体に被害が及べば、隣室や建物オーナーに対して多額の賠償をしなければなりません。また、火災だけでなく泥棒による盗難被害や、台風で窓ガラスが割れて家財が壊れるといったリスクもあります。こうした住居トラブルに備える代表的な保険が火災保険(家財保険)や個人賠償責任保険です。火災保険に加入すれば、自室の家財が火事や風水害で損壊した場合の補償が受けられますし、借家人賠償責任特約を付ければ自分の過失で建物や他の部屋に損害を与えた際の賠償もカバーされます。大学生協のデータでも、漏水事故により下の階への賠償に数百万円以上支払われた例が報告されています。保険に入っていればこうした事故の際にも金銭的な補償を受けられるため、実家から離れて生活する学生にとって心強い備えとなります。
貴重品の紛失や盗難への備え
大学生になると、高額なノートパソコンやスマートフォン、自転車など高価な持ち物を自分で管理する場面が増えます。貴重品の紛失や盗難に遭うリスクも決して低くありません。たとえば、自転車通学をしている場合は自転車の盗難被害に遭う可能性がありますし、下宿先に置いていたノートPCが盗まれたり、旅行中に荷物を失くすことも考えられます。 このようなとき、携行品損害保険や火災保険の家財補償を利用すれば、盗難や破損に対する補償金が受け取れる場合が多いです。自転車に関しても、盗難保険の中には購入費用の一部が戻ってくる商品もあります。せっかく購入したパソコンや自転車がなくなると経済的ダメージが大きいですが、保険でカバーされていれば速やかに代替品を用意することができます。保険は物の紛失・盗難という金銭面以外ではカバーしづらいトラブルが起きた際に経済的なサポートをしてくれる点も大きなメリットの1つです。
大学生に必要な保険の種類と保障内容
では具体的に、大学生にはどのような保険が必要なのでしょうか。ここでは大学生とその家族が検討すべき代表的な保険の種類と、その保障内容について説明します。
学生総合共済
学生総合共済とは、大学生活協同組合が提供する大学生向けの共済制度です。大学生協の組合員(学生)が加入できるもので、病気やケガによる入院・通院の保障、障害が残った場合の保障、そして扶養者(仕送りをしている保護者)に万一のことがあった場合の育英費用保障などがセットになっています。掛金(月額保険料)が比較的安価である点が特徴で、たとえば1年間1万円前後のプランで入院日額1万円や、死亡時に100万円の共済金が支払われるといった手厚い保障内容になっています。育英費用保障は、在学中に扶養者(主に親御さん)が不慮の事故で亡くなった・重度障害になった場合などに学生生活を経済的に支えるための給付金です。大学によっては新入生に生協の学生総合共済への加入案内が配布されるので、内容を確認して必要だと思ったら加入すると良いでしょう。共済のため、営利目的の保険会社の商品ではありませんが、基本的な仕組みは民間の保険と同様で、所定の事故や事由が発生したときに共済金(保険金)が支払われます。
学生総合保障制度
学生総合保障制度は、大学生協の共済とは別に提供されている学生向け保険パッケージです。たとえば「一般財団法人未来サポート」が運営する学生あんしんパスポートなどが該当します。この制度では、学生本人のケガ・病気による入院保障、賠償責任保障、さらには扶養者に万一のことがあった場合の育英費用保障など、大学生活に関わるさまざまなリスクを総合的にカバーしています。内容としては学生総合共済と似ていますが、こちらは民間の損害保険会社が引受保険会社となっている保険商品であり、大学生協を通さなくても加入できるケースも多いです。学生総合保障制度に加入すると、24時間365日、学内外を問わず学生生活での事故を保障してもらえます。たとえば、インターンシップ中の事故や自転車事故による賠償責任、さらにはネットトラブルによる損害賠償まで、オプションで幅広く備えられるプランもあります。掛金は共済と同様に手頃に設定されており、家計に大きな負担をかけず包括的な保障を得られるのがメリットです。大学や地域によって案内されている制度が異なる場合もありますので、興味があれば大学の学生課や取扱代理店に問い合わせてみるとよいでしょう。
個人賠償責任保険
個人賠償責任保険は、前述した他人へのケガや物損など、賠償事故全般を補償する保険です。大学生にとって特に重要な保険のひとつで、自転車事故や友人宅で物を壊してしまった場合などに活躍します。個人賠償責任保険は単独の保険として契約することもできますが、多くの場合、他の保険に特約(オプション)として追加する仕組みです。たとえば、火災保険に個人賠償特約を付ける、クレジットカード付帯保険でカバーする、自動車保険に家族の賠償責任特約を付ける、といった方法があります。また、大学生協の学生賠償責任保険もこの一種で、保険料は数百円~数千円程度と手頃な価格で加入することが可能です。補償額は1億円〜無制限のように高額となる場合もあるため、万一の重大事故でも金銭面の負担をカバーできる安心感があります。特に自転車利用者は、個人賠償責任保険への加入を必須と考えてよいでしょう。
医療保険
医療保険は、病気やケガで入院・手術をしたときに給付金が受け取れる保険です。日本の公的医療保険では、医療費の自己負担が3割となっていますが、入院が長引くとベッド代や食事代、差額ベッド代などの追加費用が発生します。医療保険に加入していれば、入院や手術の際に給付金を受け取れるため、経済的負担を大幅に軽減できます。大学生の場合、親御さんが幼い頃から医療保険に加入させているケースも多いため、まずは自分がすでに何らかの医療保険に加入しているか(親の契約に含まれているか)確認することが大切です。もし未加入で不安がある場合は、学生でも加入できる民間の医療保険を検討するとよいでしょう。ただし、既存の学生総合共済や学生総合保障制度に加入している場合は、重複加入にならないよう注意が必要です。
生命保険
生命保険(死亡保険)は、被保険者が死亡した場合に保険金が支払われる保険です。大学生本人が加入するケースは一般的ではなく、独身で扶養家族のいない学生にとっては必要性が低いと言えます。しかし、奨学金や教育ローンを学生本人が契約している場合は、万一の場合に備えて死亡時に借金を清算できる程度の生命保険に加入する選択肢もあるでしょう。また、学生自身に万一のことがあった場合の葬儀費用や、残された家族への備えとして、少額の定期保険に加入するケースもあります。ただし、大学生本人に経済的扶養者がいない場合は、まず医療保険や賠償責任保険といった、より発生しやすいリスクへの対策を優先するのが一般的です。
火災保険
火災保険は、一人暮らしの学生にはほぼ必須の保険です。賃貸物件において、火事、風災、水災、さらには盗難などのリスクに備えた家財保険が基本となります。また、借家人賠償責任特約を付けることで、自らの過失による建物や隣接部屋への損害賠償もカバーすることが可能です。家具や家電、本、衣類などの損害を補償する内容で、保険料も学生向けのプランで手頃な設定になっていることが多く、万一の備えとして加入することが推奨されています。
自転車保険やバイク保険
自転車保険は、自転車に乗る人向けの傷害保険および賠償責任保険です。近年、条例で加入が義務化されている地域もあり、自転車で通学や通勤をする学生にとって実質的な必須保険と言えます。この保険では、自転車事故による他人への損害と自身のケガに対する補償内容がセットになっている場合が多いです。バイク保険に関しては、自賠責保険(法律で定められた強制保険)に加えて任意保険に加入することで、万一の事故に備えた高額な賠償責任や修理費用などをカバーできるようになります。若いドライバーの場合、保険料は高く設定される傾向にありますが、事故のリスクを考えると加入は必須です。
育英費用保険
育英費用保険は、在学中の学生の学費や生活費を確保するための保険です。具体的には、学生を扶養している親御さんなどが死亡または高度障害状態になった場合に、学生に対して育英年金や一時金が支払われる仕組みです。奨学金や教育ローンを利用している学生に対して、親御さんに万が一のことがあった際の経済的リスクを軽減し、学業の継続を支援する目的で用いられます。すでに親御さん側で十分な生命保険に加入している場合は、新たに育英保険に契約する必要はありませんが、保障内容が不十分な場合は検討する価値があります。
大学生におすすめの保険はこちらもチェック!
大学生に必要な保険について解説してきましたが、「結局どの保険に入れば良いのか迷ってしまう…」という方もいるかもしれません。そんな場合は、複数の保険を比較検討するための資料請求を活用するのも一つの方法です。一度の手続きでまとめて複数社の保険パンフレットを取り寄せるサービスを利用することで、それぞれの保険の保障内容や保険料を詳しく知ることができます。お子さんにとって本当に必要な保険を見極めるためにも、こうしたサービスをぜひ活用してください。親御さんがしっかりと情報収集を行うことで、大学生活を送るお子さんも安心して日々を過ごすことができるでしょう。