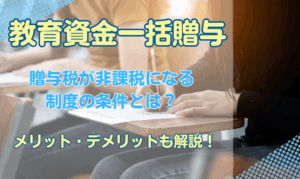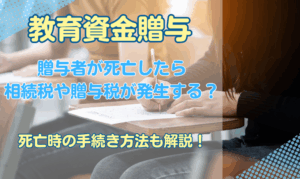ベビーカレンダー教育マガジン編集部
月間1,000万人以上が利用する医師・専門家監修の妊娠・出産・育児の情報サイト「ベビーカレンダー」の妊娠・子育てお役立ちアイテムご紹介するベビーカレンダーマガジンです。
厳選した教育サービスをアンケート結果や編集部が定義した評価基準を元にしたランキングや口コミなどでご紹介しています。
子どもの教育資金を準備するための方法として代表的な学資保険(貯蓄型保険)ですが、実際にはどれくらいの家庭が加入しているのでしょうか。2025年時点で学資保険に加入している親の割合は約38.4%に留まり、裏を返せば6割以上が学資保険に入っていません。
https://life.oricon.co.jp/rank-educational-insurance/special/knowledge/uninsured-rate
本記事では、学資保険に入っていない人の割合や特徴、加入しない理由、代替手段や公的支援制度などを解説します。学資保険への加入を検討しているのであれば、判断の一助になれば幸いです。
みんな入ってる?学資保険に入ってない割合とは
学資保険に入っていない割合は61.6%
ソニー生命保険の「子どもの教育資金に関する調査2025」によれば、高校生以下の子どもを持つ親で学資保険を利用して教育資金を準備している人は38.4%でした。裏を返せば約61.6%の親は学資保険を利用しておらず、教育費の準備方法として学資保険以外の手段を選んでいます。この調査は複数回答形式ですが、「銀行預金」(54.3%)に次いで2番目に多いのが学資保険(38.4%)という結果です。つまり、学資保険は教育資金準備の手段として一定の支持はあるものの、過半数の家庭は利用していません。
意外と思われるかもしれませんが、実際には多くの家庭が預貯金や他の方法で教育費を貯めていることが分かります。「みんな入っているからうちも入らなきゃ」と焦る必要はなく、まずは事実として学資保険未加入の家庭も多数派であると押さえておきましょう。
学資保険に入ってない割合(所得層別の傾向、シングルマザーの加入状況)
学資保険の加入には世帯の経済状況も大きく影響します。経済的に余裕がない家庭ほど学資保険に加入できない傾向が強く、実際に「世帯収入が高い世帯ほど学資保険への加入率が高い」という調査結果もあります。本当は学資保険に入りたくても、金銭的理由で入れない家庭が少なからず存在します。
特にシングルマザーは経済的負担が大きく、学資保険の保険料を捻出するのが難しくなっています。児童扶養手当などの支援はあるものの、日々の生活費や子育て費用に充てられるため、学資保険までは手が回りません。実際、シングルマザー世帯の中には「学資保険に加入する余裕がないので、貯金や他の支援に頼っている」という声もあります。収入が十分でない場合、まずは生活の安定が優先されるため、無理に学資保険に入るより他の方法で教育費を備えている家庭も多いでしょう。
学資保険の加入率の推移
学資保険への加入率は時代とともに変化しています。過去のデータを見ると、2016年頃に学資保険の利用率が約60%とピークを迎え、その後低下しました。2018年には学資保険利用率が46.3%まで下がり、半数を割っています。一方で同じ時期には銀行預金による教育資金準備の利用率が上昇しており、当時は「教育費の貯め方」として預金が学資保険を上回る傾向がみられました。
直近のソニー生命の調査結果でも学資保険の加入割合は減少傾向にあります。例えば、2024年調査では学資保険利用者は43.7%でしたが、2025年には38.4%まで低下しました。
学資保険加入率の推移(一例)
・2016年:約60.6%(ピーク時)
・2018年:約46.3%(半数以下に低下)
・2024年:約43.7%
・2025年:約38.4%
この背景には、近年の低金利や後述する学資保険のデメリットが影響しています。また、2024年から拡充された新たな投資非課税制度など、資産運用で教育資金を用意する家庭が増えていることも一因でしょう。
以上のように、学資保険の加入率は長期的には減少傾向にあります。「昔はみんな入っていたから安心」ということはなく、近年では学資保険以外の選択肢も広がっていることがうかがえます。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険に入ってない人の特徴
未加入の人にはそれぞれ合理的な理由や代替策があります。ここでは、学資保険に入っていない人によく見られる特徴を紹介します。
自分で計画的に教育費を貯められる
自力で計画的に貯蓄できる人は、あえて学資保険に加入しません。学資保険の大きな役割は「強制的な貯蓄」ですが、自分で毎月コツコツと教育資金を預金などで貯められる人にとっては、保険料を払わずとも目標金額に到達できるためです。例えば、給与天引きで教育資金用の貯蓄口座に積み立てたり、ボーナス時に学費用として定額を貯金したりといった工夫で、保険に頼らず計画的に資金準備をしている家庭もあります。
貯蓄が得意な人は、保険料の管理や保険商品選びの手間を省きつつ、自分のペースで柔軟に貯めたいと考えるため加入しません。
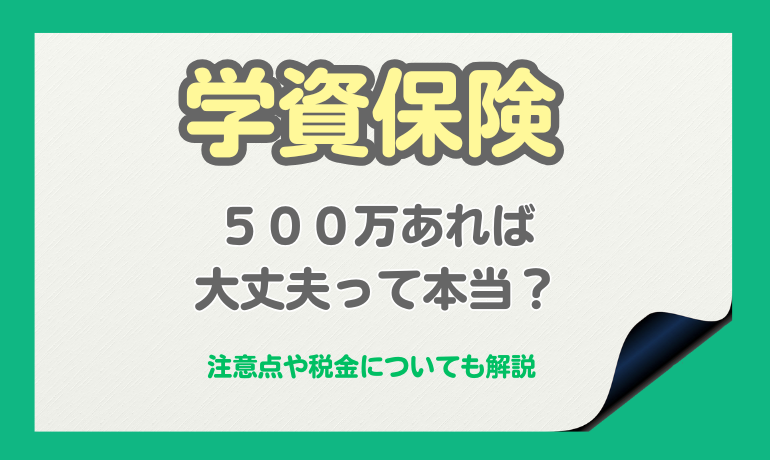
すでに十分な貯蓄がある
すでに教育費目的の貯蓄が十分にある家庭も、学資保険に入らない傾向があります。
主に、出産の祝い金や親戚からの贈与で十分に資金が賄えている家庭が当てはまります。
十分な貯蓄がある人にとって、学資保険は返戻率の低い金融商品でもあるため、無理に加入する必要がありません。むしろ、手元資金を住宅ローンの繰上返済や他の資産運用に充てたり、子どもの教育以外の目的に使ったりします。既に教育資金が確保できていれば、学資保険は「なくても困らないもの」となり得ます。
学資保険の代わりになる資産運用をしている
学資保険の代替として資産運用を選択している人もいます。近年、少額から始められる投資制度が充実し、長期の資産運用で教育資金を準備する家庭も増えてきました。実際、教育資金準備に「株式投資・投資信託・非課税投資制度」などの資産運用を利用している親が一定割合を占めており、学資保険以上に資産運用が選ばれつつある状況です。
資産運用を選ぶ理由は、学資保険より高いリターンを期待できる可能性があるからです。学資保険の返戻率はせいぜい110%前後ですが、運用がうまくいけばそれ以上の利回りも狙えます。また、学資保険の途中解約が難しい反面、資産運用であれば途中で資金が必要になった場合にも柔軟に引き出せます。もっとも、運用には元本割れリスクも伴うため、計画的に行う必要があります。
十分な生命保険に加入している
既に十分な生命保険に加入している人は学資保険を不要と考える場合があります。例えば、親が高額の死亡保障や収入保障保険などに加入しており、自分に万一のことがあっても遺族が教育費を含め生活費に困らない備えがある場合です。生命保険に加入済みの方は、学資保険の「親の死亡時に保険料免除+満期学資金保障」という機能は代替できます。

また、最近では学資保険ではなく終身保険を代用し、後で解約返戻金を学資として受け取る方法を推奨する声もあります。終身保険であれば万一の保障を持ちながら資金を貯められるため、生命保険で保障を兼ねつつ資産形成したい人は、あえて学資保険を選ばないこともできます。
入りたいけど学資保険に入る余裕がない
経済的に学資保険の加入が難しい人も少なくありません。育児には何かとお金がかかるため、毎月の保険料捻出が家計を圧迫します。特にお子さんが小さいうちは保育料や生活費の支払いが精一杯で、「学資保険どころではない」というのが本音でしょう。
調査によれば、教育資金のために備えている金額は平均で一定水準に留まっており、学資保険に加入すると、長期間にわたって保険料を支払わなければならない点で、収入に余裕がないと途中で支払いが困難になるリスクがあります。そのため、無理に加入せず「余裕ができたら検討しよう」と見送っている人もいます。
経済的に厳しい状況であれば、学資保険以外の方法で少しずつ教育費を蓄えるか、公的支援を活用する方が現実的といえるでしょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
入れるのに学資保険に入らない理由
学資保険に加入する経済力があっても、あえて加入しない選択をする人もいます。ここでは「学資保険は入らない方がいい」と言われる主な理由を3つ解説します。
デメリット1:金利が低い
学資保険は低金利環境に強く影響される商品です。昨今の超低金利下では、学資保険に預けてもお金が増えにくく、「お金を効率よく増やせない」点がデメリットとして挙げられます。金利が高かった時代には学資保険の利率も良く、払込保険料よりもかなり多い満期金を受け取れるケースが一般的でした。しかし、現在は保険の運用利回りが下がっており、学資保険の魅力だった増やす力が以前ほど期待できません。
例えば、学資保険の返戻率(受取総額÷払込総額の割合)が110%の場合、総支払保険料365万円に対して満期学資金は約400万円受け取れる計算です。しかし、現在110%を超える高返戻率の商品は少数派です。多くの学資保険は返戻率100~105%台程度であり、長期間預ける割に増えるお金がわずかしかありません。「それなら銀行預金と大差ない」「インフレで実質目減りする可能性もある」との指摘もあり、金利の低さから学資保険を敬遠する声があります。
デメリット2:返戻率が低い
学資保険の返戻率の低下もデメリットです。返戻率とは支払った保険料総額に対して受け取れる学資金の割合で、高いほど「お得な保険」ということになります。以前は110~120%超の返戻率を誇る学資保険もありましたが、近年は返戻率が徐々に低下し、学資保険は一概に有利な商品と言えなくなっています。
保険会社各社が返戻率を下げている背景には、低金利による運用益の減少や、保障の充実によるコスト増などがあります。結果として、「保険料を払っても増えない」「むしろ元本ギリギリしか戻らない」商品が増えました。学資保険の平均的な返戻率は100%前後から高くても110%程度であり、20年近く資金を預けて得られるリターンとしては決して高いとはいえません。仮に返戻率105%の保険なら、200万円預けて10万円しか増えないことになります。
そのため、資産運用や他の高利回り商品と比べるとリターンが見劣りします。特に物価上昇が続く局面では、返戻率100%程度では将来の学費高騰に対応しきれない恐れもあります。インフレリスクに弱いことも含め、返戻率の低さは学資保険のデメリットといえるでしょう。
デメリット3:途中解約で元本割れする
学資保険は長期間継続してこそメリットが出る商品であり、途中解約すると大きな損失となります。万が一、途中で資金が必要になったり、保険料負担が困難になって解約したりした場合、解約返戻金はそれまで支払った保険料総額より少なくなるのが一般的です。
例えば、15年満期の学資保険を10年で解約したとすると、返戻率が大きく目減りして払込総額の7~8割程度しか戻らないことも珍しくありません。解約時期が早いほど戻り率は低く、「途中解約=元本割れ」がほぼ避けられないのが学資保険の特徴です。保険には払済保険への変更や契約者貸付など途中救済措置もありますが、予定通り満期まで払い込めなければ当初計画した学資金を受け取れないのは間違いありません。
そのため、将来の収入不安や支出増加リスクがある場合には、学資保険加入がむしろ危険な手段となります。加入後に解約すると損をする可能性が高い以上、長期の家計負担を確実に続けられるか慎重に見極めないといけない商品であることは押さえておきましょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険に入るメリットとは
ここまでデメリットを述べましたが、もちろん学資保険ならではのメリットも存在します。学資保険が依然一定の人気を保っているのは、他の手段にはない利点が評価されているからです。
メリット1:計画的かつ確実に教育資金を準備できる
学資保険に加入すると、契約時に決めた保険料が毎月自動的に引き落とされます。半強制的な積立効果により、「つい使ってしまう」「貯金が三日坊主」という人でも確実に資金を貯められる点は大きなメリットです。貯蓄が苦手な人でも仕組みとして貯金が続けられるので、計画通りに教育費を用意しやすくなります。
メリット2:元本割れのリスクが低い
学資保険は契約時に将来受け取る満期金額が確定しており、満期まで解約せず支払い続ければ預けた元本以上の学資金を受け取れる商品です。預貯金と同様に元本が保障された貯蓄性を持ちながら、多少なりとも利息が付くのがメリットです。途中解約しなければ、株式投資のように元本が減るリスクがなく、確実に目標額を準備できる安心感があります。
メリット3:契約者に万が一のことがあっても保障される
学資保険最大のメリットとも言えるのが、契約者が死亡または高度障害状態になった場合の保険料免除特約です。加入中に契約者である親に万が一のことが起きても、その後の保険料支払いは免除され、契約は継続します。つまり、親が払い込まなくても満期金や祝い金は契約時の予定通り受け取れる仕組みです。親にとっても大きな安心材料であり、「自分にもしものことがあっても子どもの学費だけは確保できる」という心強い保障になります。通常の貯金では真似できない、保険ならではのリスクヘッジ機能です。
メリット4:所得税の生命保険料控除が受けられる
学資保険は契約形態にもよりますが多くが生命保険扱いとなるため、支払保険料は生命保険料控除の対象になります。毎年払った保険料の一定額を所得控除でき、結果として所得税・住民税の負担が軽減されます。わずかではありますが、学資保険に加入することで税金が戻ってくるメリットが得られます。貯金にはない学資保険特有の利点と言えるでしょう。
これらのメリットにより、「貯金が苦手だから学資保険で強制貯蓄したい」「万が一の保障も欲しいから加入する」といった声があるのも事実です。学資保険は万能ではありませんが、堅実に教育費を用意したい方には有効な手段となります。自分の性格や家計状況に照らし、デメリットだけでなくメリットも踏まえて判断することが大切です。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険は無理してでも入るべき?
結論からいえば、学資保険は経済的に無理をしてまで加入する必要はありません。代替手段や公的サポートもあるため、学資保険は必ずしも万人に必要なものではなく、
家計に余裕がない状態で無理に入っても、後々保険料の支払いに行き詰まるリスクがあります。途中解約すれば元本割れとなり、それまでの努力が無駄になりかねません。そうした事態を避けるためにも、日々の生活を圧迫してまで学資保険に加入するのは得策ではありません。家計をしっかり見直し、「保険料を払っても他の支出を賄えるか」「貯金やローン返済に支障はないか」を冷静に判断しましょう。
学資保険のメリットである「強制貯蓄」は、自動積立の定期預金や財形貯蓄などでもある程度代用できます。また、どうしても心配なら親の生命保険で死亡保障を手厚くしておく方法もあります。万一の際の学費保障は生命保険で確保し、普段は無理せず貯金するという選択肢もあります。
一方で、「貯金が本当に苦手で、このままでは貯められそうにない」という方は、小額のプランから学資保険に入るのも一つの手です。無理のない範囲の保険料を設定すれば、家計負担を抑えつつ、強制的に貯蓄できます。最初は月々5千円~1万円のプランから始め、余裕が出たら増額や追加契約を検討するといった柔軟な使い方も可能です。
学資保険は教育費を工面するための手段の一つに過ぎないため、無理なときは他の手段で、余裕があるときは活用して、といった具合に柔軟に考えて問題ありません。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
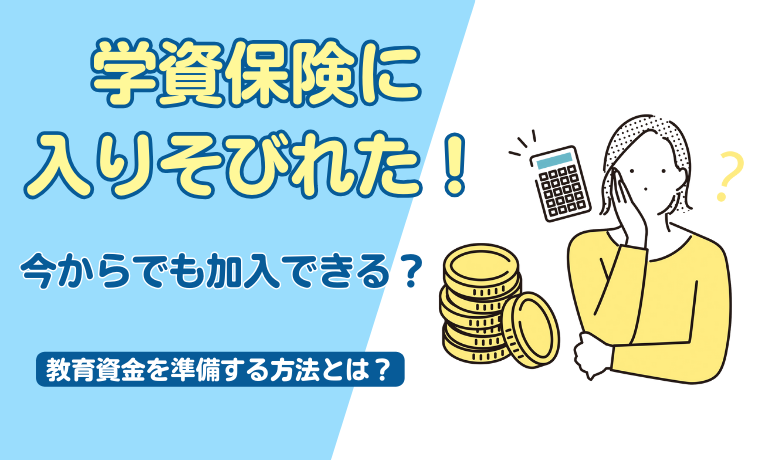
余裕がなくて学資保険に入ってない人が利用できる制度
学資保険に入っていなくても、公的な支援制度を活用することで教育費を賄えます。経済的に余裕がない家庭やシングルマザー世帯でも利用できる代表的な制度をいくつか紹介します。
児童手当
18歳到達後の最初の3月31日までの子どもを持つ家庭に支給される公的手当です。3歳未満は月額15,000円で、第三子以降は30,000円支給されます。3歳以降は第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円となります。この児童手当を教育資金として貯蓄に回せば、学資保険の保険料に充てることも可能です。例えば児童手当を使わず毎月貯金すれば、15年間で約200万円以上の教育資金を準備できます。家計の負担を増やさずに貯められるため、まずはこの手当をしっかり貯蓄に充てることが基本といえるでしょう。
高等学校等就学支援金制度(高校授業料無償化)
高校生のいる家庭向けの支援制度で、公立高校の授業料を実質無償化するものです。年収目安910万円未満の世帯であれば、高校在学中に年間11万8,800円の就学支援金が支給され、授業料相当額が実質タダになります。私立高校の場合は、年収590万円未満の世帯には、年間最大39万6,000円の支援金が支給され、年収590万円以上910万円未満の場合は、年間11万8,800円の支援金が支給されます。ただし、教科書代や制服代など授業料以外の費用は自己負担ですので、それらへの備えは別途必要です。
奨学金制度(給付型・貸与型)
大学や専門学校への進学時には、学生支援機構などの奨学金を利用できます。奨学金には返済が必要な貸与型と、返済不要の給付型があります。近年は住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯の学生を対象にした給付型奨学金制度も拡充されており、学費の心配なく進学できる道が用意されています。所得制限はありますが、対象であれば大学の授業料が全額免除になったり、毎月数万円の給付を受けられる場合もあります。貸与型奨学金も無利子・有利子から選択でき、多くの学生が利用しています。親が十分に教育費を用意できなくても、奨学金を上手に活用すれば高等教育への進学は可能です。特に成績優秀者向けや地方自治体・民間団体の奨学金など、多様な制度がありますので、進学前には情報収集しておきましょう。
児童扶養手当
シングルマザー・シングルファザーなどひとり親家庭向けの公的手当です。18歳到達年度末まで、子ども1人目で月最大4万円強の給付が行われます。基本的に生活費の補助ですが、間接的に教育費に充てる余力を生むことができます。例えば児童扶養手当で生活費を賄い、その浮いた分を子どもの学費貯金に回すといった活用も可能です。さらに自治体によってはひとり親向けの教育支援制度や奨学金が用意されている場合もあります。経済的に厳しいひとり親でも子どもの教育機会を確保できるよう、国・自治体の支援策を積極的に利用すると良いでしょう。
以上のような制度をうまく活用すれば、学資保険に入らずとも公的資金でかなりの部分をカバーできます。特に児童手当は全世帯が対象となる基本の支援策なので、確実に受け取りましょう。公的制度は申請が必要だったり所得制限があったりしますが、該当する場合は漏れなく利用して教育費負担を軽減することが賢明です。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
おすすめの学資保険はこちら!
学資保険に入ろうか検討している方は、人気の学資保険商品についても情報を集めておくと安心です。学資保険は各社から様々な商品が出ており、返戻率の高さや受取タイミング、保険料払込期間の柔軟性など、それぞれ特徴があるため、比較検討する際には専門家の解説が参考になります。
ベビーカレンダーでは「学資保険の人気8社を比較!おすすめランキングと目的別のイチ押し商品」といった内容で学資保険を詳しく紹介しています。返戻率の良い学資保険や、保障内容に特徴のある商品などがピックアップされていますので、具体的な商品選びの際にはぜひ参考にしてみてください。学資保険を選ぶ際は、各家庭のニーズに合った商品を選ぶことが大切です。返戻率だけでなく、払込免除特約の有無や受取方法なども考慮し、お子さんの将来設計にフィットする一本を見つけましょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
まとめ
学資保険の加入率は年々下がっており、2025年現在では4割弱と、むしろ加入していない家庭の方が多数派であることが分かりました。学資保険に入っていない人には、経済的な事情や他の手段で教育費を賄っているなど、それぞれの理由があります。計画的に貯蓄できる人や十分な蓄えがある人、他の資産運用や生命保険で代替している人にとって、学資保険は必ずしも必要ではない場合も多いのです。また、金利や返戻率の低下、途中解約時のデメリットなどから「無理に入らなくてもいい」という声もあります。
一方で、学資保険には強制貯蓄の仕組みや万一の保障、節税効果といったメリットも確かに存在し、そうした利点を求めて加入する意義もあります。つまり、学資保険の必要性は各家庭の状況によって異なると言えるでしょう。大切なのは、学資保険の良い点・悪い点や公的支援策・代替策を理解した上で、自分たちに合った教育資金準備の方法を選択することです。
「みんな入っているから」「入らないと不安だから」という理由だけで飛びつく必要はありませんし、逆に「デメリットがあるから絶対不要」と決めつけるのも早計です。家計に余裕がない場合は無理せず公的制度や預貯金でコツコツ貯め、余裕がある場合や貯蓄が苦手な場合は学資保険を上手に活用する、といった柔軟な発想で構いません。重要なのは、お子さんの将来に向けて確実に教育費を準備することです。その手段として学資保険がふさわしいかどうか、本記事の情報を参考にぜひ検討してみてください。必要性を見極め、後悔のない選択をすることで、安心してお子さんの成長を見守っていきましょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!