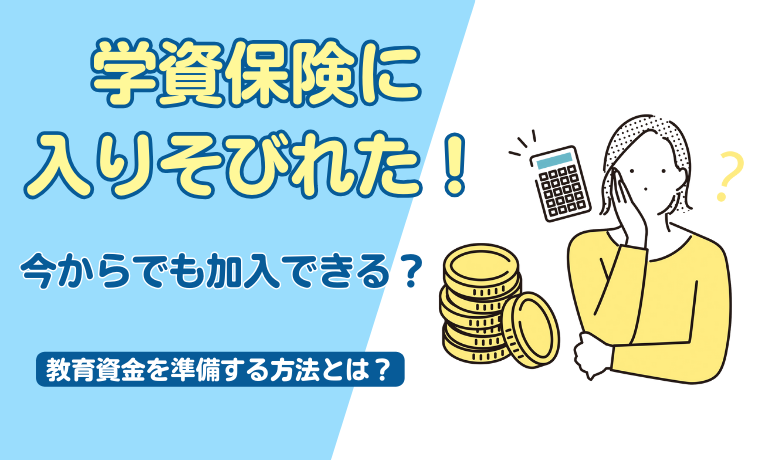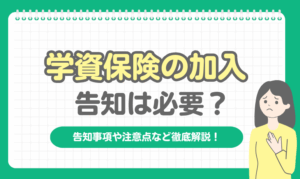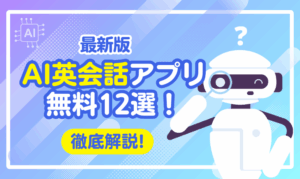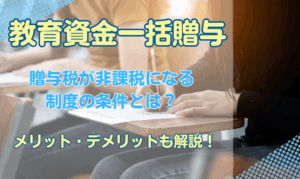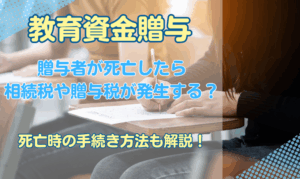子どもが生まれたときに「学資保険に入っておこう」と考えていたものの、忙しさや経済的な理由からタイミングを逃し、学資保険に入りそびれた方もいるのではないでしょうか。学資保険に加入しないまま子どもが大きくなってしまうと、「今から学資保険に加入できるの?」「もう間に合わないのでは?」と不安に思う人もいます。
結論として、学資保険は早く加入するに越したことはありませんが、生まれた直後でなくても加入できる商品はありますし、学資保険以外の方法でも教育資金を準備することは可能です。
本記事では、学資保険に入りそびれた方向けに「いつまでなら学資保険に加入すべきか」や、学資保険以外で教育資金を準備する方法について詳しく解説します。さらに、今から学資保険に加入するメリット・デメリットや、学資保険が本当に必要かどうかについても説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。
学資保険に入りそびれた!いつまでなら加入すべき?
学資保険は、出生前後に加入する人が多いです。とはいえ、商品によっては小学生になってから加入することもできます。しかし子どもが成長してから加入する場合、年齢によってもメリット・デメリットが変わるので、慎重に見極める必要があります。
ここではまず、いつまでなら加入するのがおすすめなのか見ていきましょう。
3歳程度までの加入なら心配する必要なし
学資保険は、加入時期が早ければ早いほど返戻率(へんれいりつ)が高く有利になる傾向があります。しかし、出産直後に入れなかったとしても、幼稚園入園前の3歳くらいまでであればそれほどリスクについて心配する必要はありません。確かに0歳で契約した場合と比べればわずかに不利にはなりますが、3歳までの加入であれば元本割れ(受取総額が払込総額を下回ること)のリスクもほとんどなく、堅実に教育資金を準備できます。また、子どもが3歳頃だと月々の保険料は0歳契約より多少高くなるものの、総支払額の差はそれほど大きくありません。無理のない範囲で支払い続けられる保険料であれば、3歳までに加入するメリットは十分あると言えるでしょう。
遅くとも小学校入学までには加入するのがおすすめ
多くの学資保険では、子どもの加入可能年齢を6歳(小学校入学前)までに定めています。そのため、学資保険に入りそびれた場合でも、遅くとも小学校入学までには加入することを検討したほうが良いでしょう。子どもが7歳以上になってしまうと、申し込める学資保険の商品数がぐっと減ってしまいます。
学資保険は長期間かけて資金を積み立てるほどメリットが大きい商品なので、加入時期が遅くなると返戻率が下がり元本割れのリスクが高まる点に注意が必要です。小学校入学直前になって学資保険を検討する場合は、そのメリット・デメリットを十分に確認した上で判断するようにしましょう。
中学生まで加入できる学資保険もある
学資保険は基本的に早めに加入するに越したことはありませんが、中には子どもが10歳~12歳(商品によっては15歳前後まで)でも加入を受け付けている学資保険もあります。そのため、「子どもがもう小学生だから学資保険は無理だ」とあきらめる必要はありません。
ただし、加入できる商品の選択肢はごくわずかで、保険料負担が大きく返戻率も低くなりがちです 。仮に中学生でも加入できる商品が見つかったとしても、元本割れのリスクが高く基本的にはおすすめできません。万一に備えたい特別な事情がない限り、中学生から無理に学資保険に入るより他の方法を検討したほうがよいでしょう。
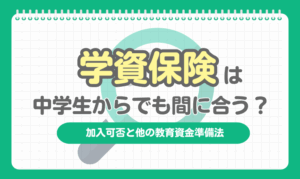
そもそも学資保険に入ってない割合も高い
「学資保険に入りそびれてしまったのは自分だけでは?」と不安に思う人もいますが、実は学資保険に加入していない家庭の割合も決して低くありません。ソニー生命が行った「子どもの教育資金に関する調査2024」によると、学資保険に加入している家庭は約4割程度という結果が出ています。裏を返せば、約6割の家庭は学資保険に加入していないということです。
学資保険に入っていない主な理由として、「経済的な余裕がない」「他の方法で積み立てたい」「すでに親が生命保険に入っていて必要性を感じない」などが挙げられます。特にシングルマザーのように収入面で余裕がない家庭では、毎月の保険料を支払うのが難しく学資保険に入る余裕がないケースも多いようです。したがって、学資保険に加入していないからといって過度に不安になる必要はありません。学資保険の有無よりも、各家庭に合った方法で計画的に教育資金を準備できているかどうかが大切なのです。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
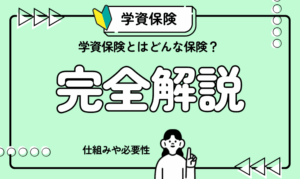
遅くても学資保険に加入するメリット
「子どもが大きくなってから学資保険に入るなんて意味がないのでは?」と思う方もいるでしょう。しかし、今からでも学資保険に加入することで得られるメリットはいくつか存在します。ここでは、学資保険への加入が遅れてしまった場合でも享受できる主なメリットを紹介します。
万が一のときでも教育資金が準備できる
学資保険最大のメリットは、契約者である親に万が一のことがあっても子どもの教育資金を確保できる点です。契約者が死亡または高度障害状態になった場合、以後の保険料の払込が免除され、契約はそのまま継続します(※学資保険の種類によって異なる場合があります)。つまり、保護者にもしもの事態が起きても、満期時には契約時に定めた満期保険金を受け取ることができるのです。これは加入のタイミングに関わらず常に得られる保障であり、子どもの出生直後に学資保険に加入できなかった人でも「今から加入しておけば万一の際には教育費を残せる」という大きな安心につながります。
計画的に教育資金を準備できる
学資保険は貯蓄型の保険であり、契約すると一定期間保険料を支払い続けることになります。そのため、途中で解約しない限り強制的に貯蓄を続けられる点は大きなメリットです。自分で毎月積み立てようとしても意志が続かずお金を使ってしまう人でも、学資保険を契約していれば半強制的に教育資金を積み立てることができます。特に「あればあるだけ使ってしまう」「計画的な貯金が苦手」という方は、遅れてでも学資保険に加入することで計画的に教育資金を確保しやすくなるでしょう。
支払額以上に満期金を受け取れる可能性がある
学資保険は預貯金とは異なり、満期まで継続することで払込保険料総額より多い満期保険金を受け取れる可能性があります。いわゆる返戻率は加入時の子どもの年齢や契約内容によって異なりますが、早期加入の場合は105%前後になる商品が多く、遅めの加入だと100%前後、場合によっては下回ることもあります。それでも、貯金では増えないお金が増える可能性がある点は学資保険の魅力です。特に低金利の現在、銀行預金ではお金はほとんど増えませんので、多少でもプラスで受け取れる可能性がある学資保険には加入する価値があると考える人もいるでしょう。
生命保険料控除で節税できる
学資保険は生命保険の一種なので、支払った保険料に応じて生命保険料控除の対象になります。生命保険料控除を受けることで所得税や住民税の負担が軽減され、節税効果が期待できることもメリットの一つです。子どもが大きくなってからの加入でも、払込期間中は毎年控除を受けられるため、その分支払う税金が少なくなります。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
子どもが大きくなってから学資保険に加入するデメリット
次に、子どもがある程度大きくなってから学資保険に加入する場合のデメリットについて見ていきましょう。学資保険は基本的に早期加入が有利な商品のため、加入が遅くなればなるほど不利になる点がいくつか存在します。ここでは、学資保険への加入時期が遅い場合に特に注意すべきデメリットを解説します。
加入が遅いほど元本割れのリスクが高まる
学資保険は長期間にわたり保険料を積み立てることで、リターンを得る仕組みです。そのため、加入が遅ければ遅いほど運用期間が短くなり、元本割れのリスクが高くなります。例えば0歳で加入した場合は18年間運用できますが、5歳で加入すれば13年間、10歳で加入すれば8年間しか運用できません。運用期間が短ければ、その分受け取れる満期金も少なくなり、場合によっては受取額が支払額を下回ってしまう(元本割れする)可能性もあります。特に10歳以上からの契約では返戻率が著しく低下し、普通に貯金した場合と比べてもメリットが少なくなってしまうでしょう。
月々の保険料が高くなる
加入時期が遅くなると、毎月の保険料負担が高額になる点にも注意が必要です。例えば、0歳から18歳まで18年間かけて200万円を準備するプランと、10歳から18歳まで8年間で200万円を準備するプランを比べると、後者の方は1年あたりの積立額を倍以上にしなければなりません。当然、月々の保険料もかなり高い金額になります。「学資保険に入っておけば大学入学時にまとまったお金が受け取れる」とはいえ、月々の支払いが家計を圧迫しては本末転倒です。学資保険を検討する際は、無理なく払込できる保険料かどうか、加入時の子どもの年齢に応じてシミュレーションしてみることが大切です。
学資保険を選びにくくなる
子どもの年齢が上がるほど、加入可能な学資保険商品の選択肢が少なくなる点もデメリットです。多くの学資保険は7歳くらいまでしか申し込みできないため、例えば子どもが10歳を過ぎてしまうと加入できる学資保険はかなり限られてきます。せっかく学資保険に入りたくても、希望する保障内容や満期時期に合致する商品が見つからない可能性もあります。また、親の年齢も高くなると契約者の引受条件に制限が出る場合もあり、親子の年齢両面で制約が厳しくなることを覚えておきましょう。
途中解約やインフレによるリスクもある
これは加入時期に限った話ではありませんが、学資保険そのものの注意点として途中解約やインフレによるリスクも押さえておく必要があります。学資保険は長期契約なので、家庭の事情で途中解約するとそれまでに支払った保険料総額より解約返戻金が少なくなるケースが多く、保険料の滞納(未払い)が続いて契約が失効した場合も同様です。また、学資保険の満期金は契約時に決まった額を受け取れますが、契約から満期までの間に物価や学費相場が上昇するインフレが起こると、受け取った満期金の実質的な価値が目減りしてしまう恐れもあります。こうした点も踏まえ、学資保険だけに頼りすぎない計画を立てることが重要です。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
そもそも学資保険は必要?遅くとも入った方がいい人って?
ここまで学資保険の加入時期による影響やメリット・デメリットを見てきましたが、そもそも「学資保険は本当に必要なのか?」と疑問に思っている方もいるでしょう。学資保険に入りそびれたままではまずいのか、あるいは今からでも入るべきなのかは、各家庭の状況によって異なります。学資保険が必要かどうかを判断するため、どんな人が学資保険に加入したほうがいいのか、逆に加入しなくても大丈夫な人はどんなケースかを整理してみましょう。
学資保険へ加入したほうがいい人
学資保険の必要性が高い人の特徴として、例えば次のようなケースが挙げられます。
・計画的な貯蓄が苦手な人:自分で貯金しようとしてもつい使ってしまう人は、学資保険に加入することで強制的に積立ができるため向いています。
・万が一に備えたい人:保険による保障を重視し、親に万一のことがあった場合に教育費を残せるようにしたい人には学資保険が適しています。特に他に生命保険に入っていない場合は、学資保険で保障と貯蓄を兼ねる意義があります。
・堅実に貯めたい人:投資のようにリスクのある方法よりも、確実性の高い方法で教育資金を準備したい人にも学資保険が合っています。満期まで続ければ元本確保あるいはわずかながら増やせる可能性もあるため、リスクを避けたい家庭にとっては安心感があります。
学資保険へ加入しなくても大丈夫な人
一方で、以下のようなケースでは学資保険に加入しなくても問題ないでしょう。
・自力で計画的に貯蓄できる人:定期預金や積立投資など、自分で計画的にお金を貯められる人は必ずしも学資保険に頼る必要はありません。学資保険では自由に引き出せない分、自分で管理できる人なら他の方法でも十分対応できます。
・代わりの手段がある人:すでに親が十分な生命保険に加入していたり、祖父母から教育資金の援助が見込めたりと、学資保険以外で教育費を賄えるめどが立っている場合は加入しなくても大丈夫です。また、奨学金や教育ローンで賄う計画がある家庭も同様です。
・リスクを理解の上で増やしたい人:多少のリスクがあっても教育資金を増やしたいと考える場合は、学資保険より高いリターンが見込める方法(後述のNISAなど)を選ぶのも一つの手です。元本保証ではありませんが、その分大きなリターンが期待できます。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
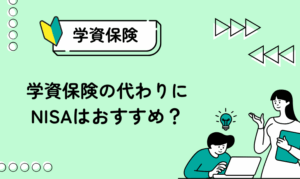
学資保険に入りそびれた人が教育資金を準備する方法
最後に、学資保険以外で教育資金を準備する代表的な方法を紹介します。「もう子どもが大きいから学資保険には入れない」「学資保険の代わりになる手段を知りたい」という方は、以下のような方法も検討してみましょう。
終身保険
終身保険とは、一生涯の死亡保障が受けられる貯蓄型の生命保険です。解約時に解約返戻金を受け取れるため、学資保険の代わりに教育資金の積立手段として活用する人もいます。親が終身保険に加入し、子どもの大学入学時期などに合わせて解約返戻金を受け取れば、学資保険と同じように教育資金を確保できます。
終身保険のメリットは、加入年齢の制限がない(親が加入する保険なので子どもの年齢は関係ない)ことや、満期がなく一生涯保障が続くため資金受取の時期を柔軟に調整できることです。例えば学資保険だと18歳や22歳で満期が来ますが、終身保険なら子どもの進路に合わせて解約時期を選べます。
ただし終身保険は、学資保険に比べて返戻率が高くなるまでに時間がかかる商品です。短期間で解約すると元本割れのリスクが高いため、子どもが既に大きい場合には適しません。したがって、お子さんがまだ小さくて長期運用できる場合に限り、学資保険の代わりとして終身保険を検討する価値があるでしょう。
NISA
教育資金の準備方法として、NISA(少額投資非課税制度)を活用する手もあります。2024年から制度が拡充された新NISAでは、従来よりも長期の資産運用がしやすくなりました。NISA口座を通じて投資信託や株式に積み立てれば、運用益が非課税となるため効率的に資産を増やすことが期待できます。
学資保険と比べたNISAのメリットは、自分のペースで自由に積み立てや引き出しができる柔軟性と、市場の成長によってはより高いリターンを得られる可能性がある点です。一方で元本保証がないことや市場変動リスクがある点には注意が必要です。特に子どもの進学直前に大きな値下がりが起こると必要な時に資金が目減りしてしまう恐れがあるため、NISAを利用する際は運用期間やリスク管理に十分注意しましょう。それでも学資保険より効率よく教育資金を準備できる可能性があり、学資保険に入りそびれた方にとって有力な代替手段と言えます。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
おすすめの学資保険はこちらをチェック!
学資保険に興味はあるけれど「どの保険を選べばいいか分からない」という方は、おすすめの学資保険を紹介している記事を参考にしてみましょう。下記のリンクから人気の学資保険の内容をチェックできます。