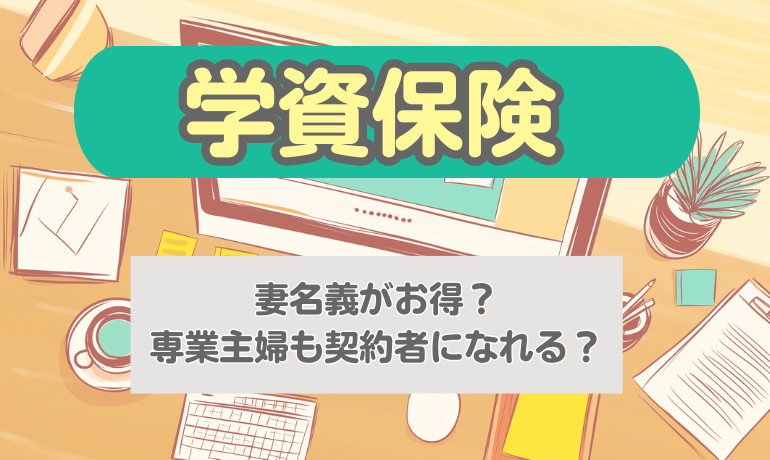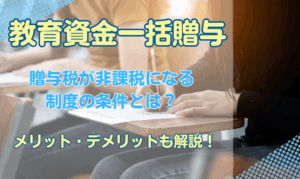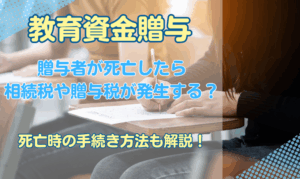学資保険に加入する際、「契約者(保険契約をする人)は夫と妻のどちらにすべきか?」と迷う方も多いのではないでしょうか。一般的には収入の多い夫が契約者になるケースが多い一方で、「妻名義にした方が保険料も安く返戻率(へんれいりつ)も高くなる」といった話も耳にします。果たして、学資保険の契約者は夫より妻名義の方が良いのでしょうか。本記事では、学資保険を妻名義で契約することのメリット・デメリットを中心に、契約者として誰を選ぶべきかについて詳しく解説します。
学資保険の契約者は夫より妻名義がいいって本当?
まずは、学資保険の契約者に関する基本的な考え方を整理しましょう。契約者選びでは一般的な傾向と、妻名義にすることによる利点・留意点があります。
収入が多い方が契約者になるのが一般的
学資保険では、毎月数千円~数万円の保険料を子どもの高校や大学進学時まで長期間払い続ける必要があります。そのため、家計で収入が多い方(主に大黒柱)が契約者になるケースが一般的です。契約者は保険料を支払う義務を負い、契約内容の変更や解約などの権限も持ちます。多くの場合、家計の経済的基盤を支える夫が契約者となり、妻子を支える立場で学資保険に加入しています。
また、学資保険は「保険料払込免除特約」(保険料の払い込み免除)という仕組みが付帯している商品がほとんどです。これは契約者が死亡したり高度障害状態になった場合に、以後の保険料支払いが不要になる保障です。契約者に万一のことがあったときでも、残りの保険料負担なしで満期学資金を受け取れるようにする目的があります。そのため、収入の多い夫を契約者にしておくことで、万一夫に何かあった場合でも子どもの教育資金を確保しやすくなります。
一方で、「妻を契約者にした方が良い」と言われる理由も存在します。それが、次に紹介する保険料や返戻率の違いです。
妻名義のメリットは保険料が安く、返戻率も高いこと
実は契約者を妻名義(母親)にすると、夫名義と比べて保険料が割安になり、その分返戻率も高くなるケースが少なくありません。学資保険は貯蓄性の商品ですが、同時に契約者の死亡保障(払込免除特約)が付いた生命保険の一種でもあります。基本的に生命保険は男性より女性の方が保険料が割安で、年齢が若いほど安くなります。保険会社から見ると、若い女性の方が病気や死亡のリスクが低く長生きすると判断されるため、その分保険料が低く設定されるからです。
保険料が安いということは、同じ満期金を受け取る場合に払い込む総保険料が少なく済むので結果的に返戻率(受取総額÷支払総額×100)も高くなることを意味します。例えば、以下はある学資保険(子ども0歳、受取総額300万円、10年払込)のケースで夫30歳契約と妻20歳契約を比較した試算です。
| 契約者の年齢 | 月額保険料 | 払込保険料総額 | 満期受取総額 | 返戻率 |
| 夫:30歳 | 23,310円 | 2,797,200円 | 3,000,000円 | 107.2% |
| 妻:20歳 | 23,244円 | 2,789,280円 | 3,000,000円 | 107.5% |
このケースでは妻契約の方が総支払保険料が7,920円安く、返戻率も0.3%高くなっています。月々の差額はわずかですが、払込期間トータルでは数千円~数万円の差となり、少しでも返戻率を高められるのは嬉しいポイントでしょう。劇的に保険料が変わるわけではありませんが、学資保険は10年以上払い続けることも多いため、このような小さな差でも積み重なるとば無視できません。
健康状態や年齢も契約者選びのポイント
契約者を決める際は、夫婦それぞれの健康状態や年齢も重要な判断材料になります。学資保険は契約者に万一のことがあった場合の保障が付くため、加入時には健康状態について告知(健康状態の申告)や審査があります。そのため、夫の健康状態に不安があるのなら、妻を契約者にすることを検討するのもよいでしょう。夫が健康上の理由で通常の学資保険に加入できない(もしくは保険料が割増になる)場合、告知不要の学資保険商品を選ぶ手もあります。しかしその場合は保険料が高く返戻率が悪くなりがちで、本来のメリットが減ってしまいます。夫が病気で学資保険に加入しづらいケースでは、妻を契約者(被保険者)にして返戻率の高い通常の学資保険に加入するのが賢明だと言えるでしょう。
また契約者の年齢も見逃せません。前述の通り、契約者が若ければ若いほど保険料は安く返戻率も高くなります。夫婦で年齢差がある場合は、より若い方を契約者にすることも選択肢の一つです。特に妻が夫よりかなり若いようなら、その分だけ保険料面で有利になります。学資保険の商品によっては契約者の加入年齢の上限が定められており、高齢の親は契約できないケースもあります。その場合は、妻や祖父母が契約者となることが多いです。このように、健康面・年齢面で有利な方を契約者に選ぶことがポイントです。
一般的には収入面から夫が契約者になることが多いものの、妻を契約者にすることで得られる保険料・返戻率のメリットや健康・年齢上の理由も考慮すると、一概に「夫が良い・妻が良い」とは言い切れません。それでは次に、実際に妻名義で契約した方が良い具体的なケースを見ていきましょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
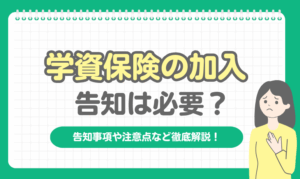
学資保険を妻名義で契約した方がいい4つのケース
前章で述べたポイントを踏まえ、ここでは妻名義で学資保険に加入することが適している代表的なケースを4つ紹介します。以下のいずれかに当てはまるご家庭では妻を契約者とするメリットが大きいので、検討する際の参考にしてみてください。
1. 夫よりも妻の収入が多い
まず紹介するのは、妻の収入が夫より多い場合 です。共働き家庭で妻が大黒柱、または夫婦共に働いているが妻の方が収入額が高いケースでは、学資保険の契約者を妻にするのが自然な選択と言えます。学資保険の保険料支払いは契約者が行うことになるため、収入の多い妻が契約者となった方が支払い能力の面で安心です。
また、収入が多い=所得税・住民税などの税負担も大きい傾向があります。そのため、生命保険料控除(※)を活用できるメリットも大きなポイントです。妻に十分な所得がある場合、学資保険の保険料を妻が支払えば年末調整や確定申告で生命保険料控除を受けることができます。夫婦どちらか一方だけが高収入という家庭では、基本的にその高収入の方が契約者となり払い込む保険料で税控除を受ける方がおトクです。
※生命保険料控除: 支払った生命保険や学資保険などの保険料に応じて所得から一定額を差し引ける税制上の控除制度。一般の生命保険料控除は新契約の場合、所得税で最大4万円(旧契約は5万円)までの控除枠がある。
妻の収入が夫より多い場合は上記のように、支払いの実行力と税控除の両面で妻契約のメリットが大きくなります。
2. 妻のほうが夫よりもかなり若い
2つ目のケースは、妻の年齢が夫よりかなり若い場合です。夫婦の年齢差が大きいときは、前述の保険料・返戻率の観点からより若い妻を契約者にした方が有利です。同じ条件であれば妻の方が月々の保険料は割安になり、夫より年下であればあるほどその差は大きくなります。例えば夫婦が同い年の場合でも女性である妻の方が保険料は幾分安くなりますが、妻が夫より5歳・10歳若ければさらに保険料の負担は軽くなります。保険料の負担が軽くなる分、総支払額に対する受取額の割合(返戻率)も高くなり、貯蓄効率が良くなるというわけです。特に20代後半~30代で子どもを迎えたご夫婦では、奥様が旦那様より年下というケースも多いでしょう。その場合は契約者を若い妻にすることで、長期的な保険料負担を抑えられます。
ただし、契約者を妻にすると夫に万一のことがあった場合でも保険料の払込免除にならない点には注意が必要です。妻が若い=夫が相対的に高年齢とも言えるため、夫の保障については学資保険以外の手段(例えば別途生命保険に加入するなど)でしっかり確保しておく必要があります。
3. 夫の健康状態が悪い
夫の健康上のリスクが高い場合も、妻名義で契約した方が良いケースです。学資保険は契約者に万一の事態が起きた際の保障が付く性質上、加入時には健康状態についての告知(健康状態の申告)や審査があります。仮に夫が健康上の理由で学資保険への加入が難しい場合、妻を契約者にすることで問題をクリアできる可能性が高いです。
例えば、夫に重い持病があると学資保険の払込免除特約を付けられなかったり、加入自体を断られたりすることがあります。このような場合でも、妻が契約者(被保険者)なら通常通り契約できることが多いです。最近では告知なしで入れる学資保険商品もありますが、その多くは一般の学資保険に比べて保険料が割高になり返戻率も下がってしまいます。一方、妻が健康であれば通常の(返戻率の高い)学資保険に加入できるため、家計への影響を抑えることが可能です。
まとめると、夫の健康に不安があるときは無理に夫名義で契約しようとせず、妻名義で加入を検討するのがおすすめです。契約者を妻にすれば、より良い条件の学資保険を選べる可能性が高まります。
ただし、契約者を妻にすると夫に万一のことがあった場合でも保険料の払込免除にならない点には注意が必要です。妻が若い=夫が相対的に高年齢とも言えるため、夫の保障については学資保険以外の手段(例えば別途生命保険に加入するなど)でしっかり確保しておく必要があります。
4. 保険の契約数が多い
最後に紹介するのは、すでに加入している保険契約が多く夫の生命保険料控除が上限に達している場合です。例えば、夫が既に他の生命保険や医療保険に加入していて年間の保険料が生命保険料控除の上限額まで達しているケースでは、学資保険まで夫名義で加入してもそれ以上の税控除メリットは得られません。しかし妻名義で学資保険に加入すれば、妻の年末調整で新たに控除を受けることができ、夫側の控除上限を超えて無駄になる部分を減らせます。
共働きの場合、夫婦それぞれが最大で年間4万円(所得税)まで一般生命保険料控除を受けられます。学資保険を夫婦別々の名義で契約すれば、控除枠を2人分有効に活用できるというわけです。夫が既にいくつかの生命保険に加入しているのなら、学資保険は妻名義にした方が家計全体で見たときに節税効果が高くなります。
なお、妻名義で契約する場合は実際の保険料支払いも妻の口座から行うようにしましょう。生命保険料控除は「誰が支払ったか」に基づき適用されるため、契約者を妻にしても実質夫が支払っていると認められると妻の年末調整で控除できない可能性があります(その場合でも夫の控除枠に入れることは可能ですが、夫が上限に達していれば結局控除は受けられません)。また、妻が産休・育休で収入がゼロになる年は妻側で年末調整ができなくなってしまう点にも注意が必要です。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険は専業主婦の妻でも契約できる?
ここまで妻が契約者となるメリットについて述べてきましたが、「我が家は妻が専業主婦だけど契約者になれるの?」という疑問をお持ちの方もいるでしょう。結論から言うと、専業主婦の妻でも学資保険の契約者になることは可能です。ここからは、専業主婦が契約者になる場合のポイントを解説していきます。
専業主婦でも学資保険の契約者になれる
学資保険の契約者は、必ずしも本人に収入がなくてはならないわけではありません。専業主婦の妻でも、夫の収入から保険料を支払う形で契約者になることが可能です。実際に、妻が無収入(または低収入)であっても契約者として学資保険に加入しているケースは珍しくありません。「契約者=保険料負担者」である必要はなく、極端に言えば契約者の名義が誰であっても、実際に保険料を負担している人が生命保険料控除を受けられる決まりになっています。
当然、専業主婦の契約だからといって保険会社に断られることも基本的にありません。申込書には主な生計維持者や世帯主の情報を記入する欄がありますが、世帯全体で支払い能力があれば妻が契約者になっても問題ないでしょう。
夫の年末調整の控除対象にもなる
専業主婦の妻が契約者となった場合、気になるのは夫の税金の控除(年末調整)に影響するかという点です。結論から言うと、契約者が妻名義であっても条件を満たせば夫の生命保険料控除の対象に含めることが可能です。国税庁の定める生命保険料控除の要件では、「実際に保険料を支払っている人が自分または配偶者・親族を受取人とする生命保険契約であれば控除を受けられる」とされています。そのため、契約者が妻でも夫が保険料を負担していれば夫の所得から控除できるのです。
具体的には、夫が「生命保険料控除証明書」に基づいて年末調整で申告する際、学資保険の契約者名義が妻であっても夫がその保険料を支払っていれば一般生命保険料控除の対象として申請できます。「妻が契約者の学資保険でも夫の年末調整で控除できる」ということを知らずに控除を受け損ねる人もいますので、忘れずに申請しましょう.
では、妻がパート収入を得ている場合はどうでしょうか。妻がパートなどで働いている場合でも、年収が103万円以下で夫の扶養内(配偶者控除の対象内)であれば、自身で所得税の納税をしていないため年末調整は行いません。その場合も先ほどと同様に妻名義の学資保険料を夫の生命保険料控除として申告することが可能です。まとめると、専業主婦や扶養内の主婦でも学資保険の契約者になることは可能で、その場合夫の生命保険料控除を適用できるので税制面で損をする心配はありません。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険は夫から妻に契約者変更もできる
学資保険は一度契約者を決めて加入した後でも、途中で契約者を変更(名義変更)することが可能です。例えば「最初は夫名義で契約したけれど途中で妻名義に変えたい」といった場合でも、所定の手続きを踏めば契約者を妻に変更できます。
契約者変更の基本的な方法は、以下のとおりです。
- 保険会社に連絡する: 現在加入している保険会社の窓口に、学資保険の契約者を変更したい旨を連絡します。問い合わせると、変更手続きに必要な書類を郵送してもらえます。各社で手続き方法や必要書類が多少異なるため、まずは確認しましょう。
- 書類の記入・提出: 郵送されてきた契約者変更用の書類に必要事項を記入し、保険会社に提出します。契約者を夫から妻へ変える場合、手続きを行えるのは現契約者である夫です。また、書類に夫婦双方の署名押印欄が設けられていることが一般的です。
- 保険会社での手続き完了: 書類が保険会社に受理されると、所定の審査・処理を経て契約者変更が承認されます。契約者が妻へと変更されれば、以後の保険料支払い義務や保険金受取権利は妻に移行します。保険証券の名義人も妻の名前に書き換えられます。
以上が大まかな流れです。契約者変更を行う際には、夫(現契約者)の手続きなしに妻へ名義を書き換えることはできません。 そのため、例えば離婚時に学資保険を妻が引き継ぐことになった場合でも、勝手に名義変更することはできず、必ず双方の合意のもとで手続きを進める必要があります。
契約者変更を行う理由は、夫婦の収入バランスの変化(妻が職場復帰して収入が増えたので妻名義にしたいなど)、契約後に夫の健康が悪化した、離婚を見据えて妻に引き継ぎたいなど様々です。それぞれの状況で注意点は異なりますが、学資保険の契約者は後からでも夫→妻へ変更可能だと覚えておきましょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!

学資保険の契約者を妻にするときの注意点
最後に、学資保険の契約者を妻名義にする際の注意点について解説します。妻を契約者にすることで生じるメリットに注目しがちですが、同時に把握しておくべきリスクやデメリットもあります。以下で紹介するポイントを、しっかり理解しておきましょう。
受取人も妻にしないと贈与税の対象になる
学資保険の契約者と保険金受取人の名義の組み合わせによって、将来受け取る進学資金・満期金などに課される税金の種類が変わります。特に注意すべきなのは、契約者と受取人が異なるケースです。この場合、受け取った保険金は「贈与税」の対象となってしまいます。
例えば妻が契約者で満期金200万円を受け取る際に受取人が子どもになっていると、妻から子への贈与とみなされ、基礎控除110万円を超える部分(この例では90万円)に対して贈与税が課税されます。贈与税は税率も高く控除枠も小さいため、せっかく学資保険で増やした資金に思わぬ税負担が生じてしまうのです。
一方、契約者と受取人が同一人物の場合は贈与税は発生しません。学資保険の満期金を契約者自身が受け取る場合、増えた分の利益に対しては「一時所得」として課税されますが、50万円の特別控除や1/2課税といった優遇があり、よほど大きな利益が出ない限り税金はほとんどかかりません。
したがって、学資保険では契約者と受取人を同じ名義にしておく方が税負担を抑えられるのです。
そのため、妻を契約者にする場合は保険金受取人も妻(契約者本人)に設定するようにしましょう。
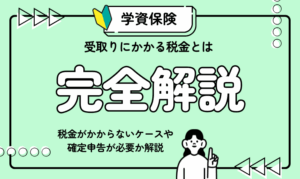
夫の自己破産で処分対象となる可能性がある
「学資保険を妻名義にしておけば、万一夫が借金で自己破産しても子どもの教育資金は守られるのでは?」と考える方もいます。しかし、夫が自己破産する場合、妻名義の学資保険だからといって必ずしも守られるわけではない点に注意が必要です。
法律的には、自己破産手続きで処分の対象となるのは原則「破産者本人の財産」に限られます。ただし、名義が破産者本人でなくても、実質的に破産者の財産とみなされる場合には処分の対象に含まれる可能性があります。
具体的には「妻名義の学資保険だが、保険料の原資は夫の収入であり実質的に夫の財産の一部を成す」と判断されるケースです。
例えば妻は無収入で家計は夫の収入のみ、それでいて多額の学資保険の積立を妻名義で行っている場合には、「妻名義ではあるが夫の財産隠しではないか」と判断される可能性もゼロではありません。その場合、妻名義の学資保険も解約され、解約返戻金が債権者への配当に回される恐れがあります。実際の破産実務では、解約返戻金が20万円以下の保険契約は処分対象外とされることも多いようですが、学資保険は長年積み立てれば数十万円~数百万円の解約返戻金が発生しますので油断できません。
このことから、夫に多額の負債があったり自己破産の懸念があったりする場合、学資保険を妻名義にしていても万全ではないことを理解しておきましょう。どうしても教育資金を確保したいのなら、親族名義で預金しておく、学資保険以外の金融商品を活用するといった方法も検討するとよいでしょう。
離婚で勝手に解約されることがある
夫婦が離婚することになった場合の学資保険の扱いにも注意が必要です。学資保険の契約者が妻名義であっても夫名義であっても、離婚時にきちんと取り決めをしておかないとトラブルになる可能性があります。
例えば、契約者が夫のままで離婚した場合について考えてみましょう。子どもの親権は妻が持つことになっても、学資保険の契約者兼受取人が夫である限り満期金を受け取る権利は元夫にあります。離婚後に夫が保険料を払い続けてくれないどころか、最悪の場合学資保険を勝手に解約して解約返戻金を自分のものにしてしまうリスクさえあるのです。実際に、「離婚した元夫が通知なく学資保険を解約していた」という事例も報告されています。
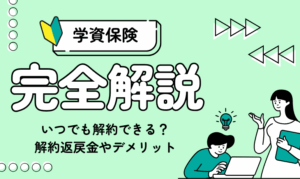
反対に、契約者が妻名義で離婚した場合でも注意点はあります。契約者である妻に保険の管理権限があるため、今度は元夫が関与できず不安になる可能性が高いです。夫が離婚後も保険料を負担していたとしても、契約者である元妻がある日突然解約してしまえば夫は防ぎようがありません。また、離婚後に夫からの養育費が滞った場合、妻が苦渋の選択で学資保険を解約して生活費に充てざるを得なくなるケースも考えられます。
このように、離婚時に契約者を変更せず放置すると
贈与税が発生する可能性(契約者と受取人が夫婦で分かれる場合)
保険料の支払い滞納で知らぬ間に失効してしまう可能性(支払担当だった側が支払わなくなる恐れ)
一方の独断で解約されてしまう可能性(契約者でない側がノータッチだと防げない)
といったリスクが生じます。
対策としては、離婚が決まった時点で契約者を子どもの親権者側に変更しておくことが望ましいでしょう(前述のとおり、契約者変更には現契約者の同意が必要です)。離婚協議書でも学資保険の取り扱いを明確に取り決め、勝手に解約しない・定期的に状況を共有するといった約束をしておくと安心です。大切な教育資金が夫婦の離別によって無駄になってしまわないよう、離婚時には学資保険についても十分話し合っておくことをおすすめします。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
まとめ
学資保険を妻名義で契約することのメリット・デメリットや留意点について詳しく解説しました。まとめると、学資保険の契約者選びは収入・年齢・健康状態・税制など様々な観点を踏まえて検討すべきであり、妻名義にすることで得られる保険料面や税制面のメリットは確かに存在します。特に共働きで妻が夫より若かったり健康面で有利だったりするのであれば、妻を契約者にした方が返戻率も高く合理的です。
しかし一方で、契約者を妻にすることで夫に万一のことがあった場合の保障が無くなる点や、離婚時・破産時の取り扱いなど注意すべき事項もあります。「契約者=夫」か「契約者=妻」か正解は一つではなく、各ご家庭の状況によって最適な選択は異なるでしょう。ぜひ本記事で挙げたポイントを参考に、どちらを契約者にすべきかご夫婦で話し合ってみてください。お子さまの将来のために最適な学資保険の形を選び、安心して教育資金づくりに取り組みましょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!