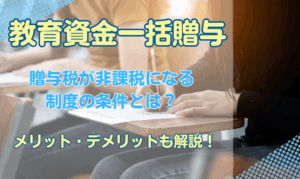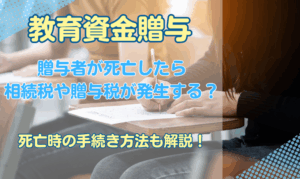離婚に際して、子どものために加入した学資保険をどのように取り扱うべきか悩む方は多いでしょう。学資保険は夫婦で築いた財産として財産分与の対象にもなり、離婚後にどちらが契約を引き継ぐかでトラブルになるケースもあります。そこで本記事では、離婚時の学資保険の名義変更(契約者変更)の必要性や具体的な手続き方法、名義変更しない場合のリスク、さらに名義変更のメリット・デメリットについて詳しく解説します。
離婚するときは学資保険の名義変更が必要?
学資保険は本来、「子どもの教育資金」を準備するための保険です。離婚時には基本的に、学資保険の契約者を子どもの親権者に変更することが望ましいとされています。なぜなら契約者が保険料を支払い、満期学資金の受取人にもなるのが通常のため、離婚後も契約者と子どもの親権者が一致している方がトラブルになりにくいからです。以下では、離婚時の学資保険の名義変更について、詳しく見ていきましょう。
契約者は子ども親権者に変更するのがおすすめ
離婚に伴い親権者が変わる場合、学資保険の契約者も子どもの親権者に揃えることが推奨されています。例えば、契約者が母親で離婚後も母親が親権者になるなら名義変更は不要ですが、契約者が父親で親権者が母親になる場合は契約者を父親から母親に変更することが望ましいです。契約者=親権者としておくことで、離婚後も親権者が責任を持って保険料を払い続け、将来の学資金を確実に受け取れる状況を作ることが可能です。
なお、状況によっては学資保険を解約し、解約返戻金を夫婦で分け合う選択肢もあります。しかし解約には元本割れや保障消失などのデメリットもあるため、基本的には現在の契約を活かしつつ親権者側へ契約を引き継いだ方が子どものためには良いと言えるでしょう。

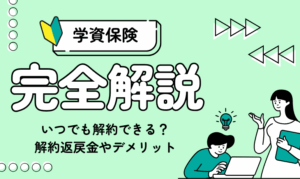
契約者以外は名義人の変更ができない
学資保険の契約者変更を行う際に注意すべきなのは、契約者本人しか名義変更の手続きをできないという点です。離婚後に親権者となった元妻であっても、契約者が元夫名義のままでは勝手に名義変更の手続きはできません。契約者である元夫が保険会社に申請しない限り、契約者変更は成立しないのです。
そのため子どものために学資保険を自分名義に変えたい場合、元夫の協力なしには手続きできないことを覚えておきましょう。かんぽ生命のように一部の保険会社では契約者が委任状を作成すれば代理人が手続きすることも可能ですが、いずれにせよ現契約者の意思・署名が必要になります。そのため、離婚時には学資保険の取り扱いについて夫婦間でしっかり話し合い、円満に合意しておくことが重要です。
なお、契約者であれば本人の判断だけで学資保険を解約することが可能です。裏を返せば、契約者でない側(非契約者側)は相手が解約するのを止める法的権限がありません。後述するように、契約者が一存で解約できてしまうことも離婚後の大きなリスクとなります。
名義変更しても財産分与の対象となる
学資保険も、婚姻中に夫婦で積み立ててきたものなので離婚時の財産分与の対象となります。たとえ離婚後に学資保険の契約者を親権者側に変更したとしても、それまでに払い込んだ保険料相当分の価値については本来夫婦で分けるべき財産です。
つまり、契約者を引き継いだ親権者は、離婚時点までに元配偶者が積み立てた保険料部分の公平を図る必要があります。具体的には、離婚時点の解約返戻金相当額の半額を代償金として支払うなどの方法で清算しておくと良いでしょう。
ポイント: 学資保険を「子どものためのもの」として離婚時に親権者がそのまま取得するケースもあります。しかし、その場合でも夫婦間で「学資保険は親権者が受け取る代わりに他の財産は〇〇を分与する」といった合意を明確にしておくことが大切です。暗黙の了解のままにすると、後から贈与と見なされたりトラブルの火種となる恐れがあります。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
離婚しても学資保険の名義変更をしないリスク
離婚後も学資保険の契約者名義を変更せず、元配偶者(非親権者)が契約者のままになっていると、さまざまなリスクが生じます。代表的なものとして、以下の4つが挙げられます。
- 贈与税が発生する可能性
- 勝手に解約される可能性
- 保険料を滞納される可能性
- 保険金を渡してくれない可能性
順に、具体的な内容を見ていきましょう。
贈与税が発生する可能性
学資保険を名義変更せず契約者が非親権者のままだと、満期学資金を受け取った際に贈与税が発生する恐れがあります。通常、学資保険では「契約者=学資金の受取人」となっており、離婚後も契約者だった元配偶者が給付金を受け取ることになります。その後、それを子どもや親権者に渡そうとすると、他人に金銭を贈与した扱いになってしまうのです。
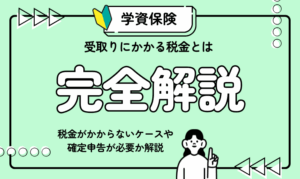
贈与税には年110万円までの基礎控除がありますが、学資保険の給付金は一般にそれを超える高額になるため課税対象となり得ます。一方、契約者と受取人が同一人物であれば贈与ではなく契約者自身の所得として扱われ、所得税(一時所得や雑所得)の範囲で課税されます。所得税であれば計算上控除枠もあり、贈与税より大幅に負担が軽くなるケースが多いです。贈与税を避けるためにも、契約者と受取人を子どもの親権者側に揃えておくことが望ましいでしょう。
勝手に解約される可能性
学資保険は、契約者の判断でいつでも解約可能です。そのため、契約者が非親権者(元夫・元妻)のままだと、親権者の知らないうちに勝手に解約されてしまう恐れがあります。実際に、離婚後に子どもと離れて暮らす元配偶者が「もう自分には必要のない保険だ」と考えて途中解約してしまうケースは珍しくありません。
元配偶者が再婚し新たな家庭を持てば、前の子どもの学資保険料を払い続けることに負担や疑問を感じることもあるでしょう。経済的事情から「払えなくなったから解約する」ということも起こり得ます。いずれにせよ、離婚後に連絡を取らなくなった相手の場合、解約された事実に気付くのが受取予定の時期になってからという最悪の事態も考えられます。いざ進学という時にあてにしていた学資金が無いとなれば、子どもの教育資金計画が大きく狂ってしまうでしょう。
保険料を滞納される可能性
契約者が保険料を支払わなければ、保険契約は維持できません。離婚後、非親権者である元配偶者が経済的に苦しくなったり、生活環境が変わったりすれば、学資保険の保険料を滞納する可能性もあります。例えば仕事の収入減や新たな家庭の生活費負担などで余裕がなくなると、真っ先に前の家族の保険料支払いを止めようとする人も少なくありません。
保険料の未払いが一定期間続くと、学資保険は失効(契約解除)してしまいます。そうなると満期学資金は受け取れず、また契約に付帯していた保険料免除特約(契約者に万一のことがあった場合の払込免除)も無効になってしまうのです。そのため、子どもの教育資金を確実に確保するには、契約者自身が責任を持って保険料を払い続けられる状態にしておく必要があります。
保険金を渡してくれない可能性
仮に離婚後も元配偶者が最後まで保険料を払い続け、予定通り学資保険の給付金を受け取れたとしましょう。しかしその場合でも、元配偶者が子どもや親権者にその保険金を渡さない可能性があります。学資保険の契約者=受取人が元配偶者のままだと、受け取った給付金は法律上一旦契約者本人の財産となります。
長年保険料を払い続けてきた元配偶者が、「その給付金は自分が貯めたお金」と思う可能性もゼロではありません。所得税の申告上も契約者本人の一時所得となれば、ますます「別れた家族に渡すのは惜しい」という心理が働く可能性があります。結果として、本来子どもの学費に充てるべきお金を契約者が自分の目的に使ってしまう危険も否定できません。
このように、離婚後に学資保険の契約者を元配偶者のまま放置すると、金銭面でも保障面でもリスクが大きいです子どものために積み立ててきた学資金を確実に守るためにも、やはり離婚時に名義変更をすることが賢明です。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
離婚に伴い学資保険の名義変更をする方法
離婚にあたって学資保険の契約者を変更する場合、具体的にどのような手続きを踏めば良いのでしょうか。基本的な流れは、以下の通りです。
- 必要書類の準備
- 保険会社へ連絡し所定の手続きを依頼
- 書類の提出と名義変更の実行
- 新契約内容(保険証券)の受け取り
保険会社や契約内容によって詳細が異なるため、まずは現在加入している保険会社に確認するのが確実です。以下では一般的な必要書類と手続きの流れを解説し、かんぽ生命・アフラック・ソニー生命といった主要保険会社での対応についても触れていきます。
名義変更の必要書類
名義変更時に求められる書類は保険会社によって若干異なる場合がありますが、一般的には次のようなものを用意します。
・保険証券(現在の契約内容が記載された証書)
・契約者(現契約者)の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなどのコピー)
・新契約者(名義変更後の契約者)の本人確認書類
・契約者変更請求書(名義変更申請書)(保険会社所定の用紙)
・印鑑(契約者および新契約者の署名・押印が必要)
このほか保険会社によっては、戸籍謄本のような家族関係を証明する書類や新契約者の口座情報(保険料振替口座の変更のため)を求めるケースもあります。また学資保険によっては、新契約者となる方の健康状態に関する書類の提出が必要となる場合もあります。事前に必要書類を確認し、漏れなく準備しておきましょう。
名義変更の手続き方法
名義変更の具体的な手順は、次の通りです。
- 保険会社に連絡する
まず現在契約している保険会社の窓口に連絡し、学資保険の契約者を変更したい旨を伝えます。担当の保険代理店や営業担当者が分かっている場合は、直接依頼するとスムーズです。分からない場合でも、各社のコールセンターやホームページに記載されている問い合わせ先に電話すれば案内してもらえます。 - 必要書類の記入・提出
保険会社から名義変更のための書類(契約者変更請求書など)が送付されるか、窓口で渡されます。それに必要事項を記入し、前述の必要書類一式とともに提出します。郵送で手続きする場合、返信用封筒が用意されていることが多いです。来店窓口で行う場合は、その場で担当者が書類に不備がないか確認してくれるでしょう。 - 保険会社での審査・処理
提出書類に基づき、保険会社側で契約者変更の処理が行われます。多くの場合、特別な審査や医師の診査などは不要で、書類手続きのみで完了します。ただし前述の通り、新契約者の健康告知が必要な場合や契約内容によって保険金額が調整されるケースもあるため、保険会社からの説明内容をよく確認してください。 - 名義変更完了
名義変更が完了すると、新契約者名義で新しい保険証券が発行・交付されます。これを受け取ったら、手続きは完了です。名義変更後は保険料の引き落とし口座も新契約者側に変更されますので、継続して支払いを続けましょう。
保険会社ごとの対応例
かんぽ生命:
郵便局やかんぽ生命のマイページで手続き可能。被保険者(子ども)の同意が必要(未成年の場合は親権者が代諾)で、委任状を用意する場合を除き基本的には旧契約者側から申し出る必要がある点に注意しましょう。
アフラック:
コールセンターまたは担当代理店に連絡して契約者変更書類を取り寄せ、郵送で提出する流れです。被保険者(子)の同意が必要である点は他社と同様です。オンライン手続きサービスもありますが、契約者変更は電話での問い合わせが確実でしょう。
ソニー生命: 基本的な名義変更の方法としては、保険の担当者またはカスタマーセンターに連絡し、送られてきた請求書類に記入後、必要書類と共に郵送します。ただし学資保険の場合は通常の手続きとは方法が異なるので、まずは担当者もしくはカスタマーセンターに連絡しましょう。
各社とも基本的には「旧契約者の了承と申請」が前提であり、その上で親権者への名義変更を進める仕組みとなっています。保険会社によって手続き窓口や書類名が異なるため、必ず事前に確認しましょう。
受取人も変更しておこう
名義変更と併せて忘れてはならないのが、保険金受取人の変更です。一般的に学資保険では契約者=満期保険金受取人となっている場合が多いですが、契約者変更のタイミングで受取人も新契約者と同一に揃えておくことが大切です。
受取人が契約者以外のままだと、前述した贈与税の問題が生じる可能性があります。契約者を母親に変更したのに受取人が元父親のままという状況は通常起こりませんが、「子ども」を受取人に指定している場合は注意が必要です。その場合、満期金を受け取る際に母親から子どもに贈与する扱いになるため、契約者変更と同時に受取人も親権者に変更しておくと良いでしょう。
名義変更手続きをする際には、契約者と受取人を同時に変更する届出用紙が用意されていることがほとんどです。「契約者=受取人=親権者」の形に整えておけば、将来子どもが進学で学資金を必要とする時に、親権者がスムーズに保険金を受け取って使うことができます。子どものための資金を確実に活かすためにも、受取人変更の手続きも忘れず行いましょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
離婚するのに学資保険の名義変更してくれないときはどうする?
相手が学資保険の名義変更に応じてくれないのは、親権者としては頭を悩ませる問題です。前述のように契約者本人しか名義変更手続きができないため、相手の協力を得られないと契約者を変更することができません。では、そのような場合にどのような対処法があるでしょうか。ここでは具体策を紹介します。
弁護士への依頼、公正証書の活用など具体的対処法
弁護士や専門家に相談する
相手が頑なに名義変更に同意しない場合、早めに弁護士に相談して対応策を検討しましょう。離婚協議の段階であれば、財産分与や養育費の話し合いの中で学資保険の取り扱いも交渉事項に含めてもらうのが得策です。法律の専門家を介入させることで冷静な話し合いが期待でき、子どものために最善の解決策が見つかりやすくなります。調停や裁判手続きに移行する場合でも、有利な主張ができるよう準備してくれるでしょう。
公正証書を活用する
名義変更はできなくても、「離婚後も相手に学資保険の保険料を払い続けてもらう」「満期金は子どもの学費に充てるため渡す」などの約束を取り付けることはできます。その場合は口約束で終わらせず、公正証書にしておくのがおすすめです。公正証書とは公証人が作成する公文書で、法的な強制力があります。養育費代わりに保険料を支払う約束を公正証書にしておけば、万一支払われなかった際に強制執行(給料や所有物の差押えなど)も可能です。離婚公正証書の中に学資保険に関する取り決めを盛り込んでおけば、後々のトラブル防止に大いに役立ちます。
解約して財産分与する
相手がどうしても契約者変更に応じない場合、学資保険自体を解約して、解約返戻金を折半する方法も現実的な選択肢です。経済的理由で名義変更に同意できない相手でも、解約して返戻金を公平に分ける方法なら納得してもらいやすいでしょう。解約返戻金を分与すれば双方に現金が残るため、不公平感なく財産を清算できます。子どものために解約を避けようとする人も多いですが、返戻金を基に新たに自分名義で学資保険に加入し直すことも可能です。解約によるデメリット(元本割れ)はありますが、相手の協力が得られない状況では安全策として検討せざるを得ないでしょう。
離婚調停・審判で決着を図る
協議離婚で合意できない場合、家庭裁判所の調停手続きを利用する方法もあります。調停委員を交えて話し合う中で、学資保険の扱いも議題にしてもらいましょう。調停でまとまらなければ最終的に審判(裁判官の判断)となりますが、学資保険は解約返戻金の額によっては財産分与額に算入される可能性があります。裁判所は契約者変更自体を命じることはできませんが、その代わりに解約返戻金相当額の分割支払いを判断するケースもゼロではありません。いずれにせよ法的手続きになる前に、できる限り当事者間か調停内で折り合いをつける方が望ましいでしょう。
上記のように、名義変更に応じてもらえない場合でもいくつかの対処法はあります。最も穏便なのは公正証書による取り決めですが、それも信頼関係が大前提です。最悪、相手が学資保険を自分のものとして抱え込んでしまうリスクも考慮し、子どもの教育資金を守るために何がベストか専門家とともに判断してください。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険を解約ではなく名義変更するメリットとデメリット
最後に、学資保険を解約せず名義変更して継続することのメリット・デメリットを整理します。離婚時には解約して現金化する方が良いのか、それとも名義変更してでも継続すべきか悩むところです。それぞれの利点・欠点を理解し、夫婦で十分話し合って最適な方法を選びましょう。
名義変更するメリット
満期まで継続することで元本割れの可能性を減らせる
学資保険は途中解約すると払い込んだ保険料総額より返戻金が少なくなることが多く、元本割れのリスクがあります。名義変更して契約を継続すればこうした元本割れを避け、満期時に予定通りの学資金(ボーナス利息含む)を受け取れる可能性が高まります。特に加入から年数が浅い場合、解約すると大きく目減りするため継続メリットは大きいでしょう。
契約者の万一の場合の保障(保険料免除)が維持される
多くの学資保険には契約者(親)が死亡・高度障害状態になった場合に、以後の保険料支払いが免除される特約が付いています。これは子どもの教育費を確保する上で重要な保障です。解約してしまうとこの保障はなくなりますが、名義変更して保険を継続すれば引き続きその保障が得られます。離婚後はシングルで子育てを担うことになるため、契約者の万一の場合に備える意義はむしろ高まります。
子どもの年齢制限や保険料負担の問題がない
学資保険は子どもが小さいほど有利な商品設計になっており、一定の年齢を超えると新規加入できなかったり保険料が割高になったりします。そのため、離婚時に解約して後から入り直そうとしても、子どもの年齢制限に抵触して加入できない可能性があります。実際に、小学生以上になると加入できる学資保険は限られるため注意が必要です。名義変更して現在の契約をそのまま継続すれば、こうした心配も不要です。また新規に入り直す場合、月々の保険料負担も子どもが大きいほど高額になる傾向にあります。今の契約を維持する方が総支払額を抑えられるケースも多いでしょう。
(場合によっては)税制上の控除や優遇を受けられる
学資保険は契約形態によっては、生命保険料控除のような税制上のメリットがあります。契約者を親権者に変更し保険料を支払えば、その親権者が生命保険料控除を受けられる可能性があります(学資保険が貯蓄型保険料控除の対象となる商品であれば、年末調整や確定申告で一定額の所得控除の対象)。また満期金受取時も一時所得の控除が適用され、課税されない範囲が広がる利点があります。贈与税が課される状況に比べれば、名義変更して受取人を揃えた方が税負担面でもメリットが大きいです。
子どもの教育資金計画を当初の予定どおり進められる
名義変更により学資保険を継続できれば、夫婦が離婚しても子どもの教育資金準備計画を中断せずに済みます。これは、子どもにとって大きなメリットです。なぜなら解約して現金を得た場合、そのお金を他の目的に使ってしまう恐れもありますが、保険として残しておけば確実に教育費に充当できるからです。将来の学費を着実に貯められるという安心感は、親権者にとっても精神的なメリットと言えるでしょう。
名義変更するデメリット
相手への財産分与や調整が必要になる
名義変更して一方が学資保険を引き継ぐ場合は、他方への財産分与に配慮する必要があります。例えば離婚時に解約返戻金相当額の半分を相手に渡すように経済的な調整が必要です。そのため親権者側には、学資保険を守る代わりに現金や他の財産を譲渡する負担が生じる可能性があります。離婚直後は何かとお金が必要な中、その負担をどう捻出するか検討しなければなりません。
名義変更に相手の同意が必要(協議が難航する場合がある)
名義変更自体は書類手続きだけで難しくありませんが、そもそも相手の協力・同意を得られないと実行できない点が大きなハードルです。相手によっては、「子どものため」と説得しても首を縦に振らない場合もあります。特に学資保険に多額の解約返戻金がある場合、それを手放したくないと考える人もいるでしょう。名義変更を巡って離婚協議がこじれるリスクもあり、精神的な負担が増える可能性があります。
離婚後の保険料支払い負担が増える
名義変更後は、親権者が単独で保険料を支払っていくことになります。離婚によって収入が減ったり、シングル家庭となって生活費の負担が重くなったりする中で、学資保険の保険料を払い続けるのは簡単ではありません。十分な貯蓄や安定した収入がない場合、無理に保険料を支払い続けることで生活に支障をきたす恐れもあります。名義変更しても払込が困難になれば結局途中解約せざるを得なくなり、本末転倒となってしまいます。継続する以上、離婚後の家計で無理なく払えるか慎重に見極めるようにしましょう。
一時的に手元資金が減少する(流動性の低下)
学資保険を継続すると、解約して現金化した場合と比べて手元に残るお金が少なくなります。離婚に伴い新生活のための引っ越しや家具家電の購入などで出費が嵩む中、学資保険に資金を固定してしまうと当面の現金不足に陥るケースも少なくありません。解約すれば得られるはずの何十万円もの返戻金を受け取らずに置いておくと、このように離婚直後の生活再建資金が足りなくなるデメリットがあります。十分な蓄えがない場合は無理に継続せず、まずは生活の立て直しを優先した方が良いケースもあるでしょう。
契約条件が変わるリスク
稀なケースですが、契約者を変更することで保険契約の条件が変わる場合があります。例えば契約者の年齢や性別によって保険金額や特約の適用条件が影響を受ける保険商品では、名義変更後に満期金額が若干調整される可能性があります。また新契約者の健康状態によっては、告知内容次第で契約継続が難しくなるケースもゼロではありません。名義変更には、こうした契約上の不確定要素が伴う点も留意しましょう。
上記の内容を踏まえ、離婚時の学資保険については「解約して財産分与するか」「名義変更して継続するか」を夫婦できちんと話し合うことが大切です。子どもの将来の教育費という観点を最優先に考えつつ、双方にとって納得のいく方法を選びましょう。判断に迷う場合はファイナンシャルプランナーや弁護士など専門家に相談し、メリット・デメリットを整理してもらうのも有効です。大切な子どものために、離婚後も最善の方法で準備を進めていきましょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!