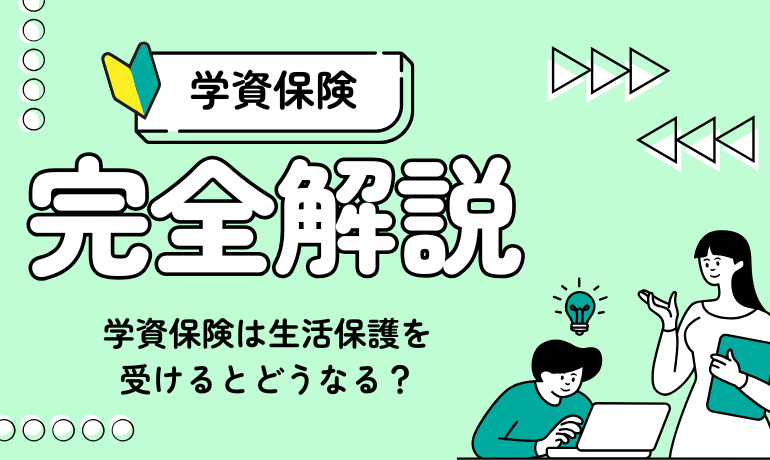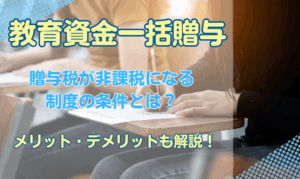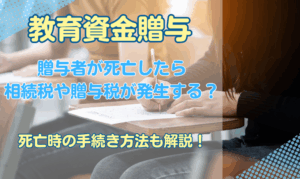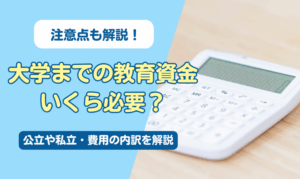「子どもの将来のために学資保険に入っているけれど、生活が苦しく生活保護の申請を考えている」
「生活保護を受けているけれど、子どもの進学費用をどう準備すればいいのだろう」
このような悩みを抱えていませんか?
生活保護制度は、生活に困窮する人々にとって最後のセーフティネットですが、利用するには一定の条件があります。特に、学資保険のような貯蓄性のある保険に加入している場合、その取り扱いは非常に重要なポイントとなります。
この記事では、生活保護と学資保険の関係について、以下の点を詳しく解説します。
- 生活保護を受ける際に学資保険は解約が必要か
- 学資保険の加入を隠していてもバレるのか、そのリスク
- 特定の条件下で学資保険を残す方法
- 実際の判例から見る学資保険の扱い
- 名義変更で学資保険を継続する可能性
- 学資保険以外の教育資金準備方法
この記事を読めば、あなたの状況に合わせて最善の選択をするための知識が身につき、不安を解消できるでしょう。
学資保険に加入していても生活保護を受けられる?
結論から言うと、学資保険に加入したまま生活保護を受けることは、原則として非常に困難です。また、生活保護受給中に新たに学資保険に加入することも認められていません。
なぜなら、生活保護制度は、利用できる資産や能力を最大限活用してもなお、最低限度の生活を維持できない場合に適用される制度だからです。ここでは、その具体的な理由を詳しく見ていきましょう。
生活保護を受けるには原則的に学資保険の解約が必要
生活保護を申請すると、まず世帯の資産状況が厳しく審査されます。学資保険は、満期保険金や祝い金を受け取れる貯蓄型の保険であり、途中解約した際に戻ってくる「解約返戻金」が資産として見なされます。
生活保護の原則は「利用し得る資産は、まず生活のために活用すること」です。そのため、解約返戻金が見込める学資保険に加入している場合、福祉事務所から以下のような指導を受けるのが一般的です。
- 学資保険を解約する
- 解約返戻金を受け取る
- そのお金を生活費に充てる
- 生活費が尽き、それでもなお生活が困窮する場合に、生活保護の受給が開始される
つまり、学資保険という資産を先に活用し、それでも足りない部分を生活保護で補う、という考え方です。これは、預貯金や利用していない土地・家屋など、他の資産がある場合と同様の扱いです。
子どもの将来を思ってコツコツと積み立ててきた保険を解約するのは、非常に辛い決断かもしれません。しかし、これが生活保護制度の基本的な仕組みであることを、まずは理解しておく必要があります。
生活保護受給者は学資保険に加入できない
では、生活保護を受給している間に、新たに学資保険に加入することはできるのでしょうか。これも原則として認められていません。
その理由は、生活保護費の使途にあります。生活保護費は、憲法第25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために支給されるものです。食費、住居費、光熱費、医療費など、生活に不可欠な費用に充てることが前提です。
この観点から、学資保険の保険料を支払う行為は「貯蓄」と見なされ、最低限度の生活を維持する上で必要不可欠な支出とは認められません。福祉事務所からは、保険料を支払う余裕があるならば、その分を生活費に充てるべきだと判断されてしまいます。
もし、生活保護受給中に内緒で学資保険に加入し、その事実が発覚した場合は、不正受給と見なされる可能性があります。その場合、保険料として支払っていた金額の返還を求められたり、最悪の場合は保護の打ち切りにつながるリスクもあるため、絶対にやめましょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険を隠して生活保護を受けてもバレる
「解約したくないから、学資保険に入っていることを隠して生活保護を申請すればいいのでは?」と考える方がいるかもしれません。しかし、その考えは非常に危険です。学資保険の加入を隠し通すことは、ほぼ不可能であり、発覚した際のリスクは計り知れません。
なぜ隠し事がバレるのか?
福祉事務所(ケースワーカー)には、生活保護の申請者や受給者の資産状況を正確に把握するため、法律で定められた強力な調査権限が与えられています。
- 金融機関への照会: 福祉事務所は、銀行や信用金庫などの金融機関に対し、申請者名義の預貯金口座の有無や残高を照会できます。
- 保険会社への照会: 同様に、生命保険会社や損害保険会社に対しても、保険契約の有無、契約内容、解約返戻金の額などを調査することが可能です。申請者の同意がなくても照会できるため、隠すことはできません。
- マイナンバーによる情報連携: マイナンバー制度の導入により、行政機関は個人の所得や資産情報をより正確かつ迅速に把握できるようになりました。税務情報などから保険料控除の申告が判明し、そこから保険加入が発覚するケースも考えられます。
- 定期的な家庭訪問・調査: ケースワーカーは受給者の生活状況を把握するため、定期的に家庭訪問を行います。その際の会話や室内の様子から、申告していない収入や資産の存在が疑われることもあります。
このように、幾重にも張り巡らされた調査網があるため、「バレないだろう」という安易な期待は通用しないのです。
バレた場合の深刻なペナルティ
もし、学資保険の加入を意図的に隠して生活保護を受給していたことが発覚した場合、それは「不正受給」と見なされ、厳しいペナルティが科せられます。
- 保護の停止・廃止: 不正が確認された時点で、生活保護の支給が止められたり、打ち切られたりする可能性があります。
- 不正受給額の返還: 隠していた期間に受け取った生活保護費の全額、または一部を返還するよう求められます。
- 加算金の徴収: 返還額に加えて、最大でその金額の40%に相当する「加算金」の支払いを命じられることがあります。
- 刑事告発(詐欺罪): 特に手口が悪質であると判断された場合は、詐欺罪(刑法第246条)として警察に刑事告発される可能性もあります。有罪になれば、10年以下の懲役という重い罰が科せられます。
たった一度の「隠し事」が、生活の再建をさらに困難にし、社会的信用を失い、最悪の場合は犯罪者となってしまうリスクを伴います。子どもの将来を思うからこそ、正直に申告し、正しく制度を利用することが何よりも大切です。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
生活保護を受けても学資保険を残せる3つの条件
原則として解約が必要な学資保険ですが、全てのケースで解約が必須というわけではありません。特定の条件を満たすことで、福祉事務所の判断により、例外的に学資保険の保有が認められる可能性があります。
ただし、ここで紹介するのはあくまで「残せる可能性がある条件」であり、最終的な判断は、お住まいの自治体の福祉事務所や担当のケースワーカーが行います。これらの条件を満たせば必ず残せるという保証はないことを念頭に置き、必ず事前にケースワーカーに相談してください。
一般的に、以下の3つの条件を総合的に判断されることが多いと言われています。
- 満期保険金を受け取るのが18歳以下であること
- 解約返戻金が50万円以下であること
- 同世帯の子どもの就学目的であること
それぞれ詳しく見ていきましょう。
満期保険金を受け取るのが18歳以下
1つ目の条件は、学資保険の満期保険金や祝い金の受取人が、生活保護を受給している世帯の子ども(被保険者)本人であり、その年齢が18歳以下であることです。
これは、受け取る保険金が、高校卒業後の進学や就職準備など、子どもの自立を助けるために直接使われることが明確であるためです。生活保護制度の目的の一つには「世帯の自立の助長」があり、子どもの将来の自立に直接的かつ有効に役立つと判断されれば、保有が認められやすくなります。
逆に、受取人が親であったり、受け取る子どもの年齢が高すぎる場合(例えば20歳満期など)は、子どもの自立目的というよりは、世帯の一般的な貯蓄と見なされ、解約を指導される可能性が高まります。
解約返戻金が50万円以下
2つ目の条件は、解約した場合に戻ってくるお金(解約返戻金)の額が、一定の基準額以下であることです。
この基準額は自治体によって異なりますが、一般的には50万円が一つの目安とされています。これは、生活保護世帯が保有を認められる預貯金の額の上限(最低生活費の半分程度)に準じた考え方です。
解約返戻金がこの基準額を大幅に超える場合、それはすぐに生活費に充てることができる資産と見なされ、解約を求められる可能性が極めて高くなります。現時点での解約返戻金の額がいくらになるかは、保険証券を確認するか、保険会社に問い合わせて正確に把握しておくことが重要です。
同世帯の子どもの就学目的であること
3つ目の条件は、学資保険の目的が、生活保護を一緒に受けている同世帯の子どものための就学費用(高校や大学、専門学校への進学費用など)であることが明確である点です。
これは1つ目の条件とも関連しますが、学資保険が本来の目的通り、子どもの教育資金として活用されることが大前提となります。例えば、契約書や保険証券で、その目的が明確に示されていることが望ましいでしょう。
また、保険料の支払いが家計を著しく圧迫していないことも、総合的な判断の中で考慮される場合があります。月々の保険料が、支給される生活保護費(最低生活費)の中から見て、過度に高額でないことも、継続を認めてもらうための一つの要素となり得ます。
これらの条件は、あくまで一般的な目安です。繰り返しになりますが、ご自身のケースで学資保険を残せるかどうかは、必ず福祉事務所のケースワーカーに正直に相談し、その指示に従うようにしてください。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
生活保護受給者の学資保険に関する判例
生活保護受給世帯における学資保険の満期金の扱いについては、過去に裁判で争われた事例があります。特に有名なのが、2003年から最高裁まで争われた「札幌市学資保険訴訟」です。この判例を知ることで、行政や司法がこの問題をどのように捉えているかを深く理解できます。
札幌市学資保険訴訟の経緯と争点
この裁判は、生活保護を受給していた母子家庭が、子どもの高校進学のために受け取った学資保険の満期金約50万円の扱いを巡って、札幌市を訴えたものです。
- 争点: 受け取った満期金は、子どもの高校進学費用という「特定の目的」のために使われるべきものか、それとも世帯の「収入」として認定し、その分生活保護費を減額・停止すべきか。
- 母親側の主張: この満期金は、長年にわたり子どもの高校進学という目的のために積み立ててきたもの。これを収入と見なされてしまうと、入学金や制服代などが支払えなくなり、子どもの進学の機会が奪われてしまう。これは、生活保護制度が目指す「自立の助長」に反する。
- 札幌市側の主張: 生活保護法では、稼働収入や年金、仕送りなど、あらゆる実質的な金銭の授受を「収入」として認定するのが原則である。学資保険の満期金も例外ではなく、収入として認定し、保護費を調整するのは法の定めに従った正当な処分である。
裁判所の判断とその変遷
この裁判は、地方裁判所、高等裁判所、そして最高裁判所で、それぞれ判断が分かれました。
- 第一審(札幌地裁)と第二審(札幌高裁)の判断:
地裁・高裁は、母親側の主張を認めました。「満期金を進学費用に充てることは、子どもの将来の自立を助ける上で極めて有効。これを収入認定することは、制度の目的である自立助長の観点から見て妥当ではない」とし、市の処分を取り消す判決を下しました。当事者や支援者にとっては、画期的な勝利判決でした。 - 最高裁判所の判断:
しかし、最高裁判所は地裁・高裁の判決を覆し、母親側の逆転敗訴という判断を下しました。最高裁は、「生活保護法は、稼働収入など一部の例外を除き、すべての収入を認定することを原則としている。学資保険の満期金を収入認定の例外とする明確な規定はない」と指摘。そして、「進学費用の必要性は、生活保護制度の中の『生業扶助』などで対応を検討すべきであり、満期金を収入認定から除外する理由にはならない」と結論付けました。
この判例からわかること
この一連の判例は、私たちにいくつかの重要なことを示唆しています。
- 法律上の原則は厳しい: 司法の最終判断として、学資保険の満期金は原則として「収入」と見なされる、という考え方が示されました。
- 自立助長の観点: 一方で、地裁・高裁では「子どもの自立」という観点が重視され、収入認定が取り消されました。これは、個別の事情によっては行政の判断に裁量の余地があることを示しています。
- 福祉事務所の判断が基本: 現実的には、最高裁の判例以降、多くの自治体で満期金は収入認定されるのが基本となっています。しかし、法律が全てではなく、担当のケースワーカーや福祉事務所が、個々の世帯の状況を考慮して柔軟な対応をする可能性もゼロではありません。
この判例は、法律の原則と、個々の生活実態との間で揺れる難しい問題であることを示しています。だからこそ、一方的に諦めたり、隠したりするのではなく、行政と正直に向き合い、相談することが不可欠なのです。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険は名義変更すれば継続できる?
学資保険を解約せずに済むもう一つの方法として、「名義変更」が考えられます。具体的には、保険の契約者を、生活保護を受給する親から、受給世帯ではない親族(例えば、祖父母)に変更する方法です。
この方法が認められれば、学資保険は「生活保護受給世帯の資産」ではなくなるため、解約する必要がなくなります。
名義変更を成功させるための重要ポイント
ただし、単に契約者の名前を変えるだけでは不十分です。名義変更を福祉事務所に認めてもらうためには、以下の点が非常に重要になります。
- 契約者と保険料負担者を一致させる:
契約者を祖父母に変更するだけでなく、その後の保険料も、すべて祖父母が自身の財産から支払う必要があります。もし、契約者名は祖父母でも、保険料の支払いが生活保護費から行われていたり、親が働いて得た収入から支払われていたりすると、それは「名義貸し」と判断され、実質的には親の資産と見なされてしまいます。 - 贈与と見なされないようにする:
名義変更のタイミングや、それまでの保険料の支払い状況によっては、税法上の「贈与」と見なされる可能性があります。例えば、親が支払ってきた解約返戻金相当額を、祖父母に贈与したと解釈されるケースです。通常、基礎控除額(年間110万円)の範囲内であれば贈与税はかかりませんが、念のため、手続きを行う前に保険会社や税務の専門家に確認しておくと安心です。 - 福祉事務所への事前相談:
名義変更を行う前に、必ず担当のケースワーカーにその旨を相談し、了承を得ることが不可欠です。「名義変更をしたので、もう私たちの資産ではありません」と事後報告するのではなく、「子どもの将来のために、祖父母の援助を受けて契約者を変更し、保険料も支払ってもらう形にしたいのですが、問題ないでしょうか?」と事前に相談しましょう。誠実な対応が、ケースワーカーとの信頼関係を築き、スムーズな手続きにつながります。
契約者変更の手続きは、保険会社のコールセンターに連絡し、所定の書類を取り寄せて行います。現在の契約者、新しい契約者、被保険者(子ども)の署名や捺印、本人確認書類などが必要となります。
祖父母などの親族に経済的な余裕があり、孫のために援助をしたいという意思がある場合には、この名義変更は非常に有効な選択肢となり得ます。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険以外で教育資金を準備する方法
生活保護を受けながら、子どもの教育資金を準備することは決して不可能ではありません。学資保険を解約せざるを得なかったとしても、利用できる公的な支援制度がいくつか存在します。諦めずに、これらの制度を活用しましょう。
1. 教育扶助・生業扶助(生活保護制度内)
生活保護制度の中には、子どもの教育を支援するための仕組みがあります。
- 教育扶助: 義務教育(小・中学校)期間中の子どもがいる世帯に対して、学用品費、教材代、給食費、通学費などが現金で支給されます。
- 生業扶助(高等学校等就学費): 高校に通う子どもがいる場合に、教育扶助と同様に、学用品費や通学費などが支給されます。これは、高校教育が一般的になった社会状況を反映した制度です。
これらの扶助だけでは大学進学費用まではカバーできませんが、義務教育や高校生活を送る上での経済的な負担を大きく軽減してくれます。
2. 就学援助制度
生活保護は受けていないものの、それに準ずるほど経済的に困窮している世帯を対象とした、市町村の制度です。学用品費、給食費、修学旅行費などの一部が援助されます。生活保護が廃止になった後なども、この制度の対象となる可能性があります。
3. 高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金)
住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯の学生を対象に、大学、短期大学、専門学校などの教育費を支援する国の制度です。いわゆる「高等教育無償化」と呼ばれるもので、以下の2つの支援がセットになっています。
- 授業料・入学金の減免: 入学金や授業料が、大学の設置者(国公立・私立)や世帯収入に応じて、免除または減額されます。
- 給付型奨学金: 返済が不要な奨学金が、日本学生支援機構(JASSO)から支給されます。学生生活を送るための生活費として利用できます。
生活保護世帯の子どもは、この制度の最も手厚い支援の対象となります。大学等への進学を考える上で、最も重要な支援制度と言えるでしょう。
4. 奨学金制度
上記の修学支援新制度に加えて、様々な奨学金があります。
- 貸与型奨学金: 卒業後に返済が必要な奨学金です。無利子の第一種奨学金と、有利子の第二種奨学金があります。
- 地方自治体や民間団体の奨学金: 都道府県や市町村、民間の育英会などが、独自の給付型(返済不要)または貸与型の奨学金制度を設けています。
これらの制度は、それぞれ申請条件や期間が異なります。高校の先生や、市役所の担当課、進学希望先の大学の窓口などで早めに情報を集め、計画的に準備を進めることが大切です。学資保険がなくても、子どもの学びたいという意欲を支える道は必ずあります。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
まとめ
今回は、生活保護と学資保険の関係について、解約の必要性からバレるリスク、残すための条件や代替案まで詳しく解説しました。最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。
- 原則は解約: 生活保護を受けるには、資産と見なされる学資保険は原則として解約し、返戻金を生活費に充てる必要があります。
- 隠すのは絶対にNG: 福祉事務所の調査権限は強力です。隠しても必ずバレると考えましょう。不正受給となれば、返還義務や罰則など、非常に重いペナルティが待っています。
- 残せる可能性もある: 「解約返戻金が少額」「子どもの自立目的が明確」などの条件を満たせば、例外的に保有が認められる可能性があります。ただし、必ずケースワーカーへの調査と相談が不可欠です。
- 名義変更も選択肢: 祖父母など、援助してくれる親族がいれば、契約者変更を行い、保険料の支払いもその親族に任せることで、保険を継続できる可能性があります。
- 公的支援を活用: 学資保険を解約しても、教育扶助や高等教育の修学支援新制度など、子どもの進学を支える公的な制度が多数あります。
生活が苦しい中で子どもの将来を案じる気持ちは、誰もが同じです。大切なのは、一人で抱え込まず、目の前のルールを正しく理解し、利用できる制度を最大限に活用することです。
まずは、お住まいの自治体の福祉事務所の窓口で、現状を正直に話して相談することから始めてみてください。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!