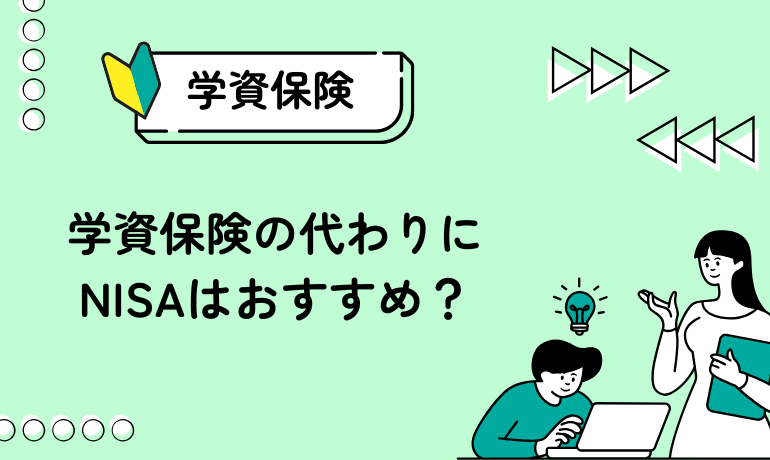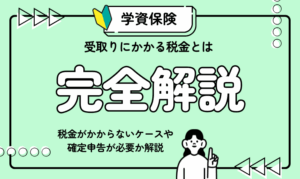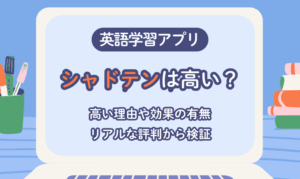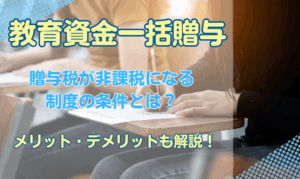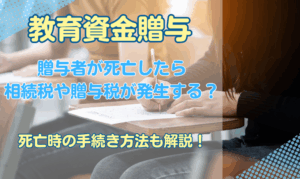子どもの教育資金準備は、親にとって重要な課題の一つです。従来は学資保険が主流でしたが、近年では投資による資産運用への関心が高まり、NISAを活用した教育資金準備を検討する方が増えてきています。
しかし、学資保険とNISAには大きな違いがあり、それぞれにメリット・デメリットが存在するので、事前に把握しておくのがおすすめです本記事では、学資保険代わりにNISAを活用することについて、両者の特徴を比較しながら詳しく解説していきます。
学資保険の代わりにNISAで教育資金を準備するのはおすすめ?
教育資金の準備方法として、学資保険とNISAはどちらも有効な選択肢です。しかし、それぞれの特性が異なるため、すべての人に同じ方法が適しているわけではありません。個人の状況や価値観、リスク許容度によって、最適な選択は変わってきます。
学資保険は、保険商品として安定性と保障機能を備えており、計画的な積立が可能です。一方、NISAは投資商品として、より高いリターンを期待できる可能性がありますが、同時にリスクも伴います。どちらを選ぶかは、それぞれの特徴を理解した上で、自身の状況に合わせて判断することが重要です。
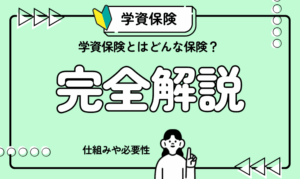
学資保険の方がおすすめの人
学資保険は、保険会社と契約を結び定期的に保険料を支払うことで、子どもの進学時期に合わせて満期保険金や学資金を受け取れる保険商品です。保険機能と貯蓄機能を併せ持ち、契約者(親)に万が一のことがあった場合でも保険料の支払いが免除され、予定通りの学資金を受け取ることができます。
学資保険がおすすめの人の特徴は、以下の通りです。
• 確実に教育資金を準備したい人
• 投資のリスクを避けたい人
• 万が一の保障も同時に確保したい人
• 計画的な積立が苦手で、強制的に貯蓄したい人
• 生命保険料控除を活用して節税したい人
• 投資の知識や経験がなく、運用に不安がある人
• 教育資金の使用時期が明確に決まっている人
NISAがおすすめの人
NISA(少額投資非課税制度)は、投資で得た利益が非課税になる制度です。2024年から始まった新NISAでは年間投資枠が大幅に拡大し、非課税保有期間も無期限となりました。投資信託や株式などの金融商品を通じて資産運用を行い、教育資金を準備することができます。
なお、かつて存在したジュニアNISAは2023年末で新規口座開設が終了し、現在は新規での利用はできません。また、旧NISAから新NISAへの制度改正により、より使いやすい制度となっています。
NISAがおすすめの人の特徴は、以下の通りです。
• より高いリターンを期待したい人
• 投資の知識や経験がある程度ある人
• 資金の使い道や時期に柔軟性を持たせたい人
• リスクを理解し、許容できる人
• 長期的な資産運用を考えている人
• 投資額を自由に調整したい人
• 非課税メリットを最大限活用したい人

学資保険とNISAは併用もおすすめ
学資保険とNISAは、どちらか一方を選ばなければならないわけではありません。両方を併用することで、それぞれのメリットを活かしながら、デメリットを補完することができます。
併用のメリットとして、まず基本的な教育資金は学資保険で確実に準備し、プラスアルファの資金をNISAで運用するという戦略が可能です。これにより、最低限必要な教育資金は確保しつつ、余裕資金でより高いリターンを狙うことができます。
また、リスク分散の観点からも併用は有効です。学資保険の安定性とNISAの成長性を組み合わせることで、バランスの取れた教育資金準備が可能となります。さらに、学資保険による生命保険料控除とNISAの運用益非課税という、それぞれの税制優遇を同時に活用できるメリットもあります。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険とNISAの違い
学資保険とNISAには、運用方法や制度設計において大きな違いがあります。以下、主要な違いを詳しく見ていきましょう。
運用方法の違い 学資保険は保険会社が運用を行い、契約時に将来の受取額がほぼ確定します。一方、NISAは自分で投資商品を選択し、運用成績によって将来の受取額が変動します。
投資上限の違い 学資保険には明確な上限はありませんが、一般的に月額1万円から3万円程度の保険料設定が多いです。新NISAは、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円、合計で年間360万円まで投資可能です。
リスクとリターンの違い 学資保険は元本割れリスクが低い代わりにリターンも限定的で、返戻率は100%から110%程度が一般的です。NISAは市場の変動により元本割れリスクがありますが、長期運用により高いリターンが期待できます。
税金面の違い 学資保険は生命保険料控除の対象となり、所得税・住民税の軽減効果が狙えます。満期保険金は一時所得として課税対象になる場合があります。NISAは、投資額自体は所得控除の対象になりません。しかし、運用益は非課税で受け取れます。
加入可能年齢の違い 学資保険は子どもの年齢に制限があり、多くの商品で0歳から6歳頃までが加入可能期間です。NISAは、18歳以上であれば年齢上限なく口座開設が可能です。
柔軟性の違い 学資保険は契約内容の変更が難しく、途中解約すると元本割れのリスクが高いです。NISAはいつでも売却可能で、投資額の変更も自由に行えます。
保障機能の違い 学資保険には、契約者の死亡・高度障害時の保険料払込免除特約があります。NISAには保障機能はなく、純粋な投資商品です。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険のメリットとデメリット
学資保険とNISAはどちらも教育資金準備に役立てられますが、それぞれメリットとデメリットがあると先ほどお伝えしました。ここではまず、学資保険のメリット・デメリットから解説していきます。
学資保険のメリット
学資保険には、教育資金準備において多くのメリットがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
計画的に教育資金を準備できる
学資保険の最大のメリットは、計画的かつ確実に教育資金を準備できることです。契約時に将来の受取額と受取時期が決まるため、子どもの進学スケジュールに合わせた資金計画が立てやすくなります。
毎月決まった保険料を支払うことで、自動的に積立が行われるので、貯蓄が苦手な人でも確実に教育資金を準備できます。また、銀行預金と異なり、簡単に引き出せないため、他の用途に使ってしまう心配もありません。
保険会社によっては、中学入学、高校入学、大学入学といった節目に合わせて学資金を受け取れるプランもあり、実際の教育費の支出タイミングに合わせた設計が可能です。
万が一のときの保障がある
学資保険には、契約者(通常は親)に万が一のことがあった場合の保障機能があります。保険料払込免除特約を付加することで、契約者が死亡または高度障害状態になった場合、以後の保険料の支払いが免除されるのです。
この場合でも、満期保険金や学資金は予定通り受け取ることができるため、親に何かあっても子どもの教育資金は確保されます。これは単なる貯蓄にはない、保険ならではの大きなメリットです。
特に一家の大黒柱が契約者となる場合、この保障機能は家族の安心につながります。生命保険の役割も兼ねているため、別途死亡保険に加入する必要がなくなる場合もあります。
生命保険料控除の対象になる
学資保険の保険料は、生命保険料控除の対象となります。これにより、所得税や住民税の軽減効果が期待できます。
生命保険料控除は年間の支払保険料に応じて、所得税で最大4万円、住民税で最大2.8万円の所得控除を受けることが可能です。例えば、所得税率20%の人が年間8万円以上の保険料を支払った場合、所得税で4万円、住民税で2.8万円の合計6.8万円の節税効果があります。
この節税効果は毎年継続するため、長期間にわたって考えると大きな金額です。実質的な返戻率を高める効果があるため、学資保険の魅力の一つとなっています。
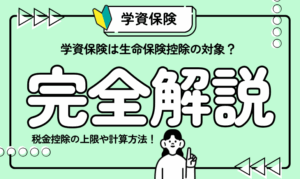
学資保険のデメリット
一方で、学資保険にはいくつかのデメリットも存在します。加入前にしっかりと理解しておくようにしましょう。
子どもの年齢によっては加入できない
学資保険は、子どもの年齢に応じて加入制限があります。多くの商品で、子どもの年齢が0歳から6歳頃までとなっており、それ以降は加入できません。また、契約者(親)の年齢にも上限があり、一般的に男性は18歳から60歳頃、女性は16歳から65歳頃までとなっています。
学資保険も他の保険と同様に、加入時期が遅くなればなるほど保険料が高くなる傾向があります。例えば、0歳で加入する場合と5歳で加入する場合では、同じ満期保険金額でも月々の保険料に大きな差が生じるケースが多いです。
そのため、学資保険への加入を検討している場合は、できるだけ早い時期に検討を始めることが重要です。出産前から検討を始め、子どもが生まれたらすぐに加入手続きを行う人も多くいます。
解約すると元本割れするリスクが高い
学資保険は長期契約を前提とした商品のため、途中解約すると支払った保険料総額を下回る解約返戻金しか受け取れない場合がほとんどです。特に契約から数年以内の解約では、大幅な元本割れとなることが一般的です。
例えば、契約から5年で解約した場合、支払保険料の60%から70%程度しか返ってこないケースも珍しくありません。これは、保険会社が契約初期に多くの経費を計上するためです。
家計の急変や転職などにより保険料の支払いが困難になった場合でも、安易に解約すると大きな損失を被ることになります。そのため、無理のない保険料設定で契約することが重要です。
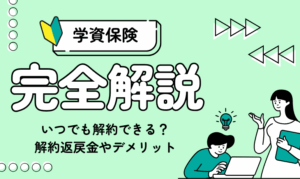
満期保険金などは課税対象になる
学資保険の満期保険金や祝い金を受け取る際、その金額によっては税金がかかる場合があります。契約者と受取人が同一の場合は一時所得として、契約者と受取人が異なる場合は贈与税の対象です。
一時所得の場合、受取金額から支払保険料総額を差し引いた利益が50万円を超えると課税対象となります。ただし、一時所得には50万円の特別控除があるため、実際に課税されるケースは限定的です。
贈与税の場合は、年間110万円の基礎控除を超えた部分が課税対象となります。満期保険金が高額な場合は、受取方法を工夫することで税負担を軽減できる場合もあります。
インフレに弱い
学資保険は契約時に将来の受取額が確定するため、インフレによる貨幣価値の下落に対応できません。例えば、現在100万円で契約した満期保険金も、18年後にはインフレにより実質的な価値が目減りしている可能性があります。
過去の日本では長期間デフレが続いていたため、この問題は顕在化していませんでしたが、近年は物価が上昇傾向にあることから、インフレリスクへの対応も重要です。
特に教育費は一般的な物価上昇率を上回るペースで上昇する傾向があるため、学資保険だけでは将来の教育費をカバーしきれない可能性もあります。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
NISAのメリットとデメリット
続いて、NISAのメリット・デメリットを見ていきましょう。
NISAのメリット
NISAを活用した教育資金準備には、投資ならではのメリットがあります。
お金が必要なときに現金化できる
NISAの大きなメリットが、必要なときにいつでも現金化できる柔軟性です。学資保険のように満期まで待つ必要がなく、市場の状況や家計の事情に応じて売却タイミングを自由に選べます。
例えば、想定より早く教育資金が必要になった場合や反対に奨学金などで資金需要が減った場合など、状況に応じて対応できます。また、一部だけを売却することも可能なため、必要な分だけを現金化し、残りは運用を継続することも可能です。
ただし、売却時の市場価格によっては損失が出る可能性もあるため、余裕を持った運用計画が必要です。
投資額を変更できる
NISAでは、家計の状況に応じて投資額を自由に変更できます。収入が増えた時は投資額を増やし、支出が多い時期は減額するなど、柔軟な対応が可能です。
新NISAのつみたて投資枠では、月100円から投資を始められる証券会社もあり、無理のない金額から始めることができます。また、ボーナス時にまとめて投資することも可能で、年間投資枠の範囲内で自由に配分できる点もポイントです。
この柔軟性により、ライフステージの変化に合わせた資産形成が可能となり、長期的な継続がしやすくなります。
売却益や配当金は非課税で受け取れる
NISAの最大のメリットは、投資で得た利益が非課税になることです。通常、投資信託や株式の売却益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座内での取引であればこの税金が一切かかりません。
例えば、100万円投資して150万円になった場合、通常なら利益50万円に対して約10万円の税金がかかりますが、NISAなら全額を受け取ることができます。長期運用で大きな利益が出た場合、この非課税メリットは非常に大きくなるでしょう。
また、投資信託の分配金や株式の配当金も非課税で受け取れるため、運用期間中の収入も税金を気にすることなく再投資や生活費に充てることができます。
NISAのデメリット
NISAにも、注意すべきデメリットがあります。これらを理解した上で活用することが重要です。
投資額は税金控除の対象外
NISAへの投資額は、学資保険のように所得控除の対象にはなりません。つまり、投資した金額に対する節税効果はないということです。
学資保険の場合は生命保険料控除により所得税・住民税が軽減されますが、NISAは運用益が非課税になるだけで、投資元本に対する税制優遇はありません。そのため、短期的な節税効果を期待する場合は、学資保険の方が有利になることがあります。
ただし、長期的に見れば運用益の非課税メリットの方が大きくなる可能性が高いため、トータルでの判断が必要です。
大きな損失が出るリスクがある
NISAは投資商品であるため、元本保証はありません。市場の変動により、投資元本を下回る可能性があります。特に短期的には大きな値動きがあり、一時的に大きな損失を抱えることもあります。
例えば、リーマンショックやコロナショックのような金融危機が発生した場合、投資信託の価格が30%以上下落する可能性もゼロではありません。教育資金のように使用時期が決まっている資金の場合、このタイミングで現金化せざるを得ないと大きな損失が確定してしまいます。
このリスクを軽減するためには、長期分散投資を心がけ、使用時期が近づいたら徐々に安全資産へシフトしていくなどの対策が必要です。
投資額に上限がある
新NISAには、年間投資枠の上限があります。つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円で、合計360万円までしか投資できません。また、生涯投資枠は1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)という制限もあります。
高額な教育資金を準備したい場合、この上限を制約と感じるケースも少なくありませんす。特に複数の子どもがいる家庭では、NISA枠だけでは不足する可能性があります。
ただし、夫婦それぞれがNISA口座を開設すれば、世帯全体での投資枠を増やすことができます。また、NISA以外の課税口座での運用と組み合わせることも可能です。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険やNISA以外で教育資金を準備する方法
教育資金の準備方法は、学資保険とNISAだけではありません。他にも様々な選択肢があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
終身保険を活用する方法
終身保険は一生涯の死亡保障がある保険商品ですが、解約返戻金を教育資金として活用することができます。学資保険と異なり、子どもの年齢制限がないため、子どもが大きくなってからでも加入することが可能です。
メリットとして、死亡保障が一生涯続くため、教育資金として使わなかった場合は老後資金や相続対策として活用できます。また、保険料払込期間を短くすることで、早期に解約返戻金を増やすことも可能です。
デメリットは、保険料が学資保険より高額になりやすいことと、早期解約時の元本割れリスクが大きいことです。また、教育資金として特化した商品ではないため、受取時期の設定などを工夫する必要があります。
投資信託(課税口座)で運用する方法
NISA枠を使い切った後やNISA口座開設前でも、通常の課税口座で投資信託を購入することができます。投資対象や金額に制限がないため、自由度の高い運用が可能です。
メリットは、投資額に上限がないことと、損失が出た場合に他の投資利益と損益通算できることです。また、つみたて投資を自動設定すれば、NISA同様に積立投資ができます。
デメリットは、運用益に約20%の税金がかかることです。長期運用で大きな利益が出た場合、税負担が大きくなります。ただし、教育資金贈与の非課税制度と組み合わせるなど、工夫次第で税負担を軽減することも可能です。
預貯金で準備する方法
最もシンプルな方法は、銀行の定期預金や普通預金で教育資金を準備することです。元本保証があり、いつでも引き出せる安心感があります。
メリットは、元本割れリスクがないことと必要な時にすぐに使えることです。また、預金保険制度により、1金融機関あたり1,000万円までは保護されています。
デメリットは、現在の低金利環境ではほとんど利息が付かないことです。インフレに対応できず、実質的な価値が目減りする可能性があります。
ジュニアNISAの活用(既存口座のみ)
2023年末で新規口座開設は終了しましたが、既にジュニアNISA口座を持っている場合は2024年以降も運用を継続できます。18歳まで非課税で運用でき、2024年以降は年齢に関わらず払い出しが可能になりました。
財形貯蓄の活用
勤務先に財形貯蓄制度がある場合、給与天引きで確実に積立ができます。一般財形、住宅財形、年金財形の3種類があり、目的に応じて選択可能です。
メリットは、給与天引きのため確実に貯蓄できることと、会社によっては奨励金が付く場合があることです。デメリットとしては、利率が低いことと、勤務先に制度がないと利用できないことが挙げられます。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
まとめ
学資保険とNISAは、それぞれ異なる特徴を持つ教育資金準備の方法です。学資保険は確実性と保障機能を重視する方に、NISAは柔軟性と成長性を重視する方に適しています。
どちらか一方に決める必要はなく、両方を併用することでバランスの取れた教育資金準備が可能です。重要なのは、自身の家計状況、リスク許容度、投資経験などを総合的に判断し、無理のない計画を立てることです。
また、教育資金の準備は早めに始めることが大切です。時間を味方につけることで、より多くの選択肢を持つことができます。定期的に見直しを行いながら、子どもの将来のために着実に準備を進めていきましょう。
最後に、どの方法を選ぶとしても、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。ファイナンシャルプランナーや保険代理店、証券会社の相談窓口などを活用し、自分に最適な方法を見つけてください。子どもの教育は、一生に一度の大切な機会です。後悔のない選択をするためにも、しっかりと情報収集を行い、計画的に準備を進めていきましょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!