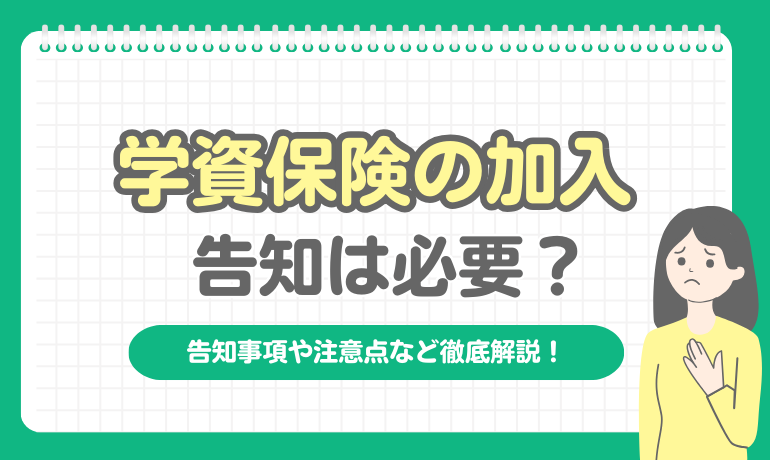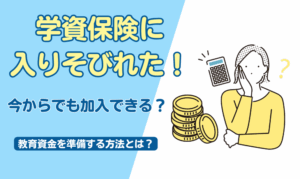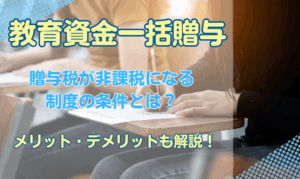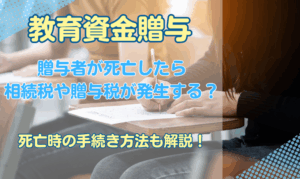学資保険に加入する際、「健康状態の告知義務」はあるのか気になる方も多いでしょう。
そこで本記事では、学資保険の加入時に必要な告知事項や告知を怠った場合のリスク、そして健康状態に不安がある場合の対応策などについて詳しく解説します。学資保険の告知義務や健康状態に関する疑問を解消し、正しい知識を持って安心して学資保険を検討できるよう、専門的な情報を網羅しました。まずは、告知の必要性から見ていきましょう。
学資保険の加入には告知が必要?
学資保険は子どもの教育資金を準備する保険ですが、生命保険の一種でもあり、基本的には加入時に持病や健康状態を申告(告知)する必要があります。ここでは、告知の内容や対象者について、詳しく説明していきます。
学資保険には告知が必要なことが多い
先述の通り、学資保険に加入する際は告知が必要なケースがほとんどです。。告知義務とは、保険契約の公平性を保つために持病や過去の病歴などの重要事項を正直に伝える義務のことです。
学資保険は生命保険の要素を持つ商品であり、親に万一のことがあった場合に以後の保険料が免除される保険料払込免除保障が付加されています。そのため、生命保険と同様に加入時に審査があり、契約者や被保険者の健康状態をチェックする必要があるのです。告知書では持病の有無や最近の通院歴などを申告することになっています。
もっとも、学資保険の中には保障内容をシンプルにした商品もあり、例外的に告知が不要なケースも存在します(詳細は後述「告知なしの学資保険もある」を参照)。しかし大半の学資保険は健康状態の告知が必要だと考えておきましょう。保険料を出し合う制度上、加入時の健康状態告知は避けて通れないものなのです。
親(契約者)と子ども(被契約者)の告知が必要
学資保険は親が契約者(保険料支払者)となり、子どもが被保険者(保険の対象者)となる保険です。そのため、基本的に親(契約者)と子ども(被保険者)の双方について告知が必要です。保険会社は契約者である親の健康状態だけでなく、被保険者である子どもの健康状態も確認して審査を行います。親については、万一親が死亡・高度障害となった場合に保険料の支払いを免除する保障(払込免除特約)のリスク判断のため、必ず健康状態の告知が求められます。一方、子どもについても学資保険によっては死亡給付金や医療特約などが付いている場合があり、また被保険者としてのリスク判断のために健康状態告知を求める保険会社が多いです。
ただし、保険会社や商品によって告知範囲に違いがあります。例えばフコク生命の学資保険では契約者である親の告知のみ必須で、子どもの健康状態告知は不要です。また日本生命(ニッセイ)の学資保険も子どもの健康状態の告知は不要で、子どもが過去に病気をしていても契約できます。一方、明治安田生命の学資保険「つみたて学資」では契約者(親)・被保険者(子)ともに告知が必要となっています。ソニー生命の学資保険も健康状態を自己申告する告知書扱いで加入でき医師の診査は不要ですが、やはり申込時に決められた内容の告知が必要です。
このように、「親と子どもの両方が告知対象となる場合」と「親のみ告知すればよい場合」がありますが、一般的には両者の告知事項に問題があると審査に通らない点に注意しましょう。誰の告知が必要かは保険商品によって異なるため、加入を検討する際には各社の約款や募集要項を確認するか、担当者に確認することをおすすめします。
告知なしの学資保険もある
「健康状態に不安があり、審査に通るか心配…」「できれば告知なしで加入できる学資保険はないの?」と考える方もいるでしょう。結論から言うと、告知不要で加入できる学資保険もあります 。これは主に、保険料払込免除特約(親の死亡や高度障害などで保険料免除になる保障)を付けないタイプの学資保険です。
一般的に保険には貯蓄性重視の保険と保障重視の保険がありますが、告知なしで加入できる学資保険は貯蓄性重視型に当たります。具体的には、契約者に万一のことが起きても以後の保険料免除といった保障が付かない代わりに、健康告知なしで契約できる商品です。例えばJA共済の学資保険「学資応援隊」は、「共済掛金払込免除不担保特則」を付加して保険料免除の保障を無くすことで、健康状態や年齢にかかわらず申し込めるようになっています。また、アフラックの「夢みるこどもの学資保険」は、保険料払込免除特則を付加しない場合は契約者・被保険者とも告知不要で加入できます。
このような告知不要の学資保険は、持病がある方や高齢の祖父母が孫のために契約するケースでも加入しやすい点がメリットです。親の健康面に不安があっても、払込免除を付けなければ祖父母が契約者として学資保険に加入し、孫への教育資金贈与に活用できる場合があります。高齢者は健康上の理由で通常の学資保険加入が難しいことがありますが、告知なしプランには契約者年齢の上限が高く設定されている商品もあり(JA共済は契約者75歳まで可能)、状況に合わせて柔軟に利用できます。
ただし、告知なしの学資保険には注意点もあります。先述の通り、払込免除を付けない分契約者に万一のことが起きても保険料免除などの保障が一切ない点には留意しましょう 。例えば親が途中で亡くなった場合でも、その後の保険料を払い込まなければ満期金を受け取れません。保障が薄い分、返戻率(貯蓄性)はやや高く設定される傾向がありますが、貯蓄機能だけのための保険になることを理解しておく必要があります。
また、告知が不要だからと言って虚偽の申告をして良いわけではない点にも注意が必要です 。健康告知が省略される契約でも、もし過去に大きな持病がある場合は代理店などに相談し、必要に応じて伝えておくのが無難です。告知なしで加入できる学資保険を利用する際は、保障内容が限定的であることを理解し、必要に応じて別途生命保険や養老保険などで保障を補完することも検討しましょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
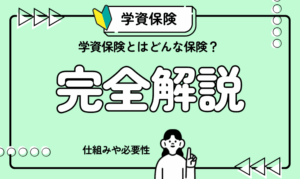
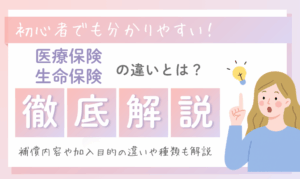
学資保険の告知をしないとどうなる?
告知が必須の学資保険では、告知をしないと当然加入することができません。しかし告知したとしても、内容によっては契約を解除されてしまうケースがあります。ここでは、告知義務違反の内容とペナルティについて解説していきます。
告知義務違反がバレると契約解除の可能性がある
学資保険に限らず生命保険では、告知義務違反(本来告知すべき事項を故意に告げない、または虚偽を告げること)が判明した場合、契約者にとって重大なペナルティがあります。それは、契約の解除(無効化)です。加入時の告知で事実と異なる申告をしていたことが発覚すると、保険会社は契約を解除し、保障を打ち切ることができます。契約解除となれば学資保険は中途解約扱いとなり、それまで積み立てた保険金は元本割れの解約返戻金として戻ってくるので大きな損失になりかねません 。
基本的に、契約から2年以内に判明した告知義務違反については保険会社は解除しやすい(いわゆる「告知義務期間」)とされています。ただし注意すべきは、2年を過ぎていても悪質な告知漏れが発覚した場合には契約時に遡って解除される可能性があることです。たとえば契約から数年後に当時申告していなかった持病の存在が判明し、それが契約引受不可のレベルであれば、期間を問わず契約取消しが行われるケースもあります。このように告知義務違反は時が経っても免責にはならない場合があるため、初めから正確に申告することが重要です。
契約が解除されてしまうと、せっかく積み立てた教育資金計画が崩れてしまう恐れがあります。また、一度告知義務違反で解除になった記録が残ると、他社で新たに保険に加入する際にも不利になる可能性が高いです。従って「審査に通りたいから」といって嘘の告知をすることは絶対に避けましょう。
悪質なケースでは支払い済みの保険料も返還されない
告知義務違反による契約解除の中でも、特に悪質なケースと保険会社に判断された場合、これまで支払った保険料すら戻ってこないことがあります。通常、契約解除となった場合でも解約返戻金など何らかの形で手元に資金が返ることが多いですが、悪質とみなされると契約が無効(取消し)扱いとなり、一切の返戻金が支払われないのです。
では「悪質なケース」とは、具体的にどのような場合でしょうか?一例として、現在の医療では治療困難な重い病気にかかっているのに、それを知りながら告知せずに契約した場合が挙げられます。例えば契約者(親)が高度な心疾患やがんを患っており、死亡リスクが高いにもかかわらず故意に告知しなかったようなケースです 。そのように契約者の不告知に重大な過失や故意が認められる場合、保険会社は契約を遡って取り消し、払込済み保険料も全て没収する措置を取ることがあります。
このような事態になると、払い込んだお金を全て失うばかりか、肝心の保障も受けられず何も残りません。学資保険は長期間にわたる貯蓄計画でもあるため、一度の告知違反で将来の教育資金計画が破綻するリスクがあります。そうならないためにも、告知事項については「まあ大丈夫だろう」と自己判断で隠さず、気になることは事前に保険会社に相談した上で正直に申告することが肝心です。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険の告知義務違反は絶対NG!バレる可能性が高い
保険の告知義務違反は厳しい処分に繋がることを説明しましたが、「本当にバレるの?」と疑問に思う人もいることでしょう。しかし結論として、告知義務違反は高い確率で発覚します。現代は医療機関の診療情報がデータベース化され、保険会社は必要に応じて契約者・被保険者の過去の医療記録を容易に確認できる時代です。例えば保険金の支払い事由(親の死亡や高度障害など)が発生した際、保険会社はその時点で契約者の病歴を調査します。過去の入院記録や処方履歴は病院のカルテから照会可能であり、契約時に遡って当時の健康状態がすぐに明らかになるのです。
また、近年では保険金詐欺防止の観点から保険会社間での情報共有も進んでおり、不自然な契約や告知内容には注意が払われています。特に注意されているのは高額保障が絡む生命保険ですが、学資保険も保険料免除特約のように生命保険的要素がある以上、保険会社は告知内容を重視します。「小さな嘘だから大丈夫だろう」と思っても、いざという時には隠した事実が発覚すると考えてください。
したがって、学資保険加入時に告知義務違反を企てるのは絶対にNGです。たとえ現在健康に問題があっても、正直に告知した上で加入できる保険を探す方が結果的に安心につながります。最近では引受基準緩和型(持病があっても加入しやすい)保険も増えていますし、学資保険が難しければ他の手段(例えば親自身の死亡保険+貯蓄)で教育資金を確保する方法もあります。嘘の告知で一時的に契約できても将来のリスクを抱えることになるため、適切な保障を選び正攻法で審査を受けましょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
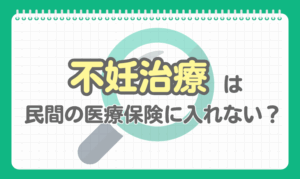
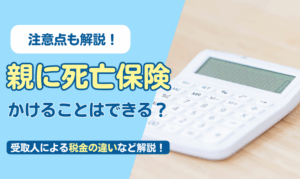
学資保険の加入に必要な基本の告知事項
ここでは、学資保険に加入する際、具体的にどのような項目について告知(申告)しなければならないのかを押さえておきましょう。保険会社が学資保険の申し込み時に提出を求める告知書では、主に次のような事項について質問されます。ここでは基本的な告知事項を3つのカテゴリーに分けて紹介します。
契約者と被契約者の基本情報
まず求められるのは、契約者(親)および被保険者(子ども)の基本的な個人情報です 。具体的には、以下のような項目を告知書に記入します。
・氏名・性別・生年月日(年齢)
・身長・体重
・(契約者について)職業や勤務先、年収など
・(契約者について)他に加入している保険契約の有無・内容
氏名や性別・生年月日は、本人確認および年齢の確認に使われます。学資保険には加入年齢の上限があり、契約者(親)の年齢は男性で50~55歳程度、女性で60歳程度までと定められている商品が多いです。被保険者(子ども)の加入可能年齢も、0歳から6歳(小学校入学前)までが一般的な上限です。例えば明治安田生命の学資保険では契約者は満18歳~上限は市場金利情勢などによって変動し、子どもは0~満6歳までとされています。
身長・体重は健康状態とも関連しますが、基本情報として登録されます。近年は保険会社でもデジタル化が進み、例えば日本生命では指紋や顔認証で本人確認できるアプリを導入して、本人特定の精度向上に努めています。基本情報が正確に登録されることで、将来の保険金請求時などに本人確認で混乱するリスクを下げることができるでしょう。
契約者の職業についても、告知書で尋ねられることがあります。これは職業による危険度の評価のためです。例えば契約者の仕事が危険を伴うものであれば、万一の事故のリスクが高くなるため保険会社が留意する場合があります。もっとも、学資保険程度の保険金額であれば職業で加入を断られるケースは稀ですが、生命保険全般の審査項目として含まれていることを知っておきましょう。
契約者と被契約者の健康状態
次に、契約者(親)と被保険者(子ども)の健康状態や病歴について詳しく告知する必要があります。具体的な告知事項は保険会社によって表現が異なりますが、以下のような質問が設けられていることが多いです。
・最近3か月以内に医師の診察・検査・治療・投薬を受けたか
・過去5年以内に病気やケガで連続7日以上の診察・治療または投薬を受けたか
・手術や継続7日以上の入院を過去にしたことがあるか
・過去2年以内に健康診断や人間ドックなどで異常を指摘されたことがあるか
・現在、視力・聴力・言語・そしゃく機能に障害があるか
・(保険会社によっては)過去○年以内にがんや心疾患など大病の罹患歴はあるか
このように、直近数か月から数年以内の治療歴・検査歴が主な告知対象となります。期間については「3か月」「2年」「5年」など項目ごとに異なりますが、これは症状の重大度に応じて確認する範囲を変えているためです。基本的に、最近の診療(3か月)や検査結果(2年)に異常がないか、そしてある程度長期の治療歴(5年)がないかという観点で質問が設計されています。
告知にあたって重要なのは、質問に該当する事実があれば正直に「はい」と答えることです。例えば「5年以内に7日以上の入院歴がありますか?」という問いに該当する入院歴があれば、必ず申告しましょう。完治から5年以上経った病気は告知不要とされていますが、例外としてがんについては完治後10年経過していても告知義務があります。この点は見落としやすいポイントなので注意が必要です。なぜ5年なのかというと、医療機関のカルテ保存期間が概ね3~5年であることから保険会社が確認できる範囲として設定しているためとも言われています。
健康状態の告知内容に少しでも相違があると、先述した告知義務違反に問われる可能性があります。軽微な症状で告知に迷う場合でも、自己判断で「申告しなくてもいいだろう」と決めつけないことが大切です。花粉症や軽い風邪程度であれば通常告知不要ですが、判断に迷う場合は事前に保険会社の窓口や担当者に確認しましょう。告知項目は専門用語も多く分かりにくいことがありますが、不明点はプロに相談して正確に記入することが重要です。
被保険者の出生時の状態
最後に、被保険者である子どもの出生時の健康状態についての告知事項があります。これは子どもがまだ小さい場合(特に満3歳未満)に重視される項目です。典型的な内容は、以下の通りです。
・子どもの出生時の身長・体重
・在胎週数(何週目で出生したか)
・出生時に特に異常や治療を要したことがあるか(未熟児や低体重で生まれた等)
・母体の妊娠中・出産時の異常の有無(出生前加入の場合)
これらは、被保険者である子どもが健康に生まれてきたかを確認するための事項です。特に低出生体重児(未熟児)で生まれた場合や出生時に治療措置を受けた場合、その後の健康リスクを保険会社が考慮する可能性があるため告知が求められます。一般的に満3歳未満の子どもは出生時情報の告知が必要になることが多いです。これは、新生児期~幼児期にかけて先天性疾患の発症リスクが高かったり、出生時の体重が将来的な健康に影響するケースがあるからです。
例えば出生時体重が極端に低かった場合、学資保険によっては一定期間加入を見合わせる(もう少し成長して健康状態が安定してから加入する)よう指示されることもあります。また、出生直後にNICUに入るような治療があった場合も詳しく申告し、保険会社の判断を仰ぐようにしましょう。フコク生命の学資保険のように子どもの健康告知が不要な商品もありますが、それは子どもの医療保障を付けない場合の話で、医療特約を付加する際にはやはり告知が必要になります。
子どもが過去に大きな病気を経験していたり、現在治療中だったりする場合、学資保険への加入可否はケースバイケースです。保険会社によって基準が異なるため、一社で断られても別の会社なら加入できることもあります。いずれにせよ、出生時や幼少期の情報についても聞かれたことには正確に答え、必要なら医師の診断書を提出して審査を受けることになるでしょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険の審査に通らない理由とは
学資保険の申込みをしても、健康状態や既往歴などの理由で審査に通らないケースがあります。ここでは、学資保険に加入できない理由について取り上げます。持病のように健康上の問題が原因となる場合が多いですが、稀に「借金があるけど大丈夫か?」といった健康以外の不安も聞かれるため、それについても触れておきます。
学資保険に入れない病気とは
まず健康上の理由についてですが、どのような病気があると学資保険に入れない場合があるのか解説します。一般論として、学資保険で加入を断られやすい持病は保障内容(払込免除)に直接関係する重篤な病歴です。具体的には、心疾患や脳疾患などの病歴がある場合が該当します。契約者である親がこれらの病歴を持つと、死亡や高度障害となるリスクが高いと判断され、保険料払込免除の特約リスクが大きいため加入を断られることがあります。また、現在がんや糖尿病、肝疾患など重い病気で治療中の場合も加入を見送られるケースが少なくありません。
一方で、学資保険の保障内容と直接関係のない持病であれば、告知しても加入できる可能性があります。例えば親が軽度のぜんそくを持っている場合や過去に骨折で手術歴がある程度なら、学資保険の審査では大きな問題にならないことが多いでしょう。要は「親の死亡リスク」に直結しない病気であれば、保険会社も柔軟に判断する傾向にあります。また、子どもに持病がある場合は、会社によって扱いが異なります。学資保険の多くは親を契約者・子を被保険者としますが、子どもの健康状態によって加入が難しい場合、親のみ死亡保障を用意して子は貯蓄だけにするプラン(例えば子どもに医療特約を付けず、親の払込免除も外す)で契約できる可能性があります。
先述の通り各社の引受基準は異なるため、ある保険会社で断られたからと言って他社でも加入できないとは限りません。学資保険の相談窓口や保険代理店では、事前に健康状態を伝えることで「この条件ならA社は厳しいがB社なら可能」といったアドバイスをしてもらえることもあります。どうしても加入が難しい場合は、学資保険だけにこだわらず代替策も検討しましょう。例えば親が十分な死亡保障のある終身保険や定期保険に加入し、子どもの教育資金は貯蓄で準備する方法も有効です。学資保険で払込免除の恩恵を受けられなくても、他の保険でレバレッジ(少ない保険料で大きな保障)を効かせて教育費リスクに備えることは可能なのです。
借金があると学資保険の審査に落ちる?
健康状態以外で心配されることとして、「借金(負債)があると保険の審査に通らないか?」という疑問が挙げられます。結論から言うと、借金の有無そのものは学資保険の審査にほとんど影響しません。なぜなら借金は告知事項ではなく、通常は審査上重視されないからです。保険加入時に申告が求められるのは健康状態や職業などであり、「住宅ローンがある」「カードローン残高がある」といった個人の債務状況を告知する必要は基本的にありません。
ただし、生命保険全般の考え方としてモラルリスクという概念があります。極端に多額の借金を抱えている人が高額な死亡保険に加入する場合、万一故意の事故や自殺で保険金を債務返済に充てようとする不正を防がなければなりません。そのため、契約者の収入に対して明らかに不釣り合いな高額保障を申し込むと、保険会社から借金状況を含め詳しく事情を聞かれることがあります。しかし学資保険は貯蓄が主な目的で死亡保険金額もそれほど大きくないため、通常の範囲の借入であれば問題視されることはほぼありません。
まとめると、借金があること自体で学資保険に加入できなくなる可能性は低いでしょう。むしろ借金よりも、収入に対する保険料負担の方が現実的な懸念点です。毎月の返済が厳しいほど借金がある場合、そもそも保険料の払い込みが困難になってしまいます。学資保険に加入する前に、まずは無理のない返済計画と保険料負担のバランスを検討することが大切です。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
各保険会社の学資保険の告知事項
ここでは、主な保険会社の学資保険における告知事項や引受条件を見ていきましょう。学資保険の商品ごとに、「誰の告知が必要か」「どんな告知が行われるか」に違いがあります。以下では、明治安田生命・かんぽ生命・ソニー生命・フコク生命・アフラック・ニッセイ(日本生命)について紹介します。
明治安田生命の学資保険の告知
明治安田生命「つみたて学資」では、契約者(親)および被保険者(子ども)の双方について告知が必要となっています。告知書に基づき、親と子の健康状態をそれぞれ申告し、同社の審査基準でチェックされます。明治安田生命の学資保険は払い込み期間を最長15歳までとすることで高い返戻率を実現しているのが特徴ですが、その分健康面・年齢面で条件があります。実際の告知内容は一般的な生命保険と同様で、直近の通院歴や過去の入院歴など標準的な質問項目が中心です。子どもについても出生時の状況を含め申告する必要があるため、例えば低体重で生まれたお子さんの場合は事前に担当者に相談しておくと良いでしょう。
審査難易度として特別厳しいわけではありませんが、親子どちらかに持病があると加入を見送られる可能性があります。他社と比べて健康告知の基準が緩いという情報は特にないため、標準的な告知義務が課されると考えてください。明治安田生命は大手生保として慎重な引受を行う傾向にありますので、もし告知内容に不安がある場合は事前に正直に相談し、場合によっては他社商品も検討するのが賢明です。
かんぽ生命の学資保険の告知
かんぽ生命の学資保険「はじめのかんぽ」は、契約者(親)と被保険者(子)の健康状態について基本的に告知義務があります。かんぽ生命は日本郵政グループの保険会社で、公的性格もあるため引受基準は比較的オーソドックスです。学資保険「はじめのかんぽ」には親に万一のことがあった際の保険料免除保障が標準で付帯しているため、契約者である親の健康告知は必須です。また子どもも、簡易な医務査定が行われる場合があります。
特徴的なのは、かんぽの学資保険はコースによって祝い金や満期金の受取パターンを選べることや、出生前(妊娠中)から契約できる点です。出生前加入特則を利用する場合、契約者を被保険者の父か母にしなければならず、出生後一定期間内に出生したことを申告する流れとなっています。通常加入の場合は他社同様、過去の入院・手術歴や現在の通院状況などを告知しましょう。
かんぽ生命の商品は比較的加入可能な年齢の範囲が広めで、契約者年齢の上限も高めに設定されています。そのため祖父母が契約者となるケースもありますが、その際も契約者本人の健康告知は必要です。なお、かんぽ生命のFAQによると「一部の商品を除き、契約者や被保険者には健康状態等の告知義務があります」と明記されています。学資保険も基本的には告知義務の例外ではないと考えましょう。
ソニー生命の学資保険の告知
ソニー生命の学資保険では、健康状態を自己申告する告知書による申込みが採用されています。医師の診査は不要で、告知書に健康状態を記入するだけで手続きが完了するため、煩雑さが少ないとされています。ただし告知自体は必要であり、質問項目は他社と同様です。契約者(親)の最近の病歴や通院歴、過去の大きな病気などについて記入し、被保険者(子ども)についても所定の質問に回答します。
ソニー生命の学資保険は保障内容をシンプルにして貯蓄性を高めたプランが特徴で、基本的に保険料払込免除の保障が付いたシンプルな設計です。そのため、親の健康状態は重要な審査ポイントになります。子どもの医療特約は付帯できないタイプの商品ですので、子どもの健康状態が理由で加入不可となるケースは少ないと考えられます(子どもの死亡保障も最低限のため)。実際に、ソニー生命の公式サイトでも「健康状態を自己申告していただく方法なので、事前の医師の診断は不要です」と案内されており、持病があっても加入できるかはソニー生命の内部基準によるところが大きいです。
審査の難易度としては標準的ですが、ソニー生命は契約者(親)の年齢に応じては医療的な追加資料を求める場合もあります(例えば一定年齢以上で保険金額が大きい場合に健康診断結果の提出など)。しかし学資保険の範囲では、多くの場合そこまで厳格にはならないでしょう。基本は告知書記入のみで完了するので、正直に回答すれば問題ありません。親に持病があって加入できなかった場合でも、ソニー生命はライフプランナー経由で他のプランも提案してくれることがあるため、まずは相談してみることをおすすめします。
フコク生命の学資保険の告知
フコク生命の学資保険「みらいのつばさ」は、契約者である親の健康状態のみ告知が必要という点が大きな特徴です。学資保険に医療保険をパックして加入しない限り、子どもの健康告知は不要と公式に案内されています。すなわち、基本的な学資保険は親の告知だけで契約可能であり、子どもに持病があっても加入できる可能性があります。これは、子どもの医療保障を付帯しないシンプルな学資保険であれば子どもの健康リスクは保険会社にとって大きな懸念点にならないためです(子どもが万一亡くなった場合、払込済み保険料相当額が給付される程度でリスクは限定的)。
したがってフコク生命の学資保険は、親の告知内容さえクリアすれば契約しやすいと言えます。親の告知事項は他社と同様で、過去数年の入院歴や現在の健康状態などを申告します。フコク生命の場合、他社に比べて若干加入年齢の幅が広めで、契約者年齢が高めでも検討できるようです(公式資料によれば祖父母が孫のために加入することも可能とあります)。その際も子どもの健康状態は問わないので、例えば生まれつき疾患を持つお子さんでも親や祖父母が契約者となって学資保険を用意できるメリットがあります。
注意点として、フコク生命では学資保険に医療保険をセット契約することもできますが、その場合は子どもの告知書提出が求められます。医療保障を付けると途端に審査ハードルが上がる(子どもの持病によっては断られる)ので、子どもに健康不安がある場合は無理に医療特約を付けず、貯蓄部分だけ契約する方が良いでしょう。フコク生命の学資保険は子どもの告知負担がなく契約しやすい商品と言えますが、契約者である親自身の健康状態についてはしっかり審査がありますので正確な告知が必要です。
アフラックの学資保険の告知
アフラックの「夢みるこどもの学資保険」は、告知条件が少しユニークです。保険料払込免除特則(親に万一のことがあった場合の保障)を付けない契約の場合、契約者・被保険者ともに健康告知不要で加入できます。一方、払込免除特則を付加する場合は契約者(親)の告知が必要で、子どもの告知は不要となっています。つまり、アフラックでは契約時に保険料免除の保障を付けるかどうかで審査内容が変わります。
払込免除特則なしの場合、親に持病があっても子どもに健康不安があっても、告知せずに契約可能です。これは貯蓄性に特化した商品設計で、保障を一切付けない代わりに誰でも加入しやすくしているためです。ただしこの場合、親に万一のことが起きても保険料の支払いは継続する必要があり、保障面でのメリットはありません。その代わり審査ハードルは極めて低く、基本的に断られる可能性は低いでしょう。
払込免除特則ありの場合は、契約者(親)の健康状態告知が求められます。具体的には他社と同様、過去の入院・手術歴や現在の病状、職業などについて契約者が告知する必要があります。アフラックの学資保険は子どもの死亡保障も付かない純粋な学資契約なので、子どもの医療リスクは考慮しない設計なのでしょう。
アフラックは「医師の診査が不要で告知書提出だけでOK」と公式に謳っており、利便性をアピールしています。そのため、告知内容に問題がなければスムーズに契約できるでしょう。ただし払込免除特則を付ける場合、他社同様に契約者の健康状態によっては引受不可があり得ます。その際は無理に特則を付けず貯蓄契約のみに切り替えて加入するという選択肢も検討するのがおすすめです。学資保険としては異例ですが、健康告知なしで入れるプランを用意しているのがアフラックの特徴と言えます。
ニッセイの学資保険の告知
日本生命(ニッセイ)の学資保険は、フコク生命やアフラックと同様に子どもの健康状態に関する告知は不要です。契約者(親)の健康告知のみで申し込みが可能であり、子どもが病気にかかったことがある場合でも契約できることが特徴とされています 。日本生命は大手生保でありながら、学資保険では柔軟な引受をしている点が魅力です。
具体的には、親の過去の病歴・現在の健康状態や職業などを告知書で申告しますが、子どもの持病や障がいについては尋ねられません。ただし親については当然ながら告知義務があり、内容によっては引受を断られる場合もあります(ニッセイの場合、特に払込免除特約が標準付帯なので親の健康リスクを重視します)。一方で祖父母が契約者となることも可能であり、払込期間を短く設定すれば高齢の契約者でも加入できることも大きなポイントです。その場合も祖父母(契約者)の健康告知さえクリアすれば、孫の健康状態にかかわらず契約できるメリットがあります。
ニッセイの学資保険は配当金つきで貯蓄性もあり人気商品ですが、告知面でも利用者に優しい設計と言えるでしょう。子どもの告知不要という点ではフコク生命やアフラックと共通しており、「親(契約者)の告知一本」に絞ることで審査手続きを簡素化しています。とはいえ、契約者の告知内容に虚偽があった場合は他社同様に契約解除のリスクがありますので注意してください。ニッセイは長年の実績から経営健全性も高く、告知さえ正しく行えば安心して長期間預けられる学資保険と言えるでしょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
おすすめの学資保険はこちらをチェック!
学資保険への加入を検討する際は、各社の商品特徴や告知の条件を比較し、自分たちの状況に合った保険を選ぶことが大切です。例えば「親に持病があるので子どものために保障は要らないから貯蓄重視で入りたい」場合は告知なしで入れるプランを提供している保険会社(アフラックやJA共済など)を検討できますし、「多少返戻率が下がってもいいから万一の保障も付けて安心したい」場合は大手生保の学資保険を選ぶと良いでしょう。
世の中には多くの学資保険がありますが、人気の高い主要商品の特徴をおさらいすると以下の通りです(返戻率や保障内容の比較は、専門サイトも参照してください)。
・返戻率重視:明治安田生命「つみたて学資」など返戻率100%超えの商品。健康告知は必要だが貯蓄性重視。
・告知緩和:フコク生命・ニッセイ・アフラックの学資保険は子どもの告知不要で契約しやすい。親の健康状態に不安が少ないなら有力。
・契約者年齢の柔軟性:JA共済「学資応援隊」は契約者75歳までOKで祖父母契約も想定可能。払込免除不担保特則で告知なし加入も可。
・保障充実型:第一生命「こども応援団」には契約者のがんや障害状態で保険料免除対象になるタイプもある(その分告知項目も増える)。
契約にあたっては、申込条件(契約者年齢や子ども年齢の範囲、告知事項)を事前に確認しておきましょう。また、保険会社によっては公式サイトでシミュレーションや資料請求ができますので、複数の商品を比較検討することをおすすめします。迷ったときは保険ショップや保険相談サービスを利用して、プロの意見を聞きながら選ぶのも一つの方法です。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
まとめ
学資保険は告知義務を含め生命保険の基本ルールに沿った商品です。告知事項を正確に伝えさえすれば、将来の教育資金準備にとても有用な制度と言えます。この記事で解説したポイントを参考に、ぜひご自身のニーズに合った学資保険を選んでみてください。お子さまの大切な未来のため、無理のない範囲で賢く備えていきましょう。必要に応じて各社の学資保険おすすめランキングや資料請求も活用して、納得のいく一件を見つけてくださいね。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!