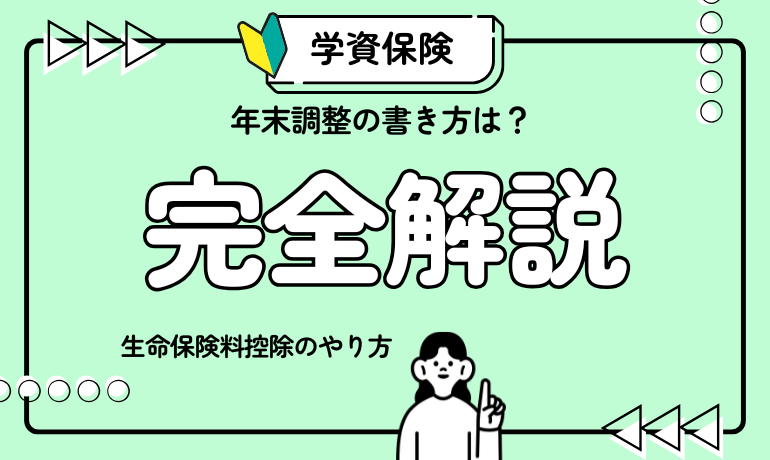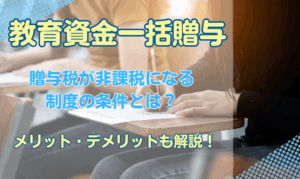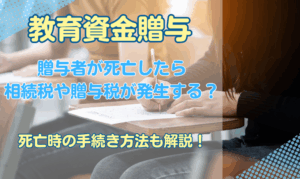子どもの教育費を準備するために学資保険に加入している方の中には、年末調整での控除申請の書き方がわからず困っている人も多いのではないでしょうか。学資保険の保険料は生命保険料控除の対象となり、年末調整で適切に申請することで所得税や住民税の軽減が期待できます。
この記事では、学資保険に加入後初めて年末調整を行う方や満期保険金を受け取った方に向けて、学資保険の年末調整における書き方や注意点について詳しく解説します。かんぽ生命、明治安田生命、富国生命、アフラック、第一生命、日本生命、JA共済、ソニー生命など、どの保険会社の学資保険でも基本的な手続きは同じです。
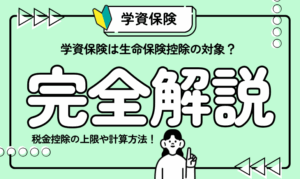
学資保険の年末調整に必要な「保険料控除申告書」の書き方
先述の通り、学資保険の保険料は生命保険料控除の対象となります。生命保険料控除は所得控除の一つで、支払った保険料に応じて所得税や住民税の負担を軽減できる仕組みです。
学資保険は生命保険の一種として位置づけられているため、「一般の生命保険料」として扱われます。この制度を活用することで、年間で支払った保険料の一部が所得控除として認められ、結果的に税負担の軽減につながります。
学資保険の保険料控除を年末調整で申請できるのは、会社員や公務員などの給与所得者です。個人事業主やフリーランスの方は、年末調整ではなく確定申告で同様の控除を申請することになります。
控除を受けるための主な条件は以下の通りです。
- 本人が保険料を支払っていること
- 保険金の受取人が契約者本人またはその配偶者、もしくはその他の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)であること
- 保険期間が5年以上であること(一部例外あり)
これらの条件を満たす場合、年末調整で生命保険料控除の申請が可能です。
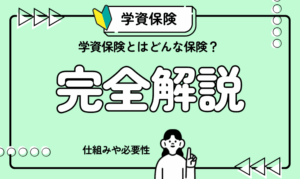
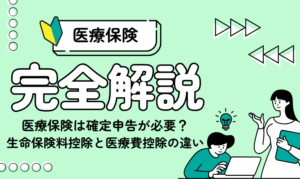
年末調整の必要書類
学資保険の年末調整を行うために必要な書類は以下の通りです。
保険料控除申告書:
正式名称は「給与所得者の保険料控除申告書」で、勤務先から配布される書類です。この申告書に学資保険の詳細情報を記入します。
生命保険料控除証明書:
保険会社から毎年10月頃に送付される証明書で、その年に支払った保険料の金額が記載されています。明治安田生命、日本生命、ソニー生命、JA共済など、どの保険会社でも同様の証明書が発行されます。この証明書は申告書と一緒に提出するのが必須です。
「給与所得者の保険料控除申告書」は、会社の給与担当者や人事部から入手できます。提出期限については、勤務先に確認しましょう。
「一般の生命保険料」の書き方
保険料控除申告書を手に入れたら、「一般の生命保険料」欄に学資保険の情報を記入します。以下では、各項目の具体的な記入方法を説明します。
項目1:保険会社等の名称
「項目1:保険会社等の名称」欄には、学資保険を契約している保険会社の正式名称を記入します。例えば、
- 株式会社かんぽ生命保険
- 明治安田生命保険相互会社
- 富国生命保険相互会社
- アフラック生命保険株式会社
- 第一生命保険株式会社
- 日本生命保険相互会社
- 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
- ソニー生命保険株式会社
保険の種類については「学資保険」または「こども保険」と記入します。保険会社によって商品名が異なるため、生命保険料控除証明書に記載されている正確な名称を確認して記入しましょう。
項目2:保険等の契約者の氏名
学資保険の契約者の氏名を記入します。多くの場合、子供の保険であっても契約者は親や祖父母になっています。夫婦で学資保険に加入している場合、それぞれが契約者となっている保険については、自分が契約者となっているもののみを記入しましょう。
また、契約者と保険料の実際の支払者が異なる場合には注意が必要です。控除を受けられるのは実際に保険料を支払っている人であり、契約者が配偶者であっても実際に保険料を支払っているのが申告者本人であれば控除の対象となります。
項目3:あなたが本年中に支払った保険料等の金額
その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った、学資保険の保険料総額を記入します。生命保険料控除証明書に記載されている「申告額」の欄の金額を転記してください。
項目4:(a)のうち新保険料等 / 旧保険料等の金額の合計額A・B
学資保険は契約時期によって、新制度または旧制度のいずれかに分類されます。
新制度(平成24年1月1日以降の契約)
平成24年1月1日以降に契約した学資保険は新制度の対象となります。項目3で記入した金額をそのまま「新保険料等の金額の合計額A」欄に記入します。
旧制度(平成23年12月31日以前の契約)
平成23年12月31日以前に契約した学資保険は旧制度の対象となります。項目3で記入した金額を「旧保険料等の金額の合計額B」欄に記入します。
生命保険料控除証明書には新制度・旧制度の区分が明記されているため、証明書を確認して正しい欄に記入しましょう。
項目5:計(①+②)
他の生命保険契約がある場合は、それらの保険料と学資保険の保険料をそれぞれ計算式に当てはめて導き出した数字を合計した金額を記入します。この計算方法については、後ほど詳しく紹介します。
項目6:②と③のいずれか大きい金額
旧制度の保険料から導き出した金額②と項目5の金額③のうち、大きい方を記入します。
「介護医療保険料」の書き方
学資保険は一般的に「一般の生命保険料」に分類されるため、「介護医療保険料」欄への記入は不要です。ただし、一部の学資保険には医療保障や入院給付金が付帯している商品もあります。
このような医療保障付きの学資保険の場合、保険料の一部が介護医療保険料控除の対象となる可能性があります。生命保険料控除証明書に介護医療保険料として記載されている金額がある場合は、その金額を「介護医療保険料」欄に記入しましょう。
介護医療保険料控除の対象となる保険料がある場合の記入方法は、一般の生命保険料と同様です。保険会社名、契約者氏名、支払保険料等の金額を各項目に記入します。
「控除額計算」の書き方
控除額には上限があり、計算式を用いて導き出す必要があります。ここでは、その上限額と計算方法について解説していきます。
控除額の上限
生命保険料控除では、所得税と住民税それぞれに上限額が設定されています。
所得税の控除額上限
- 新制度:年間40,000円
- 旧制度:年間50,000円
住民税の控除額上限
- 新制度:年間28,000円
- 旧制度:年間35,000円
いくら戻るかについては、控除額に税率を掛けた金額が実際の税額軽減効果となります。所得税は所得に応じて5%から40%の税率が適用され、住民税は一律10%の税率が適用されます。
控除額の計算方法
控除額の計算式は、支払った保険料の金額に応じて段階的に設定されています。
新制度における所得税の控除額の計算方法(平成24年1月1日以降契約)
年間支払保険料20,000円以下の場合:
控除額 = 支払保険料の全額
年間支払保険料20,001円から40,000円の場合:
控除額 = 支払保険料 × 1/2 + 10,000円
年間支払保険料40,001円から80,000円の場合:
控除額 = 支払保険料 × 1/4 + 20,000円
年間支払保険料80,001円以上の場合:
控除額 = 40,000円(上限)
旧制度における所得税の控除額の計算方法(平成23年12月31日以前契約)
年間支払保険料25,000円以下の場合:
控除額 = 支払保険料の全額
年間支払保険料25,001円から50,000円の場合:
控除額 = 支払保険料 × 1/2 + 12,500円
年間支払保険料50,001円から100,000円の場合:
控除額 = 支払保険料 × 1/4 + 25,000円
年間支払保険料100,001円以上の場合:
控除額 = 50,000円(上限)
新制度における住民税の控除額の計算方法(平成24年1月1日以降契約)
年間支払保険料12,000円以下の場合:
控除額 = 支払保険料の全額
年間支払保険料12,001円から32,000円の場合:
控除額 = 支払保険料 × 1/2 + 6,000円
年間支払保険料32,001円から56,000円の場合:
控除額 = 支払保険料 × 1/4 + 14,000円
年間支払保険料56,001円以上の場合:
控除額 = 28,000円(上限)
旧制度における住民税の控除額の計算方法(平成23年12月31日以前契約)
年間支払保険料15,000円以下の場合:
控除額 = 支払保険料の全額
年間支払保険料15,001円から40,000円の場合:
控除額 = 支払保険料 × 1/2 + 7,500円
年間支払保険料40,001円から70,000円の場合:
控除額 = 支払保険料 × 1/4 + 17,500円
年間支払保険料70,001円以上の場合:
控除額 = 35,000円(上限)
具体的な計算例
月1万円(年間12万円)の学資保険料を支払っている場合の新制度での所得税控除額の計算は、以下のとおりです。
年間支払保険料:120,000円 計算式:120,000円 × 1/4 + 20,000円 = 50,000円
ただし、新制度の上限は40,000円のため、実際の控除額は40,000円となります。
この金額により、所得税率が10%の場合は4,000円の税額軽減効果が期待できます。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険の年末調整を行うときの注意点
学資保険の年末調整を行う際には、注意しなければならない点がいくつかあります。ここではその注意点を紹介していきますので、予め把握しておきましょう。
受取人が親族以外の第三者の場合
学資保険の保険金受取人が契約者の親族以外の第三者である場合、生命保険料控除の対象外となります。控除を受けるためには、保険金の受取人が以下のいずれかに該当する必要があります。
- 契約者本人
- 契約者の配偶者
- 契約者のその他の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)
親族の範囲には、子、孫、両親、兄弟姉妹、祖父母、叔父叔母、甥姪などが含まれます。学資保険の場合、契約者本人や配偶者以外では子どもが受取人となることが多いため、この条件を満たすケースがほとんどです。
ただし、離婚などにより親権者が変更となった場合や、特殊な契約形態の場合は注意が必要です。受取人の関係に疑問がある場合は、保険会社に確認することをおすすめします。
契約者と支払者が違う場合
学資保険の契約者と実際の保険料支払者が異なる場合、控除を受けられるのは実際に保険料を支払っている人です。
例えば、夫が契約者となっている学資保険の保険料を妻が支払っている場合、控除申請できるのは妻になります。この場合、妻が自分の年末調整で控除申請を行い、夫は控除申請を行うことができません。
共働き夫婦の場合、税率の高い方が控除申請を行った方が節税効果が大きくなります。そのため、手続きを行う前にどちらが控除申請を行うのが有利かを検討することが重要です。
また、保険料を誰が支払っているかを明確にするため、銀行口座の名義や振込記録などの証拠を保管しておくことをおすすめします。
学資保険の保険期間が5年未満の場合
保険期間が5年未満の場合は、原則として生命保険料控除の対象外となります。これは、短期間の保険契約による税制上の優遇措置の濫用を防ぐためです。
ただし、以下の条件を満たす場合は例外的に控除の対象となります。
- 傷害や疾病により身体の傷害に基因して保険金が支払われる保険契約
- 傷害や疾病により働けなくなった場合に保険金が支払われる保険契約
一般的な学資保険は教育資金の積立を目的としているため、保険期間が5年未満の商品は控除対象外となる可能性があります。契約前に保険期間を確認し、控除を受けたい場合は5年以上の商品を選択しましょう。
学資保険の満期保険金を受け取ったときは確定申告が必要
学資保険の満期保険金や祝い金を受け取った場合、年末調整ではなく確定申告が必要になるケースがあります。
一時所得として課税される場合:
契約者と受取人が同一人物の場合、受け取った保険金は一時所得として課税されます。一時所得の計算式は以下の通りです。
一時所得 = (受取保険金 – 支払保険料総額 – 特別控除50万円)× 1/2
特別控除50万円があるため、利益が50万円以下の場合は課税されません。利益が50万円を超える場合は、超過分の2分の1が所得税の課税対象となります。
贈与税として課税される場合:
契約者と受取人が異なる場合、受け取った保険金は贈与税の対象となります。贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、それを超える場合は贈与税が課税されます。
住民税への影響:
一時所得は住民税の計算にも影響します。所得税と同様に、一時所得の金額が住民税の所得割額の計算に含まれるため、住民税額も増加する可能性があります。
確定申告の際は、生命保険料控除証明書や保険金支払通知書などの必要書類を準備し、正確な申告を行いましょう。申告内容に不明な点がある場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
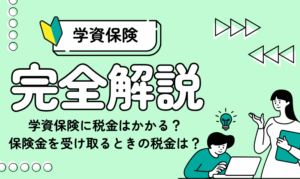
まとめ
学資保険の年末調整は、適切に行うことで所得税や住民税の負担を軽減できる重要な手続きです。保険料控除申告書への正確な記入と必要書類の提出により、年間最大40,000円(新制度)または50,000円(旧制度)の所得控除を受けることができます。
主なポイント:
- 学資保険の保険料は「一般の生命保険料」として控除対象
- 生命保険料控除証明書の内容を正確に転記することが重要
- 契約時期により新制度・旧制度の区分が異なる
- 受取人や支払者の関係、保険期間などの条件を確認する必要がある
- 満期保険金受取時は確定申告が必要になる場合がある
かんぽ生命、明治安田生命、富国生命、アフラック、第一生命、日本生命、JA共済、ソニー生命など、どの保険会社の学資保険でも基本的な手続きは同じです。初めて年末調整を行う方は、この記事を参考に正確な申告を行い、適切な控除を受けましょう。
不明な点がある場合は、勤務先の担当者や保険会社、税務署に相談することで、安心して手続きを進めることができます。学資保険の税制上の優遇措置を最大限活用し、子どもの教育費準備と節税の両方を実現しましょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!