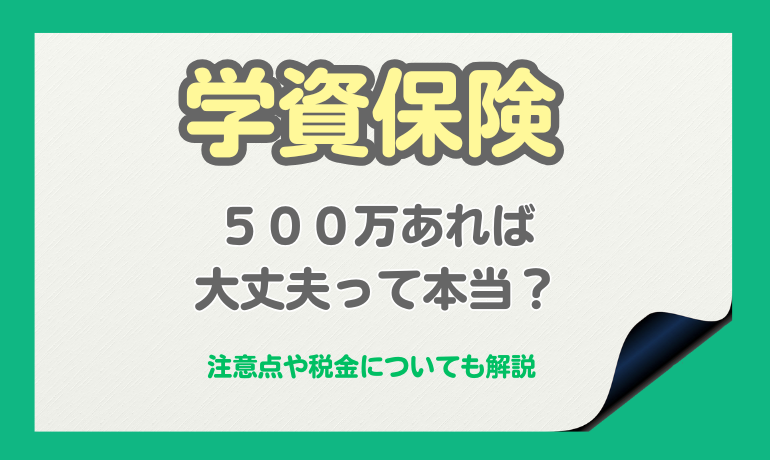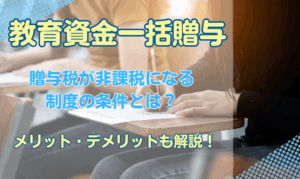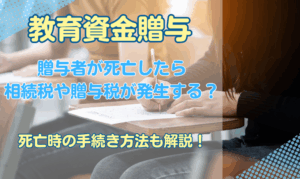学資保険で教育資金を準備する場合、500万円は一つの目安となる金額と言われています。その額を学資保険で貯めようと考えている方も多いのではないでしょうか?本記事では、「学資保険で500万貯めれば教育費は足りるのか?」という疑問に答えるとともに、500万円の学資保険に加入した場合の月々の保険料の目安、注意すべきポイントや税金の扱いについて解説します。教育資金準備の方法として学資保険が本当におすすめかどうか、他の選択肢とも比較しながら詳しく見ていきましょう。
子どもの教育資金は学資保険で500万円貯めれば大丈夫?
まず、500万円という金額が子どもの教育費として十分かどうかを確認しましょう。子どもの進路(公立か私立か)によって必要となる教育費総額は大きく異なります。公立と私立それぞれの場合の教育費総額の目安を把握し、学資保険の満期保険金500万円でどこまで賄えるのかを見極めましょう。
子どもの教育に必要な費用の目安(公立・私立別、総額の表を含める)
ここでは、文部科学省の調査データをもとに、幼稚園から大学卒業までに必要な教育費の平均を公立・私立別に見ていきます。以下は進学パターン別の教育費総額の目安です。
| 進学パターン | 教育費総額の目安 |
| 幼稚園から大学までオール公立 | 約1,000万円 |
| 幼稚園から大学までオール私立 | 約2,500万円 |
| (参考)大学4年間のみ国公立 | 約500万円 |
| (参考)大学4年間のみ私立 | 約700万~800万円 |
公立と私立では幼稚園~高校までの学費にも大きな差がありますが、特に大学の学費が教育費総額を押し上げる要因です。上記のとおり、公立だけの場合でも大学までの合計で約1,000万円、すべて私立だと約2,500万円もの費用が必要になることがわかります。
大学には満期保険金が500万円では不足する
上記のデータを見ると、「学資保険の満期保険金500万円ではまったく足りないのでは?」と不安に感じる人が多いです。確かに、私立大学まで含めたすべての教育費を500万円でまかなうことはできません。特に私立大学では4年間で700~800万円程度、国公立大学でも約500万円の学費が必要になるのが一般的です。したがって、大学まで含めた教育費全体として見ると500万円では不足するケースが多いでしょう。
しかし、幼稚園から高校までの学費は月謝や授業料を15年以上にわたり少しずつ支払っていく形になるため、一度に大きな負担が発生することはあまりありません。一方、大学進学時には入学金や前期授業料などで初年度にまとまった支出が必要となり、年間100万円以上の出費が集中します。
こうした事情から、大学入学時に合わせて満期金が出る学資保険で500万円を準備しておくことは、非常に有用と言えます。500万円あれば少なくとも国公立大学の学費をほぼカバーでき、私立大学の場合でも学費の大部分を賄うことができます。このことから学資保険の満期保険金500万円という金額は、「大学進学時に備える教育資金」としてひとつの目安となる適正額だと考えて良いでしょう。
ポイント: 教育費総額から見れば500万円は十分ではないものの、大学入学時のまとまった出費に備える額としては500万円は適切であり、公立大学の費用相当を準備できる安心感があります。不足分やそれ以外の教育費については、児童手当の貯蓄や家庭ごとの預貯金・奨学金などで補うことも視野に入れましょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険で500万円貯めるための月々の支払額はいくら?
では、学資保険で満期時に500万円を受け取る場合、毎月の保険料(掛け金)はどのくらいになるのでしょうか。月々の支払額は、加入時の子どもの年齢や保険料の払込期間によって大きく変わります。ここではケース別の目安について解説していきます。
子供が0歳・親が30歳のケース(払込期間:18歳/10歳)
まずは出生直後(0歳)から学資保険に加入し、満期(18歳)時に500万円を受け取るケースを見ていきましょう。契約者(親)が30歳の場合、一般的な学資保険の商品設計で試算すると、18歳満期・18歳払い込みの場合、月々の保険料は約2.1万~2.3万円程度が目安です。実際、シミュレーションでは月額2万950円という結果になっています。
一方で、払込期間を短縮して10歳までに払い込みを完了する契約(=10歳払済)にすると、月々の保険料負担はさらに高くなります。0歳加入・10歳までの10年間で500万円を積み立てるには、単純計算で月々約4.2万円(500万円÷120カ月)程度が必要です。実際には払込期間を短く設定した方が返戻率が上がる傾向がありますが、それでも月額3.5万円~4万円程度の保険料負担は覚悟する必要があります。払込期間を短縮すると月々の負担が数千円単位で増加するケースもあるため、18年間ゆっくり支払うプランと比較するとかなりの負担増となります。
ポイント: 0歳から加入し18歳まで払込む場合と、10歳までの短期で払込む場合を比較すると、払込期間が短いほど月々の保険料は大幅に高くなる傾向があります。無理のない範囲で払込期間を設定しましょう。
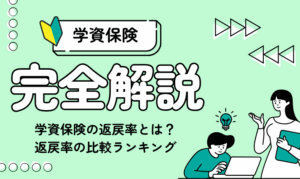
子供が5歳・親が35歳のケース(払込期間:18歳/10歳)
次に、子どもが5歳になってから学資保険に加入したケースです。満期は同じく18歳(大学入学時)だとすると、払込期間は開始時から13年間です。この場合、13年で500万円を貯めるための月額保険料はおおよそ3万円台後半が目安になります。0歳から18年積み立てるより期間が短いため、月々の負担額は増加します。例えば、あるシミュレーションでは、5歳から加入し13年で積み立てる場合、月々3万円を超えるケースが一般的です。
さらに極端なケースとして、5歳加入で払込期間を10歳まで(5年間)に設定すると、わずか60カ月で500万円を積み立てる必要があり、月々8万円前後という非常に高額な保険料が必要になります。多くの学資保険は10歳払済プランの場合、加入可能年齢が制限されているため、このような短期払い込みプランを検討する際は、家計への影響を十分考慮するようにしましょう。
まとめ: 学資保険で500万円を準備する場合、加入するタイミングが早いほど月々の負担を軽減できます。0歳から18年かけて積み立てれば月2万円台前半ですが、加入するのが遅れたり払込期間を短縮したりすると月3~4万円以上の負担も発生します。契約前に保険料シミュレーションを行い、無理なく払い続けられる設定にすることが重要です。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
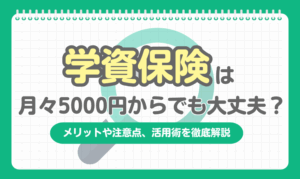
学資保険で500万円を貯めるときの4つの注意点
満期保険金500万円の学資保険に加入する際に、特に注意すべきポイントを4つ解説します。高額な学資保険だからこそ生じるリスクやデメリットもありますので、契約前にしっかり確認しておきましょう。
払い続けられる保険料を設定する
学資保険の満期金額を500万円のように高額に設定すると、その分月々の保険料負担も大きくなります。先述のとおり、子ども0歳から18歳満期500万円の場合でも月2万円以上の保険料を18年間払い続ける必要があります。この金額は決して小さくないため、家計に無理のない保険料水準に抑えることが大切です。
契約当初は支払えると思っていても、将来の収入減や支出増(例:兄弟が増える、住宅ローンの開始など)によって保険料の捻出が苦しくなるケースもあります。学資保険は長期契約のため、途中で支払えなくなるリスクを避けるためにも、ライフプランに合わせた保険料の設定が必要です。余裕があるなら、払込期間を短縮して子どもが小さいうちに支払いを終えるプランも検討するとよいでしょう。
途中解約で元本割れするリスクがある
学資保険は契約期間中に途中解約すると、支払った保険料に対して返戻金が少なく、元本割れしてしまうリスクがあります。解約時点での返戻率が低い場合、長期間の契約で既に支払った保険料の一部が失われることになるため、急な出費があってもすぐに解約できない点には十分注意が必要です。
満期前にはお金を引き出せない
多くの学資保険は、契約期間中に原則として中途解約ができない仕組みを採用しています。そのため、急な資金需要が発生した場合でも、満期前には原則としてお金を引き出すことができません。計画的に貯蓄を進める必要があることを理解しておきましょう。
満期保険金に税金がかかることがある
場合によっては、学資保険の満期保険金に対して税金がかかることがあります。具体的には、受取方法と受取人によって税金がかかるかどうかと税金の種類が変わります。契約前に、税務上の取り扱いについて十分に確認し、必要であれば専門家に相談するようにしてください。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
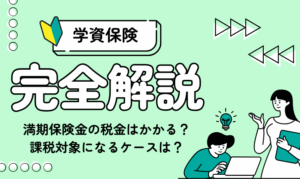
500万円の教育資金の準備に学資保険は本当におすすめ?
学資保険で500万円を貯める方法にはメリットとデメリットがあり、全ての家庭に最適とは限りません。ここでは学資保険がどのような人に向いているか、また向いていないかについて整理し、他の教育資金準備方法とも比較してみましょう。
リスクを抑えてコツコツ貯めたい人にはおすすめ
学資保険が向いている人:
リスクを抑えてコツコツ貯めたい人
学資保険は、確実に毎月決まった額を積み立て、子どもの大学入学時にまとまった金額を受け取る仕組みです。急激な市場変動のリスクが少なく、貯蓄として安定しています。
計画的に将来の学費を準備したい人
学資保険は、長期にわたって計画的に積み立てられるため、ライフプランに合わせた支払いができます。家計の計画が立てやすいのもメリットです。
学資保険が向いていない人:
急な資金需要が発生する可能性の高い人
満期前には原則として引き出せないため、急な出費が発生する可能性の高い人には向いていません。
投資運用による資産増加を狙いたい人
学資保険は、保険としての機能と貯蓄機能を併せ持っていますが、市場運用型の投資商品と比べるとリターンが限定される場合があります。
| 項目 | 学資保険のメリット | 学資保険のデメリット |
| リスク管理 | 安定した積み立てが可能 | 途中解約すると元本割れするリスクがある |
| 計画性 | 長期にわたり計画的に貯蓄できる | 急な資金引き出しができない |
| 運用利回り | 安定収入が期待できる | 投資運用型と比べリターンが限定的 |
学資保険以外で500万円を準備する方法
学資保険以外にも、教育資金として500万円を準備する方法は複数あります。例えば、NISAや定期預金などがあり、それぞれメリット・デメリットがあります。代表的な方法とメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| 方法 | メリット | デメリット |
| 学資保険 | 安定した積み立てが可能、計画性がある | 途中解約時に損失が生じるリスク、流動性が低い |
| NISA | 投資リターンが見込める、税制優遇がある | 市場変動リスクがある、元本保証ではない |
| 定期預金 | 元本保証がある、リスクが低い | 利息が低く、インフレに弱い |
どの方法も一長一短があるため、ご自身の家計状況やリスク許容度に合わせた選択が重要です。特に学資保険は、計画的に教育資金を貯めていきたい方にとって安心感のある選択肢となり得ますが、他の方法も併用することでリスクを分散させるのも一つの方法です。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
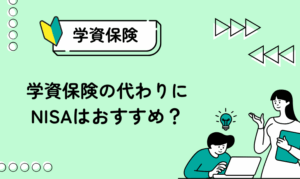
おすすめの学資保険はこちらをチェック!
最終的に、実際の商品の選定については、複数の商品を比較検討することが重要です。各保険会社が提供する学資保険にはそれぞれ特徴があり、支払額や返戻率、税制上の優遇措置なども異なります。最新の情報を踏まえ、複数商品のシミュレーションや比較を行い、ご自身の状況に最も適した学資保険を選ぶことをおすすめします。
まとめ
学資保険500万円の意義
教育全体の費用としては足りなくても、大学入学時のまとまった出費に備えるための一助として500万円は妥当な目安と言えます。
月々の保険料
加入時の子どもの年齢や支払い期間によって、月々の支払額が大きく変わるため、各シミュレーションを確認することが大切です。
注意点
学資保険は長期契約のため、家計に無理のない保険料設定、途中解約リスク、満期前の資金流動性の低さ、及び税金の課税リスクをしっかり把握する必要があります。
教育資金の準備方法の選択
学資保険以外にも、NISAや定期預金などさまざまな方法があり、各商品のメリット・デメリットを比較して、総合的に判断することが求められます。
以上の点を踏まえ、500万円を確実に準備するためのプランとして、学資保険は一つの有効な方法と言えます。ご自身のライフプランに合わせて事前シミュレーションを行い、将来の教育資金準備の選択肢の一つとして検討していただければと思います。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!