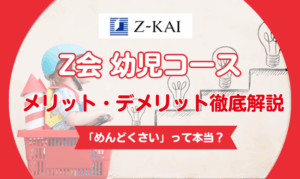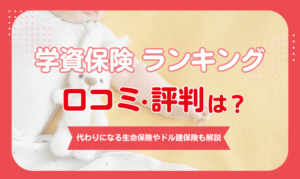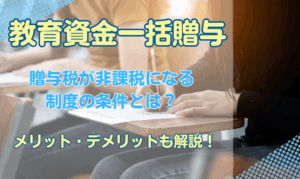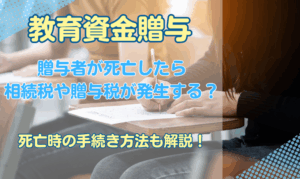子どもが小学生になったのに学資保険にまだ入っていない…今からでも加入できるの?と不安に感じている保護者の方も多いのではないでしょうか。乳幼児のうちに入る人が多い学資保険ですが、小学生からでも間に合うのか気になりますよね。本記事では、学資保険は小学生でも加入できるのか、そして小学生から加入する場合のメリット・デメリットについて詳しく解説します。さらに、学資保険以外で小学生から教育資金を効率よく貯める方法も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください
学資保険は小学生からでも入れる?
まず気になるのは、学資保険は子どもが小学生になってからでも入れるのかという点です。結論から言えば、小学生からでも加入できる学資保険は存在します。学資保険は子どもが生まれてすぐや幼稚園のうちに加入するケースが一般的ですが、保険商品によっては加入できる年齢の上限が小学校入学ギリギリの6歳や7歳、さらには小学校を卒業する12歳までと設定されているものもあります(つまり10歳からでも加入できる学資保険が存在するということです)。
ただし、焦って学資保険に駆け込むのはおすすめできません。というのも、子どもの年齢が上がるほど加入できる学資保険の選択肢は減り、加入時の条件もシビアになる傾向があるからです。「小学生のうちに急いで入らないと損するかも…」と慌てる前に、まずは小学生から加入する場合の注意点や学資保険の仕組みをしっかり理解しておきましょう。
小学生からでも入れる学資保険はある
実際に、小学生からでも申し込める学資保険商品は存在します。すべての保険会社が対応しているわけではありませんが、主要な学資保険の中には子どもが9歳まで申し込めるものや12歳まで加入可能なものもあるのです。
例えば、郵便局の学資保険(かんぽ生命「はじめのかんぽ」)には子どもが12歳まで加入できるプランがあります。また、JA共済の「こども共済」も同じく12歳まで申し込みが可能です。さらに、住友生命の「こどもすくすく保険」は子どもの加入可能年齢が0歳~9歳となっており、小学校に入学してからでも十分間に合う学資保険として知られています。
このように小学生でも加入できる学資保険は少ないながらも存在します。しかし、子どもの年齢制限ギリギリで入ろうとすると、「満期までの期間が短くなる分だけ返戻率(受け取れる金額の割合)が低下しやすい」のように、後述するデメリットもある点には注意が必要です。「加入できるから大丈夫!」と安心する前に、加入条件や満期時の受取額など細かい部分まで確認しておきましょう。
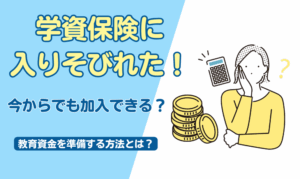
親の年齢が原因で入れないこともある
学資保険は子どもの年齢制限だけでなく、契約者(親)も加入できる年齢が限定されていることを忘れてはいけません。保険商品によって異なりますが、契約者となる親の年齢上限は一般的に父親で50~60歳前後、母親で60歳前後に設定されている場合が多いです。つまり、子どもが年齢制限内であっても、親御さんの年齢が高すぎると新規に学資保険へ加入できない可能性があります。
この基準は商品によって異なり、先述の住友生命のように契約者が69歳までOKという例外もあります。小学生から学資保険に申し込む際は契約者となる親の年齢制限にも注意し、自分たちが条件を満たしているか確認しましょう。
また、親の年齢が高くなると保険料も割高になる傾向があります。場合によっては健康状態の告知も必要になるケースがあるため、親世代の年齢条件や負担も考慮して検討することが大切です。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
学資保険はダメ?小学生から加入する3つのデメリット
続いて、「小学生から学資保険に入るなんて損じゃないの?」という疑問について考えてみましょう。確かに、学資保険は早く加入するほど有利と言われています。そのため、小学生になってからの加入にはいくつかデメリットが存在するのも事実です。ただし、ダメなわけではなく、あくまで赤ちゃんの頃に入った場合と比べて不利になる点があるという意味です。ここでは、小学生から学資保険に加入する主なデメリットを3つ紹介します。
返戻率が低くなり元金割れのリスクが上がる
学資保険を評価する指標として返戻率(へんれいりつ)があります。返戻率とは、支払った保険料総額に対して受け取れる満期金や祝い金の割合を示す数字です。例えば、返戻率が105%であれば支払い総額より5%多く受け取れる計算になり、100%を下回れば支払ったお金より受取額が少なくなる(元本割れする)ことを意味します。
小学生から学資保険に加入すると、この返戻率が100%を下回りやすい傾向があります。というのも、加入が遅れるほど保険料の運用期間が短くなり、十分に増やす時間が確保できないからです。実際、0歳で加入して18歳満期の場合は18年間の運用期間がありますが、例えば8歳から加入して18歳満期にするケースでは運用期間は10年間に短縮されます。
実例として、先ほど紹介したかんぽ生命「はじめのかんぽ」では、子ども8歳・払込期間10年というケースで返戻率が約97~98%とされています。つまり満期金は支払総額の97~98%程度であり、多少なりとも元本割れになる計算です。小学生から加入する学資保険は、このように返戻率が100%未満=受取額が支払額を下回る商品が多くなっています。このように、せっかく積み立てたのに増えないばかりか目減りしてしまうリスクが高い点はデメリットと言えるでしょう。小学生から学資保険に入る場合は、契約前に返戻率が何%になるのか必ず確認し、納得できるか検討することが大切です。
保険料が高くなるので家計の負担になる
加入時期が遅くなるほど、一括で準備できる期間が短くなるため月々の保険料負担が大きくなります。なぜなら、同じ満期金額を目標にする場合でも、0歳から18歳まで18年間かけて払うのと小学生になってから10年程度で払うのとでは、月々の支払額に大きな差が出るからです。
例えば、満期金200万円の学資保険に加入するケースを考えてみましょう。0歳から18歳まで18年間コツコツ払うのであれば、毎年約11万円(毎月約9千円強)の積立で済みます。しかし、8歳から18歳までの10年間で同じ200万円を用意しようと思うと毎年20万円(毎月約1万6千~1万7千円)程度の負担が必要になります。つまり、短期間で目標額を積み立てようとすると月々の保険料は高額になりがちです。
保険料が高くなるということは、家計への負担が増すということでもあります。毎月の出費がかさむと途中で支払いが難しくなる可能性も出てきます。そして、学資保険の保険料が払えなくなって途中解約してしまうと、解約返戻金が払込総額を下回り元本割れとなってしまうことが多いですす。「これ以上家計の支出を増やして大丈夫か?」という点は慎重に見極めましょう。
学資保険だけで教育資金を準備するのが難しい
学資保険だけで子どもの教育費すべてをまかなうのは、小学生からでは現実的に難しい場合があります。というのも、子どもの教育に必要な費用は想像以上に大きいからです。文部科学省などの調査によると、幼稚園から大学卒業まで公立のみで進んだ場合でも総額で約800~1000万円、高校まで公立・大学から私立といったケースではトータルで1500万円以上かかることも珍しくありません。小学生から学資保険を始めて、例えば10年間でこれだけの金額を積み立てようとすると、月々の保険料負担は非常に高額になってしまうでしょう。
そのため、学資保険だけで教育資金の全てを準備するのは困難であり、「学資保険で賄えるのは教育費の一部」と考えておくのが現実的です。残りの不足分は別途貯金や他の方法で補う必要があるでしょう。「学資保険に入っているからもう安心!」と全て任せきりにせず、他の積立方法も併用することを考える必要があります。この点はデメリットというより計画上の注意点ですが、学資保険だけに頼れないという意味で覚えておきたいポイントです。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
小学生からでも学資保険に加入する3つのメリット
ここまでデメリットを中心に述べましたが、小学生から学資保険に加入することにもメリットはあります。加入が遅れたからといって意味がないわけではなく、学資保険特有の利点は小学生からでも享受できるのです。ここでは、主なメリットを3つ紹介します。
万が一のことがあっても教育費を準備できる
学資保険最大のメリットは、契約者(親)に万が一のことが起きても子どもの教育資金を確保できる点です。学資保険では、契約者である親が死亡または高度障害状態になった場合、それ以降の保険料の払い込みが免除され、契約時に定めた満期金や祝い金を受け取ることができます。要するに、親にもしものことがあっても子どものための教育費を計画通り用意できるという安心感が得られるのです。
貯蓄中に万一働き手に不測の事態が起きると、その時点で教育費の貯金はストップしてしまいます。しかし学資保険に加入していれば、万が一の場合でも満期時に教育資金を受け取れるため、子どもの将来に備える強力なバックアップとなります。小学生からの加入であっても、この保障の恩恵は同じように受けられます。
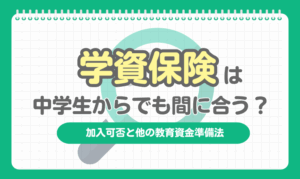
生命保険料控除を利用できる
学資保険の保険料は、生命保険料控除の対象になります。生命保険料控除とは、毎年支払った保険料の一定額を所得から差し引くことで、所得税や住民税の負担を軽減できる税制上のメリットです。簡単に言えば、学資保険に入って保険料を支払っていると税金の一部が戻ってくる可能性があるということです。
毎年支払う学資保険の保険料の一部は生命保険料控除として所得から控除できるため、所得税や住民税の負担がいくらか軽減されます。控除を活用すれば、毎年数千円程度の税金が戻ってくる可能性もあり、小さいながらも経済的メリットと言えるでしょう。
確実に貯蓄ができる
学資保険は契約してしまえば定期的に保険料を払い込む必要があるため、半強制的に貯蓄ができるという点もメリットです。貯金が苦手な人でも、保険料の支払いという形であれば毎月コツコツ積み立てを続けやすくなります。銀行預金だと「ちょっと今月は余裕がないから…」と後回しにしてしまったり、せっかく貯めたお金を他の目的に流用してしまったりする人も少なくありません。しかし学資保険なら満期まで基本的に引き出せない(解約すると元本割れリスクがあるので簡単には引き出せない)ため、貯めたお金に手を付けず計画的に積み立てられます。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
小学生からでも学資保険の加入がおすすめの人とは
上記のメリット・デメリットを踏まえると、小学生からの学資保険が向いている人とそうでない人が見えてきます。どんな人にとって小学生からの学資保険加入がおすすめなのでしょうか。
◎ 小学生からでも学資保険に加入するのがおすすめの人:
・万が一の保障を重視する人:自分に万一のことがあった場合に備えて、子どもの教育費を確実に残せる手段が欲しい方。学資保険なら親に万一のことがあっても教育資金を準備できるので安心です。
・計画的な貯蓄が苦手な人:つい貯金を後回しにしたり使ってしまったりする性格で、強制的にでも積み立てしたい方。学資保険なら契約上払わざるを得ないので確実に貯蓄できます。
・一定の余裕資金があり保険料負担に耐えられる人:小学生からの加入だと保険料は割高になりますが、それを無理なく支払っていけるだけの家計の余裕がある方。しっかり払込を続けられるなら途中解約の心配も減ります。
◎ 小学生からの学資保険をおすすめできないケース:
・高い利回りや柔軟性を重視する人:学資保険の返戻率は小学生からだと低くなりがちで、運用益はほぼ期待できません。利息を増やしたい人、あるいは急な出費時に柔軟にお金を引き出したい人には不向きです。
・家計に余裕がなく保険料継続が不安な人:これ以上毎月の出費を増やすのが難しい方や、収入が不安定で将来保険料を払い続けられるか心配な方。無理して加入して途中で解約すると元本割れで損をしてしまう可能性が高いため、無理な加入はおすすめできません。
要するに、「多少返戻率が低くても保障や強制貯蓄のメリットを取りたい」という方には、小学生からでも学資保険は有効な選択肢になり得るでしょう。一方で、「できるだけお金を増やしたい」「柔軟に手元で資金管理したい」という方には、学資保険以外の方法の方が向いている可能性があます。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!

小学生でも加入できるおすすめの学資保険
では、子どもが小学生だけど学資保険に入りたい場合、具体的にどのような商品があるのでしょうか。ここでは小学生でも加入可能な学資保険の例をいくつか紹介します。
・かんぽ生命「はじめのかんぽ」(郵便局の学資保険):子ども12歳まで加入可能な学資保険です。大学入学時に備えたプランも用意されています。返戻率は加入時期やプランによって異なりますが、小学生からの加入では100%を下回ることもある点に注意しましょう。
・JA共済「こども共済 学資タイプ」:JA共済が提供する学資保険で、こちらも子どもが12歳まで加入できます。特徴は比較的高めの返戻率と充実した保障で、契約者(親)に万一のことがあった場合の保障が手厚い点が評価されています。
・住友生命「スミセイのこどもすくすく保険」:子どもの加入年齢が0歳~9歳までと幅広く、小学生でも間に合うプランです。さらに契約者の年齢も男性は69歳、女性は75歳までと非常に広く設定されているため、祖父母世代が契約者となることも可能です。
上記の商品は、小学生のお子さんでも加入できる数少ない学資保険です。ただし、加入可能年齢内であっても細かな条件やプランによって返戻率や月々の保険料は異なります。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!
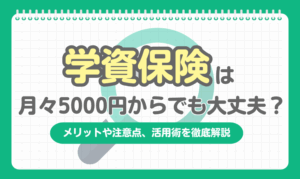
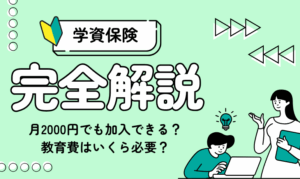
学資保険以外で子供の教育資金を貯める方法
最後に、学資保険以外で教育資金を準備する方法も押さえておきましょう。小学生から教育費を貯め始めるなら、学資保険だけでなく他の手段も併用・検討することで効率よく貯蓄できる場合があります。ここで、代表的な方法を3つ紹介します。
・終身保険を活用する:学資保険の代わりに貯蓄型の終身保険で積み立てる方法です。終身保険は一生涯保障が続きますが、教育資金が必要になったときに解約や契約者貸付でお金を取り出し、学費に充てることができます。親自身に保障を持たせながら貯蓄もできるため、一石二鳥の手段とも言えます。
・NISAのような積立投資を利用する:より高い利回りを目指すなら、NISA(少額投資非課税制度)を活用した積立投資も一つの方法です。例えば、毎月一定額を投資信託や株式に積み立てていけば、長期的な運用益が期待できます。NISAであれば運用益が非課税になるメリットもあり、教育資金作りに適した制度です。ただし、市場変動による元本割れリスクもあるため、リスク許容度を見極めた上で計画的に運用する必要があります。
・預貯金・定期積金で地道に貯める:シンプルですが確実な方法は、銀行の預貯金でコツコツ貯めていくことです。財形貯蓄や銀行の自動積立定期預金などを利用すれば、強制力を持たせつつ元本割れの心配なく貯蓄ができます。現在は超低金利で預金利息はほとんど付きませんが、元本が減るリスクがないというのは大きな安心材料です。例えば毎月1万円でも定期積金で積み立てれば、10年間で120万円+利息を確実に準備できます。地道な方法ですが、確実性を重視するなら預貯金は基本と言えるでしょう。
これらの方法にはそれぞれ一長一短があります。終身保険は保障を持ちながら貯蓄できますが途中で解約しないと教育資金として使えない、投資は利回りが期待できる反面リスクもある、預貯金は安全だが増えにくい、といった特徴も覚えておきましょう。大切なのは、自分たちのリスク許容度や経済状況に合わせて適切な方法を選ぶことです。学資保険にこだわらなくても、教育資金を貯める手段はいくつもあります。「うちの場合はどの方法が合っているかな?」と検討してみてください。
まとめ
学資保険には小学生からでも加入できる商品がありますが、加入時期が遅い分リターン面では不利になることが多いです。それでも保険ならではの保障や強制貯蓄のメリットは得られます。「損だからダメ」と決めつけずに、メリット・デメリットを踏まえて自分の家庭に合った方法で教育資金を準備することが大切です。小学生のお子さんがいるご家庭も、今から計画的に貯蓄を始めて将来の教育費に備えましょう。

120,000人以上のママパパが利用しているインズウェブの学資保険資料請求!
資料請求ご利用の方全員に今だけライフプラン情報ブックプレゼント中!この機会にぜひ!