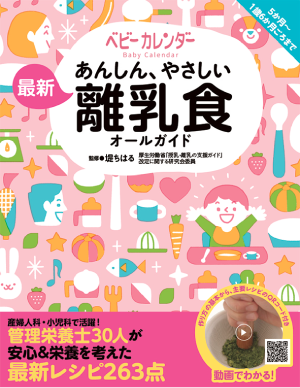離乳食の進め方

離乳食とは、母乳やミルクから固形の食事に移る時期に赤ちゃんに与える食事のこと。母乳やミルクだけを飲んできた赤ちゃんにとって、初めての食事です。栄養面ばかりに目が向きがちですが、それ以外にも大きな意味があります。焦らず、赤ちゃん一人ひとりに合った方法で進めましょう。
離乳食の3つの役割
役割1「エネルギーや栄養をとる」こと
低月齢のうちは母乳やミルクを飲むだけで成長・発達できていた赤ちゃんも、生まれてから半年ほどすぎると、それだけでは成長に必要な分をまかなえなくなります。胎内でママからもらっていたエネルギーや栄養素も、だんだんと減っていきます。そのため、母乳やミルク以外の食べ物からエネルギーや栄養素をとっていかなければなりません。特に母乳育児の場合、6カ月ごろから鉄不足に気をつけましょう。
役割2目、手、口の協調動作を育て、「食べる練習」をすること
赤ちゃんはこれまで母乳やミルクだけを飲んできたので、「すぐにモグモグかんで、ムシャムシャ食べる」とはなりません。そもそも、母乳やミルクを飲むときの口の動きと、形のあるものを食べるときの口の動きはまったく違うもの。赤ちゃんの成長・発達に合わせて、その時期に食べやすいもの・形状・調理法を変えながら、「口に入れる」「かむ」「飲み込む」練習をする必要があります。また、目で見たものをつかんで口に入れるという、目、手、口の協調動作を育てます。
大きさや形状の変化
最初はトロトロの状態からスタート。徐々につぶ感を残し、最後はかみとれるようにします。 にんじんを例に、形状と大きさの変化を見てみましょう。
5~6カ月ごろ
最初は裏ごししたり、すりつぶしたりして、なめらかに。慣れてきたら、少しずつ水分を減らして、ヨーグルトのようなべたべたの状態にします。
7~8カ月ごろ
指で軽くつぶせるくらいにやわらかくゆでて、少しつぶ感のあるくらいにすりつぶします。慣れてきたら2~3㎜大に。魚や肉はパサつきがちなので、とろみづけなど飲み込みやすくなる工夫を。
9~11カ月ごろ
力は弱いですが、歯ぐきでかんでつぶすことができます。指でつぶせるくらいにやわらかくゆでて、5~8㎜大に。慣れてきたらコロコロサイズに。魚や肉は、細かくほぐします。最初はとろみをつけると、食べやすいです。
1歳~1歳6カ月ごろ
かむ力が増し、前歯でかみとることができます。食材はフォークがスッと通るぐらいの硬さにゆで、食べやすいサイズにします。にんじんならいちょう切りなどに、慣れてきたら半月切りがおすすめ。魚や肉も食べやすいサイズにほぐしたり、切ったりします。
役割3「食べる楽しさを知る」こと
赤ちゃんにとって食べ物は「未知の世界」であることに加え、一人ひとり成長や発達の度合い・個性・好みも違うもの。マニュアル通りにはいきません。少ししか食べなかったり、逆に食べすぎたりすると、つい「大丈夫かな?」と心配になってしまいますが、焦りやイライラは赤ちゃんにも伝わってしまいます。それぞれの赤ちゃんに合った進め方で、大人もできるだけリラックスして食べさせると、赤ちゃんも自然に食事の楽しさが分かるようになるはずです。
離乳食はいつから始めるの?
離乳食の開始時期は5~6カ月ごろが基本的な目安となり、次の様子が見られたら開始してOKのサインです。
- 赤ちゃんの首がすわり、支えると座れるようになった
- 大人の食事を見ると、よだれを出しながら口を動かすなど興味を持っている
- 唇に触れても嫌がらなかったり、スプーンを口に入れても舌で押し出すことが少なくなった
離乳食の進め方・スケジュール
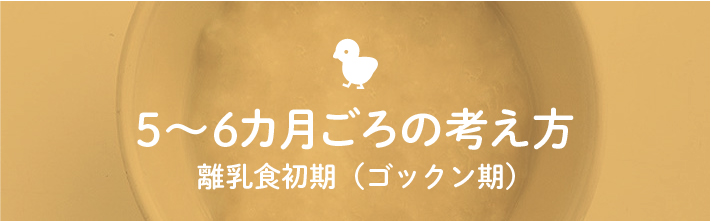
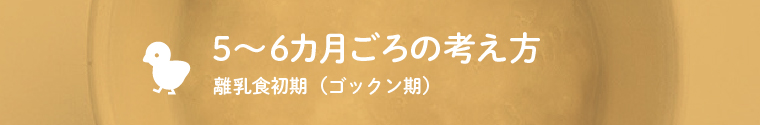
| 回数・時間 | はじめのうちは1日1回。1カ月ぐらいをすぎたら1日2回に |
|---|---|
| 赤ちゃんの食べ方 (口の中の動き) |
舌の上にのった食べ物を奥に押し込んで飲み込めますが、つぶしたりかんだりはできません |
| 硬さの目安 | とろとろのポタージュ状からスタートし、慣れたらヨーグルト状に |
| 1回あたりの目安量 | 炭水化物 10倍がゆを赤ちゃん用スプーン1さじからはじめ、慣れてきたらいも類やパンがゆやうどんがゆなどを1さじから、少しずつ増やしていく ビタミン・ミネラル 野菜・果物を1日1さじから、少しずつ増やしていく たんぱく質 白身魚・豆腐・卵黄などを1日1さじ(卵は耳かき1さじから)少しずつ増やしていく |
| 栄養バランスと 献立の立て方 |
離乳食を飲み込むこと、その舌触りや味に慣れることが主な目的のため、栄養面はあまり気にせず、いろいろな食材を体験させます |
離乳食の進め方
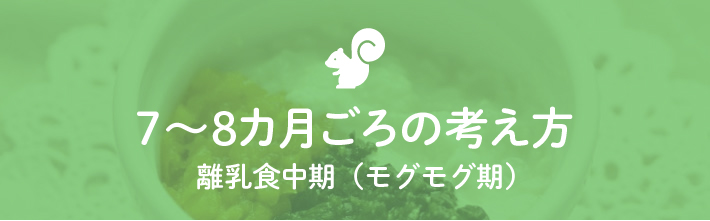
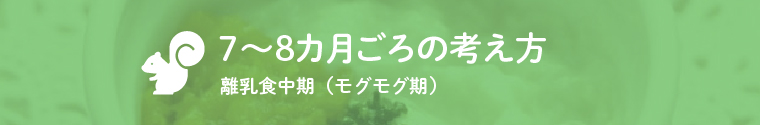
| 回数・時間 | 1日2回 |
|---|---|
| 赤ちゃんの食べ方 (口の中の動き) |
舌と上あごで食材を押しつぶしてモグモグし、唾液と混ぜ合わせて飲み込む |
| 硬さの目安 | 絹ごし豆腐程度の硬さ |
| 1回あたりの目安量 | 炭水化物 5倍がゆ50~80g ビタミン・ミネラル 野菜・果物20~30g たんぱく質 魚10~15g |
| 栄養バランスと 献立の立て方 |
主食・主菜・副菜という組み合わせも、 少しずつ意識していきます。母乳育児の場合は不足しがちな鉄分の補給を意識して |
離乳食の進め方

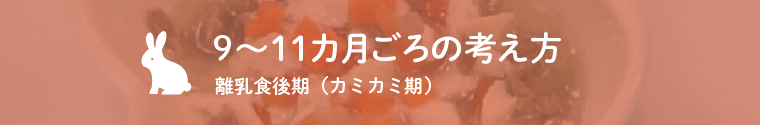
| 回数・時間 | 1日3回 |
|---|---|
| 赤ちゃんの食べ方 (口の中の動き) |
舌を上下・左右に動かし、歯ぐきでかんでつぶして食べる |
| 硬さの目安 | バナナ程度の硬さ |
| 1回あたりの目安量 | 炭水化物 5倍がゆ90g~軟飯80g ビタミン・ミネラル 野菜・果物30~40g たんぱく質 魚15g |
| 栄養バランスと 献立の立て方 |
主食・主菜・副菜をそれぞれ1品ずつ用意します。不足しがちな鉄分は積極的に取り入れて |
離乳食の進め方
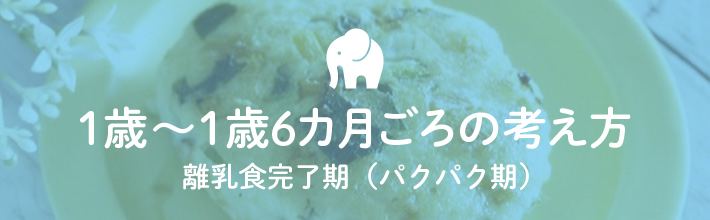
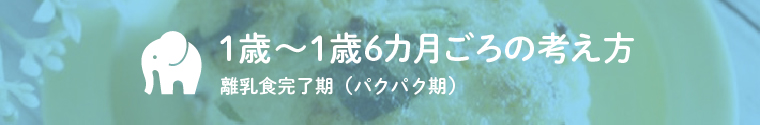
| 回数・時間 | 1日3回+おやつ(間食) |
|---|---|
| 赤ちゃんの食べ方 (口の中の動き) |
前歯でかじりとり、歯の奥や歯ぐきでつぶして食べる |
| 硬さの目安 | 肉団子ぐらいの硬さ |
| 1回あたりの目安量 | 炭水化物 軟飯80g~普通のごはん80g ビタミン・ミネラル 野菜・果物40~50g たんぱく質 魚15~20g |
| 栄養バランスと 献立の立て方 |
主食・主菜・副菜を1品ずつの組み合わせを基本にし、不足しがちな栄養をおやつで補います |
離乳食の進め方
離乳食を食べないときは?
赤ちゃんが離乳食を食べないとき、「ちゃんと食べてくれない」「栄養が足りているのかな」と不安になり、ついイライラしてしまうこともありますよね。
離乳食期はいろいろな味を経験し、食べることの楽しさを覚えていく時期でもあります。ママやパパの不安やイライラが赤ちゃんに伝わってしまうと、赤ちゃんは食事の時間が楽しくなくなり、ますます食べなくなってしまいます。
大切なのは、食事の時間を楽しい雰囲気にすること。赤ちゃんのペースに合わせながら、少しずつ固形食に慣れていけるよう、温かく見守っていきましょう。ゆっくりと「食べる喜び」を育んでいけば、自然と食べる量も増えていきます。
食べる日と食べない日の差が激しく、栄養面などが心配です
「そんな日もあるよね」という気持ちで
前の授乳から時間があいていなかったり、先に授乳をしてしまったりすると、空腹を感じず、食べなくなることがあります。空腹で離乳食の時間を迎えられるように生活リズムを整えます。食べムラは、大人でもありますよね。体調が悪くないのに、なんとなく食べたくない日など。赤ちゃんだって同じです。「そんな気分の日もあるよね」とゆったりと構えてください。
食べることに集中せず、遊んでしまいます
集中できる環境を
空腹の状態で食べられていますか?テレビがついていたり、おもちゃが目の前にあったりしませんか? 集中できる環境を整えましょう。食事時間は20~30分を目安にして、途中から遊んで食べなくなったら、赤ちゃんと一緒に「ごちそうさま」の合図をして、食事を切り上げてしまいます。このくり返しで、食事の時間にしっかり食べることをことを学んでいきます。
離乳食の食器の選び方
月齢の離乳食に合った形
離乳食に適した食器は、赤ちゃんの発達段階によって異なります。
5~6カ月ごろ(離乳食初期)は、なめらかなペースト状の離乳食に対応できる深めの皿が適しています。9~11カ月ごろ(離乳食後期)以降になると、手づかみ食べの練習を始めるため、食材をとりやすい浅めの平皿も必要となります。
発達に合った食器を選ぶことで、赤ちゃんは食べやすく、離乳食を進めやすくなるでしょう。
離乳食の食器の賢い選び方
電子レンジや食器洗浄機で使えるプラスチックやシリコン製の食器は、洗い物がラクになり家事の負担を軽減できます。
また、赤ちゃんが食事中、食器を落としたり、持って叩いたりしたときのために、割れにくく丈夫な食器だと安心ですね。幼児期まで長く使える食器を選ぶのもおすすめです。
離乳食の食器の洗い方のポイント~消毒は必要?~
赤ちゃんは大人より細菌への抵抗力が弱いため、哺乳瓶などは生後3カ月ごろまでは消毒をしますが、生後5~6カ月で離乳食を始めるころは、食器は洗浄のみでよいでしょう。
食器の洗浄は次の手順でおこないます。
- 洗剤でよく洗う
- 通気性の良い場所で乾燥させる
細菌が繁殖しないよう、食べ終わったら早めに洗浄し十分に乾燥させてから清潔な状態で収納しましょう。
離乳食の食材別食べていいもの・ダメなもの
- たんぱく質類
大豆・大豆製品・豆類豆腐、高野豆腐、油揚げ...
卵・うずら卵卵黄、卵白、卵...
白身魚鯛、ひらめ、カレイ...
赤身魚ぶり、まぐろ、かつお...
青背魚あじ、さば、さんま...
そのほかの魚介類かき、ほたて、えび...
魚加工品しらす干し、ツナ缶、さけフレーク...
乳製品加糖ヨーグルト、プレーンヨーグルト、カッテージチーズ...
肉類鶏ささみ、鶏ひき肉、鶏むね肉...
肉加工品コンビーフ、ソーセージ、ハム...
- そのほかの食品
そのほかの食品ジャム、プリン、ゼラチン...
調味料塩、醤油、砂糖...
各月齢の離乳食レシピ
離乳食の調理のきほん
離乳食の調理のきほん
きほんの主食・だしの作り方
作りおき・保存方法のきほん(フリージング)

管理栄養士/相模女子大学栄養科学部教授
堤ちはる先生
相模女子大学栄養科学部教授。保健学博士。管理栄養士。日本女子大学大学院家政学研究科修士課程修了、東京大学大学院医学系研究科保健学専門課程修士・博士課程修了後、青葉学園短期大学専任講師、助教授、日本子ども家庭総合研究所母子保健研究部栄養担当部長を経て、現職。調理学、母子栄養学、食育関連分野を 専門とし、妊産婦・乳幼児期の食育に関する研究や、講演会・研修会などの講師を務める。厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド」改定に関する研究会委員。
離乳食のお悩みを管理栄養士などの専門家に個別相談してみませんか?